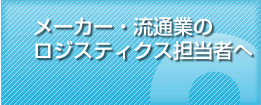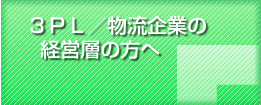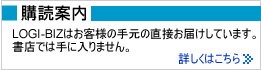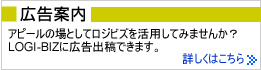|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

DECEMBER 2006 76
日本では、欧米より一足遅れて
二〇〇〇年度から国際会計基準の
導入が本格化した。
もはや財務諸
表を連結中心で構成するのは当た
り前だが、ロジスティクスを連結
ベースで機能させられる体制まで
整えた日本企業はわずかだ。
さら
に最近の企業不祥事の急増は、グ
ループ全体をにらんだサプライチェ
ーン管理の新しい課題を浮き彫り
にしている。
子会社の不祥事が親を直撃する
前号で解説した商法の大改正とは
別に、近年、企業経営のルールをめ
ぐってもう一つ大きな変化があった。
二〇〇〇年度から国内で本格化した
国際会計基準の導入がそれだ。
九〇年代の日本では、親会社と子
会社はそれぞれ別々の決算書を作成
していた。
そして、これが多くの弊害
につながっていた。
たとえば物流子会
社(未上場)に親会社(上場企業)
の余剰人員を移すことによって親会
社の経営を実態よりもスリムに見せ
たり、不良在庫を子会社に押し付け
て決算操作を行うといったことが簡
単にできた。
当時から国際的には常
識になっていた連結決算書の作成は、
海外での活動を意識する企業にしか
関係のない話だった。
しかし、急速に進んだ経済のグロ
ーバル化が、日本国内でしか通用し
ない会計ルールの見直しを迫った。
日
系企業が海外に進出するうえでも国
際会計基準の導入は不可欠だった。
九
〇年代の後半になると?会計ビッグ
バン〞が声高に叫ばれるようになり、
ほどなく会計ルールを国際標準に合
わせる改革が断行された。
その際、ま
ず柱となったのが「連結重視の経営」
と「時価会計の導入」の二つである。
現在では「会社四季報」などが連
結財務諸表の数値を中心に記載され
ていることでも明らかなように、連結
重視への変更はすでに日本企業に浸
透しつつある。
ただ国際会計基準の
導入そのものは、来年四月から適用
される新・会社法など、まだ段階的
に進められている(
図1)。
このような状況にあって、私は、最
近のCSRブームを通じて浮き彫り
になってきた連結経営時代の新たな
課題に注目している。
この連載でも繰り返し指摘してき
たように、CSR(企業の社会的責
任)が世間の耳目を集めるようにな
った背景には企業不祥事の続発があ
る。
いまや子会社の引き起こした不
祥事への批判は、ダイレクトに親会
社に向けられるようになった。
雪印ブ
ランドの失墜をダメ押ししたのは子
会社の雪印食品による牛肉偽装事件
だったし、日本ハムの牛肉偽装事件
についても不正を犯したのは一〇〇%
子会社だった。
一昔前であれば、子会社の不祥事
に対する批判が直接、親会社に向か
うことなど稀だった。
仮に子会社の不祥事についてマスコミからコメント
を求められたとしても、「子会社のし
たことなので詳細が分からない。
いま
調査中のため事実が判明し次第、厳
しく対応する」とでも言っておけば大
事には至らなかった。
最近の事例に
見られるように「親会社としてどう
責任を取るつもりなのか!」とマスコ
ミに詰問されるのは、よほど特殊なケ
ースだけだった。
連結経営の時代に企業がとるべき対応
第6回
それが近年では、批判の矛先が容
赦なく親会社の経営陣へと向かうよ
うに様変わりした。
雪印や日本ハム
のケースでは、これへの親会社の対
応が稚拙だったために、当事者であ
る子会社の廃業や、親会社の経営ト
ップの辞任という最悪の事態を招い
てしまった。
こうした変化を制度面から後押し
してきたのが、連結経営の浸透だ。
ま
た、連結経営の実践は、ロジスティ
クスが本来めざすべき「一気通貫の
在庫管理」を実現していくうえでも
有効なアプローチといえる。
関係者
はこうした時代の変化を見過ごして
はいけない。
連結ベースで機能するロ
ジスティクスを実現できていない企業
は、もはや生き残れない時代になって
いることを自覚すべきだろう。
「株式支配権」と「経営支配権」
では、どのような要件に当てはまる
会社を、連結経営の対象とすべきな
のだろうか。
親会社が発行済み株式
の過半を保有している子会社だけを
連結しておけばいいと思っている人は
多い。
たしかに会社法のなかの「親
会社が議決権の過半数を有する株式
会社」(=株式支配権)という項目が、
これに該当する。
しかし、子会社と
みなされるもう一つの要件、「親会社
がその経営を支配している法人」(=
経営支配権)という項目については
軽視されがちだ。
「株式支配権」については、株式の
保有比率によって明快なため理解し
やすい。
これに対して後段の「経営
支配権」は、表現が漠然としていて、
実際にどのような会社を指している
のか分かりにくい。
会社法の施行規
則では「四〇%以上の議決権を所有
していて、かつ、その取締役会の構
成員の五〇%超が、現に親会社の役
員・使用人」であるような企業を子
会社と定義している。
さらに、欧米で広く通用している
考え方として、ある取引先の売上高
の五割以上を自社で占めている場合
は、株を持っていようといまいと、事
実上の子会社として連結対象とみな
すという国際ルールがある。
国際ルールに従うことも国際会計
基準の導入とともに生じた重要な変
更点の一つなのだが、きちんと理解
されているとは言いがたい。
しかも実
態として「経営支配権」を握ってい
る会社が連結財務諸表から漏れてい
ても、外部からの指摘が極めて困難
という運用上の難しさもある。
一般的な話として、懇意にしてい
る取引先とのパイプが太くなり過ぎ
て「経営支配権」を握ってしまうこ
とはありえる話だ。
親会社の出身者
が経営に携わっている中小企業の売
り上げの大半を自社で占めていると
いったケースも考えられる。
しかし、
そのような取引の実態は、何か問題
でも発生しない限り、親会社の社員
といえどもごく一部の人間にしか分
からない。
だからこそ国際会計基準が導入さ
れたとき、社内監査役の役割も大幅
に見直された。
従来は子会社の監査役に任せておけばよかったことが、連
結経営の下では、最終的な管理責任
まで親会社の監査役が負うようにな
ったためだ。
かつて普通の企業の監査役は、週
に一度か二度だけ会社に顔を出せば
いいような気楽な存在だった。
そして、
いざ問題が発生したときには、「そん
な報告は受けていない」と逃げれば、
実質的な責任を問われる可能性は低
かった。
それが今や、子会社の引き
起こした不祥事に対して賠償責任を
負わされかねない立場に変わった。
監
査役にとって連結経営へのシフトは、
まさに世の中がひっくり返るほど大き
な変化だった。
課される「責任」が重たくなる一
方で、行使できる「権限」は強化さ
れた。
「監査役の子会社調査権」もそ
の一つだ。
これは、親会社の監査役
は必要に応じて子会社の業務および
財務状況を調査でき、正当な理由が
なければ子会社はこれを拒むことがで
きない、というものだ。
この「子会社調査権」は実は七〇
年代の商法改正の際に新設された規
定だが、当初はさほど強力なもので
はなかった。
そのせいか、その後も子
会社を使った不正な経理処理などが
後を絶たず、国際会計基準の導入を
機に大幅に強化されることになった。
そのための権限も監査役に与えられ、
子会社の調査をきちんとしないこと
が逆に監査役の職務怠慢に相当する
ようになった。
従来は「知らなかっ
た」で済んだ話が、知らないことその
ものが落ち度とみなされるようになっ
たのである。
飲み屋の夜逃げが経営を直撃
!?
こうしたルール変更を社内に浸透
させるため、私は味の素ゼネラルフーヅ(AGF)で常勤監査役をしてい
たときに、「経営支配権」について取
締役会で次のような説明をしたこと
がある。
「銀座や赤坂のクラブのなかには株
式会社によって経営されている店が
少なくない。
うち(AGF)の社員
の中には、特定の店を使えと社内で
推奨している人もいるようだが、その
77 DECEMBER 2006
業は独自の工夫によって特殊な業務
を手掛けている。
そして、その工夫が
同業大手に漏れて模倣されでもした
ら、一気に競争力を失うという脆弱
な経営基盤の上に存立している。
こ
のような企業に対して情報を開示せ
よと迫っても教えてもらえる可能性
は低い。
とは言え、買い手サイドにしてみれ
ば、CSR時代に求められている「食
の安全・安心」を確保するために、原
料に法律違反の成分が含まれていな
いかなどを徹底的にチェックする必
要がある。
だからこそ機密保持契約
を交わしたりして取引先に情報の開
示を促すのだが、さきに述べたような
中小企業としては、自社の命運を左
右する情報をそれぐらいでは開示し
ないところが多い。
どうしても情報を欲しいのであれば、
「御社が半分以上の製品を買い取ると
いう保証をしてくれたら開示する」と
いった交換条件が必然的に出てくる。
食品業界で通称「パートナー契約」と
呼ばれている関係である。
こういう取
引では、「経営支配権」を買い手が握
る状態が結果として生まれてしまう。
法律上は連結決算の対象とすべき企
業となってしまうのだ。
これをいちいち連結決算の対象に
していたらキリがない。
だが万一、そ
ういう取引先が負債を残して経営破
たんしたとする。
さらに債権者の中に
知恵者がいて、過去の取引実績に基
づいて「お前らが?親会社〞なんだ
から弁済しろ」と迫ってきたら、法
的にはその申し出に応じざるを得な
い。
これは企業にとって大きなリスク
だ。
国際会計基準の導入は、このよ
うに実務面で多くの変化を伴ってい
る。
この事実を十分に認識しておく
必要がある。
国際取引に商社を使う意味
最近では単なる取引先の不祥事で
すら、サプライチェーンの中核企業に
深刻な影響を及ぼすようになってき
た。
そうでなくともトータル・サプラ
イチェーンの管理は、これからの企業
にとって避けられない経営課題だ。
会
計上の連結経営の話からは少し離れ
るが、ビジネスのグローバル化という
観点から、国際調達の難しさについ
ても簡単に触れておきたい。
日本では、いまだにサプライチェー
ンというのが自社の工場からスタート
するかのごとく勘違いしている人たち
がいる。
現に私も、そう公言する企
業人を少なからずみてきた。
しかし、連結経営やトータル・サ
プライチェーンといった括りでグルー
プ全体の管理を求められるようにな
った現在、このような認識は企業の
潜在的なリスクを増大させるだけだ。
誤った認識を改められなければ、私
がこの連載のなかで繰り返し主張し
てきた?CSR経営を実践するため
のロジスティクス〞の実現も絵空事
に終わってしまうはずだ。
企業が不祥事発生などのリスクを
最小化するためには、連結経営の対
象も含めて、調達から販売に至るサ
プライチェーン全域を自ら管理する
のが理想的だ。
しかし現実のサプラ
イチェーン管理は、それほど単純では
ない。
とりわけ食品メーカーにとって
は、製品の原料となる農産物の国際
調達が欠かせず、そこでは関税や産
出国の政治的判断などが複雑に絡み
合い、一般的な食品メーカーの手に
負えない話が多い。
結果として、商
社などと組んで全体の最適化に取り
組むことになる。
だが、誰の手を借りて原料を調達
しようと消費者には関係ない。
何ら
かの問題を抱えた原料、たとえば日
本で使用が禁じられている農薬が使
われている原料がそこに含まれていた
りしたら、社会的な批判の矛先は最
終製品のブランドを有する食品メー
カーに向かう。
関税対策などのため
に商社の持つ機能を活用する一方で、
残留農薬の検査や、原料段階での遺
店の売上高の五割以上を当社が占め
ているとすれば、国際ルールの下では、
その店の『経営支配権』をうちが握
っているとみなされてしまう。
もしそ
の店の経営者が負債を残して夜逃げ
でもしたら、下手をしたら当社が責
任をとらざるを得なくなる。
この場に
も特定の店に通い詰めている人がい
るようだが、そういったケースでは個
人財産で責任を取っていただきたい。
この取締役会で、こういう話を私は
たしかにしましたからね」と最後にハ
ッキリと念を押したため、みんな笑っ
ていた。
このときは「経営支配権」という
連結経営時代の新たな会計ルールを
分かりやすく説明するために極端な
例を挙げたのだが、原料・包材や備
品類などの調達についても似たよう
な話がたくさんある。
とりわけ中小企
業を中心に五万社以上がひしめき合
う食品メーカーの業界では、取引先
の売り上げの過半を一社だけで占め
るといった事態が起こりうる。
これは
産業構造が多段階で中小企業が多く
の役割を担っている日本では、ある
意味で避けられないことだ。
とくに他社には真似のできない特
殊技術を持つ中小企業との取引では、
期せずして「経営支配権」を握って
しまうケースがある。
こうした中小企
DECEMBER 2006 78
伝子組み換えの有無などは、買い手
である食品メーカーが主体的にコン
トロールする必要がある。
また、たとえばAGFの基幹製品
の原料となるコーヒー豆であれば、四
年ほど前に東京でも商品取引所が開
設されたが、それ以前は市場そのも
のがニューヨークとロンドンにしか存
在しなかった。
そういった市場に「場
立ち」するとなると、取り扱い規模
の小さい日本の一企業の出る幕はな
い。
「場立ち」できるプレイヤーと組
む必要がある。
さらに、市場で買った原料を原産
国から輸入するときの税金の問題や、
残留農薬の問題などをクリアしなが
ら自社工場まで輸送する作業も、A
GFが単独で手掛けていてはコスト
アップになってしまう。
商社などがす
でに持っている機能を利用するほう
が得策だ。
ただし、その際に利用する商社な
どは、あくまでも食品メーカーにとっ
ては自社の代行機関に過ぎない。
事
前に安全面などについて細かく条件
設定をして、その条件をクリアできた
ときにだけ買う。
そもそも商社のよう
な機能にCSR経営に欠かせない倫
理観を求めるのは現実には難しい。
そ
こはメーカーの責任において、安全・
安心を担保する仕組みを構築してい
くしかない。
必然的に普及するカンパニー制
連結経営やトータル・サプライチ
ェーンに軸足を置いた経営(見方を
変えればCSR経営)を実践するに
は、企業内の組織も改める必要があ
る。
かつての「事業部制」のような
体制を見直して、グループを機能別
に切り分ける「カンパニー制」に移
行すべきだ。
実際、欧米の先進企業
は、連結経営が本格化した一〇年余
り前にこぞってカンパニー制に移行し
た。
日本でも一部の先進企業はすで
にそうなっている。
日本の企業のなかには、製品群ご
とに分かれていた事業部を括り直し
て?カンパニー制〞と称しているとこ
ろもあるようだが、連結経営の追求
によって必然的に行きつく「カンパニ
ー制」は、これとは似て非なるものだ。
欧米流のそれは非常にシンプルで、
本部である?「ヘッド・クォーター」
と、本部が立案した戦略を執行する?
「オペレーション・カンパニー」、そし
て全グループを対象に支援機能を担う?「サポート・カンパニー」の三つ
のセクションからなる(
図2)。
なぜカンパニー制が連結経営時代
の必然的な組織なのかというと、連
結対象となるグループ全体の経営効
率を高めるうえで適しているからだ。
従来のようにオペレーションを担当す
る企業が、ロジスティクスやITなど
の支援部門や戦略部門をそれぞれに
フル機能で抱えていると、全体の効
率を高めるのはどうしても難しい。
こ
れに対して、それぞれの機能を抜き
出してグループ全体で管理すれば、と
くにロジスティクスのような支援機能
の効率は格段に高めることが可能に
なる。
重複していた間接部門を減ら
せるためだ。
経営の効率が高まれば、企業の株
価は上がる。
このような好循環の発
生が、欧米の先進企業が競い合うよ
うにカンパニー制を導入した最大の
理由だったと私は理解している。
他
方、日本でも、連結経営の時代にな
って親会社がすべての責任を負うよ
うになりつつある。
今後はグループを
一手に管理しやすいカンパニー制の
普及が日本でも進むと見るのが妥当
だろう。
いずれにせよ、これから日本で国
際会計基準の浸透が進めば進むほど、
連結経営が本格化していくのは間違
いない。
そこではコーポレート・ガバ
ナンスやコンプライアンスについても
連結ベースで対応することが求めら
れる。
当然、ロジスティクスについて
も連結ベースで機能させる必要があ
る。
物流=ロジスティクスといった認
識をいまだに捨てきれない企業は、は
るか後方に取り残されることを覚悟
しておいた方がいい。
79 DECEMBER 2006
|