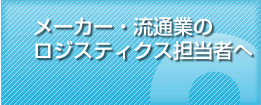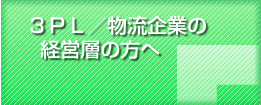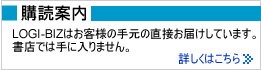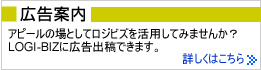|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

NOVEMBER 2007 68
共同物流
──包摂と排除との差異
第6章
基本モデルの展開
本シリーズを書こうと考え始めたのは今年
の三月であった。
その後、約半年に近い年月
の間、苦悩の連続であった。
社会システム理
論をロジスティクスの領域に活用しようとい
う企ては、これまで誰も経験していない。
乏
しい才能が試行錯誤の迷路に落ち込むばかり
であった。
しかし、ようやく前途に光明が見
えてきたように思う。
第一章から第四章までは、主としてこの
社会システム理論の必要性並びにこれを支え
ている基礎的概念装置の紹介に終始していた。
内容的にはいわば準備段階であった。
第五章
になって「直交する基本モデル」を提示する
ことができて、ようやくロジスティクス・シ
ステム論の本論のスタートを切ることができ
たというのが実情である。
この基本モデルを土台として、これを展開
していくことによって、自己創出型ロジステ
ィクスが目指しているシステム理論をベース
にした本論に入っていこうと考えている。
端的にいって、基本モデルは、ロジステ
ィクスの段階的発展論でいうならば、第一段
階の物流の領域に留まるものである。
しかし、
理論体系の基本となるものとして、この物流
の基本モデルこそが、しっかりと理解せねば
ならぬものなのである。
第五章で述べた程度
では、まだ十分に説明されていない。
もっと
詳細な議論が必要なことは承知している。
あ
るいは、第一章で少し触れたように、効用選
好理論から行動予期論への転換、システム合
理性というものについても解説する必要があ
るだろう。
だが、それらは次の機会に譲るこ
とにしたい。
現在、ロジスティクスにおけるホットな話
題は、やはりサプライチェーンや共同物流に
ある。
基本モデルをこれらの広域的ロジステ
ィクス問題に応用展開していくと、いかなる
内容をもつことになるのか。
あるいは、その
ことが有効に行われ得ることを確認すること
ができれば、現在の問題として自己創出型ロ
ジスティクスの有用性を証明することになる
かもしれない。
そこで本章では、共同物流を取り上げる。
ロジスティクスの進化
共同物流は、筆者が提唱するロジスティク
スの段階的発展論でいえば、サプライチェー
ン・ロジスティクスと共に、その第三段階に
当たるものだ。
わが国の共同物流にはかなり長い歴史があ
る。
にもかかわらず成功例は少ないといわれ
る。
また、一時は成功したかに見えても、長
続きしないことが多い。
そのなかにあって、
日用雑貨メーカーの共同物流機構「プラネッ
ト物流」は数少ない成功例の一つといってよ
いのではないだろうか。
筆者は、その成功原因をシステム理論で説
明しようと試みたことがある。
(1)その後、
あぼ・えいじ 1923年、青森市生まれ。
早稲田大学理工学部卒。
阿保味噌醸
造、早稲田大学教授(システム科学研
究所)、城西国際大学経営情報学部教
授を経て、現在、ロジスティクス・マ
ネジメント研究所所長。
北京交通大学
(中国北京)顧問教授。
物流・ロジス
ティクス・SCM領域の著書多数。
ロジスティクスは進化する。
その発展段階の1 つを
共同物流は追求している。
それは複数企業の物流を
単に寄せ集めたものとはまったく違う。
複数の企業が
各自のロジスティクス・システムを止揚して、新しい
共同システムを創造することでなくてはならない。
69 NOVEMBER 2007
プラネット物流は共同物流の成果を着実に拡
げている。
それに対して筆者もまた、「直交
する基本モデル」という改良版を打ち出した。
この基本モデルに基づいて改めてプラネット
物流をシステム理論の立場から論じてみたい。
そもそも、ロジスティクスの段階的発展論
の基本的考え方は、「ロジスティクスは進化
する」という哲学にある。
各段階で創発して
いる「システム平面」は段階が進むにつれ
て上昇している。
それは各段階のシステム構
造が変容することによってもたらされる「進
化」なのだという主張である。
共同物流もその哲学を貫くものでなければ
ならない。
共同物流が単に複数の企業が集っ
て、物流活動を共同で行うことによるスケー
ル・メリットを追求するだけのものである
のなら、少しも魅力はない。
それは「一ダースで買えば
安くなる」式の極めて安易
なものであり、単なる寄せ
集めである。
システム理論の立場に立
つならば、共同物流とは複
数の企業が各自のロジスティ
クス・システムを止揚して、
新しい共同システムを創造す
ることでなくてはならない。
それは新しい「システム/
環境」差異を産み出すもの
である。
筆者は、監査役という肩
書きでプラネット物流に関係をもつようにな
った当初から、そのように考えていた。
もっ
とも筆者は同社の設立に関係したわけでもな
いし、その後の政策決定に関わったわけでも
ない。
一時の傍観者だったに過ぎない。
し
たがって、筆者のシステム理論は同社の事業
運営に何らの影響も及ぼしていない。
それでも、同社の行動はシステム理論的観
点からしても、はなはだ興味深いものがあっ
た。
それは同社社員の意図せざる知恵だった
のかもしれない。
この辺の事情は既に発表し
たことなので、いまさら詳細について触れる
ことは止めにしておきたい。
ただし、その後
の、そして現在も進行中の同社の行動を加味
して、詳細に観察することで見えてくるもの
がある。
そこには大きな教訓が含まれている。
何を共同化するのか
今から二〇年程前、日用消費財の流通はま
だまだ未成熟な状態にあった。
わが国におけ
る物流活動そのもののインフラも未整備であ
ったし、多数の中小の流通業者から構成され
ている同業界における配送を始めとする物流
事業には、多数の困難性が存在していた。
この困難性を打開するために、採用した戦
略において、花王とライオンのそれが際立っ
て対照的であったことは、世上良く知られて
いるところである。
いうなれば、花王のと
った戦略は、小規模企業の集約であり、排
除であった。
一方、ライオンのそれは小規
図1 直交する基本モデル
物理的
空間
位相空間
構造的カップリング
連続的作業系列
ロジスティクス・システム
(アベイラビリティの循環)
コミュニケーション
仕分
ピッキング運搬
活動
図2 プラネット物流の発展史
1987年 11月
1989年 8月 プラネット物流(株)設立
1989年 9月 「物流委員会」「情報システム専門委員会」発足
中部流通センターが営業開始
1989年 10月 東北流通センターが営業開始
1989年 11月 「パレット専門委員会」「外装表示専門委員会」発足
1994年 4月 九州流通センターが営業開始
1996年 6月 九州に「ITF 活用無線LANシステム」導入
1998年 4月 北海道流通センターが営業開始
1998年 6月 共同物流情報システム(PRISM)構築
2000年 8月 幹線共同輸送がスタート
2000年 10月 九州で返品検収業務開始
2002年 1月 外装表示基準書作成
2002年 2月 南関東流通センターが営業開始
2003年 2月 返品商品の共同集荷・共同輸送がスタート
2003年 9月 南関東より東北への広域配送スタート
2004年 8月 関東流通センターが営業開始
2005年 4月 クロスドッキング配送がスタート
2005年 12月
2006年 1月 北海道で医薬品取り扱い開始
2006年 4月 販促物管理スタート
web データ交換システム開発
中部地区における日用消費財メーカー、共同配送実
験スタート
グリーン物流パートナーシップモデル事業認定へ補助
金交付
出典:プラネット物流資料
NOVEMBER 2007 70
模企業の包摂であったといえるだろう。
この戦略の違いが、今日の両者のロジステ
ィクス態勢の違いに直結していると、筆者は
考えている。
一方は、自社の経済性が強調さ
れた「大規模ロジスティクス・ネットワーク」
であり、他方は、社会性をも重んじる「共同
物流システム」であるとの解釈である。
この二つの態勢の優劣は、何れ歴史が冷厳
な判定を下すことになるだろう。
筆者はそれ
の判定者ではない。
ただ、共同化という戦略
の実現において、システム理論が果たしてい
る役割を訴えたいだけである。
プラネット物流を機能させるために、各社
は何を共同化したのか。
また、そのためにい
かなる手順を踏んだのか。
これについてシス
テム理論は、世間の常識とは少し違った説明
をする。
プラネット物流における共同化は、従来
の共同保管や共同配送とは全く趣を異にする。
また、最近の3PLや4PLとも異質のもの
だ。
それらは、畢竟するに各々の物流活動を
物流事業者に集中的に委託しているのであっ
て、自らの物流システムと物流専業者の営業
システムとの間には、財貨のやり取りは存在
していても、システム構造的な接触は何ら存
在しない。
ところが、プラネット物流における共同化
では、システムこそが問題なのである。
もっ
と突っ込んで言えば、それら
の構造間の相互関係において、
問題を解決しようとしている
のである。
具体的に説明しよう。
こ
の共同物流に参加している
A、B、C‥‥I社は、そ
れ以前は各自の物流システム
が、それぞれ顧客である卸店
との間で直接的に物流活動を
コントロールしていた。
とこ
ろが、共同化にあたって、「プ
ラネット物流の共同物流シス
テム」を新設し、自らと卸
店の間に介在させたのである。
これは流通の階層を一段
階増加させることであって、従来の考え方か
らすれば、物流費を増加させはしても、節減
にはならないはずである。
しかし、この策は、
「共同物流システム」の新しい「構造構築」に、
その命運をかけているのである。
しかも、その新しい「構造構築」のため
に採用した手段は、後から振り返ってみると、
大変巧妙なものであった。
その手段とは、各
社およびプラネット物流から選出された委員
によって構成された、「物流委員会」という
ものを設けることであった。
単一企業であれば、情報収集力においても
選択力においても、単一次元的かつ同質的な
思考のもとに単眼的な見方からの発想に終わ
ることが多い。
人材は限られているし、知的
資源も自社ベースに依存するからだ。
複数企業が共同化していることの強みは、
多次元的で異質混合的な思考をベースに、複
眼的観点から発想できることである。
情報源
も多様となる。
各社からの参加メンバーで構
成されるため、人材的にも多彩になるし、利
用できる知的資源もバラエティに富んでくる。
しかも、この委員会における発言が、従来
の企業内、企業間の関係にとらわれることな
く、自由な立場を尊重するようになれば、創
発的効果を期待することができる。
かように
人間が集ってフェース・トゥ・フェースで議
論し合うことを「相互作用」というのである。
その相互作用によって創発される優れたア
イデアを、共同物流システムの構造への刺激
図3 相互作用と構造変容
構造効果
A 社の
物流システム
B 社の
物流システム
C 社の
物流システム
I 社の
物流システム
物流委員会において
相互作用を起こす
●情報システム専門委員会
●パレット専門委員会
●外装表示専門委員会
●返品処理専門委員会
●幹線共同輸送専門委員会
●配送部会
●倉庫部会
構造的カップリング
構造的カップリング
期待する差異
プラネット物流の
共同物流システム
物流品質会議における
相互作用
委員委員
物流事業者
改 善
構造効果
卸 店
71 NOVEMBER 2007
あり、同時にその境界形成の原理なのである。
また参加する委員が誰なのかによって、その
集まりの性格は左右される。
ロジスティクス・システムは境界によって
外部の環境から遮断されていることで、自己
保全ができている。
反面、その環境とはコミ
ュニケーションできないし、コミュニケーシ
ョンではない事態や出来事からも分離されて
いる。
こうした閉塞性の下では、そのシステ
ムの環境内での出来事を知らせてくれるセン
サーだけが頼りとなる。
これらのセンサーは、
コミュニケーション・システムと十分に相互
浸透できる人間にほかならない。
委員会を構成する委員達には、任務として
環境に関する知覚(取引先や市場その他に関
する経済情報、また技術情報等)をもち、か
つ委員同士でコミュニケーションし合うこと
が求められる。
かつ、出席している委員間の
相互作用において、
再帰的なディスカ
ッションを通して、
一種の「内部環境」
が形成される。
委
員間の相互依存・
相互協力が、リー
ダーあるいはそれ
に準ずる人を基軸
として進められる。
それによってしか
るべき目的に向け
て議論が収束される。
その成果としてさまざまなアイデアの創発
されることが期待される。
相互作用はシステ
ムを産み出すエピソードであるといわれる。
アイデアが期待されるといったが、システム
論的にはそれは既存のロジスティクス・シス
テムとの差異を産み出すことである。
その差
異を手がかりとして、この場合では共同物流
システムやメーカーの物流システムの構造形
成や構造変容を誘発していくのである。
公式的にいうと、社会と相互作用との差異
は、社会─文化的進化が可能となるための前
提条件にほかならない。
(2)
包摂と排除の差異
共同物流構築の基礎原理は「包摂/排除の
差異」にある。
(このような表現は慣れない
人には奇異に感じるかもしれないが、システ
ム理論の常套手段である)何のために共同化
するのか。
花王のように次第に業界のガリバ
ーへと拡大しつつある企業に対抗するために
は、中小の企業は共同化の道を選ぶ戦略に出
ざるを得ない。
このような考えがすぐに思い
浮かぶかもしれない。
しかし、われわれはそ
のような情緒的な議論をしようというのでは
ない。
「包摂」の戦略を採用したものは共同
化を指向し、「排除」の戦略を採用したものは、
自社独自の拡大路線を歩もうとしていると認
めるのである。
「包摂/排除の差異」はすこぶる鋭利であり、
として、構造形成に役立てようとしたのであ
る。
それだけではない。
その刺激を、各委員
が自社の物流システムの構造へも反映させて、
構造効果を促し、自らの物流システムの構造
変容にも役立てたのである。
共同物流システムの構造が充実したからと
いって、それだけで効果が上がるわけではな
い。
各メーカーの物流システムの構造もレベ
ルアップしないことには、全体としての物流
活動の効率化は実現しない。
ここには相互作
用を活用することの大きな意義がある。
それでは、そもそも相互作用とはいかなる
ものか。
少し詳しく見てみよう。
相互作用
図4に示したように、相互作用は社会シス
テムを構成する一員であるが、諸社会(経済
やロジスティクスも含む)とは異なる。
相互作用は、そこに居合わせている人達が
行為することによって成立している。
そこに
居合わせている人達とは、例えば物流委員会
に出席している委員達のことで、互いに目の
あたりにしている人達である。
この人達によ
って行われるすべての行為が相互作用に該当
する。
提案やディスカッションのみならず隣
の席の人との会話までもそこに含まれる。
そして委員会が終わって、散会すると、(少
なくともつぎの委員会が開かれるまでは)相
互作用は解消される。
そこに居合わせている
ことが相互作用というシステムの構成原理で
図4 各種のシステム
システム
機 械有機体
相互作用組 織諸社会
社会システム心理システム
出典:ニクラス・ルーマン著 佐藤勉監訳「社会シス
テム理論」恒星社厚生閣 1993 年
重大な効果を有していると、ルーマンもいっ
ている。
(3)この差異が社会の構成に大き
な影響を与えているのは、まぎれもない事実
である。
われわれも日用消費財の流通業界に
その好例を見出すことができる。
既に第四章で「カップリングはきわめて選
択的に行われている。
あるものは取り込まれ、
それ以外のものは排除される。
すなわち、包
摂と排除の両面の機能をもっている」ことを
述べた。
コミュニケーション・システム(念
をおすと、ロジスティクス・システムもその
一種である)は外部の情報を直接知覚する能
力をもっていない。
それなるが故にクローズ
ド・システムなのだ。
そこで外部環境に接触
する方法として、構造的カップリングという
極めて細い水路を活用するのである。
排除の戦略を採用した、システムの構造は、
「一つの軽減、一つの高度の無関心、そして
内部では感受性の上昇を導く」(4)とルー
マンもいっている。
筆者はその好例を花王の
流通戦略に感じるのである。
本誌の二〇〇七年八月号の記事によれば
(5)「一九六七年に花王は従来の特約店卸を
経由するチャネルを改め、全国に一二八の販
社を設立した。
その時点で流通在庫は一二八
カ所に分散していた。
その後、販社の統合に
よる広域化と商物分離を段階的に進めていき、
二〇〇〇年頃までに拠点を約三〇カ所に集約
した」という。
ここには排除の戦略が働いている。
旧来の
卸店を経由することが排除されている。
代行
店に集約化することで、小規模物流の非効率
性を排除したのである。
これによって花王は全国八工場、二一物流
拠点という大規模ロジスティクス・ネットワ
ークの構築を果たした。
その結果、生産・ロ
ジスティクスの経済的計画化・運営を、数理
計画やシミュレーション手法をも駆使して達
成したと、本誌は解説している。
花王は排除、システム論的にいうならば、
自社と差異概念を異にする他社のシステムを
排除して、あくまでも自社の経営方針を貫い
ている。
他者を排除し、純粋に自己であるこ
とを保持することにより、経済性の追求を徹
底しているのである。
その姿は第四章で引用したルーマンの人間
の脳が構造カップリングによって獲得した能
力の飛躍的向上、すなわち「脳システムは外
部からの影響によって過剰な負担にさらされ
ることがなくなる。
そして学習効果が生じ得
るのであり、脳の内部に複雑な構造が構築さ
れる」ことの実現を見る思いがするのである。
花王の戦略はドライであり、プラネット物
流のような戦略はウェットであると評する人
がいる。
中小企業の非効率な物流マネジメン
トは切り捨て、排除してしまい、独自の経済
性をあくまで追求する。
それに反し、中小業
者といえども、共存共栄で行く。
確かに対比
的であるが、経済はある時には非情さが要求
されるのであろう。
しからば、包摂の戦略は経済競争において
は決定的に不利なのか。
われわれはこのこと
をもっと詳細に検討する必要がある。
第四章
で述べたように、自己言及とは唯我独尊では
ない。
自己の枠を飛び出て、より広い環境の
情報を吸収し、より豊かな自己となって再参
入する。
これこそが自己言及の実践だった。
そして共同物流システムとは、他のメーカ
ー、関連会社、物流事業者、そしてもっとも
重要なことは顧客をも含めて、これらの諸シ
ステムの間の構造的カップリングによって構
築されるものである。
これが包摂である。
既に前節で説明したように、そこでは相互
作用というものを活用している。
それは各種
委員会の委員を始めとし、関係業者のもろも
ろの人材を介在して、外界からの情報を吸収
する手段であった。
それは知覚能力の増強で
あると同時に、言語というコミュニケーショ
ン手段を活用した「共進化」なのである。
これについて次章で詳しく紹介する。
NOVEMBER 2007 72
※1 阿保栄司「成功する共同物流システム─グ
リーンロジスティクスへの挑戦─ 」生産性出版 一九九六年
※2 ニクラス・ルーマン著 佐藤勉監訳「社会シ
ステム理論」恒星社厚生閣 一九九三年
※3 Niklas Luhmann,“Die Gesellschaf der Gese
llschaft”, Kapitel , Suhrkamp, 1998
※4 ニクラス・ルーマン著 土方透監訳「システ
ム理論入門─ニクラス・ルーマン講義録(1)」新泉
社 二〇〇七年
※5 LOGI-BIZ 二〇〇七年八月号「最新物流施設
─第一部拠点戦略の考え方・進め方」
参考文献
? - ?
|