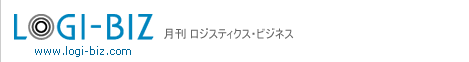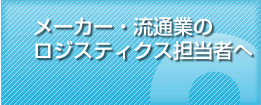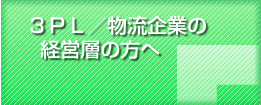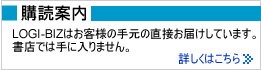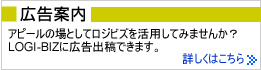|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

¬η9 ≤σ
«·¥÷ΞιΞσΞΥΞσΞΑΞ≥ΞΙΞ»ΛœΓΓΕα≈¥Θ≈ΘΊΘ–ΛΈ»Ψ §Α ≤ΦΓΓ
ΓΓ¬γΦξΙ“ΕθΞ’Ξ©ΞοΓΦΞάΓΦΛΈΆΙΝΞΙ“Εθ
ΞΒΓΦΞ”ΞΙΓ ΘΌΘΝΘ”ΓΥΛœΓΔΆη«·ΜΆΖνΛΈ
≤‘ΤΑΛΥΗΰΛ±ΛΤΦΓ¥ϋ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷ΘΌ
Θ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉΛΈ≥Ϊ»·ΛρΩ ΛαΛΤΛΛΛκΓΘ
ΖΉ
≤ηΛ«ΛœΛόΛΚ≤ΛΫΘΥΓΩΆΛΈΑλΦ“ΛΥΤ≥ΤΰΛΖ
ΛΤΓΔ»Ψ«·Ρχ≈ΌΛΈΞΤΞΙΞ»≤‘Τ·ΛρΙ‘ΛΠΓΘ
Λ≥
ΛΈΟ ≥§Λ«…‘ΕώΙγΛ Λ…ΛρΫΛάΒΛΖΓΔ¥Αά°
≈ΌΛρΙβΛαΛΩΛΠΛ®Λ«≤Θ≈Η≥ΪΛΙΛκΓΘ
Λ…ΛΈ
ΟœΑηΛΪΛιΤ≥ΤΰΛΖΛΤΛΛΛ·ΛΪΛœΧΛΡξΛάΛ§ΓΔ
ΤσΓΜΑλΤσ«·ΜΑΖνΥωΛόΛ«ΛΥΛœΝ¥άΛ≥ΠΛΊ
ΛΈΤ≥ΤΰΛρ¥ΑΈΜΛΙΛκΆΫΡξΛάΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛΥΛηΛΟΛΤ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΛρΚΰΩΖ
ΛΖΓΔΗΫΨθΛ«Λœ ΘΩτΛΔΛκΜ≈Ν»ΛΏΛρΞΑΞμΓΦ
Ξ–ΞκΛ«≈ΐΑλΛΙΛκΓΘ
≥Ϊ»·ΛδΤ≥ΤΰΛΈΛΩΛα
ΛΥΖΉ≤ηΛΖΛΤΛΛΛκΆΫΜΜΛœΜΆΓΜ≤·±ΏΓ Υή
Φ“ΓΠΨπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΛΈΩΆΖο»ώΛœΫϋΛ·ΓΥΓΘ
ΛΙΛ«ΛΥάΛ≥Π≈ΐΑλΞΖΞΙΞΤΞύΛρΦ¬ΗΫΛΖΛΤ
ΛΛΛκΞιΞΛΞ–ΞκΛΈΕα≈¥Ξ®Ξ·ΞΙΞΉΞλΞΙΓ ΘΥ
ΘΉΘ≈ΓΥΛΥ»φΛΌΛκΛ»ΓΔ≥ Ο ΛΥΨ·Λ ΛΛ≈ξ
ΜώΒ§ΧœΛ«ΦΓάΛ¬εΛΈ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΛράΑ
»ςΛΖΛηΛΠΛ»ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΛΫΛβΛΫΛβΘΌΘΝΘ”Λ»ΘΥΘΉ
Θ≈Λ»Λ«ΛœΓΔΘ…Θ‘≥ηΆ―ΛρΟ¥
ΛΠΝ»ΩΞΛδΆΫΜΜΒ§ΧœΛ§ΛόΛκ
Λ«ΑέΛ ΛκΓΘ
ΘΌΘΝΘ”ΞΑΞκΓΦ
ΞΉΛΥΛœΓΔΥήΦ“ΛΈΓ÷Ψπ σΞΖ
ΞΙΞΤΞύ…τΓΉΛΥΧσΜΆΓΜΩΆΛ»ΓΔ
Λ≥Λ≥ΛΪΛιάΛ≥Π≥ΤΟœΛΥΫ–Ηΰ
ΛΖΛΤΛΛΛκΧσΑλΓΜΩΆΛ»ΓΔΖΉ
ΗόΓΜΩΆΛΈΘ…Θ‘Ο¥≈ωΦ‘Λ§ΛΛ
ΛκΓΘ
Αλ ΐΛΈΘΥΘΉΘ≈ΞΑΞκΓΦ
ΞΉΛœΓΔΨπ σΜ“≤ώΦ“ΛόΛ«¥ό
ΛαΛκΛ»άΛ≥ΠΟφΛΥΜΆΓΜΓΜΩΆ
ΕαΛΛΘ…Θ‘ΆΉΑςΛρ ζΛ®ΛΤΛΛ
ΛκΓ ΥήΜοΓΜΦΖ«·ΕεΖνΙφΜ≤
Ψ»ΓΥΓΘ
ΓΓΈΨΦ“ΛΈΘ…Θ‘ΛΈ«·¥÷ΞιΞσ
ΞΥΞσΞΑΞ≥ΞΙΞ»ΛβΑψΛΠΓΘ
œΔΖκ
«δΨεΙβΛΥάξΛαΛκΘ…Θ‘Ξ≥ΞΙ
Ξ»»φΈ®ΛœΓΔΘΌΘΝΘ”Λ§ΑλΓσ
ΛράΎΛκΞλΞΌΞκΛ ΛΈΛΥ¬–ΛΖΓΔΘΥΘΉΘ≈Λœ
ΤσΓσΛρΡΕΛ®ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛΈ
Τ≥ΤΰΛρΥή≥ ≤ΫΛΖΛΤΗΚ≤ΝΫΰΒ―»ώΛ Λ…Λ§
ΥΡΛύΤσΓΔΜΑ«·ΗεΛΥΛœΓΔΛΒΛΙΛ§ΛΥΘΌΘΝ
Θ”ΛΈΞ≥ΞΙΞ»»φΈ®ΛβΙβΛόΛκΓΘ
ΛΫΛλΛ«Λβ
ΑλΓΠΗόΓσΡχ≈ΌΛΔΛλΛ–Υΰ¬≠Λ«Λ≠ΛκΜ≈Ν»
ΛΏΛρΙΫΟέΛ«Λ≠ΛκΛ»Τ±Φ“ΛœΛΏΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΘ
ΌΘΝΘ”Λ«Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΡΙΛρΧ≥Λα
ΛκΤΘΑφΥ°…ΉΦΙΙ‘ΧρΑςΛœΓΔΓ÷≈ωΦ“ΛΈΘ…Θ‘
¥…ΆΐΛΈΤΟΡßΛœΓΔΞΖΞΙΞΤΞύΛρΟ¥≈ωΛΙΛκ
Φ“ΑςΛΈΩτΛ§»σΨοΛΥΨ·Λ ΛΛΛ»Λ≥ΛμΓΘ
ΦΪ
ΝΑΛ«ΩΆΚύΛρΑιΛΤΛΤΞΖΞΙΞΤΞύΛρ≥Ϊ»·ΛΙΛκ
ΛΈΛ«ΛœΛ Λ·ΓΔ≥Α…τΛΈάλΧγ≤»ΛδΞ―ΞΟΞ±
ΓΦΞΗΛρ≥ηΆ―ΛΖΛΩΛέΛΠΛ§ΓΔΟΜ¥ϋ≈ΣΛΥΙβ
≈ΌΛ ΞΒΓΦΞ”ΞΙΛρΦθΛ±ΛιΛλΛκΓΘ
Ζκ≤Χ≈Σ
ΛΥΞ»ΓΦΞΩΞκΞ≥ΞΙΞ»ΛβΑ¬Λ·ΆόΛ®ΛιΛλΛκΓΉ
Λ»άβΧάΛΙΛκΓΘ
ΓΓΗΫΚΏΛΈΘΌΘΝΘ”ΛœΓΔΙώΤβ≥ΑΛ«ΛόΛΟΛΩ
Λ·ΑέΛ ΛκΤσΖœ≈ΐΛΈ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΛρ Μ
Ά―ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΤϋΥήΙώΤβΛ«ΛœΦΪΦ“≥Ϊ»·
ΛΖΛΩΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛρΜ»ΛΛΓΔ≥Λ
≥ΑΛ«ΛœΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛρΞΌΓΦΞΙΛΥΚνΛξΙΰΛσ
ΛάΓ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘Θ≈ΘΆΘ≤ΓΉΛρΝ¥ΑηΛΥ≈Η≥Ϊ
ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
Φ“≥ΑΜώΗΜΛρ≥ηΆ―ΛΖΛΤΡψΞ≥ΞΙΞ»Λ«≥Ϊ»·ΓΠ±ΩΆ―
40≤·≈ξΛΗΛκΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΧδΛοΛλΛκΩΩ≤Ν
ΆΙΝΞΙ“ΕθΞΒΓΦΞ”ΞΙ
ΓΓΞΔΞΠΞ»ΞΫΓΦΞΖΞσΞΑΟφΩ¥ΛΈ≥Ϊ»·¬Έά©Λ»Ξ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΞΫΞ’Ξ»ΛΈά―ΕΥ≥ηΆ―ΛΥΛηΛΟΛΤΓΔITΛΈ
ΞμΓΦΞ≥ΞΙΞ»±Ω±ΡΛρΦ¬ΗΫΛΖΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΦΓ¥ϋ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷YUNASΓΉΛ«ΛœΛ≥ΛΈ ΐΩΥΛρ
ΛΒΛιΛΥ≈ΑΡλΛΖΓΔ≈ξΜώ≥έ40≤·±ΏΛ«άΛ≥Π≈ΐΑλΞΖΞΙΞΤΞύΛρΤ≥ΤΰΛΙΛκΖΉ≤ηΛάΓΘ
ΕΞΙγ¬ΨΦ“
ΛΥ»φΛΌΛκΛ»≥ Ο ΛΥΨ·Λ ΛΛIT≈ξΜώΛ«ΓΔΛ…Λ≥ΛόΛ«¥Αά°≈ΌΛΈΙβΛΛΞΖΞΙΞΤΞύΛρΙΫΟέΛ«Λ≠Λκ
ΛΈΛΪΟμΧήΛΥΟΆΛΙΛκΓΘ
ΦΙΙ‘ΧρΑςΛΈΤΘΑφΥ°…ΉΨπ σΞΖΞΙ
ΞΤΞύ…τΡΙ
Γ‘±η≥ΉΓ’ΤϋΥήΛ»ΛΫΛλΑ ≥ΑΛΈΟœΑηΛ«ΓΔΛόΛΟΛΩΛ·ΑέΛ Λκ2ΡΧΛξΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛρΜ»ΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΙώΤβΛΈ
¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷ECHOΓΉΛœΛΙΛΌΛΤΦΪΦ“≥Ϊ»·Λ«ΓΔ1991«·ΛΈΆΔΤΰΞΖΞΙΞΤΞύ≤‘ΤΑΛρ»ιάΎΛξΛΥΓΔ
94«·ΆΔΫ–ΞΖΞΙΞΤΞύΓΔ98«·≥ΛΨεΞΖΞΙΞΤΞύΛ»Ο ≥§≈ΣΛΥΒΓ«ΫΛράΑΛ®ΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΛΫΛλΛΨΛλΛΥΤ»Έ©
ΛΖΛΩΞΖΞΙΞΤΞύΛράή¬≥ΛΖΛΤΓ÷ECHOΓΉΛ»ΝμΨΈΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓ≥Λ≥ΑΛ«ΛœΓΔ87«·ΛΥΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛΈΓ÷YASTEMΓΉΛρ ΤΙώΛ«ΫιΛαΛΤ≤‘Τ·ΛΖΓΔ13ΞΪΙώ11ΥΓΩΆ
ΛόΛ«Τ≥ΤΰΛΖΛΩΓΘ
¬≥ΛΛΛΤ96«·ΛΪΛιΤ≥ΤΰΛΖΛΩΗεΖ―ΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΛœΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗ≥ηΆ―ΛΥ ΐΩΥΛρ≈Ψ
¥ΙΛΖΓΔ±―ΙώάΫΛΈΞΫΞ’Ξ»ΛρΞΌΓΦΞΙΛΥΩΖΛΩΛΥΓ÷YASTEM2ΓΉΛρ≥Ϊ»·ΓΘ
άΛ≥Π≥ΤΟœΛ«≤‘ΤΑΛΒΛΜΛΩΓΘ
ΗΫΚΏΓΔάΛ≥Π5ΕΥΓ ΤϋΥήΓΠ≤ΛΫΘΓΠΤνΥΧΞΔΞαΞξΞΪΓΠΤνΞΔΞΗΞΔΓθΞΣΞΜΞΔΞΥΞΔΓΠ≈λΞΔΞΗΞΔΓΥΛΈΛΠΛΝΤϋΥήΑ
≥ΑΛœΓ÷YASTEM2ΓΉΛ«≈ΐΑλΚ―ΛΏΓΘ
¬ΨΛΥ≤ώΖΉΛδΡΧ¥ΊΓΔΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙΛΈ §ΧνΛ«ΛœΓΔ¥π¥¥ΞΖΞΙ
ΞΤΞύΛΈΒΓ«ΫΛ« δΛ®Λ ΛΛΒΓ«ΫΛρΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛδΦΪΦ“≥Ϊ»·ΞΖΞΙΞΤΞύΛ« δ¥ΑΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓ2005«·4ΖνΛΥ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΝ¥ΧΧ≈ΣΛ ΚΰΩΖΛρΖηΟ«ΓΘ
2«·ΆΨΛξΛΪΛ±ΛΤΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύ
Γ÷YUNASΓΉΛΈΨρΖοΛρΒΆΛαΓΔ07«·7ΖνΛΥΞΛΞσΞ…ΛΥΥήΦ“ΛρΟ÷Λ·Ξ’Ξ©ΓΦΞΫΞ’Ξ»Φ“Γ 4SΦ“ΓΥΛΈΞ―ΞΟ
Ξ±ΓΦΞΗΛράΛ≥Π≈ΐΑλΞΖΞΙΞΤΞύΛ»ΛΖΛΤΚΈΆ―ΛΙΛκΛ≥Λ»ΛρΖηΛαΛΩΓΘ
08«·4ΖνΛΥ≤ΛΫΘΛΈ1ΥΓΩΆΛ«ΞΤ
ΞΙΞ»Τ≥ΤΰΛΖΓΔ12«·3ΖνΛόΛ«ΛΥάΛ≥Π≈Η≥ΪΛρΫΣΛ®Λκ ΐΩΥΓΘ
ΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛΊΛΈ≈ξΜώ≥έΛœ40≤·
±ΏΛρΆΫΡξΛΖΛΤΛΛΛκΓ ΥήΦ“ΞΖΞΙΞΤΞύ…τΧγΛΈΩΆΖο»ώΛœΫϋΛ·ΓΥΓΘ
ΔΓΥήΦ“Ν»ΩΞΓΓΓΓΨπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΛΥΧσ40ΩΆΛ§Ϋξ¬ΑΓΘ
…τΤβ
ΛΥΛœ4ΛΡΛΈ≤ίΛ§ΛΔΛξΓΔΤβΧθΛœ?¥π¥¥…τ §ΛΈ ίΦιΛ Λ…ΛρΟ¥
≈ωΛΙΛκΓ÷¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύ≤ίΓΉ10ΩΆΓΔ?ΞΆΞΟΞ»ΞοΓΦΞ·ΛδΟΦ
ΥωΛ Λ…ΛρΟ¥≈ωΛΙΛκΓ÷ΞΖΞΙΞΤΞύ±ΩΆ―≤ίΓΉ10ΩΆΓΔ?±ΡΕ»ΜΌ
±γΛ Λ…ΛρΟ¥≈ωΛΙΛκΓ÷WebΞΫΞξΞεΓΦΞΖΞγΞσ≤ίΓΉ11ΩΆΓΔ?
ΦΓ¥ϋ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύYUNASΛράλΧγ≈ΣΛΥΦξ≥ίΛ±ΛκΓ÷ΞΛΞΈ
ΞΌΓΦΞΖΞγΞσΩδΩ ≤ίΓΉ6ΩΆΓΔ¬ΨΛ»Λ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΒΛιΛΥΥήΦ“
ΛΈΨπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΛΪΛιΛΈΫ–ΗΰΦ‘Λ»ΛΖΛΤ≥Λ≥ΑΓ ΤϋΥήΑ ≥ΑΛΈ
4ΕΥΛΣΛηΛ”ΟφΙώΓΥΛΥΖΉ9ΩΆΛ§ΟσΚΏΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΔΓΨπ σΜ“≤ώΦ“ΓΓΓΓΛ ΛΖ
ΞμΓΦΞ≥ΞΙΞ»±Ω±Ρ
DECEMBER 2007ΓΓΓΓ52
ΞΔΞΠΞ»ΞΫΓΦΞΖΞσΞΑ
±ΩΆ―ΛΈ¬γ»ΨΛρΤΟΡξΛΈΘ…Θ‘ΞΌΞσΞάΓΦΛΥ
ΞΔΞΠΞ»ΞΫΓΦΞΖΞσΞΑΛΖΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΛόΛΩΓΔΑλ
Ε廧ΦΖ«·ΛΥΫιΛαΛΤ≥Λ≥ΑΥΓΩΆΛΥΤ≥ΤΰΛΖ
ΛΩ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘Θ≈ΘΆΓΉΛ«
ΛœΓΔΩΤ≤ώΦ“Λ«ΛΔΛκΤϋΥήΆΙΝΞΛΈΨπ σΜ“
≤ώΦ“Λρ≥ηΆ―ΛΖΛΩΓΘ
ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΦΪΦ“≥Ϊ
»·Λ§≈ωΛΩΛξΝΑΛάΛΟΛΩΜΰ¬εΛΥΩΆΚύΛρ ζ
Λ®ΙΰΛόΛΚΓΔΨπ σ…τΧγΛρ §Φ“≤ΫΛΙΛκ…§
ΆΉά≠Λβ«ωΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ¬ηΤσάΛ¬εΛΈ≥Λ≥ΑΞΖΞΙΞΤΞύΛ»ΛΖΛΤΕε
œΜ«·ΛΪΛιΤ≥ΤΰΛΖΜœΛαΛΩΓ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘Θ≈
ΘΆΘ≤ΓΉΛ«ΛœΓΔ≥Λ≥ΑΒρ≈άΛΈΒόΝΐΛδΕ»Χ≥
ΤβΆΤΛΈ≥»¬γΛΥ≥Ϊ»·Λ§Ρ…ΛΛΛΡΛΪΛ ΛΛΛ»
ΛΛΛΠΆΐΆ≥ΛΪΛιΓΔΛΫΛλΛόΛ«ΛΈΦΪΦ“≥Ϊ»·
ΛρΟ««ΑΓΘ
±―ΙώάΫΛΈΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛρΚΈΆ―
ΛΖΛΩΓΘ
Λ≥ΛΈΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛœΓ÷≤ΛΫΘΛΈ¬γ
ΦξΞ’Ξ©ΞοΓΦΞάΓΦΛΊΛΈΤ≥ΤΰΦ¬ά”Λ§Υ≠…Ό
Λ«Ω°Άξά≠Λ§ΙβΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈ»Τ
Ά―ά≠Λδ≥»ΡΞά≠Λβ…Ψ≤ΝΛ«Λ≠ΛΩΓΉΛ»Ψπ σ
ΞΖΞΙΞΤΞύ…τΓΠΞΛΞΈΞΌΓΦΞΖΞγΞσΩδΩ ≤ίΛΈ
ΑΛΫ–άνΩ≠Αλ≤ίΡΙΛœΩΕΛξ ÷ΛκΓΘ
ΓΓΕεœΜ«·ΛΈ ΤΙώΥΓΩΆΛΊΛΈΤ≥ΤΰΛρ»ιάΎ
ΛξΛΥΓΔΘΌΘΝΘ”ΛœΛ≥ΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛρΞΔΞΗ
ΞΔΓΔ≤ΛΫΘΛΥΛβΤ≥ΤΰΛΖΛΩΓΘ
Γ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘
Θ≈ΘΆΘ≤ΓΉΛΥΛœΙώΛ¥Λ»ΛΈΕ»Χ≥ΛΥ¬–±ΰΛ«
Λ≠ΛκΞΣΞΉΞΖΞγΞσΒΓ«ΫΛ§ΛΔΛξΓΔΞΌΓΦΞΙΛ»
Λ ΛκΞΉΞμΞΑΞιΞύΛœ ―Λ®ΛΚΛΥ≥ΤΟœΛΈΗΡ Χ
ΞΥΓΦΞΚΛρ»Ω±«Λ«Λ≠ΛκΓΘ
ΓΓΛόΛΩΓΔ≤ώΖΉΛδΡΧ¥ΊΛΈΛηΛΠΛΥΓΔ≥ΤΙώ
Λ«άλΆ―ΞΖΞΙΞΤΞύΛρ≥ηΆ―ΛΖΛΩΛέΛΠΛ§Ά≠
ΆχΛ Ε»Χ≥ΛΥΛΡΛΛΛΤΛœΗΡ ΧΛΥ≥Α…’Λ±ΛΖ
ΛΩΓΘ
Τ≥ΤΰΛδ±ΩΆ―ΜΌ±γΛΥΛβΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗ
ΛΈ≥Ϊ»·ΗΒΛρ≥ηΆ―ΛΖΛ Λ§ΛιΓΔΤϋΥήΑ ≥Α
ΛΈΤσ»§ΞΪΙώΓ ΤσΦΖΥΓΩΆΓΥΛρΓ÷ΘΌΘΝΘ”
Θ‘Θ≈ΘΆΘ≤ΓΉΛ«≈ΐΑλΛΖΛΤΛΛΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΤβ≥ΑΛ«ΑέΛ ΛκΤσΡΧΛξΛΈΘ…Θ‘¥…ΆΐΛρ
Φξ≥ίΛ±ΛΤΛ≠ΛΩΛ≥Λ»Λ§ΓΔΙώΤβΛ«Γ»¥ί≈ξ
Λ≤Γ…ΛΥ¥ΌΛκΛΈΛβΥ…ΛΛΛ«Λ≠ΛΩΓΘ
ΝΑΫ“ΛΖ
ΛΩΡΧΛξΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛœ≥Α…τΞΌΞσΞάΓΦ
ΛρΜ»ΛΟΛΤΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛΖΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈΒΓ«Ϋ
Λδ≥Ϊ»·Ξ≥ΞΙΞ»Λ§≤Λ ΤΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛ»Λ…ΛΠ
ΑψΛΠΛΈΛΪΛœΘΌΘΝΘ”ΦΪΩ»Λ§ΛηΛ·Άΐ≤ρΛΖ
ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛάΛΪΛιΛ≥ΛΫΡΙ«·ΛΈΦηΑζ¥ΊΖΗ
ΛΥΛΔΛκΘ…Θ‘ΞΌΞσΞάΓΦΛ»ΛβΓΔΑλ ΐ≈ΣΛ
ΑΆ¬Η¥ΊΖΗΛ«ΛœΛ ΛΛΓ÷Ξ―ΓΦλΠΓΦΞΖΞΟΞΉ
Λ§ά°Έ©ΛΖΛΤΛΛΛκΓΉΛΈΛάΛ»ΛΛΛΠΓΘ
Ν¥ΧρΑςΛ»Ν¥…τΡΙΛρ¥§Λ≠ΙΰΛΏΓΓ≤ΘΟ«≈ΣΛ ≥Ϊ»·¬Έά©ΛρΙΫΟέΓΓ
ΓΓΘ
ΌΘΝΘ”ΛœΦΪ §ΛΩΛΝΛΈ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύ
ΛΥΛΣΛΣΛύΛΆΥΰ¬≠ΛΖΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΛάΛ§≥Ϊ»·
ΛΪΛιΫΫ«·ΕαΛ·Ζ–ΛΝΓΔΛΒΛΙΛ§ΛΥΗΫΨλΛΈ
ΆΉΥΨΛΥ±ΰΛ®Λ≠ΛλΛ ΛΛΧΧΛ§Ϋ–ΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
≈Ό
Ϋ≈Λ ΛκΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛΈΦξΡΨΛΖΛβΗ¬≥Π
ΛΥΟΘΛΖΛΤΛΣΛξΓΔΛΛΛΚΛλΛœ¬γΞ ΞΩΛρΩΕ
ΛκΛΟΛΤΛΙΛΌΛΤΛρΗΪΡΨΛΒΛ Λ±ΛλΛ–Λ Λι
Λ ΛΛΛ≥Λ»Λ§ΧάΛιΛΪΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΓΜΗό«·ΜΆΖνΛΥΓΔΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΝ¥ΧΧΚΰ
ΩΖΛρΩ ΛαΛκΛΩΛαΛΥΓ÷Θ…Θ‘άοΈ§Α―Ας≤ώΓΉ
Λρ»·¬≠ΛΖΛΩΓΘ
Α―Ας≤ώΛœΛόΛΚ»Ψ«·¥÷Λέ
Λ…»ώΛδΛΖΛΤΓΔΘ…Θ‘≥ηΆ―ΛΈΗΫΨθΛρ≈ΑΡλ
§άœΛΖΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΤβΆΤΛœΓΔΞΖΞΙΞΤΞύΙΫ
ά°ΛδΒΓ«ΫΓΔ≈ξΜώ≥έΓΔΛΒΛιΛΥΛœΖ–Κ―ά≠
Λδ ίΦιά≠ΓΔΕΞΙγ¬ΨΦ“Λ»ΛΈ»φ≥”Λ»ΛΛΛΟ
ΛΩ…Ψ≤ΝΛΥΛόΛ«ΒΎΛσΛάΓΘ
ΛΫΛΖΛΤΖ–ΆΐΛδ
ΝμΧ≥ΓΔ±ΡΕ»ΜΌ±γΞΖΞΙΞΤΞύΛ Λ…Θ…Θ‘Λ§
ΆμΛύΕ»Χ≥ΛΙΛΌΛΤΛρ¬–ΨίΛ»ΛΙΛκΓ÷Ρ¥ΚΚ
σΙπΫώΓΉΛρΛόΛ»ΛαΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈ≥ηΤΑΛρΗεΡ…ΛΛΛΙΛκΛηΛΠΛΥΓ÷Ξ”
ΞΗΞΆΞΙΆΉΖοΞοΓΦΞ≠ΞσΞΑΞΑΞκΓΦΞΉΓΉΛβΤΑ
Λ≠Ϋ–ΛΖΛΩΓΘ
Λ≥ΛΝΛιΛΥΛœΞφΓΦΞΕΓΦ¬ΠΛΈ¬ε
…ΫΦ‘Λ§ΫΗΛόΛξΓΔΦΓ¥ϋ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈ
ΙΫΟέΛΥΗΰΛ±ΛΤ≤ΰ≥ΉΞΤΓΦΞόΛράωΛΛΫ–ΛΖ
ΛΩΓΘ
ΥήΦ“ΛΈ≤ίΡΙΞ·ΞιΞΙΛ§ΟφΩ¥ΛΥΛ ΛΟ
ΛΤΓΔ≥ΑΜώΖœΞ≥ΞσΞΒΞκΞΩΞσΞ»ΛΈΜΌ±γΛβΦθ
Λ±Λ Λ§ΛιΒΡœάΛρΫ≈ΛΆΛΩΓΘ
Ζκ≤ΧΛœΓΔΘ…
Θ‘ΛρΜ»ΛΟΛΩΞ”ΞΗΞΆΞΙάοΈ§ΛδΗήΒ“ΞΒΓΦΞ”
ΞΙΓΔΦ¬ά”¥…ΆΐΛ Λ…ΛΥ¥ΊΛΙΛκΓ÷Θ…Θ‘ΆΉ
Ζο σΙπΫώΓΉΛ»Λ ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΝ¥άΛ≥ΠΛΈΫΨΕ»ΑςΛρ¬–ΨίΛ»ΛΖΛΩΞΠΞ®
Ξ÷ΛΈΞΔΞσΞ±ΓΦΞ»ΛδΓΔΤΘΑφΦΙΙ‘ΧρΑςΛΥ
ΛηΛκΝ¥ΧρΑςΛΊΛΈΞ“ΞΔΞξΞσΞΑΛβΦ¬ΜήΛΖ
ΛΩΓΘ
Κ«ΫΣ≈ΣΛΥΛœΓΜœΜ«·ΕεΖνΛΥΓΔΛ≥Λλ
ΛιΛΈ≥ηΤΑΛΈΫΗ¬γά°Λ»ΛΖΛΤΓ÷ΦΓ¥ϋ¥π¥¥
ΞΖΞΙΞΤΞύΓΓΞΑΞιΞσΞ…Ξ«ΞΕΞΛΞσΡσΑΤΫώΓΉ
ΛρΚνά°ΓΘ
Λ≥Λ≥ΛΥΛœΞœΓΦΞ…ΛΈΙΫά°Λδ≈ξ
ΜώΕβ≥έΛ Λ…ΓΔΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛΥ¥ΊΛΙΛκ
ΛΔΛιΛφΛκΨπ σΛ§άΙΛξΙΰΛόΛλΛΩΓΘ
ΓΓΑλœΔΛΈ≥ηΤΑΛΈΛ ΛΪΛ«Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύ
…τΛœΓΔΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛΈ≥Ϊ»·ΛρΝ¥Φ“≈Σ
Λ ΞΛΞΌΞσΞ»ΛΥΙβΛαΛΤΛΛΛ≥ΛΠΛ»…εΩ¥ΛΖΛΡ
Λ≈Λ±ΛΩΓΘ
Γ÷≈ωΦ“ΛΈΨπ σΞΖΞΙΞΤΞύΛœΓΔΛΫ
ΛλΛ ΛξΛΥΨεΦξΛ·ΛδΛξΛ Λ§ΛιΛβΓΔΦ“Τβ
ΓΓΤϋΥήΗλ¬–±ΰΛΈΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛ§ΞΣΞΎ
ΞλΓΦΞΖΞγΞσΕ»Χ≥ΛρΛ≠ΛαΚΌΛΪΛ·ΞΒΞίΓΦΞ»
ΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛΥ¬–ΛΖΓΔΓ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘Θ≈ΘΆ
Θ≤ΓΉΛœ±―ΗλΛάΛ±ΛρΜ»ΛΠΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΓΔ≥Τ
ΙώΛΈΗΡ ΧΜωΨπΛηΛξΛβ…ΗΫύ≤ΫΛρΆΞάηΛΖ
ΛΤ≈Η≥ΪΛΖΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
Λ≥ΛλΛιΛρΆηΫ’ΛΪΛι
ΫγΦΓΓΔΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛΥΟ÷Λ≠¥ΙΛ®ΓΔΙώ
Τβ≥ΑΛ«ΑέΛ ΛκΞΖΞΙΞΤΞύΛρΜ»ΛΛ §Λ±Λκ¬Έ
ά©ΛΥΫΣΜΏ…δΛρ¬«ΛΡΓΘ
ΓΓΘ
ΌΘΝΘ”ΛΈάΛ≥Π≈ΐΑλΞΖΞΙΞΤΞύΛ§ΜΉœ«
ΡΧΛξΕΞΝηΈœΛρ»·¥χΛΙΛκΛ…ΛΠΛΪΛœΓΔ≥Η
Λρ≥ΪΛ±ΛΤΛΏΛ Λ±ΛλΛ– §ΛΪΛιΛ ΛΛΓΘ
ΛΫ
ΛλΛ«ΛβΓΔΙΞΕ»ά”Λρ¬≥Λ±ΛκΘΌΘΝΘ”Λ»ΘΥ
ΘΉΘ≈ΛΈΘ…Θ‘άοΈ§Λ§ΓΔΞΔΞΠΞ»ΞΫΓΦΞΖΞσΞΑ
Λ»ΦΪΝΑΦγΒΝΛΈΑψΛΛΛρΛΒΛιΛΥΝ·ΧάΛΥΛΖ
ΛηΛΠΛ»ΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛœ¥÷ΑψΛΛΛ ΛΛΓΘ
Θ…Θ‘Μ“≤ώΦ“ΛΙΛιΜΐΛΩΛΚΓΓΤϋΥήΈ°ΛΈΦΪΝΑΦγΒΝΛΥΒςΈΞΓΓ
ΓΓΙώΤβΛΈ¬γΦξ ΣΈ°¥κΕ»ΛΈ¬ΩΛ·Λ§ΞΑΞκ
ΓΦΞΉΤβΛΥΘ…Θ‘Μ“≤ώΦ“Λρ ζΛ®ΛΤΛΛΛκΛΈ
ΛΥ¬–ΛΖΓΔΘΌΘΝΘ”ΛΥΛœΛΫΛλΛ§Λ ΛΛΓΘ
Ε»
≥ΠΚ«¬γΦξΛΈΤϋΥήΡΧ±ΩΞΑΞκΓΦΞΉΛ«ΛœΤϋ
ΡΧΝμΙγΗΠΒφΫξΛ§Θ…Θ‘Μ“≤ώΦ“ΛΥ¬εΛοΛκ
Χρ≥δΛρΟ¥ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛόΛΩΘΥΘΉΘ≈ΛΈΨλ
ΙγΛœΓΔΙώΤβΜ“≤ώΦ“ΛœΛ ΛΛΛ§ΓΔ≥Λ≥ΑΛΥ
¬γΒ§ΧœΛ ≥Ϊ»·ΓΠ±ΩΆ―Μ“≤ώΦ“ΛρΙΫΛ®ΛΤ
ΛΛΛκΓΘ
ΘΌΘΝΘ”ΛΈΛηΛΠΛΥΥήΦ“ΛΈΘ…Θ‘…τ
ΧγΛάΛ±Λ»ΛΛΛΠΝ»ΩΞ¬Έά©ΛœΡΝΛΖΛΛΓΘ
ΓΓΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛΖΛΤΛ≠ΛΩΙώΤβΛΈ¥π¥¥ΞΖΞΙ
ΞΤΞύΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛ«ΓΔΘΌΘΝΘ”Λœ≥Ϊ»·ΓΠ
Ν¥Φ“ΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»
53ΓΓΓΓDECEMBER 2007
DECEMBER 2007ΓΓΓΓ54
Λ«Ξ÷ΞιΞΟΞ·ΞήΞΟΞ·ΞΙ
ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛΩΧΧΛ§ΛΔ
ΛκΓΘ
ΩΖΛΖΛΛΞΖΞΙΞΤΞύ
ΛΈΙΫΟέΛ«ΛœΓΔ≥ßΛΥΤ±
ΛΗ≈Ύ…ΕΛΥΨεΛ§ΛΟΛΤΛβ
ΛιΛΠ¬Έά©ΛρΚνΛΟΛΩΓΉ
Γ ΤΘΑφΦΙΙ‘ΧρΑςΓΥ
ΓΓΙώΤβΛ«ΛβΦΪΦ“≥Ϊ
»·ΛΪΛιΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗ≥η
Ά―ΛΥΦ¥¬≠ΛρΑήΛΙΛ»ΛΛ
ΛΠΛ≥Λ»ΛœΓΔΛ≥ΛλΛόΛ«
ΛœΕ»Χ≥ΛΥΙγΛοΛΜΛΤΜ≈
Ν»ΛΏΛρΚνΛΟΛΤΛΛΛΩΛΈ
Λ§ΓΔΚΘΗεΛœΕ»Χ≥ΛΈ
ΛδΛξ ΐΛρΞΖΞΙΞΤΞύΛΥ
ΙγΛοΛΜΛκΨλΧΧΛ§ΝΐΛ®
ΛκΛ≥Λ»ΛρΑ’ΧΘΛΖΛΤΛΛ
ΛκΓΘ
ΛΖΛΪΛβάΛ≥Π…Η
ΫύΞΖΞΙΞΤΞύΛ»ΛβΛ Λλ
Λ–ΓΔΤϋΥήΛΈΤΟΦλΜω
ΨπΛρΞΖΞΙΞΤΞύΛΥ»Ω±«
ΛΒΛΜΛκΛΈΛœΗ¬≥ΠΛ§ΛΔ
ΛκΓΘ
Λ≥ΛΈ ―≤ΫΛρ±Ώ≥ξ
ΛΥΨηΛξάΎΛκΛΥΛœΓΔΛΙ
ΛΌΛΤΛΈ¥ΊΖΗΦ‘ΛΈΑ’
Φ±≤ΰ≥ΉΛ§…‘≤ΡΖγΛά
ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΓ÷Ο·ΛΪΛ§ΨΓΦξΛΥΚν
ΛΟΛΩΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΛœΞφ
ΓΦΞΕΓΦΛœΜ»ΛΟΛΤΛ·Λλ
Λ ΛΛΓΘ
ΞφΓΦΞΕΓΦΦΪΩ»
Λ§Φγ¬ΈΛΥΛ Λκ…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΓΉΛ»ΤΘΑφΦΙ
Ι‘ΧρΑςΛœΕ·Ρ¥ΛΙΛκΓΘ
ΛΫΛΈΗεΓΔΓ÷Θ…Θ‘άο
Έ§Α―Ας≤ώΓΉΛœΓ÷Θ…Θ‘ΞΛΞΈΞΌΓΦΞΖΞγΞσΓΠ
ΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΓΠΞ≥ΞΏΞΟΞΤΞΘΓΦΓΉΛ»Λ ΛΟ
ΛΩΓ ΩόΘ±ΓΥΓΘ
Ξ≥ΞΏΞΟΞΤΞΘΓΦΛΈΞ»ΞΟΞΉΛœ
Φ“ΡΙΛ§Χ≥ΛαΓΔ ΗΜζΡΧΛξΝ¥Φ“≈ΣΛ ΦηΛξ
Ν»ΛΏΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Λ≥ΛλΛόΛ«ΛΈΟΏά―ΛρΑζΛ≠Ζ―Λ°ΓΓάΛ≥Π≈ΐΑλΞΖΞΙΞΤΞύΧήΜΊΛΙΓΓ
ΓΓΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛΈΝ¥ΧΧ≥ηΆ―ΛœΓΔΘΌΘΝΘ”
ΛΈΘ…Θ‘άοΈ§ΛΥΛ»ΛΟΛΤΛβΫ≈ΆΉΛ ΐΩΥ≈Ψ
¥ΙΛάΛΟΛΩΓΘ
≈ωΫιΛœΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛρΞΌ
ΓΦΞΙΛΥ±―Ηλ»«ΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛρΦΪΦ“≥Ϊ»·
ΛΙΛκΝΣ¬ρΜηΛβΗΓΤΛΛΖΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΘ…
Θ‘ΞΌΞσΞάΓΦΛΥΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛΥΛΡΛΛΛΤΜνΜΜ
ΛΖΛΤΛβΛιΛΟΛΩΛ»Λ≥ΛμΓΔ≥Ϊ»·¥ϋ¥÷ΛœΞ―
ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛηΛξΗό≥δΡΙΛ·Λ ΛξΓΔ≈ξΜώ≥έ
ΛβΤσ«ήΕαΛ·Λ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΠΛ≥Λ»Λ§»ΫΧά
ΛΖΛΩΓΘ
Λ≥ΛλΛ«ΦΪΦ“≥Ϊ»·Λ»ΛΛΛΠΝΣ¬ρΜη
ΛœΨΟΛ®ΛΩΓΘ
ΓΓΖκΕ…ΓΔΗθ δΛ»ΛΖΛΤΜΑΦοΈύΛΈΞ―ΞΟΞ±
ΓΦΞΗΛ§ΜΡΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛλΛΨΛλ≤ΛΫΘΓΔΞΔΞΗ
ΞΔΓΔΞΛΞσΞ…ΛΥΥήΦ“ΛρΙΫΛ®ΛκΞΖΞΙΞΤΞύ≤ώ
Φ“Λ§ΡσΕΓΛΙΛκΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛάΛΟΛΩΓΘ
Λ≥ΛΈ
ΟφΛΪΛιΘΌΘΝΘ”ΛœΓΔΞΛΞσΞ…ΛΥΥήΦ“ΛρΟ÷
Λ·Ξ’Ξ©ΓΦΞΫΞ’Ξ»Φ“Γ Θ¥Θ”Φ“ΓΥΛΈΞ―ΞΟΞ±
ΓΦΞΗΛρΝΣΛσΛάΓΘ
ΑλΛΡΛΈ≤Ώ ΣΛρΑλΛΡΛΈ
ΞλΞ≥ΓΦΞ…Λ«¥…ΆΐΛΙΛκ?ΞοΞσΞ«ΓΦΞΩΞΌΓΦ
ΞΙ?ΛΈΜ≈Ν»ΛΏΛΥΛηΛΟΛΤΓΔ»·Οœ¬ΠΛ«Τΰ
ΈœΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛρΟεΟœ¬ΠΛ«ΛΙΛΑΛΥΜ»Λ®
ΛκΛ≥Λ»Λ Λ…Λρ…Ψ≤ΝΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΓ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘Θ≈ΘΆΘ≤ΓΉΛ«ΡΙΛ·ΦηΑζ¥ΊΖΗ
ΛΥΛΔΛΟΛΩ±―ΙώΛΈΞΖΞΙΞΤΞύ≤ώΦ“Λ§ΓΔΦ¬Λœ
≈ω≥Κ…τΧγΛ¥Λ»Θ¥Θ”Φ“ΛΥ«ψΦΐΛΒΛλΛΤΛΛ
ΛΩΛ»ΛΛΛΠΜωΨπΛβ¬γΛ≠ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΛΡΛόΛξ
Θ¥Θ”Φ“ΛΥΛœΓΔΓ÷ΘΌΘΝΘ”Θ‘Θ≈ΘΆΘ≤ΓΉΛΈ
≥Ϊ»·Λ«ΫΫ«·ΆηΛΈ…’Λ≠ΙγΛΛΛ§ΛΔΛξΓΔΘΌ
ΘΝΘ”ΛΈΛ≥Λ»ΛρΛηΛ·ΟΈΛκΩΆΚύΛ§Ωτ¬ΩΛ·
ΚΏά“ΛΖΛΤΛΛΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΠΛΖΛΤΙϋ≥ ΛΈΗ«ΛόΛΟΛΩΦΓ¥ϋΞΖΞΙ
ΞΤΞύΛœΓΔΦ“ΤβΗχ γΛ«Γ÷ΘΌΘ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉ
Λ»ΧΩΧΨΛΒΛλΛΩΓΘ
ΗΫΜΰ≈άΛ«ΛœΛόΛά≥Ϊ»·
ΛΈ≈”ΨεΛάΛ§ΓΔΛ≥ΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛ§ΞΪΞ–ΓΦ
ΛΙΛκΕ»Χ≥ΈΈΑηΛœΖ–±Ρ¥…ΆΐΛΪΛι±ΡΕ»ΜΌ
±γΓΔΦ¬ά”¥…ΆΐΛΥΜξΛκΛόΛ«¬Ω¥τΛΥΛοΛΩ
ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Θ¥Θ”Φ“ΛΈΓ÷eTransΓΉΓ Ξ’
Ξ©ΞοΓΦΞ«ΞΘΞσΞΑΓΥΛδΓ÷elogΓΉΓ ΞμΞΗΞΙ
ΞΤΞΘΞ·ΞΙΓΥΓΔΓ÷eAccountsΓΉΓ ≤ώΖΉΓΥΛ»
ΛΛΛΟΛΩΞβΞΗΞεΓΦΞκΛρΝ»ΛΏΙγΛοΛΜΛΤΓΔΘΌ
ΘΝΘ”ΛΈ¬γ»ΨΛΈΕ»Χ≥ΛρΛόΛΪΛ Λ®ΛκΛηΛΠ
ΛΥΛΙΛκ ΐΩΥΛάΓ ΩόΘ≤ΓΥΓΘ
ΓΓΗΫΚΏΓΔ±―ΙώΛΥάΏΟ÷ΛΒΛλΛΩΘ¥Θ”Φ“ΛΈ
≥Ϊ»·Βρ≈άΛ«ΓΔ≈Ύ¬φΛ»Λ ΛκΞΖΞΙΞΤΞύΛρΒό
Ξ‘ΞΟΞΝΛ«ΙΫΟέΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΥήΦ“ΛΈΨπ σ
ΞΖΞΙΞΤΞύ…τΛΪΛιΛβΟ¥≈ωΦ‘Λ§ΡΙ¥ϋΫ–ΡΞ
ΛΖΛΤΛΣΛξΓΔΛ≥ΛΈΚνΕ»ΛΥΜ≤≤ΟΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΥΝΤ§Λ«ΛβΫ“ΛΌΛΩΛ»ΛΣΛξΓΔΛόΛΚΛœΆη«·
ΜΆΖνΛΥ≤ΛΫΘΛ«ΞΤΞΙΞ»Τ≥ΤΰΛΙΛκΓΘ
Λ≥Λ≥
Λ«Φ¬ΟœΗΓΨΎΛρΙ‘ΛΟΛΤ≈Ύ¬φΛρΚνΛξΙΰΛσ
ΛάΛΠΛ®Λ«ΓΔΑλΒΛΛΥάΛ≥Π≈Η≥ΪΛΥ¬«ΛΟΛΤ
Ϋ–ΛκΖΉ≤ηΛάΓΘ
Ξ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗ≥ηΆ―
Ωό1ΓΓΦ“ΡΙΛρΞ»ΞΟΞΉΛ»ΛΙΛκΝ¥Φ“≤ΘΟ«≈ΣΛ ΞΖΞΙΞΤΞύΚΰΩΖΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»IT Innovation
Project Committee
ΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΣΓΦΞ ΓΦ
ΜωΧ≥Ε…ΡΙ
Ξ”ΞΗΞΆΞΙΆΉΖο
ΞοΓΦΞ≠ΞσΞΑΞΑΞκΓΦΞΉΞξΓΦΞάΓΦ
≥ΤΕΥIT Ο¥≈ω
+
Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τ
ΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙΖ–ΆΐΟ¥≈ω
Ο¥≈ω
Ι“ΕθΓΠ≥ΛΨε
Ο¥≈ω
≥ΤΙώΕ»Χ≥
ΥήΦ“Ο¥≈ω
Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τ
ΞΛΞσΞ’Ξι
ΞΝΓΦΞύ
Technology
Quality Assurance
Technical Design
Development
Analysis
Functional Design
Technical Design
Technical Support
Implementation Support
Γ‘≥Λ≥ΑΤ≥ΤΰΓ’Γ‘ΤϋΥήΤ≥ΤΰΓ’
…ΗΫύ≤ΫΞκΓΦΞκ
ΗΓΤΛ §≤ ≤ώ
Ζ–Άΐ
ΞΝΓΦΞύ
ΆΔΤΰ
ΞΝΓΦΞύ
≥Λ≥Α
ΞΝΓΦΞύ
≤ΰΝ±ΆΉΖο
ΗΓΤΛ≤ώ
ΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙ
ΞΝΓΦΞύ
±ΡΕ»¬Έ
ΞΖΞΙΞΤΞύ≥Ϊ»·
Project Manager ΞοΓΦΞ≠ΞσΞΑΞΑΞκΓΦΞΉΞξΓΦΞάΓΦ
Project Sponsor
ΞΫΞ’Ξ»≥Ϊ»·≤ώΦ“
Γ Yusen TeamΓΥ
YAS
On-shore(U.K.)
Off-shore(India)
ΞΔΞΉΞξΞ±ΓΦΞΖΞγΞσ
ΞΝΓΦΞύ
Τ≥ΤΰΞΒΞίΓΦΞ»
ΞΝΓΦΞύ
55ΓΓΓΓDECEMBER 2007
ΟΠΓΠΦΪΦ“≥Ϊ»·
ΛΪΛόΛΪΛ Λ®ΛΚΓΔΙβ≈ΌΛ ΫηΆΐΛ§…§ΆΉΛ
Ξ±ΓΦΞΙΛ«ΛœάλΆ―ΞΫΞ’Ξ»ΛρΡ…≤ΟΛΙΛκ…§
ΆΉΛ§ΛΔΛκΓΘ
ΓΓ±ΡΕ»ΜΌ±γΞΖΞΙΞΤΞύΛβΓΔΛΛΛόΤϋΥήΛ«
ΧσΗόΓΜΦοΈύΛέΛ…Μ»ΛΟΛΤΛΛΛκΞΔΞΉΞξΞ±
ΓΦΞΖΞγΞσΛΈΛέΛ»ΛσΛ…ΛœΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛάΓΘ
Ψπ
σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΓΠΘΉΘεΘβΞΫΞξΞεΓΦΞΖΞγΞσ
≤ίΛΈ¬γάνΗΕ≥Ί≤ίΡΙΛœΓΔΓ÷ΞΠΞ®Ξ÷≤ΫΛΖΛΩ
Μ≈Ν»ΛΏΛΥ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΛΪΛιΞ«ΓΦΞΩΛρ
ΦηΛξΙΰΛΏΓΔΕ»Χ≥ΜΌ±γΛΈΛΩΛαΛΥ≥ηΆ―ΛΖ
ΛΤΛΛΛκΞ±ΓΦΞΙΛ§ΗΫΨθΛ«ΛβΛΪΛ ΛξΛΔΛκΓΘ
ΚΘΗεΛœΛ≥Λ≥ΛβΦξΡΨΛΖΛΖΛΤΛΛΛ·…§ΆΉΛ§
ΛΔΛκΓΉΛ»ΛΛΛΠΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΠΛΖΛΩ≤ί¬ξΛœΓΔ≈Ύ¬φΛ»Λ ΛκΓ÷ΘΌ
Θ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉΛ§Άη«·ΜΆΖνΛΥ≤ΛΫΘΛ«ΤΑΛ≠
Ϋ–ΛΖΛΤΛΪΛιΓΔΤ≥ΤΰΟœΑηΛΈΜωΨπΛΥ±ΰΛΗ
ΛΤ¬–ΫηΛΖΛΤΛΛΛ·Λ≥Λ»ΛΥΛ ΛκΓΘ
ΛΙΛΌΛΤ
Λ§ΖΉ≤ηΡΧΛξΛΥΩ ΛαΛ–ΓΔΤσΓΜΑλΑλ«·≈Ό
ΟφΛΥάΛ≥Π≈Η≥ΪΛρ¥ΑΈΜΛΙΛκΓΘ
±έΛΙΛΌΛ≠Κ«¬γΛΈΞœΓΦΞ…ΞκΛœΓΓΓ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛΪΛιΛΈΟΠΒ―ΓΓ
ΓΓΤϋΥήΛ«ΛβΆη«·ΟφΛΥΤ≥ΤΰΞΉΞμΞΗΞßΞ·
Ξ»ΛρΞΙΞΩΓΦΞ»ΛΖΛΤΓΔΧσΤσ«·¥÷Λ«ΫΣΛ®Λκ
ΐΩΥΛάΓΘ
ΛΩΛάΛΖΚΘ≤σΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΚΰΩΖΛ«
Κ«ΛβΤώΙ“Λ§ΆΫΝέΛΒΛλΛκΛΈΛœΓΔΛ≥ΛΈΤϋ
ΥήΛάΓΘ
ΤϋΥήΑ ≥ΑΛΈΟœΑηΛœΛΙΛ«ΛΥΓ÷ΘΌ
ΘΝΘ”Θ‘Θ≈ΘΆΘ≤ΓΉΛ»ΛΛΛΠΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛ«
≈ΐΑλΛΒΛλΛΤΛΣΛξΓΔΛηΛξΙβΒΓ«ΫΛΈΓ÷ΘΌ
Θ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉΛΥΟ÷Λ≠¥ΙΛ®ΛκΛ≥Λ»ΛΥΛΒΛέ
Λ…ΧΒΆΐΛœΛ ΛΛΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛΈ
ΞΖΞΙΞΤΞύΛΖΛΪΜ»ΛΟΛΤΛ≥Λ ΛΪΛΟΛΩΤϋΥή
ΛœΑψΛΠΓΘ
ΓΓΛΪΛφΛΛΛ»Λ≥ΛμΛΥΦξΛ§ΤœΛ·ΛηΛΠΛΥΚν
ΛξΙΰΛόΛλΓΔΛΖΛΪΛβΤϋΥήΗλ¬–±ΰΛΈΓ÷Θ≈
ΘΟΘ»ΘœΓΉΛρΓΔ±―Ηλ»«ΛΈ…ΗΫύΞ―ΞΟΞ±ΓΦ
ΞΗΓ÷ΘΌΘ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉΛΥάΎΛξ¥ΙΛ®ΛκΛ»Λ
ΛλΛ–ΓΔΗΫΨλΛ«ΗΆœ«ΛΛΛ§»·άΗΛΙΛκΛΈΛœ
»ρΛ±ΛιΛλΛ ΛΛΓΘ
Λ≥ΛΈ≈άΛœΤΘΑφΦΙΙ‘Χρ
ΑςΛβΈ®ΡΨΛΥ«ßΛαΛκΓΘ
Γ÷ΛδΛœΛξΛΔΛκ…τ
§ΛΈΒΓ«ΫΛœΚοΛιΛΕΛκΛρΤάΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛΈ
ΚίΛΥΛœΞφΓΦΞΕΓΦΛράβΤάΛΙΛκΛΈΛ«ΛœΛ
Λ·ΓΔ«ΦΤάΛΖΛΤΛβΛιΛοΛ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ
ΛΛΓΘ
Λ≥ΛλΛœΑλ¬γΜωΕ»ΛάΓΉ
ΓΓΩΖΛΩΛ ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΤ≥ΤΰΛρ±Ώ≥ξΛΥΩ
ΛαΛκΛάΛ±Λ«Λœ¬≠ΛξΛ ΛΛΓΘ
≤αΒνΛΥΞΖΞΙ
ΞΤΞύΛρΦΪΦ“≥Ϊ»·ΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«≥ΆΤάΛΖΛΤ
Λ≠ΛΩΞΈΞΠΞœΞΠΛρΞΦΞμΞξΞΜΞΟΞ»ΛΖΛΤΛΖ
ΛόΛΠΛΈΛβΙΆΛ®ΛβΛΈΛάΓΘ
Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύ
…τΓΠ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύ≤ίΛΈ±ßΧνΦςΨΦ≤ίΡΙ
ΛœΓΔΓ÷ΓΊΘ≈ΘΟΘ»ΘœΓΌΛ«ΟΏά―ΛΖΛΤΛ≠ΛΩΞΈ
ΞΠΞœΞΠΛρΓΔΛΛΛΪΛΥΑζΛ≠Ζ―Λ≤ΛκΛΪΛ§Μδ
ΛΈΜ≈ΜωΓΉΛ»ΗάΛΛάΎΛκΓΘ
ΓΓΓ÷ΘΌΘ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉΛœΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΛ«ΛœΛΔ
ΛκΛ§ΓΔΘ¥Θ”Φ“Λ»ΛœΞΫΓΦΞΙΞ≥ΓΦΞ…ΛόΛ«
«ψΛΛΦηΛκΖάΧσΛρΗρΛοΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
Θ¥Θ”
Φ“ΛΈΖ–±Ρ«ΥΟΨΛ Λ…ΥϋΑλΛΈΕέΒόΜΰΛΥΛœΓΔ
ΘΌΘΝΘ”Λ§ΦΪ §Λ«ΞΖΞΙΞΤΞύΛρΦξΡΨΛΖΛ«
Λ≠ΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛάΛ§ΓΔΛΫΛΈ
ΛΩΛαΛΥΛœΞΖΞΙΞΤΞύΛΥάΚΡΧΛΖΛΩΩΆΚύΛ§
Φ“ΤβΛΥΛΛΛ Λ±ΛλΛ–œΟΛΥΛ ΛιΛ ΛΛΓΘ
Λ≥
ΛλΛόΛ«Γ÷Θ≈ΘΟΘ»ΘœΓΉΛρ ίΦιΛΖΛΤΛ≠ΛΩ
ΩΆΚύΛΈΚΤΕΒΑιΛβΒόΧ≥ΛάΓΘ
ΓΓΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛρΜ»ΛΟΛΩΥήΕ»ΛΈΕΞΝη
ΈœΕ·≤ΫΛβΖγΛΪΛΜΛ ΛΛΓΘ
ΗΫΜΰ≈άΛ«ΘΌΘΝ
Θ”ΛΈΘ…Θ‘Ξ≥ΞΙΞ»ΛœΓΔΞιΞΛΞ–ΞκΛΥ»φΛΌΛΤ
≥ Ο ΛΥΑ¬ΛΛΓΘ
Λ≥ΛλΛœΗΪ ΐΛρ ―Λ®ΛλΛ–ΓΔ
ΞιΞΛΞ–ΞκΛœΘ…Θ‘ΛΥ¬ΩΛ·ΛΈΜώΕβΛρ≈ξΛΗ
Λ Λ§ΛιΛβΓΔΗΫΚΏΛΈΆχ±ΉΩεΫύΛρ≥Έ ίΛΖ
ΛΤΛΛΛκΛ»ΛβΛΛΛ®ΛκΓΘ
ΓΓΓ÷Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύΛ»ΛΛΛΠΛΈΛœΛΔΛ·ΛόΛ«
ΛβΞΡΓΦΞκΛΥΛΙΛ°Λ ΛΛΓΘ
Κ«ΫΣΞ¥ΓΦΞκΛœΕώ
¬Έ≈ΣΛ ά°≤Χ ΣΛρΤάΛκΛ≥Λ»ΛΥΛΔΛκΓΘ
ΞΖ
ΞΙΞΤΞύΛρΆ≠Ηζ≥ηΆ―ΛΖΛΤΓΔ±ΡΕ»άοΈ§Λδ
Ζ–±ΡΛβ¥όΛαΛΤΛΛΛΪΛΥ…’≤Ο≤ΝΟΆΛΈΙβΛΛ
ΛβΛΈΛράΗΛΏΫ–ΛΖΛΤΛΛΛ·ΛΪΛ§ΧδΛοΛλΛΤ
ΛΛΛκΓΉΓ ΤΘΑφΦΙΙ‘ΧρΑςΓΥΓΘ
ΓΓΛόΛΚΛœΖΉ≤ηΡΧΛξΛΥάΛ≥Π≈Η≥ΪΛρ¥ΑΈΜ
ΛΒΛΜΛκΛΈΛ§ΝΑΡσΛάΛ§ΓΔΛΫΛΈΨεΛ«ΞΖΞΙ
ΞΤΞύΛΈΚΰΩΖΛΥΛηΛΟΛΤΕΞΝηΈœΛ§ΙβΛόΛΟ
ΛΩΛ≥Λ»ΛρΩτΜζΛ«Φ®ΛΜΛ Λ±ΛλΛ–ΓΔΨπ σ
ΞΖΞΙΞΤΞύ…τΧγΛ§Χρ≥δΛρ≤ΧΛΩΛΖΛΩΛ≥Λ»
ΛΥΛœΛ ΛιΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΒπ≥έΛΈΜώΕβΛρ≈ξΛΗΛΤΝωΛξΫ–ΛΖΛΩΑ
ΨεΓΔΖΉ≤ηΡΧΛξ≤‘ΤΑΛΒΛΜΛκΛ≥Λ»ΛœΛβΛœ
ΛδΚ«ΡψΨρΖοΛάΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΘ…Θ‘ΛΈΚΰΩΖΛ§
≈ωΫιΛΈΜΉœ«ΡΧΛξΛΥ±ΩΛ–Λ ΛΛΞ±ΓΦΞΙΛœ
ΖηΛΖΛΤΨ·Λ Λ·Λ ΛΛΓΘ
Λ≥ΛΈΚ«ΫιΛΈΞœΓΦ
Ξ…ΞκΛρΞ·ΞξΞΔΛΖΛΩΨεΛ«ΓΔ¬ΨΦ“Λ»ΚΙ Χ
≤ΫΛΙΛκΛΩΛαΛΈάοΈ§≈ΣΛ Μ≈Ν»ΛΏΛΥΛόΛ«
ΑιΛΤΛιΛλΛκΛΈΛΪΓΘ
ΞιΞΛΞ–Ξκ≥ΤΦ“ΛβΗ«
¬ΟΛρΑϊΛσΛ«ΗΪΦιΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Γ Ξ’ΞξΓΦΞΗΞψΓΦΞ ΞξΞΙΞ»ΓΠ≤§Μ≥Ι®«ΖΓΥ
ΓΓΦΓ¥ϋΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΛβΓΔΞΌΓΦΞΙΛ»Λ Λκ
Γ÷ΘΌΘ’ΘΈΘΝΘ”ΓΉΛΈΒΓ«ΫΛάΛ±Λ«ΛœΞΪΞ–ΓΦ
ΛΖΛ≠ΛλΛ ΛΛΈΈΑηΛœΜΡΛκΓΘ
Λ»Λ·ΛΥΙώΛ¥Λ»
ΛΥά©≈ΌΛ§ΑέΛ Λκ≤ώΖΉΛδΡΧ¥ΊΛ«ΛœΓΔΗΫ
ΟœΜωΨπΛΥ¬®±ΰΛ«Λ≠ΛκΞΖΞΙΞΤΞύΛρ≥Α…’
Λ±ΛΖΛΩΛέΛΠΛ§ΑΆΝ≥Λ»ΛΖΛΤΆ≠ΆχΛάΓΘ
Λό
ΛΩΓΔΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙ §ΧνΛΈΘΉΘΆΘ”ΛΥΛΡ
ΛΛΛΤΛβΓΔΓ÷elogΓΉΛ«Λœ¥πΥή≈ΣΛ Ε»Χ≥ΛΖ
Ωό2ΓΓ≥Ϊ»·ΟφΛΈΦΓ¥ϋ¥π¥¥ΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷YUNASΓΉΛΈΒΓ«Ϋ≥ΒΆΉ
CRMΒΓ«Ϋ
…’¬”ΞΒΓΦΞ”ΞΙ
¥π¥¥Ε»Χ≥ΜΌ±γ
Ζ–ΆΐάΚΜΜ
Ξ…Ξ≠ΞεΞαΞσΞ»
Ξ≥ΞσΞ»ΞμΓΦΞκ
Ζ–±Ρ¥…ΆΐΓΠ §άœ
ΤβΛœ4SΦ“ΡσΕΓΛΈΞ―ΞΟΞ±ΓΦΞΗΞΫΞ’Ξ»ΧΨ
SFAΓ ±ΡΕ»…τΧγΗζΈ®≤ΫΓΥ
4S eTrans
ΡΧ¥ΊΫηΆΐ
4S eCustoms
Ι“ΕθΆΔΫ–Τΰ
4S eTrans
±ΩΡ¬άΚΜΜ
4S eAccounts
Ξ…Ξ≠ΞεΞαΞσΞ»¥…Άΐ
4S eTrans
ΞλΞίΓΦΞ»¥…Άΐ
4S iDrive
Ξ«ΓΦΞΩΞΠΞßΞΔΞœΞΠΞΙ
4S iDrive or Tool
WMS Γ Ν“ΗΥ¥…ΆΐΓΥ
4S eLog
≥ΛΜώΆΔΫ–Τΰ
4S eTrans
Αλ»Χ≤ώΖΉ
4S eAccounts
≤ΡΜκ≤Ϋ
4S VisiLog
SCM≥»ΡΞ
4S VisiLog
ΫΗ«έΞ»ΞιΞΟΞ·
4S eTrans
άΝΒαΫώΓΠΜΌ ߥ…Άΐ
4S eTrans
≈¥ΤΜΆΔΝς
4S eTrans
ΧΛΦΐΓΠΧΛ ßΛΛ
4S eTrans
|