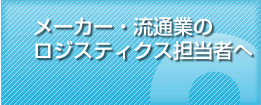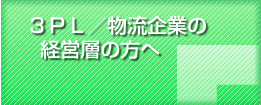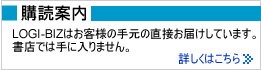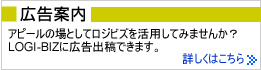|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

APRIL 2008 72
奥村宏 経済評論家
第71回いまこそ「会社の哲学」を
私の会社学研究
私が大学を卒業して新聞記者になったのは一九五三年だか
ら、それからもう五〇年以上たつ。
新聞記者時代は証券担当
として、いろんな会社を取材して回った。
その後、大阪証券経済研究所(現在の日本証券経済研究所
大阪研究所)に転職してから、本格的に会社について研究す
るようになった。
その成果を元にして一九六六年に『三井・三菱・住友』(三一
書房)という本を書いてから現在まで四三冊の本を書いてき
た。
一九八四年から龍谷大学、そして一九九四年から中央大
学教授になり、二〇〇一年に定年退職してからは家で仕事を
している。
こうして半世紀以上にわたって私が研究してきたのは会社、
とりわけ株式会社であり、そこから法人資本主義論を提唱し
てきたのだが、この研究成果を集大成した本を書きたいとか
ねがね念願していた。
そこで昨年出したのが『会社学入門』(七つ森書館)と『会
社はどこへ行く』(NTT出版)である。
前者が序論である
のに対し、後者は本論という位置付けである。
これらの本を書くに当たって私は新たに「会社学」という
ことを提唱した。
人間については人間学があり、国家につい
ては国家学があるように、会社については会社学が必要だと
いうのである。
人びとの生活を振り回しているのは会社であり、会社が国
家や社会を支配している。
それはアメリカやヨーロッパにつ
いてもいえるが、とりわけ日本ではそれが徹底している。
そ
れだけに日本でこそ会社学を打ち樹てることが必要なのであ
る。
そういう観点から、これまで半世紀以上にわたる私の研究
成果を会社学として打ち樹てようという気構えで前にあげた
二冊の本を書いたのである。
日経新聞の中傷的書評
前書については東京新聞に短い紹介が載ったほか、「信用
組合」(二〇〇八年一月号)に斉藤美彦獨協大学教授による
詳しい書評が掲載されている。
ところが後者、すなわち『会社はどこへ行く』に対して
悪意に充ちた中傷的な書評が日本経済新聞の二〇〇八年二月
一〇日付けに載っている。
この新聞の書評欄は署名入りで、書評というよりも、本
の宣伝文のような記事をたくさん載せているが、これに対し
て中傷的な書評は無署名でするというのが編集方針のようで
ある。
人間として何かをほめる時には無署名であっても、批
判する時には本人の名前を出してするというのが常識である。
それはなにも日本人に限らず、どこの国にも共通するモラル
である。
このモラルに全く反しているのが日本経済新聞であり、な
るほど「財界の御用新聞」といわれるだけのことはあると感
心するばかりである。
この書評を書いた無署名の人もおそら
く日本経済新聞に近い「御用学者」だろうが、この人は私の
本を本当に読んだのだろうか。
私の本を高橋亀吉や坂本藤良の本と並べているが、これら
が通俗的な株式会社批判であるのに対して、私の本は株式会
社についてその歴史と現実を踏まえて体系的に展開した物で、
単なる会社評論ではない。
もちろん私の主張に対して批判す
るのは歓迎する。
だがそれは自分の論拠を示して批判するの
でなければ、単なる中傷にすぎない。
「それでも『株式会社』は続くだろうというのが読後感で
ある」という書き出しでこの書評は始まる。
しかし、どうし
てそうなるのかということを全く書いていない。
というよりも、この人は私のいう「株式会社信仰に取りつ
かれた人」という以外にはない。
理由もなく信仰するのは宗
教というよりも「邪宗」という以外にはないのかもしれない。
会社という制度はこれからもずっと続いていく。
多くの人が理由もなくそう信じ
込んでいる。
“株式会社信仰”とでも呼ぶべき宗教が世界中に蔓延しているのだ。
これを批判するには会社についての哲学が必要である。
それは今の日本人にとっ
て最も必要な学問だといえるだろう。
73 APRIL 2008
哲学への回帰
私は戦後まもなく三木清や西田幾多郎の本などを読んで哲
学者になろうと思い、旧制六校の文科乙類(ドイツ語専攻)
に入った。
その後哲学とは全く関係のない職業についたのだ
が、かつての少年時代の志に立ち帰っていま新たに会社につ
いての哲学を研究しようと思い立ったのである。
そこでまず問題になるのは「会社は実体か」という問題で、
そのためにアリストテレスにまで立ち帰って、実体論を研究
しようとしている。
会社学を展開するためにはこれがまず出
発点になる。
このことは前記の『会社はどこへ行く』の第二
章の終わりのところで簡単に述べてある。
その後、廣松渉の
『物象化の構図』や『存在と意味』(いずれも岩波書店)な
どを読んでさらに深く考えるようになった。
廣松渉は実体概念に対して関係概念を対置するのだが、会
社はまさに関係概念としてとらえられるべきものであると考
えられる。
これはエルンスト・カッシーラーの『実体概念と
関数概念』(山本義隆訳、みすず書房)についても同じこと
がいえる。
問題は、会社は実体ではなく、関係概念、あるいは機能概
念でとらえられるべきものなのだが、にもかかわらず多くの
人がそれを実体と考えるのはなぜかということである。
会社をあたかもヒトかモノのように考える。
このことを
堂々と主張しているのが岩井克人(東大教授)であり、これ
に対して私は前記の本などで既に批判している。
しかしそれ
を批判するだけでなく、なぜ彼らがそう考えるのか、という
ことを検討しなければならない。
そのためには会社についての哲学を打ち樹てることが必要
なのである。
こうして私はいま八〇歳近くになって、改めて
少年時代に志した哲学の道に入ろうとしているのだが、果た
してそれがうまくいくかどうか、もちろん自信はないが、し
かし会社学を打ち樹てるためにはそれがぜひ必要なのだ。
株式会社信仰と哲学
このような無責任で無根拠な書評に対する反論をここでし
ようとするのではない。
この書評者のように株式会社信仰に
取りつかれた人たちがいかに多いか、ということを私は常日
頃から痛感している。
このような日本の風潮に対して批判していくというのが私
のかねてからの信念であり、それに基づいてこれまで四〇冊
以上もの本を書いてきたのである。
それはひと口でいえば「株式会社信仰」に対する批判とい
うことができる。
私は前記二冊の本を書き上げたあと、バートランド・ラッ
セルの『西洋哲学史』を通読した。
原書で八〇〇頁以上もあり、
これまで拾い読みはしていたが、通読していなかった。
これ
を読んでいるうちに「哲学は宗教と科学の間にある」という
ラッセルの指摘につき当たり、考えさせられた。
「そうだ『株式会社信仰』という宗教を批判するには哲学
が必要なのだ」と改めて思ったのである。
それも単なる哲学
ではなく、会社についての哲学が必要なのである。
そう考えていろいろ哲学の本を読んでいるのだが、これま
で会社について哲学的考察を加えたものはないといってもよ
い。
国家については哲学的考察を加えたものはあるし、いわ
んや人間については多くの哲学者がさまざまな考察をしてい
る。
ところが国家と同じように、あるいはそれ以上に人びとの
生活をとらえている会社について哲学者は何もいっていない、
どころか、何も考えていないのではないか。
そこでいま必要なことは会社についての哲学を研究するこ
とではないか。
そう思い立って、プラトンやアリストテレス、
そしてデカルトやスピノザ、カントやヘーゲルにまで立ち帰
って考えてみようとしているのだが、もちろんそう簡単に結
論が出るわけではない。
おくむら・ひろし 1930 年生まれ。
新聞記者、経済研究所員を経て、龍谷
大学教授、中央大学教授を歴任。
日本
は世界にも希な「法人資本主義」であ
るという視点から独自の企業論、証券
市場論を展開。
日本の大企業の株式の
持ち合いと企業系列の矛盾を鋭く批判
してきた。
近著に『会社はどこへ行く』
(NTT 出版)。
|