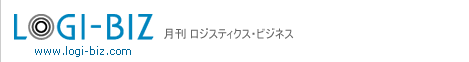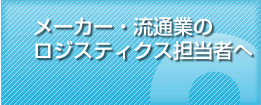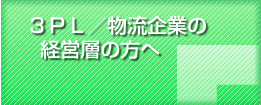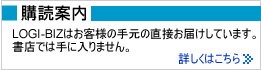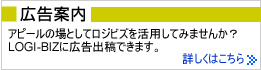|
*������PDF���ƥ����Ȥ���Ф����ǡ����Ǥ���������PDF������������

ʪή�Ҳ�Ҷ��ۤοʤ���
24����OCTOBER 2008 OCTOBER 2008����24
���ʤ��ò����Ƴ��γ���
�����桼����ή�̥����ƥ�ϰ��ϻϻǯ�˿Ʋ�ҡ�
���桼�ԡ����Ҹ������ʬΥ����Ω���뤫��������
Ω���줿��
Ȭ��ǯ�˥���ɡ�����ʤζ�Ʊ������
�ȤϤ��ư��衢���ȵ��Ϥȳ�����Ψ���Ĵ��
���礵������
���ǯ�ˤ���������˾�졢��
��ǯ����ڰ����˻����ؤ��Ȥʤ�ʤɡ������ʤ�
?������ʪή�Ҳ��?�ΤҤȤĤ���
���Ʋ�Ҥ�ʪή����ե����Ѥ��ơ��饤�Х��Ҥ�
��ʪ������ळ�Ȥdz����ټ��������롣
������
���ȼ����������Ʊ���ˡ�����ե��ƯΨ����夵��
�뤳�Ȥǡ�ʪή�����Ȥ�︺���롣
���Τ褦�ʥ��ץ�
������¿����ʪή�Ҳ�Ҥ���Ʊ�����λ��Ȳ���ޤä�
�����������������������Ϥ�����������
�����桼�����κ����ڷ����̳�������������Ĺ�ϡ�
Ʊ�Ҥ�����������뤲����ͳ�ΰ�Ĥˡֿ��ʥ����
�ζ�Ʊ�������ò����Ƥ������ȡפ�롣
�겹͢��
�Τʤ��Ǥ⤽�Υ������åȤ�ù����ʡ��ۻҡ���
����ʤɤΥ�������в٤����
to
��ʪή�˹ʤäƤ�
����
��ü����ν��ۤ䡢�����Ӵ���������¾
�ξ��ʤ˽������ܤ붲��Τ�������������ڤ�����
���ʤϰ��äƤ��ʤ���
���ɥᥤ������Τˤ����������ͥåȥ���ι���
�ȡ���ߵ�֥����ƥ�γ�ȯ��Ĺ���֤����Ƽ���Ȥ�
����
Ȭ��ǯ�˶�Ʊ�����Ѥ�����ͥåȥ���֥��桼
������פ��ȿ��������ϱ�����Ҥ�Ʊ��β���«��
����
���桼�������ˡ�ͳʤ��������Ҥ�ʬ�����Ƥ�
���ΤΡ����¾��Ĥ�ϩ���ȼԤȤ��Ƶ�ǽ���Ƥ�
�롣
�̾��ϩ���ؤȰ㤤���ﲹ������ɡ�����λ�
�����ӤС����Ƥ��뤳�Ȥ���ħ����
���強ǯ�ˤϵ�ߵ�֥����ƥ�֣ѣԣɣӡפ��ܳʲ�
Ư��������
Ʊ�Ҥε�ߵ�֥����ƥ౿�����礬��Ω��
�����桼�����ƥ��������Ĥ��Ƥ��롣
���桼�������
�����Ȥ϶����������ּ�ʤɤξ���ټ���
�Ͼ��ʤμ����ʪ�̡����ϡ����Ϥʤɤξ����
�ԣɣӤ���Ͽ��
�����ƥब��ưŪ���ۼ֤�������ۼ�
�ޥ�Ĵ����Ԥ������ꤷ�����������ȤȲټ�
��Ȥ�������ή�����Ȥߤ���
�������ϸ�μ֤Ȳ�ʪ
������Ψ�϶�Ȭ��ʾ�����˹⤤���Ȥ���ħ����
��������������ե���������¤˻��ȳ���˷�Ӥ�
������
����ǯ������������ϰ�͡���ϻϻ��
�����ߤǡ��졻��Ϣ³��������Ͽ���Ƥ���ʿޣ��ˡ�
���롼��������϶��ǯ�ʹߡ�����������Ⱦ
�ǿ�ܤ��Ƥ���Τ��Ф�����������϶��ǯ�θ�
�����컰�������ߤ��顢���ߤϰ�켷��������
�����ߤ��������Ƥ��롣
���η�̡�������Ψ�ϡ���
ǯ��Ȭ�����Ķ�������ߤ�Ȭ�͡��ã���Ƥ��롣
��
����Ʊ����������϶�Ͳ��ߤǡ�������Ψ����
�㤷�����ä�³���Ƥ��롣
�Ѻ�Ψ�����Ǽ�����������
����������������ǯ�����������㲼���뷹���ˤ��롣
����ǯ�������ʹߡ�����Ϣ³�θ��פ˴٤äƤ��롣
�Ķ����פϡ���ǯ�λ������������ߤ��须��ǯ
�ˤϰ�Ͳ��켷�������ߤ˸���������
������ñ�����Τ�dz�����ƭ�αƶ��⤢�ꡢ�����
��ǤϤ��ʤ��Ȥ�����
�����������ʶȳ����ΤΥȥ�
��ɤȤ��ơ���������ι�ƭ��ۼ�������ʤ��ʤä�
��������������Ⱦ徺ʬ���ʲ��ʤ�ž�Ǥ�������
�Ǿ������¡�
ʪή�ξ�������ʤ�����Ȥǥȥ�å�
������������Ѻ�Ψ���������Ƥ��롣
̵�����Ѻ�Ψ
��夲�褦�Ȥ���к��٤�Ǽ�ʷ����¿���ʤꡢ��
�饤�С��λĶȻ��֤������Ƥ��ޤ���
���η�̡����
���Ʋ�Ҥ�ʪή����ե��١����ˡ�Ʊ��¾�Ҥβ�ʪ�������dz���
����礷�����ȼ��������ƿƲ�Ҥ�Ϣ��軻�˹����롣
����ե��Ư
Ψ��夲�뤳�Ȥ�ʪή�����Ȥ�︺�����Ʋ�ҡ������ټ硢ʪή�Ҳ��
�Ȥ��WIN-WIN�δط����ۤ���
������ļ̿�������ʪή�Ҳ�Ҥ�¿������
���ޤ����äƤ��륱�����ϵ�����
ʪή�Ҳ�Ҥ���Ƴ���붦Ʊ����������
�����桼����ή�̥����ƥ�˳ؤ֡�
������������ �������ʼƻ����
��3��
��Ʊʪή�����ý�
25����OCTOBER 2008
�ꥳ���ȥ��åפ��Ƥ��ޤ���
���ʼ������˸������������⡢�����Ǥϼ��פ�
�����ĥ�äƤ��롣
������ǯ���ԥå��ߥ����ɻ�
�ʤɺ���ʼ��θ������Ū�ˡ�ʪή�����˴�Ϣ����
���������Ѷ�Ū�˿ʤ�Ƥ�����
����ޤǸ������
��Ǥ���ê�ϰ�ư���Τ�Τ��ڤ괹������
�����Ҹ˺�Ȼٱ祷���ƥ�פȤ������ꥸ�ʥ�Υ�����
���ȯ������١����θ����Ȥϥϥ�ǥ�ü������
����������
����ˤ�äƸ����Ȥ���ô�����ꡢ��
�����٤����夷����
����������ʪ�̤��������Ҹˤβ�
žΨ���������Ƥ��뤿�ᡢ�������Ƥ������
������ʬ�εۼ������ʤäƤ���פȡ������ھ�̳
���������롣
���������ˤ������ǤäƤ��롣
�겹���ʤ��оݤ�
��������åȤ�ϩ���ؤ˲ä���������Ʊ�ͤξ����å�
�β�ʪ���оݤȤ����֥��桼�������롼�ءפ���
��ǯ�˳�ȯ��
�����첯�ߤ��ä����夲������
�ߤϰ����ߤޤdz��礷�Ƥ��롣
�����롼�ؤαĶȤϥ��桼�������ΤαĶȤȡ����桼
������β����������ǹԤäƤ��롣
���桼��������
���˱ĶȽ����äƤ���櫓�ǤϤʤ���
���桼������
�ĶȽ꤬�ʤ����˱Ķ�ô���Ԥ���ĥ�����ܵҤγ���
�䥵�ݡ��Ȥ���⡢���θ��ˤ�������Ȥ���
�Ȥ�Ԥä��������ԡ��ǥ�������
�ҤȤΥ��ߥ�˥���
������̩�ˤȤ�롣
�۵��б��⤷�䤹���Ȥ���Ƚ��
����
�������ھ�̳�ϡ����ҤȲ����Ȥ�ñ�ʤ�ѡ��ȥʡ�
���åפδط��ǤϤ��⤷�����ʤ���
�Ͼ�ζ�Ʊ������
�ܵҳ��������ñ�ȤǤϽ���ʤ��Τǡ������Ȥ�
��ͻ��Ӥˤʤäƥ��롼�ؤΥѥ�����礷�Ƥ�����
��
����Ȥλ��ȳ���ˤ�Ĥʤ���פ��������롣
������͢���Υͥåȥ�������Ǥʤ������ꥢ���ۤ�
�ͥåȥ�����ˤ����Ϥ��Ƥ��롣
��ϻǯ��ꡢ��
�桼��������ȿ���������������פȡ�͢�������
��ʬ������
��������ˤϳ��Ϥν��ۤ�ô����Ҥ�͢
������ˤϴ���͢����ô����Ҥ�����
���ۤ�
����͢�������줾��ε�ǽ�����Ƥ������ˤ���
����ǯ���饭�桼������˽������٤��ߤ�����
����
������Ȥʤ뱿����Ҥ�����Ȥ������ꤷ����ǯ��
�������Ʊ����̳��Ԥ���
������Ȥ��̳�ƻ����
�̡�����ʤ�����졻��ʬ���줿�����λ���Ĺ�ο�
���ˤ�ä�������ؤȳʾ夲����롣
���ߡ�����
��ޤ������ϰ����ȤʤäƤ��롣
�������ȼԤ϶塻ǯ�˻ܹԤ��줿ʪή��ˡ�ˤ�뵬
�����¤αƶ�������³���Ƥ�������dz���ƭ�αƶ���
���ꡢ�ݻ�����Ȥ�̾������Ȥ������Ƥ��롣
��ʪ
ή��������̿��
�Ͼ��ͭ�ϱ����ȼԤ���ݤ�������
�֤����Ĥġ��бĴĶ��ΰ������й��Ǥ����ȿ�
�����ܻؤ��פȺ����ھ�̳�Ϥ�����
����Ʊ�������ղò��ͤ��դ��뤿�ᡢ��ǯ����͢��
��ʪ���̴ء����Ƕ�̳�ˤ����Ȥ�Ǥ��롣
����
������겹ʪή�����פ����֤��ơ�͢�����ʤ���
�ض�̳��Ԥ�������͢�������ϰ������ޤǤ�쵤��
�Ӥ˹Ԥ�����Ȥߤ���������
���Ķ��Ѳ���Ŭ�����ơ����������ǤäƤ��롣
��
��Ǥ⸺�����ˤϻ��ߤ������ʤ���
��Ȭǯ��
����������ִ��η軻�Ǥ⡢�Ķ����פϰ첯����
�������ߤ���ǯƱ���漷����������������
�̴���
�����ߤ⽽�ߤȡ���ǯƱ�����ޡ��͡�θ���
����Ǥ��롣
���ʶ��ۤ��ʥ��ơ�����
����Ʊ�����Ǵְ㤤�ʤ���ξ���������ޤ���
�ټ�
���⥹�ԡ��ǥ����ˤʤ�ޤ�������
Ʊ�Ҥ����ʤζ���
OCTOBER 2008����25
���桼����ή�̥����ƥ�
�κ����ڷ����̳����
���������Ĺ
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
99ǯ
1
1���
20
ǯ1
1���
01
ǯ1
1���
02
ǯ1
1���
03
ǯ1
1���
04
ǯ1
1���
05
ǯ1
1���
06
ǯ1
1���
07
ǯ1
1���
��1�����桼����ή�̥����ƥ��������
23358 23374 24082 23712 23083 22729 23060 23027 22914
117352
112478
107098
95369 98559
74447 78923
68162
55713
��ñ�̡�ɴ���ߡ�
�������
���롼��������
���
Σԣԥ��������ϣΣԣԤ������ǯ��ʪ
ή����ʬ�Ҳ����뤫��������Ω����ʪή�Ҳ�
�Ҥ���
��Ω����μ�ʲ�ʪ�ϥ��롼������
���õ��䥱���֥�Ȥ��ä��̿���������Ģ
�����
����Ĵ�ȤȤ������Ȥ⤢�äƤ���
���¿��ϳ����ä���
�������ȶ����Ϥ����ƿƲ�Ҥؤΰ�¸��
����æ�Ѥ��뤿�ᡢ���Τγ���˼���Ȥ����
���ܤ˾Ҳ𤵤줿�Ф���Σ��У̻��Ȥ�����
��������������ȿ����ƥ������åȤȤʤ뻺��
��ʬ�ϡ�
�����ѷ��ࡢ���ŵ�������Ū��ʤ�
��Ƥ�ŤͤƤ��ä���
���ޤ������ե��������ѤΥܥå��������֤���
��̩���������
�ꥵ�����빩�������������
����˺յ��Ǵ����˵�̩����ʤ�������Ǻ�
������Ȥ����ֵ�̩����ꥵ�����륷���ƥ��
�ʤɡ���̮ʬ����ȼ��Υ����ӥ����ʤⳫȯ��
����
���η�̡���Ω����ˤϤۤȤ�ɤʤ���
��������Ψ�����ߤϸޡ����ˤޤ�ã����
���롣
����Ʊʪή�ˤ���ꤷ�Ƥ��롣
ʣ�����̿���
���������饱���֥�٤��ơ��Σԣԥ�
��������ʪή�������ݴɡ���������ذ�
�礷��Ǽ�ʤ��Ƥ��롣
��äȤ⡢���ζ�Ʊʪ
ή�����夲��ǯ�����ߤ���������
����˲�ʤ���
����������˳��礵�����
������
�������ٶ�̳��͢�������ô����Ĺ�ϡ֥���
�֥�ζ��ۤϲ����¿�������路�Ƥ���פ�
������
�ޤ����Ѻ���ˡ����
�����֥�ϥɥ���
������Ƥ��ơ��礭�����͡���
���ƤΤ�Τ�
�ѥ�åȤDZ��٤�櫓�ǤϤʤ����Ѻܸ�Ψ���
���뤿��˥Х��Ѥߤˤ��뤳�Ȥ�¿����
ʣ����
�β�ʪ�ܤ��뤿��ˡ���Ψ���ɤ��Ѻ���
ˡ��ͤ���ɬ�פ����롣
���ֶ��ۤ�����Ȥ��äƥ����ӥ���٥�����
���櫓�ˤϤ����ʤ���
�ܵҤˤ�äƤϻ��ֻ�
�����˾�⤢�ꡢ��Ʊ�����Ȥ������ɤ���
�뤫�פȰ����Ĺ��Ƭ��Ǻ�ޤ��Ƥ��롣
OCTOBER 2008����26
�˼���Ȥ������Τ�����ʸ��Ϥ������ä���
������
�������Ⱥ��Ǥ϶��ۻ��Ȥ��Ф���桹�ιͤ������Ѥ�
�äƤ��Ƥ��롣
ñ�˲ټ�ο������䤹�����Ǥϸ�Ψ��
�ˤϤĤʤ���ʤ���
��Ʊʪή�ε�ǽ������������
ľ��ɬ�פ�����פȺ����ھ�̳�Ϲͤ��Ƥ��롣
���㤨�С��������٤Ϥ���ޤǤ������������뤳��
�����ۤȤ���Ƥ�����
�����������ʤ��������ġ�
�����Ϥ���ɬ�פ������ˤ���Τ���
�����Ϥ���ɬ��
�����륨�ꥢ�ȡ��������Ǥ������ꥢ�Ȥ��ä��ڤ��
���������뤳�ȤϤǤ��ʤ�����
��������Ʊ�Τζ�
Ʊ���������������ɬ�פ����롣
ʪή���ڤ����
�ȳ��ξ��������ѳפ��Ƥ�������ʪή��Ȥ�ô��
���夬ˬ��Ƥ��롣
������ե���߷פˤ⽤���������Ƥ��롣
�����
�ϲ����ѡ���̳�ѤȾ��ʥ��ƥ���̤�����������ʬ
���Ƥ��롣
���������˽स�ƥ�����ʬ���륱
�����������Ƥ�����
������Ф��ƥ��桼�����϶�̳�ѡ�
�����Ѥ��������ĤΥ����ǰ��äƤ��롣
�����
���ƥ���̤˺��Ԥ����������Ψ������Ǥ��롣
������Ԥο����Ф���¿��������ָ��ι�ޤ���
���������ʪή�ȼԤ�ȥ졼���ӥ�ƥ������б�����
����Τ�ɬ�����
�äˡָ�����Ĵã���ơ�������
��ޤǤΥȥ졼���ӥ�ƥ����Ϥ����äȤǤ��Ƥ����
��������¿����������Ϥ������ʪή������Υ쥤��
���ˤ���פȺ����ھ�̳�Ϥߤ롣
���
ɣå�����Ƴ������Хѥ�å�ñ�̤Ǵ������Ǥ���
�����Ȥ��������ή��������ɤळ�Ȥ��Ǥ����
�ɡ����̤��礭����
��������ñ�����졻���߶��
��ɣå������ʤ�Ž�դ��Ƥ�λ������ʤ���
����
���ɤ߹��ॲ���Ȥ�ȯ�Ϥ����Ϥ����������֤��ʤ���
�Фʤ餺���ϡ��ɤˤ����������ɬ�פˤʤ롣
����
���Ϥ��ޤ������Ƥ��ʤ���
���ֿ��ʤˤ����붦Ʊ�����ˤϤޤ��ޤ������;�Ϥ�
���롣
���ϤϤ��Ƥ��ʤ���
�������ʪή����ڤ��
�������������ˤˤʤäƤ��롣
������μ������Ϥ�
ʪή�����Ȥ�︺����ˤϸ³������Ƥ���Ȥ����ڤ�
�����פȺ����ھ�̳�Ͽ��ʶ��ۤ�⤦���ʹ⤤��٥�
�˿ʲ����������������äƤ��롣
26����OCTOBER 2008
���У����⿷�ߤ�������Ψ�ޡ����ã��
�����
Σԣԥ�������
NTT���������ΰ����ٶ�̳��
͢�������ô����Ĺ
|