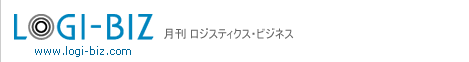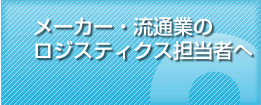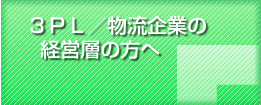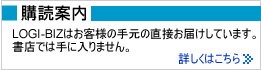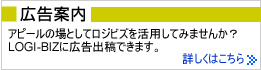|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

APRIL 2009ΓΓΓΓ66
±ßΧνΫΛΓΓΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙΞ–ΞσΞ·¬ε…Ϋ
ΣΈ°Ε»ΛΈΞξΞΙΞ·ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»
ΣΈ°Ε»ΛΈΞξΞΙΞ·ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»
¥ΡΕ≠ΞξΞΙΞ·Λρ¥…ΆΐΛΙΛκ
ΓΓΓ÷Θ…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±ΓΉΛœΓΔΘ…
Θ” ΘœΓ ΙώΚί…ΗΫύ≤ΫΒΓΙΫΓΥ Λ§
ΑλΕεΕεœΜ«·ΛΥΡξΛαΛΩ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗ
ΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΓ Environmental
Management System= Θ≈ΘΆΘ”ΓΥ
ΛΈΙώΚί…ΗΫύΒ§≥ Λ«ΛΔΛξΓΔ¥ΡΕ≠»ο
≥≤Λ»ΛΛΛΠ¬ΠΧΧΛΪΛιΞξΞΙΞ·ΞόΞΆΞΗΞα
ΞσΞ»ΛΈΦξΥΓΛρΦ®ΛΖΛΩΛβΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΛΫΛΈ¬γΛ≠Λ ΤΟΡßΛœΓΔΫγΦιΛΖΛ Λ±
ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΥΓΈßΛΫΛΈ¬ΨΛΈΆΉΒαΜω
ΙύΛ§Ωτ¬ΩΛ·¬ΗΚΏΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΦ¬ΚίΓΔΝΑΙφΛ«≤ράβΛΖΛΩΓ÷Θ…Θ”ΘœΘΙΘΑΘΑΘ±
… ΦΝΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΓΉΛΥΛœΓΔΥΓ≈ΣΆΉ
ΒαΜωΙύΛ§Ν¥Λ·Β§ΡξΛΒΛλΛΤΛΛΛ ΛΛΛ§ΓΔΓ÷Θ… Θ” Θœ
Θ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΓΉΛΥΛœΓΔ
≥ΤΦοΛΈΥΓΛΈΫγΦιΛ§Χά≥ΈΛΥΒ§ΡξΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΖ
ΛΪΛβΓΔΘ…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±ΛΈΤσΓΜΓΜΜΆ«·»«Λ«ΛœΓΔ
Β§≥ ΆΉΒαΜωΙύΛ»ΛΖΛΤΩΖΛΩΛΥΓ÷ΫγΦι…Ψ≤ΝΓ Β§≥
ΆΉΒαΜωΙύΓß 4.5.2.1 Λ»4.5.2.2ΓΥΓΉΛ§Ρ…≤ΟΛΒΛλΛΤΛΛ
ΛκΓ ΩόΘ±ΓΥΓΘ
¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΛΥΛΣΛΛΛΤΓΔΫγΥΓ
ά≠Λ§ΛΛΛΟΛΫΛΠΫ≈ΆΉΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΛ≥Λ»ΛρΦ®ΚΕΛΖΛΩ
ΛβΛΈΛ»ΗάΛ®ΛκΓΘ
ΓΓ ΣΈ°Ε»ΛΈ¥ΊΛοΛκ¥ΡΕ≠¥ΊœΔΥΓΒ§ΛœΛ≠ΛοΛαΛΤΙ≠
»œΑœΛΥΛοΛΩΛΟΛΤΛΛΛκΛ§ΓΔΦγΛ ΛβΛΈΛρΨεΛ≤ΛκΛ»Ωό
Θ≤ΛΈΡΧΛξΛ«ΛΔΛκΓΘ
Λ≥ΛλΛΥ≤ΟΛ®ΛΤΓΔ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞα
ΞσΞ»ΛρΦ¬ΜήΛΙΛκΛΥΛΔΛΩΛξΆΐ≤ρΛρΛΖΛΤΛΣΛΪΛ Λ±Λλ
Λ–Λ ΛιΛ ΛΛΛβΛΈΛ»ΛΖΛΤΓΔΫέ¥ΡΖΩΖ–Κ―ΞΖΞΙΞΤΞύΙΫ
ΟέΛΈΛΩΛαΛΈΗΕ¬ßΓ÷Θ≥Θ“ΓΉΛ§ΛΔΛκΓΘ
Θ≥Θ“Λ»ΛœΓ÷Ξξ
Ξ«ΞεΓΦΞΙΓ ReduceΓΥΓΉΓΔΓ÷ΞξΞφΓΦΞΙΓ ReuseΓΥΓΉΓΔΓ÷Ξξ
ΞΒΞΛΞ·ΞκΓ RecycleΓΥΓΉΛΈΈ§Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΛΠΛΝΞξΞ«ΞεΓΦΞΙΛ»ΛœΓΔάΫ… Λ Λ…ΛΈΨ ΜώΗΜ
≤ΫΓΠΡΙΦςΧΩ≤ΫΛ Λ…ΛρΡΧΛΗΛΤ«―¥ΰ ΣΛ»ΛΖΛΤΛΈ«”
Ϋ–ΛρΆόά©ΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
Λ≥ΛλΛΥΛœΞφΓΦΞΕΓΦΫξ
Ά≠ΛΈάΫ… ΛρΫΛΆΐΛΖΓΔάΫ… ΛΈά≠«ΫΓΠΒΓ«ΫΛρ≤σ…ϋ
ΛΒΛΜΖ―¬≥Μ»Ά―ΛΙΛκΞξΞΎΞΔΒΓ«ΫΛρ¥όΛσΛ«ΛΛΛκΓΘ
Εα
«·ΓΔ ΣΈ°¥κΕ»Λ§ΩΖΛΖΛΛΞΒΓΦΞ”ΞΙΛ»ΛΖΛΤΦηΛξΝ»Λσ
Λ«ΛΛΛκΈΈΑηΛΈΑλΛΡΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛόΛΩΞξΞφΓΦΞΙΛ»ΛœΓΔΜ»Ά―ΛΒΛλΛΩάΫ… ΛΈΛΠΛΝΆ≠
Ά―Λ ΛβΛΈΛράΫ… ΛόΛΩΛœ…τ… Λ»ΛΖΛΤΚΤΜ»Ά―ΛΖΛΤΛΛ
Λ·Λ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΣΈ°Ε»≥ΠΛ«ΆχΆ―Λ§Ι≠Λ§ΛΟΛΤΛΛΛκ
ΞξΞΩΓΦΞ Ξ÷ΞκΆΤ¥οΛβΛΫΛΈΑλΛΡΛάΓΘ
ΛΒΛιΛΥΞξΞΒΞΛ
Ξ·ΞκΛ»ΛœΓΔΜ»Ά―ΛΒΛλΛΩάΫ… ΛδάΫ… ΛΈάΫ¬ΛΛΥ»Φ
ΛΛ»·άΗΛΖΛΩ…ϊΜΚ ΣΛρ≤σΦΐΛΖΓΔΗΕΚύΈΝΓ ΞόΞΤΞξ
ΞΔΞκΓΥΛ»ΛΖΛΤΚΤάΗΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΛηΛΠΛΥΘ≥Θ“ΛœΫέ¥ΡΖΩΖ–Κ―ΞΖΞΙΞΤΞύΙΫΟέ
ΛΈΛΩΛαΛΈΗΕ¬ßΛ«ΛΔΛκΛ»Τ±ΜΰΛΥΓΔ ΣΈ°¥κΕ»ΛΥΛ»
ΛΟΛΤΩΖΛΖΛΛΞ”ΞΗΞΆΞΙΞΝΞψΞσΞΙΛ»Λ ΛξΤάΛκΜωΕ»ΈΈ
Γ‘¬η3≤σΓ’
ISO14001¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύ
ΓΓ¬ΨΦ“Λ»ΛΈΚΙ Χ≤ΫΛδΦγΆΉ≤ΌΦγΛΈΆΉάΝΛρΛ≠ΛΟΛΪΛ±ΛΥΤϋΥήΛ«Λβ
Γ÷ISO14001 ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΓΉΛΈΦηΤάΛΥΤΑΛ· ΣΈ°¥κΕ»
Λ§ΝΐΛ®ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛΈΤΟΡßΛœ¥ΊœΔΥΓΒ§ΛΈΫγΥΓά≠Λ§Ϋ≈ΜκΛΒΛλΛΤΛΛΛκ
≈άΛΥΛΔΛκΓΘ
¥κΕ»≥ηΤΑΛΥΛηΛκ¥ΡΕ≠±χάςΛρΧΛΝ≥ΛΥΥ…ΛΑΛΩΛαΛΈΞξΞΙΞ·
ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»Λ»ΛΛΛΠ¥―≈άΛΪΛιΛβISO14001 ΛΈΦηΤάΛœ¬γΛ≠Λ Α’ΧΘΛρ
ΜΐΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Ωό1ΓΓISO14001ΓΓ2004 «·»«ΛΈΒ§≥ ΆΉΒαΜωΙύ
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
Φ¬Ι‘
(Do)
D
Αλ»ΧΆΉΒαΜωΙύ
¥ΡΕ≠ ΐΩΥ
ΖΉ≤η
¥ΡΕ≠¬ΠΧΧ
ΥΓ≈ΣΒΎΛ”ΛΫΛΈ¬ΨΛΈΆΉΒαΜωΙύ
Χή≈ΣΓΔΧή…ΗΒΎΛ”Φ¬ΜήΖΉ≤η
Φ¬ΜήΒΎΛ”±ΩΆ―
ΜώΗΜΓΔΧρ≥δΓΔά’«ΛΒΎΛ”ΗΔΗ¬
ΈœΈΧΓΔΕΒΑιΖ±ΈΐΒΎΛ”ΦΪ≥–
Ξ≥ΞΏΞεΞΥΞ±ΓΦΞΖΞγΞσ
ΗΫώΈύ
ΗΫώ¥…Άΐ
±ΩΆ―¥…Άΐ
ΕέΒόΜω¬÷ΛΊΛΈΫύ»ςΒΎΛ”¬–±ΰ
≈άΗΓ
¥ΤΜκΒΎΛ”¬§Ρξ
ΫγΦι…Ψ≤Ν
…‘≈§Ιγ ¬Λ”ΛΥάßάΒΫηΟ÷ΒΎΛ”ΆΫΥ…ΫηΟ÷
Β≠œΩΛΈ¥…Άΐ
Τβ…τ¥ΤΚΚ
ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞλΞ”ΞεΓΦ
Γ Ζ–±ΡΦ‘ΛΥΛηΛκΗΪΡΨΛΖΓΥ
ΗΪΡΨΛΖ
(Act)
A
ΖΉ≤η
(Plan)
P
ΞΝΞßΞΟΞ·
(Check)
C
67ΓΓΓΓAPRIL 2009
ΑηΛ»Χ©άήΛΥ¥ΊœΔΛΖΛΤΛΛΛκΛ≥Λ»Λρ¥ΈΛΥΧΟΛΗΛΤΛΣΛ·
…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΓΘ
Θ≈ΘΆΘ”ΛΈΜ≈Ν»ΛΏΛ»ΦξΫγ
ΓΓΘ
…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±Λ«ΆΉΒαΛΒΛλΛΤΛΛΛκΘ≈ΘΆΘ”
ΛΈΝ¥¬ΈΛΈΜ≈Ν»ΛΏΛρΩόΘ≥ΛΥάΑΆΐΛΖΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΕώ¬Έ
≈ΣΛ ΦξΫγΛ» ΣΈ°¥κΕ»ΛΥΛΣΛ±Λκ±ΩΆ―ΨεΛΈΞίΞΛΞσ
Ξ»ΛœΑ ≤ΦΛΈΡΧΛξΛ«ΛΔΛκΓΘ
?¥ΡΕ≠ ΐΩΥΛΈά©Ρξ
ΓΓΘ
≈ΘΆΘ”ΛœΖ–±ΡΩΊΛΥΛηΛκΑ’ΜΉ…ΫΧάΛΪΛιΞΙΞΩΓΦ
Ξ»ΛΙΛκΓΘ
ΛΫΛΈ≤ώΦ“ΛΈ¥ΡΕ≠Ξ―Ξ’Ξ©ΓΦΞόΞσΞΙΛΥ¥ΊœΔ
ΛΙΛκΑ’ΩόΛΣΛηΛ”ΗΕ¬ßΛΥΛΡΛΛΛΤΛΈάΦΧάΛ«ΛΔΛκΓ÷¥Ρ
Ε≠ ΐΩΥΓΉΛρά©ΡξΛΙΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΤ±ΜΰΛΥΘ≈ΘΆΘ”ΛΈΙΫΟέΚνΕ»ΛρΙ‘ΛΠΛΩΛαΛΈΞΉΞμ
ΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝΓΦΞύΛβΛΖΛ·Λœ¥ΡΕ≠¬–ΚωΦΦΛ Λ…ΛΈΩδΩ
…τΧγΛρ»·¬≠ΛΒΛΜΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛκΓΘ
?¥ΡΕ≠Χή≈ΣΛ»¥ΡΕ≠Χή≈ΣΛΈάΏΡξ
ΓΓΘ
ΟΘœΘ≤ΛΈΚοΗΚΛδ¥ΡΕ≠ΥΓΈαΛΈΫεΦιΛ Λ…ΓΔ¥ΡΕ≠ ΐ
ΩΥΛΪΛιΤ≥ΛΪΛλΛκ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΛΈΧή≈ΣΛρΧάΛι
ΛΪΛΥΛΖΛΤΓΔΕώ¬Έ≈ΣΛ ΩτΟΆΧή…ΗΛράΏΡξΛΙΛκΓ Ωό
Θ¥ΓΥΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝΓΦΞύΛœΓ÷¥ΡΕ≠
¬ΠΧΧΛΈάωΛΛΫ–ΛΖΓΉΓ÷¥ΡΕ≠±ΤΕΝ…Ψ≤ΝΓΉΓ÷ΟχΛΖΛΛ¥Ρ
Ε≠¬ΠΧΧΓΉΛρΤΟΡξΛΙΛκ…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΓ ΩόΘΒΓΥΓΘ
ΓΓΛόΛΚΛœΜωΕ»≥ηΤΑ¬ΈΖœ…ΫΛρΚνά°ΛΙΛκΓΘ
ΩόΘΕ
Ωό2ΓΓ¥ΡΕ≠¥ΊœΔΥΓΒ§¬ßΓ ΈψΓΥ
ΔΘ≈ΎΟœΆχΆ―ΛΥ¥ΊœΔΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋ≈ΎΟœ¥πΥήΥΓ
ΓΓΓϋΙώ≈ΎΝμΙγ≥Ϊ»·ΥΓ
ΓΓΓϋ≈‘Μ‘ΖΉ≤ηΥΓ
ΓΓΓϋΙ©ΨλΈ©ΟœΥΓ
ΓΓΓϋΙ©Ε»Ά―ΩεΥΓ
ΓΓΓϋΖζΟέ ΣΆ―Οœ≤ΦΩεΛΈΚΈΦηΛΈΥΓΒ§ΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΔΘΗχ≥≤≈υΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋΤΟΡξΙ©ΨλΛΥΛΣΛ±ΛκΗχ≥≤Υ…ΜΏΛΈάΑ»ςΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋ¬γΒΛ±χάςΥ…ΜΏΥΓ
ΓΓΓϋΩεΦΝ±χ¬υΥ…ΜΏΥΓ
ΓΓΓϋΗ–Ψ¬ΩεΦΝ ίΝ¥ΤΟ ΧΝΦΟ÷ΥΓ
ΓΓΓϋάΞΗΆΤβ≥Λ¥ΡΕ≠ ίΝ¥ΤΟ ΧΝΦΟ÷ΥΓ
ΓΓΓϋΩεΤΜΥΓ
ΓΓΓϋ≤ΦΩεΤΜΥΓ1
ΓΓΓϋΨτ≤ΫΝεΥΓ
ΓΓΓϋΝϊ≤ΜΒ§ά©ΥΓ
ΓΓΓϋΩΕΤΑΒ§ά©ΥΓ
ΓΓΓϋΑ≠Ϋ≠Υ…ΜΏΥΓ
ΓΓΓϋ«άΟœΆ―ΛΈ≈ΎΨμΛΈ±χάςΥ…ΜΏ≈υΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋ≈ΎΨμΓΠΟœ≤ΦΩε±χάςΛΈΡ¥ΚΚΓΠ¬–ΚωΛΥ¥ΊΛΙΛκ¥ΡΕ≠Ψ ΜΊΩΥ
ΓΓΓϋΗχ≥≤ΖρΙ·»ο≥≤ΛΈ δΫΰΛΥ¥ΊΛΙΛκΗζΈ®
ΓΓΓϋ≈≈ΒΛΜωΕ»ΥΓ
ΓΓΓϋΞ§ΞΙΜωΕ»ΥΓ
ΓΓΓϋ≈≈«»ΥΓ
ΔΘ≤Ϋ≥Ί ΣΦΝΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋΙβΑΒΞ§ΞΙΦηΡυΥΓ
ΓΓΓϋΤ« ΣΒΎΛ”Ζύ ΣΦηΡυΥΓ
ΓΓΓϋ≤Ϋ≥Ί ΣΦΝΛΈΩ≥ΚΚΒΎΛ”άΫ¬Λ≈υΛΈΒ§ά©ΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋœΪΤ·Α¬Ν¥±“άΗΥΓ
ΓΓΓϋΤΟΡξ ΣΦΝΛΈΒ§ά©≈υΛΥΛηΛκΞΣΞΨΞσΝΊΛΈ ίΗνΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋΨΟΥ…ΥΓ
ΔΘ«―¥ΰ ΣΓΠΞξΞΒΞΛΞ·ΞκΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋΚΤάΗΜώΗΜΛΈΆχΆ―ΛΈ¬ΞΩ ΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋ«―¥ΰ ΣΛΈΫηΆΐΒΎΛ”άΕΝίΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΔΘή΢ΞκΞ°ΓΦΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋή΢ΞκΞ°ΓΦΛΈΜ»Ά―ΛΈΙγΆΐ≤ΫΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓΓΓϋή΢ΞκΞ°ΓΦΛΈΜ»Ά―ΛΈΙγΆΐ≤ΫΛΥ¥ΊΛΙΛκ¥πΥή ΐΩΥ
ΔΘΟœ ΐΨρΈψ
ΓΓΓϋ≈‘ΤΜ…ήΗ©ΓΠΜ‘Ρ°¬Φ¥ΡΕ≠¥πΥήΨρΈψ
ΓΓΓϋΗχ≥≤Υ…ΜΏΨρΈψ
ΔΘΛΫΛΈ¬ΨΛΈΆΉΒαΜωΙύ
ΓΓΓϋΕ»≥ΠΛΈΙ‘ΤΑΒ§»œ
ΓΓΓϋΗχ≈ΣΒΓ¥ΊΛ»ΛΈΤ±Α’ΜωΙύ
ΓΓΓϋΒ§ά©Α ≥ΑΛΈΜΊΩΥ
Ωό3ΓΓISO14001 ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΙΫΟέΓΠ±ΩΆ―Ξ’ΞμΓΦΓ PDCA ΞΒΞΛΞ·ΞκΓΥ
¥ΡΕ≠ ΐΩΥΓ Θ–ΓΥ
¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΛΈάωΫ–ΛΖ
¥ΡΕ≠±ΤΕΝ…Ψ≤ΝΓΓ
ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧ
ΥΓ≈ΣΛΫΛΈ¬ΨΛΈΆΉΒαΜωΙύ
?¥ΡΕ≠Χή≈ΣΓ Θ–ΓΥ
?¥ΡΕ≠Χή…ΗΓ Θ–ΓΥ
?¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»
ΓΓΞΉΞμΞΑΞιΞύΓ ΖΉ≤ηΓΥΓ Θ–ΓΥ
?±ΩΆ―¥…ΆΐΓ ΘΡΓΥ
?¥ΤΜκΒΎΛ”¬§ΡξΓΓ?ΫγΦι…Ψ≤Ν
…‘≈§ΙγΒΎΛ”άßάΒ ¬Λ”ΛΥΆΫΥ…ΝΦΟ÷
?¥ΤΚΚΓ ΘΟΓΥ
?Ζ–±ΡΦ‘ΛΥΛηΛκΗΪΡΨΛΖΓ ΘΝΓΥ
ΕέΒόΜω¬÷ΛΊΛΈΫύ»ςΒΎΛ”¬–±ΰ
Θ≈ΘΆΘ”ΛΈΞΒΞίΓΦΞ»ΆΉΝ«Γ߬Έά©ΒΎΛ”ά’«ΛΓΩΖ±ΈΐΓΠΦΪ≥–ΓΠ«ΫΈœΓΩΞ≥ΞΏΞεΞΥΞ±ΓΦΞΖΞγΞσΓΩΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ» ΗΫώΓΩ ΗΫώ¥…ΆΐΓΩΒ≠œΩ
4ΓΞ1ΓΓΑλ»ΧΆΉΒαΜωΙύΓΓΓΓΘ
≈ΘΆΘ”ΛΈ≥ΈΈ©Λ»ΑίΜΐΓ Θ–ΓίΘΡΓίΘΟΓίΘΝΞΒΞΛΞ·ΞκΒΎΛ”Ζ―¬≥≈Σ≤ΰΝ±ΓΥ
Ωό4ΓΓ¥ΡΕ≠Χή≈ΣΛ»¥ΡΕ≠Χή…ΗΛΈάΏΡξ
Ωό5ΓΓΜωΕ»≥ηΤΑ¬ΈΖœΛΈάΑΆΐΛΪΛι¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύΚνά°ΛόΛ«ΛΈΞΉΞμΞΜΞΙ
6 ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύ
ΜωΕ»ΫξΛΈΕ»Χ≥≥ηΤΑΓΠΚνΕ»ΓΠάΏ»ςΛ Λ…ΛράΑΆΐΛΙΛκ
ΜωΕ»ΫξΛΈΕ»Χ≥≥ηΤΑΓΠάΏ»ςΛ¥Λ»ΛΥΓΔ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓ ¥ΡΕ≠ΛΥ±ΤΕΝΛρΒΎΛήΛΙ≤Ρ«Ϋά≠ΛΈ
ΛΔΛκΆΉΝ«ΓΥΛράωΛΛΫ–ΛΙ
¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΛΈΜΐΛΡ¥ΡΕ≠±ΤΕΝΛρΧά≥ΈΛΥΛΖΓΔ¥ΡΕ≠±ΤΕΝΛρ≈άΩτ…Ψ≤ΝΛΖΛΤΓΔΞιΞσΞ·…’Λ±ΛΙΛκ
ΞιΞσΞ·…’Λ±ΛΒΛλΛΩ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΛΈΛ ΛΪΛ«ΓΔΦξΫγΫώΛΥΡξΛαΛΩΑλΡξ≈άΩτΑ ΨεΛΈΛβΛΈΛρ
Γ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛ»ΛΖΛΤ≈–œΩΛΙΛκ
Γ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛœΓΔΗΕ¬ßΛ»ΛΖΛΤ¥ΡΕ≠Χή≈ΣΓΠ¥ΡΕ≠Χή…ΗΛρΈ©ΛΤΛΤ≤ΰΝ±ΛΥΦηΝ»Λύ
Χή…ΗΟΘά°ΛΈΖΉ≤ηΛρKPΓ I Ε»ά”…Ψ≤ΝΜΊ…ΗΓΥ¥…ΆΐΛΙΛκΓΘ
ΘΒΘΉΘ±Θ»
≥ηΆ―ΤβΆΤ
Γω2008 «·ΛΈΜ»Ά―ΈΧΛΈ10% ΚοΗΚ
ΓωΦ÷ΈΨ ίΆ≠¬φΩτΛΈ10%ΛρΞœΞΛΞ÷ΞξΞΟΞ…Φ÷ΛΥΛΙΛκ
2008 «·ΛΈΜ»Ά―ΈΧΛΈ5% ΚοΗΚ
2008 «·ΛΈΜ»Ά―ΈΧΛΈ5% ΚοΗΚ
2009 «·ΙΊΤΰ… ΧήΩτΛΈΛΠΛΝΓΔ¥ΡΕ≠«έΈΗΖΩάΫ… ΛΈ≥δΙγΛρ15% Α ΨεΛ»ΛΙΛκ
ΛΔΛιΛφΛκ≥ηΤΑΛΥ¬–ΛΙΛκ¥ΡΕ≠Α’Φ±ΛρΙβΆ»ΛΒΛΜΓΔ¥ΡΕ≠ΕΒΑιΛρΦ¬ΜήΛΙΛκ
¥ΡΕ≠Χή≈Σ¥ΡΕ≠Χή…ΗΓ 2009 «·ΓΥ
Ξ§ΞΫΞξΞσΜ»Ά―ΈΧΛΈΚοΗΚ
≈≈ΒΛΜ»Ά―ΈΧΚοΗΚ
Ξ≥Ξ‘ΓΦΆ―ΜφΜ»Ά―ΈΧΛΈΆόά©
¥ΡΕ≠«έΈΗΖΩάΫ… ΛΈ≥δΙγΛΈΗΰΨε
¥ΡΕ≠ ίΝ¥≥ηΤΑΛΊΛΈΑ’Φ±ΛΈΙβΆ»
≥ηΤΑΞΉΞμΞΜΞΙ
1 ΜωΕ»≥ηΤΑ¬ΈΖœ…Ϋ
2 ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧάωΫ–ΛΖ…Ϋ
3 ¥ΡΕ≠±ΤΕΝ…Ψ≤ΝΞ«ΓΦΞΩ…Ϋ
4 ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧ≈–œΩ…Ϋ
5 ¥ΡΕ≠Χή≈ΣΓΠ¥ΡΕ≠Χή…ΗΛΥΦηΝ»Λύ
±ßΧνΫΛΓΓΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙΞ–ΞσΞ·¬ε…Ϋ
ΣΈ°Ε»ΛΈΞξΞΙΞ·ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»
APRIL 2009ΓΓΓΓ68
Λœ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΥΛΣΛ±ΛκΜωΕ»≥ηΤΑΛΈ¥ ΑΉ¬ΈΖœ
ΩόΛ«ΛΔΛκΓΘ
Λ≥ΛΈΛηΛΠΛΥΗΫΨθΛΈΕ»Χ≥ΞΉΞμΞΜΞΙΛρ
Ξ’ΞμΓΦΩόΛΥΛόΛ»ΛαΛκΓΘ
ΛΫΛΖΛΤΓΔ≥ΤΞΉΞμΞΜΞΙΛΥ
ΛΣΛ±ΛκΓ÷¥ΡΕ≠ΛΥ±ΤΕΝΛρΆΩΛ®ΛκΆΉΝ«ΓΉΓ Θ…Θ”Θœ
Θ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±Λ«ΛœΓ÷¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛ»ΗΤΛ÷ΓΥΛρΈσΒ≠
ΛΙΛκΓΘ
ΛΫΛλΛΨΛλΛΈ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΛΥΛΡΛΛΛΤΓΔΛΫΛΈ±Τ
ΕΝΛ»¥ΊœΔΥΓΛράΑΆΐΛΙΛκΓ ΩόΘΖΓΥΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΛ»Λ≠ΓΔ¥ΡΕ≠ΛΊΛΈ±ΤΕΝΛœΓΔΜ»Ά―ΛΙΛκΜώΗΜ
ΛρΓ÷ΞΛΞσΞΉΞΟλùΓΔ«”Ϋ– ΣΛρΓ÷ΞΔΞΠλιΞΟλù
Λ»ΛΖΛΤ §ΈύΛΙΛκΓΘ
Ξ»ΞιΞΟΞ·ΛΈ±Ω≈ΨΛ»ΛΛΛΠ¥ΡΕ≠
¬ΠΧΧΛ«ΛΔΛλΛ–ΓΔΞΛΞσΞΉΞΟΞ»ΛœΜ»Ά―ΛΒΛλΛκΞ§ΞΫΞξ
ΞσΛ«ΛΔΛξΓΔΗœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώΛ§ΛΫΛΈ±ΤΕΝΛ»Λ ΛκΓΘ
Λ≥ΛλΛιΛΥ¥ΊΛΙΛκ¬–ΨίΥΓΒ§ά©ΛœΓΔΨΟΥ…ΥΓΓΔΨ Ξ®
ΞΆΥΓΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΞΔΞΠλιΞΟΞ»Λœ«”ΒΛΞ§ΞΙΛ«ΛΔΛξΓΔ
Ωό6ΓΓ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΥΛΣΛ±ΛκΜωΕ»≥ηΤΑ¬ΈΖœΩό
≤ΌΦγΛΈΙ©Ψλ
Ξ»ΞιΞΟΞ·ΆΔΝς
ΤΰΗΥ
ί¥…
Ϋ–ΗΥ
Ϋ–≤Ό
Ξ»ΞιΞΟΞ·ΆΔΝς
ΜωΧ≥ΫξΞ’Ξ©ΓΦΞ·ΞξΞ’Ξ»
Ωό7ΓΓ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΥΛΣΛ±Λκ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΛ»¥ΡΕ≠±ΤΕΝ
ΞΛΞσΞΉΞΟΞ»
ΔΘΞ»ΞιΞΟΞ·ΛΈ±Ω≈Ψ
ΔΘΞ’Ξ©ΓΦΞ·ΞξΞ’Ξ»ΛΈ±Ω≈Ψ
ΔΘΚ≠ ώΚνΕ»
ΔΘΜωΧ≥Ϋξ
ΔΘΜωΧ≥Ϋξ
ΔΘΜωΧ≥Ϋξ
Ξ§ΞΫΞξΞσΛΈΜ»Ά―
≈≈ΈœΓΠΖΎΧΐΛΈΜ»Ά―
ΞΙΞ»ΞλΞΟΞΝΞ’ΞΘΞκΞύΛΈΜ»Ά―
ΈδΟ»ΥΦΛΈΜ»Ά―
Θ–ΘΟΛΥΛηΛκ≈≈ΈœΜ»Ά―
Ξ…Ξ≠ΞεΞαΞσΞ»ΛΈΜ»Ά―
λΠΓΦΞΪΓΦΞ»ΞξΞΟΞΗΛΈΜ»Ά―
Ηœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώ
Ηœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώ
Ηœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώ
Ηœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώ
Ηœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώ
Ηœ≥ιά≠ΜώΗΜΛΈΨΟ»ώ
ΓωΨΟΥ…ΥΓ
ΓωΨ Ξ®ΞΆΥΓ
ΓωΨΟΥ…ΥΓ
ΓωΨ Ξ®ΞΆΥΓ
ΓωΞΑΞξΓΦΞσΙΊΤΰΥΓ
ΓωΨ Ξ®ΞΆΥΓ
ΓωΨ Ξ®ΞΆΥΓ
ΓωΞΑΞξΓΦΞσΙΊΤΰΥΓ
«”ΒΛΞ§ΞΙ
«”ΒΛΞ§ΞΙ
ΩΕΤΑ
Νϊ≤Μ
«―¥ΰ Σ
«”ΒΛΞ§ΞΙ
«”ΒΛΞ§ΞΙ
«―¥ΰ Σ
¬γΒΛ±χάς
¬γΒΛ±χάς
≈ΎΨμ±χάς
¬γΒΛ±χάς
¬γΒΛ±χάς
≈ΎΨμ±χάς
Γω¬γΒΛ±χάςΥ…ΜΏΥΓ
Γω¬γΒΛ±χάςΥ…ΜΏΥΓ
ΓωΩΕΤΑΒ§ά©ΥΓ
ΓωΝϊ≤ΜΥ…ΜΏΥΓ
Γω«―¥ΰ ΣΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
Γω¬γΒΛ±χάςΥ…ΜΏΥΓ
Γωή΢ΞκΞ°ΓΦΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓωΗχ≥≤ΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
Γω«―¥ΰ ΣΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΓωΗχ≥≤ΛΥ¥ΊΛΙΛκΥΓΈß
ΞΔΞΠλιΞΟΞ»
Ωό8ΓΓΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΛΈΤΟΡξΓ ΈψΓΥ
ΕέΒόΜΰ
»σΡξΨοΜΰ
ΡξΨοΜΰ
ΞξΞΙΞ·ΞλΞΌΞκ
Γ ΟμΘ≤ΓΥ
¥ΡΕ≠±ΤΕΝ
¥ΡΕ≠¬ΠΧΧ
≥ηΤΑ
ΩΆ¬ΈΛΊΛΈ±ΤΕΝ
ΜώΗΜΛΈΗœ≥ι
±χάς
Ξ”ΞΗΞΆΞΙ¥ΊΖΗ
»·άΗΛΖΤώΛΛ
»·άΗΛΖΑΉΛΛ
ΞξΞΙΞ·…Ψ≤ΝΓ Ομ1ΓΥ ΒωΆΤ≤Ρ«ΫΞλΞΌΞκΓ Ομ3ΓΥ
…―ΓΓ≈Ό¥μΗ±≈ΌΓ ±ΤΕΝ≈ΌΓΥ
±ΩΆ―¥…Άΐ
ΜώΗΜΛΈΗœ≥ιΜώΗΜΛΈΗœ≥ι
ΟμΘ±ΓΓΞξΞΙΞ·…Ψ≤ΝΓΓ1 ≈ά= ±ΤΕΝΨ°ΓΓ2 ≈ά= ±ΤΕΝΟφΓΓ3 ≈ά= ±ΤΕΝ¬γ
ΟμΘ≤ΓΓΞξΞΙΞ·ΞλΞΌΞκ=Γ÷¥μΗ±≈ΌΓ ±ΤΕΝ≈ΌΓΥΓΉΛΈΞξΞΙΞ·…Ψ≤ΝΛΈΙγΖΉ≈ά
Ομ3ΓΓ≤Ω≈άΑ ΨεΛρΓ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛ»ΛΙΛκΛΪΛΥΛΡΛΛΛΤΛœISO ΛΥΒ§ΡξΛ§Λ Λ·ΓΔ≥ΤΦ“Λ§Τ»ΦΪΛΥ»ΫΟ«ΛΙΛκΓΘ
3 1 1 3 1 6 Γϊ Γϊ
3 1 1 1 2 5 Γϊ Γϊ
ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧ
Γ ΘΕ〜ΘΖ≈άΓΥ
ΦηΛκΛΥ¬≠ΛιΛ ΛΛΞξΞΙΞ·
Γ Θ±≈άΑ ΨεΓΥ
ΒωΆΤ≤Ρ«ΫΛ ΞξΞΙΞ·
Γ Θ≤≈άΑ ΨεΓΥ
ΒωΆΤ…‘≤Ρ«ΫΛ ΞξΞΙΞ·
Γ ΘΗ≈άΑ ΨεΓΥ
ΟφΡχ≈ΌΛΈΞξΞΙΞ·
Γ Θ≥〜ΘΖ≈άΓΥ
ΥΓ≈ΣΛΫΛΈ¬ΨΛΈ
ΆΉΒαΜωΙύ
Κ«Λβ»·άΗΛΖΤώΛΛ
Ξ§ΞΫΞξΞσ
ΛΈΜ»Ά―
Ξ»ΞιΞΟΞ·ΛΈ
±Ω≈Ψ
Ξ…Ξ≠ΞεΞαΞσΞ»
ΛΈΜ»Ά―
ΜωΧ≥Ϋξ
¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΞΛΞσΞΉΞΟΞ»¥ΡΕ≠±ΤΕΝ¬–ΨίΥΓΒ§ά©ΞΔΞΠλιΞΟΞ»¥ΡΕ≠±ΤΕΝ¬–ΨίΥΓΒ§ά©
69ΓΓΓΓAPRIL 2009
¬–ΨίΥΓΒ§ά©Λœ¬γΒΛ±χάςΥ…ΜΏΥΓΛ»Λ ΛκΓΘ
ΓΓΦΓΛΥΓ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛΈΤΟΡξΛ«ΛΔΛκΓΘ
Ωό
ΘΖΛΥΦ®ΛΖΛΩΛηΛΠΛΥΓΔΞξΞΙΞ· §άœΛ»ΞξΞΙΞ·ΛΈΒωΆΤ
≤Ρ«ΫΛ ΞλΞΌΞκΛρ…Ψ≤ΝΛΖΓΔ≈άΩτΛΈΙβΛΛΛβΛΈΛρΓ÷Οχ
ΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛ»ΛΖΛΤΤΟΡξΛΙΛκΓΘ
ΛΝΛ ΛΏΛΥ≤Ω
≈άΑ ΨεΛρΓ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛ»ΑΧΟ÷…’Λ±ΛκΛΈΛΪΓΔ
ΛΔΛκΛΛΛœΓ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛρΛΛΛ·ΛΡΒσΛ≤Λκ
ΛΪΛΥΛΡΛΛΛΤΛœΘ…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±ΛΈΨρ ΗΛΥΛœΒ§
ΡξΛ§Λ Λ·ΓΔ≥ΤΦ“ΛΈΚέΈΧΛΥ«ΛΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΡΧΨο
Λœ≈άΩτΛΈΙβΛΛΛβΛΈΛΪΛιΜΑ〜ΜΆΙύΧήΛρΓ÷ΟχΛΖΛΛ
¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛΥΒσΛ≤ΛκΛ≥Λ»Λ§¬ΩΛΛΓΘ
?¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύΛΈΚωΡξ
ΓΓΦΓΛΥΓΔ¥ΡΕ≠Χή≈ΣΛ»¥ΡΕ≠Χή…ΗΛΥ¥πΛ≈ΛΛΛΤΓΔΓ÷¥Ρ
Ε≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύΓΉΛρΚνά°ΛΙΛκΓΘ
¥ΡΕ≠
ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύΛ»ΛœΙ‘ΤΑΖΉ≤η…ΫΛΈΛ≥Λ»
Λ«ΛΔΛκΓΘ
Χή…ΗΛρΟΘά°ΛΙΛκΛΩΛαΛΥΓΔ≤ΩΛρΓΔΟ·Λ§ΓΔ
ΛΛΛΡΛόΛ«ΛΥΓΔΛ…Λ≥Λ«ΓΔΛ…ΛΈΛηΛΠΛΥΓ ΘΒΘΉΘ±Θ»ΓΥ
Ι‘ΤΑΛΙΛκΛΈΛΪΛρΖΉ≤η…ΫΛΥΆνΛ»ΛΖΙΰΛύΛοΛ±Λ«ΛΔ
ΛκΓΘ
Λ≥Λ≥ΛόΛ«Λ§ΓΔΘ–ΘΡΘΟΘΝΞΒΞΛΞ·ΞκΛΈΘ–Γ ΖΉ≤ηΓΥ
ΛΈΟ ≥§Λ«ΛΔΛκΓΘ
?±ΩΆ―¥…Άΐ
ΓΓ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύΛρΦ¬Ι‘ΛΖΓΔΛόΛΩ
Φ¬Ι‘ΛΥ…§ΆΉΛ»Λ ΛκΜώΗΜΛΈ≥Έ ίΓΔΕΒΑιΓΔ ΗΫώ¥…ΆΐΓΔ
Β≠œΩ¥…ΆΐΛΈΚνΕ»ΛρΤ±ΜΰΛΥΩ ΛαΛκΓΘ
?¥ΤΜκΛΣΛηΛ”¬§Ρξ
ΓΓΓ÷ΟχΛΖΛΛ¥ΡΕ≠¬ΠΧΧΓΉΛρ¥ΤΜκΓΠ¬§ΡξΛΙΛκΦξΫγ
Γ ΞΉΞμΞΜΞΙΞόΞΟΞΉΓΥΛΈ≥ΈΈ©Λ»ΑίΜΐΛ§…§ΆΉΛ»Λ ΛκΓΘ
ΞΉΞμΞΜΞΙΞόΞΟΞΉΛΥΛœΆΉΒαΜωΙύΛ§άΏΛ±ΛιΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
Ξ―Ξ’Ξ©ΓΦΞόΞσΞΙΓΔ±ΩΆ―¥…ΆΐΛ ΛιΛ”ΛΥΝ»ΩΞΛΈ¥Ρ
Ε≠Χή≈ΣΓΠΧή…ΗΛ»ΛΈ≈§Ιγά≠ΛρΡ…άΉΛΙΛκΛΩΛαΛΈΨπ
σΛρΒ≠œΩΛΙΛκΛ≥Λ»ΓΔ¥ΤΜκΒΓ¥οΛΈΙΜάΒΓΠΑίΜΐΛΣ
ΛηΛ”ΛΫΛΈΒ≠œΩΛρΛ»ΛκΛ≥Λ»ΓΔ¥ΡΕ≠ΥΓΒ§ά©ΛΊΛΈ≈§
Ιγά≠ΛρΡξ¥ϋ≈ΣΛΥ…Ψ≤ΝΛΙΛκΦξΫγΛρ≥ΈΈ©ΓΠΑίΜΐΛΙ
ΛκΛ≥Λ»Λ Λ…Λ«ΛΔΛκΓΘ
?ΫγΦι…Ψ≤Ν
ΓΓΫγΦι…Ψ≤ΝΛ»ΛœΓΔ¥ΡΕ≠ΥΓΒ§ά©ΛΊΛΈ≈§Ιγά≠Λρ
Ρξ¥ϋ≈ΣΛΥ…Ψ≤ΝΛΖΒ≠œΩΛΥΜΡΛΙΛ≥Λ»ΛρΜΊΛΙΓΘ
Θ…Θ”
ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±Λ§ΞΙΞΩΓΦΞ»ΛΖΛΩΑλΕεΕεœΜ«·»«ΛΈ
ΆΉΒαΜωΙύΛΥΛœΛ ΛΪΛΟΛΩΛ§ΓΔΤσΓΜΓΜΜΆ«·»«Λ«
ΩΖΛΩΛΥΡ…≤ΟΛΒΛλΛΩΓ Β§≥ ΆΉΒαΜωΙύΓß 4.5.2.1 Λ»
4.5.2.2ΓΥΓΘ
?¥ΤΚΚ
ΓΓΤβ…τ¥ΤΚΚΛΣΛηΛ”¬ηΜΑΦ‘ΛΥΛηΛκ¥ΤΚΚΛρΦ¬Ι‘ΛΖΓΔ
Θ≈ΘΆΘ”Λ§Ά≠ΗζΛΥΒΓ«ΫΛΖΛΤΛΛΛκΛΪΛ…ΛΠΛΪΛρΗΓΨΎΛΙ
ΛκΓΘ
Λ≥ΛΈ¥ΤΚΚΛΥΛηΛξΓΔ…‘≈§ΙγΜωΙύΛδ≤ΰΝ±ΛρΆΉ
ΛΙΛκ §ΧνΛ§ΜΊ≈ΠΛΒΛλΛΩΛιΓΔάßάΒΫηΟ÷ΛρΦ¬Ι‘ΛΖΓΔ
Θ≈ΘΆΘ”ΛρΒ§≥ ΆΉΒαΜωΙύΛΥ≈§ΙγΛΙΛκΛηΛΠΛΥ≤ΰΝ±
ΛΙΛκΛ≥Λ»Λ§ΆΉΒαΛΒΛλΛκΓΘ
?Ζ–±ΡΦ‘ΛΥΛηΛκΗΪΡΨΛΖ
ΓΓ¥ΤΚΚΛΈΖκ≤ΧΛœΞ»ΞΟΞΉΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΛΥ σΙπΛΒΛλ
ΛΤΓΔΓ÷Ζ–±ΡΦ‘ΛΥΛηΛκΗΪΡΨΛΖΓΉΓ ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»Ξλ
Ξ”ΞεΓΦΓΥΛΈΞΙΞΤΞΟΞΉΛρΤßΛύΓΘ
…§ΆΉΛΥ±ΰΛΗΛΤ¥Ρ
Ε≠ ΐΩΥΛδ¥ΡΕ≠Χή≈ΣΛΈΫΛάΒΓΔ¥ΤΜκΛΣΛηΛ”¬§ΡξΓΠ
ΫγΦι…Ψ≤Ν ΐΥΓΛΈ≤ΰΝ±Λ§Ι‘ΛοΛλΛκΓΘ
ΓΓΑ ΨεΫ“ΛΌΛΩΛηΛΠΛΥΓΔΘ…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±ΛΈΞΉ
ΞμΞΜΞΙΛβΛόΛΩΓΔ¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσλιΞμΞΑΞιΞύΛρ
ΚωΡξΛΖΓ PlanΓΥΓΔΛΫΛλΛρ±ΩΆ―¥…ΆΐΛΖΓ DoΓΥΓΔ¥Τ
ΜκΛΣΛηΛ”¬§ΡξΓΩ¥ΤΚΚΓ CheckΓΥΛΖΓΔΖ–±ΡΦ‘ΛΥ
ΛηΛκΗΪΡΨΛΖΓ ActΓΥΛρΙ‘ΛΠΛ»ΛΛΛΠΘ–ΘΡΘΟΘΝΞΒΞΛ
Ξ·ΞκΛΪΛιΙΫά°ΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΘ–ΘΡΘΟΘΝΞΒΞΛΞ·ΞκΛρΖΪΛξ ÷ΛΖΓΔΖ―¬≥≈Σ
≤ΰΝ±ΛρΩ ΛαΛκΛ≥Λ»ΛΥΛηΛΟΛΤΘ≈ΘΆΘ”ΛΥΥαΛ≠ΛρΛΪΛ±
ΛΤΛΛΛ·ΓΘ
ΛΫΛΈΖκ≤ΧΛ»ΛΖΛΤ¥ΡΕ≠ΧΧΛΥΛΣΛ±Λκ¥κΕ»
ΛΈΦ“≤ώ≈Σά’«ΛΛρΝ¥ΛΠΛ«Λ≠ΛκΓΘ
Λ≥ΛλΛιΛΈΞΖΞΙΞΤΞύ
Λρ ΣΈ°¥κΕ»ΛΈΖ–±ΡάοΈ§ΛΥΦηΛξΙΰΛσΛ«ΓΔ…αΟ ΛΈ
Μ≈ΜωΛΈΑλ…τΛ»ΛΖΛΤΦ¬Ι‘ΛΙΛκΝ»ΩΞΛρΙΫΟέΛΖΛ Λ±
ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΓΘ
Μ≤ΙΆ ΗΗΞ
ΔΘΓΊΘ…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±¥ΡΕ≠ΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΛ»
¥ΤΚΚΛΈΦ¬Χ≥ΓΌ¬γ…ΆΨ±Μ ΟχΓΔΞΣΓΦΞύΦ“ΓΔΤσΓΜΓΜΤσ
«·
ΔΘ≥τΦΑ≤ώΦ“ΤϋΥήΙώΚίΒ§≥ Ξ≥ΞσΞΒΞκΞΤΞΘΞσΞΑΓ÷Θ ΘΝΘ¬
«ßΡξΓΓΘ
…Θ”ΘœΘ±Θ¥ΘΑΘΑΘ±Ω≥ΚΚΑςΗΠΫΛΞ≥ΓΦΞΙΓΉΗΠ
ΫΛΜώΈΝΓ ΤσΓΜΓΜΜΑ«·ΤσΖν≥ΪΚ≈ΓΥ
±ßΧνΓΓΫΛΓ ΛΠΛΈΛΣΛΒΛύΓΥ
1946 «·άΗΛόΛλΓΘ
άΡΜ≥≥Ί±Γ¬γ≥Ί¬¥ΓΘ
±―ΙώΙ“ΕθΓΔΞ’ΞιΞΛΞσΞΑΞΩΞΛΞ§ΓΦΙ“ΕθΓΔ
Ξ®ΞΔΓΠΞΪΞ ΞάΓΔΞΗΞψΞ―ΞσΓΠΞΖΞßΞσΞΪΓΦΓΔ
ήηΞΜΞκΓΠΞΗΞψΞ―ΞσΛρΖ–ΛΤΓΔ2008
«·ΛΥΞμΞΗΞΙΞΤΞΘΞ·ΞΙΞ–ΞσΞ·ΛράΏΈ©ΓΔ
¬ε…ΫΛΥΫΔ«ΛΓΘ
ΗΫΚΏΛΥΜξΛκΓΘ
http://www.e-logisticsbank.com/ΓΔ
e-mailΓßuno-osamu@e-logistics
bank.com
|