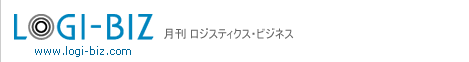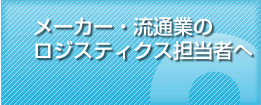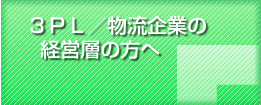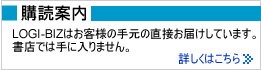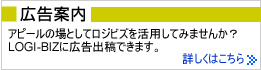|
*������PDF���ƥ����Ȥ���Ф����ǡ����Ǥ���������PDF������������

�ǡ��������Ǥϸ����ʤ�
�����ʲ��ټҤϡ�ǯ����졻�����ߤζ�̳�ѿ�
�ʲ�����
�ع��뿩��Ұ���Ʋ���뿩��Ҥʤɤ��
����ܵҤȤ��ơ��̴��졦�����϶��ϻ�Ĥλ���
����Ƥ��롣
�桹���ܥ����ե����ȥ�ʣ�
�̣ơˤϡ������ˣټҤη����Ҥ�������︺��
���ݡ��Ȥ������Ȥ����ä���
����Ϥ����ټ���
�ΤǤ�ꤿ���Ȥ�����
�����̤˿��ʲ����ϰ�̩�巿�η�����������Ʊ��
��ҤǤ��äƤ���Ƚ�ˤ�äơ��ܵҹ����Ϥ��
�����ɲ���ʸ���Ф����н���ˡ�ޤ����Ƥ��㤦��
ô���αĶȥޥ����Ƚ�Ĺ�ιͤ������ˤ�������
���Ƚ�Υ����ӥ���٥���礭���ƶ����롣
����
��夫���Χ�Dz����Ĥ��Ƥ�̵���������롣
�������Ǻ���Ϥޤ����ټҤαĶȽ�Τʤ��Ǥ��
�ⶥ��η㤷�������Ƚ���оݤȤ��ơ��������
��ľ�����ȤȤʤä���
�ټҤ�Ǽ�ʤˤϡ�?�Ķȥ�
��ˤ��������?�������Ѥμ��ҥ����åդˤ��
������?����������ˤ���������λ��Ĥ�������
���������
�桹�ϴ�����ǰ��Τơ��ޤ���
���줾��������μ��֤��İ����褦�ȹͤ�����
�����ӥǡ������ˤ��ơ������������ν�ʣ���
�����Ƽ�ξ���Ѻ��̤�����å����뤳�ȤϤǤ��롣
���������ǡ��������Ǥϸ���μ¾�ϸ����Ƥ���
����
�����ǸĿ�Ū�ˤ������˵פ��֤�Ȥʤ�Ȳ�
����Ĵ����Ԥ����Ȥˤ�����
�����ȥ�å��ν�
���ʤ˾�����Ǹ�����ǧ����ΤǤ��롣
���
�����Ƥ�������Ǥʤ��Ѥ߹��ߤ��Ѥ߹ߤ���
��Ȥʤɤϼºݤ˼�������
���оݤȤʤä��Τϡ������Ƚ�����ܤ���������
���ν�ʣ���Ƥ���»��Ƚ����ĤΥ롼�Ȥ���
�����װ�ޥ롼�ȡ�
���ˤ�����ˤޤ�������롼
�Ȥ���Ĵ�����Ƥ�����������ޤǤ˻����֤����롣
Ĵ�����������ī�����ε��������롣
ɮ��
�Τʤޤä����ΤˤϤ��ʤ꤭�Ĥ�����ƥ���
���Ǥ��ä���
�������Ĵ���ϣ����Ƚ�μ�������ʬ������ꤷ
����
�����Ƚ�θ���Ǥ���ī������ʬ���鼫��
������ξ���Ѥ߹��ߺ�ȤϤ��롣
�������̤�
�ƱĶȥޥ��������Ǥ�����åդ�Ǽ����ɼ�Ⱦȹ�
���ʤ��顢�ɥ饤����¢�������ʤȥԥå���
�Ƥ��������ʤ�ԤäƼ�ξ���Ѥ߹��ࡣ
�Ǹ����
����ʸ��̵ͭ���ǧ���롣
����ؤν�ȯ�ϼ�����
���Ǥ��ä���
���桹�ˤȤäơ��������������Ȥʤ��Ѥ߹��ߺ�
�Ȥ����˽��פʥݥ���Ȥΰ�ĤǤ��롣
��ǰ��
�뻡��Ԥä���̡��Ķȥޥ�ˤ�뼫�������ˤ⡢
��ˡ����Ĥ��뤳�Ȥ�ʬ���ä���
�٥ƥ��Ұ���
¿���ϸ������������餻�ơ����ϱĶȤ�
���˽��ƤƤ�����
������Ф��ƿ��ͤ���̼Ұ��ϡ�
���ֻ����ͥ�褵���ơ����ι�֤˱ĶȤ���Ȥ�
����������Ǥ��ä���
���ǡ��������ǤϤ��������Τ�ʤ�������������
�����礭�����λ��ϱ�����Ƥ��롣
Ʊ�褷������
���Ȥ�ƻ������β��á�Ǽ��������夷����β�
�Ф��μ�������Ǽ�ʻ���Ω���ʤɡ���ä�ñ
��ʺ�Ȥ��̤��ơ������Υҥ�Ȥ����뤳�Ȥ���
���Ĵ������Ū����
����ˤ�äơ�ɮ�Ԥϰʲ���
���Ĥλ��¤��ͤ��ߤ�뤳�Ȥ��Ǥ�����
?���ҤΡֶ��ߡס�¾�ҤȤκ��̲��װ���Ұ���
������ͭ�Ǥ��Ƥ��ʤ�
?��ʬ��ô���ǤϤʤ�������Ǽ�ʶ�̳���Ф����
JULY 2009����16
�����Ĵ���Ǹ���μ��֤��İ�
�����¿����Ѻ�Ψ�ʤɤΥǡ���������Ƚ�Ǥ�����ˤ��ܤ�
������
�����ͤ��������ȥ�å��ν����ʤ�Ʊ�褷���������
������Ȳ�����Ĵ����и礷����
����ͽ�ۤ��Ƥ��ʤ��ä�
���¤����������餫�ˤʤäƤ�����
���ʲ�Y�Ҥ�������︺
�ץ��������ȤǤΤ��Ȥ��ä���
�������졡���ܥ����ե����ȥ����ɽ
����dzؤָ����������78 ���
�ȥ�å����¡�¿�ʳ���¤�˥�������
�� �� �������������Ⱥ︺
���١�����ʤ�
?�ֻ��ֻ���פ�����������ޤ��Ǥ��뤿��ˡ�
�������Ѱ���褫������Ƥ��ʤ�
��?���Ҥζ��ߤ˴ؤ��ơ�Ʊ�褷���Ұ������˿�
�ͤ��Ȥ�������¨Ǽ�Ǥ��뤳�ȡס������ʤ��¤����ȡס�
�֤����ͤȤΥ��ߥ�˥��������ס��֥����ڡ���
�ѥ�ե�åȡפʤɡ������������㤦���Ȥ����
���ȳ��������ȤǤ���ټҡ����κǷ�����ô
����������Ƚ�ȸ��äƤ⡢����ϸĿ;�Ź�ν�
�ޤ�Ǥ��ä���
���Τ���?��ʬ���ĶȤ�ô������
���ʤ�������Ǽ�ʺ�Ȥˤϵ�������ʤ���
���
�Ȥ��ơ����Ƚ�Ȥ��Ƥ��ȿ��Ϥ��ĶȤ˳褫����
�Ƥ��ʤ��Ȥ������Ȥ���
���ֻ������Ȥ���������
��?�ֻ��ֻ���פ�����������ޤ��Ȥ����Τϡ�
�ټҰʳ��ˤ⸫���븽�ݤ���
���λ��ֻ���ϡֻ�
���ӡפȤ�������ɤ�������äƤ���Τ�������
������
�������٤�뤳�Ȥ���𤹤�е��Ƥ���
�Ϲ�����Τ���
���Ф˽�餹��ɬ�פ�����Τ���
�����⤽����ֻ��꤬���μ�����Ǽ�ʾ��˾�
���äƤ���ΤϤʤ�����
Ǽ���褫�����Ū������
�����������
����Ȥ�ټҤ�Ǽ�ʻ��֤�������
������ΤʤΤ���
�����������αĶȥޥ��
ʬ���äƤ��Ƥ⡢���θ塢�̤�ô���Ԥ˰����Ѥ�
��Ƥ����֤˸�����ͳ��ʬ����ʤ��ʤäƤ��ޤ���
��̤Ȥ��ƽ��İ������ˡֻ��ֻ���פȤ������
�������Ĥ롣
�����������ֻ�������������ӥ��ν��פʥơ�
�ޤǤ��ꡢ�ޤ������θܵҤ���������뷹
���ˤ���ΤϳΤ�����
��������������Ȥ�������
���б����ʤ���С���������˼�ξ����Ф�����
�䤹���Ȥˤʤ롣
���ֻ������Ǽ�ʸ��������Ψ
���������㲼���Ƥ��ޤ���
�����ä����������Ѱ��������֤��Ƥ���Τˡ�
������ɲ�ȯ���Ѥζ۵�Ǽ�����٤ˤ������ѤǤ�
�Ƥ��ʤ��Τ⡢Ʊ����ͳ������ä���
���Ҥξ���
�ǤϱĶȥޥ��������뤳�ȤΥ��åȤϾ�����
�ʤ���
���괶����Ǽ����ο��ʸˤ�ê������Ǥ��
���롣
���뤤�ϡ�ȯ��ô���ԤΥ��å�Ĺ���ä�
�Ǥ���褦�ˤʤꡢ��ʸ�ˤĤʤ�������Ψ��Ǽ
�ʤˤ��̣�����롣
����Ȥ�ȣ��Ҥΰ������ʤϸ�̩�ʲ����Ӵ�����
ɬ�פǡ�����٤��ʼ�갷���������롣
����
���ʤǤ���м�ξ���Ѥ߹������ˡ�����β��٤�
����Υ�٥�ޤDz����Ƥ���ɬ�פ����롣
���θ�
��ɥ��γ��ĤΤ��Ӥ˲��٤��夬�äƤ��ޤ����ᡢ
��˲��٤�����å����ʤ���Фʤ�ʤ���
���ޤ���ä����ʤϡ��̾�ͤ����Ƥ���ʾ��
�Ȥ���
�Ѥ߽Ť����������ä�����˽�˰����С���
�Ȥ���줿�ꡢ���ޤ��ˤ줿�ꤹ�롣
����������
�ˤϤʤ�ʤ���
����ˤϾ�̣���¤��ɤ߾夲�ˤ�
��ȹ硢Ǽ����Ǥ���������Ф��ˤ��êǼ�ʤ�
�ɡ�������Ψ�����ʪή��Ҥ�Ǥ����ˤ��Ը�
��������¿����
̵���˥����ȥ�������ʤ��
���б��Ǥ��ʤ��ɥ饤�С����ФƤ��롣
���������Ȥ��äơ�����٤����б���������
�櫓�Ǥ⡢���̤˼�갷���������ʤä�
����櫓�Ǥ�ʤ�Ǽ������Ф��Ƥ⡢���ƱĶȥ�
��ǽ�������Ȥ����ΤϤ��ޤ�ˤ����Ψ�Ǥ��ä���
�����ˣ����Ƚ�ȥ��ꥢ����ʣ���Ƥ���»��Ƚ�
����ĤΥ롼�Ȥβ�����Ԥʤä���
��ĤΥ롼
�Ȥ����餫��ʪ�̤��餺������ɬ�פǤ��ä���
�⤦��ĤΥ롼�Ȥ�ȿ�Ф˥���ѥ����С����Ƥ�����
���Ե�Υ��¾�Υ롼�Ȥ�ʿ���ͤ����ܤ�¿���λ�
�Ȼ��֤�ȯ�����Ƥ�����
�����Ƚ�������롼�ȡ�
Ǽ����Ȥν�ʣ�⤫�ʤ�ȯ�����Ƥ�����
�ƻ��Ƚ�
���ȼ����ۼ֤�Ԥʤ��������롼�Ȥ����ꤷ�Ƥ�
�뤿����ä���
���������ˤĤ��Ƥϸ�ˡ������Ƚ�ȣ»��Ƚ��
�ۼֶ�̳��층�����뤳�ȤǼ�ξ��������渺��
���뤳�Ȥ��Ǥ�����
�ޤ��������Ѱ��μ�ξ��ž��
��졦��ž������ž�ذ����夲���Ʊ��
�ˡ��Ķȥޥ��������ô�餷����ξ��������
�������ȥ��ȥ���ѹ����Ƽ�ξ�μ���
����ڸ�������
�������Ĵ���������ʳ��˿ʤ����
���٤϶���ʪ
ή��ңμҤ˰������Ƥ��������롼�ȤǤ��롣
��
ʪ���Ѥ߹��ߺ�Ȥϡ���������������������
����ī�ͻ�����ʬ�˳��Ϥ��롣
��ξ�ν�ȯ�⼫��
17����JULY 2009
������ƥ�����������
���A ������Ȥ��ƻ��ֻ��긷��
���B ������Ȥ��ƻ����ӻ��긷��
���C Ǽ�ʻ��֤�����������Ƥ��뤬�������ѹ�
��Ĥϼ�����ߤޤ��ǽ��������
���D Ǽ�ʻ��֤�����������Ƥ��뤬�������ѹ�
��Ĥϼ���˱ƶ��ʤ��Ԥ����Ȥ��Ǥ����ǽ
��������
���E ������Ϣ���������л��ֳ��Ǥ�����ʤ�
���F ����Ĵ����ǽ���ϸ���Ǥλפ����ߥ�٥�
������������ᤤ��
����ʬ�ȳ���ʬ���Ѥ߹���
���֡���ξ��ȯ���֤����֤��餹���Ȥǽв٥�
�ڡ�����ͭ���˳��Ѥ����ޤ�Ǽ�ʻ��֤�Ĵ������
��������
���ޤ�������μ�ξ��Ǽ�ʸ�ˤϣ����Ƚ�����
���ˡ��μҤμָˤ�ľ�����롣
���Τ���桹�β�
���Ĵ���⡢ȯ���μҤμָˤ���Ԥʤ����Ȥ�
������
����äȤ�桹�Τ褦�ʳ����Υ��륿��Ȥ�
�����Ĵ�����뤳�Ȥ�μҤ������פ��櫓�Ϥʤ���
�ټ礫��������Ǥ��뤿���Ǥ�櫓�ˤ⤤���ʤ�
�����줿�������Ƥ����Ϥ�����
��Ȥ�������ˤ⡢
���ޤ��Ϳ��������ޤȤ��ȤʤäƤ��ޤ���
����������꤬ۤɬ�פǤ��ä���
���ºݡ�ͥ���ʥץ��ɥ饤�С��ϻ�������������
��꤬�Ǥ������äƤ��롣
����Τɤ��˲����Ѥ�
�Ǥ��뤫���Ϥä����Ƭ�����äƤ��롣
���ʤ���
��Ф���������桹���Ф���ٻ���֤����ξ���
���ĽФ��Ƥ��������פ����Τ���
���������
�桹����ʪ���Ѥ߹��ߤ��Ѥ߹ߤ��������ʤμ��
�ְ㤤���ľ���˵��դ���
�ֺ����ǻ䡢���Ӥˤʤ��Ǥ���
��Ʊ�褷���ɥ饤�С������Υ���饯�������͡���
���
���ΰ�͡����˴����ޤ��Ƥ���٥ƥ��
�ɥ饤�С��ϡ������뤵���������֤������龯
���줿�����Ƥ����ʪ���ä���
�ټ���Ф��Ƥ�
��ʿ��������������������ᡢ�����Ƚ꤫���ɾ
����褷�ƹ⤯�ʤ���
���������ºݤ˲���ꤷ�ơ�
���ε��ѤȻŻ��֤���ܤˤ�������������
���㤨�С����Υ٥ƥ��ɥ饤�С��ϼ�ʬ�ǹ���
���������ʤɤλ����ʤ����ۤ��Ĥ��Ƥ�����
ʹ������Ĥ���ͳ������Ȥ�����
��Ĥ�¾��Ȣʪ
���ʤ������줷�ƻ����ʤ���»�����ʤ����ᡣ
�⤦��Ĥϡ��ޥ��ʥ���ޡ�����༼��������
�֤��Ȥǡ���Ȥ���äƤ��ޤ�ʤ��褦�ˤ��롢
�Ȥ�����ͳ�Ǥ��ä���
�������ϰ���ʾ�˲��٤��夬��ʤ���������
�ʤ����ʤ���
���Τ�����¢͢���ǹ���ʤ��Τ�����
���Υɥ饤�С�����ž�����ξ���겹����������
������¢�������ؤˤϤʤäƤ��ʤ����ᡢ�����
���Ѥ�Ǥ��롣
��������äƤ��ʼ������������
���ǤϤʤ�����Ǽ����Ǥλ��Ѥ���θ�����Τ���
�ޤ��˿��ͤλŻ��Ǥ��ä���
���ֺ����Dz�Ҥ���Ǥ��פȤ����ɥ饤�С�
�ˤ����������碌����
�ʤ�̼��͡������ư�
����ɤ�����ܲ�²���������Ȭ�ФΥɥ饤�С���
���
������ͳ��Ҥͤ��Ȥ��������Ӥˤʤ�Ȥ�����
��ȯ���Υ��륳��������å����˸����ä�����
������
�����������ݤ�Ǥ���мҤ��Ƥ����櫓�ǤϤʤ���
ī���ᤤ�������������ռबȴ���ʤ��Τ���
����
�����������ʤ����٤Ǥ��ä���
�������������
��Ϻ����Ĵ���ǡ����ζ���ʪή��Ҥ�̳��뼷
�ͤΥɥ饤�С���Ʊ�褷�����������ͤϼ���
�ཬ�����ʤ���
���뤤�ϼ��ߤ�Ȥ����ΤǤ��롣
�����ʤ�ʪή�������˹��٤ʥ������ɬ�פȤ���
�ޤ������٤���ɥ饤�С��θ��줬�����˲��
�ʾ��֤ˤ��뤫���桹�ϲ���ƻפ��Τ餵�줿��
�����ޤ����٤ʻ��ֻ��꤬��Ĥ���ͳ�Ȥʤä�
���롣
�ºݡ����ֻ����¿���ɥ饤�С��ϤޤȤ�
���뿩��Ȥ�ҥޤ��ʤ���
�ϥ�ɥ��ʤ��顢
���ˤ������ĥ�����٤Ǥ��롣
�̾Ρȥ��ߥ��ߡ�
�ȸƤФ�롣
����������Ҥ���ٷƻ��֤��뤳�Ȥ�ؤ���
��Ƥ���櫓�ǤϤʤ���
Ǽ�ʻ��֤Ȥ�Ĵ�����뿩
��Ȥ륿���ߥ�路�Ƥ��ޤ��Τ���
�ޤ�����
���äƤ�ī���ᤤ���ᡢ����ꤿ���ȸ�������
�������
���
μҤβ����Ĵ�����������ˡ��桹�ϣ����Ƚ�
���鱿�³ۤ�����ʹ������Ƥ�����
�¤��Ϥʤ���
����櫓�Ǥ�ʤ��Ȥ�����٥�Ǥ��ä���
��
��������μ��֤��ܤ�������ˤ��ơ��μҤΥɥ�
���С���¿���ϣټҤζ�̳�˸���Ū�˼���Ȥ��
���ꡢ�ʤ����������˹��٤ʶ�̳�ʤ��Ƥ���
���Ȥ˶ä���������ʤ��ä���
���Ȥ������������бĥ�٥�Ǹ���ȡ�������
��λ�ʧ��ʪή����Ф��ƺλ�����äƤ���Τϡ�
�������Ƥ���ޥ������桢�����ΤߤǤ��ꡢ
¾���ĤΥ������ϥ����ȳ�줷�Ƥ�����
�������
�Ѻ�Ψ�������ä���
�����������θ����ϣμҤλ�
���֤�䱿�����ǤϤʤ����ټҼ��Ȥˤ��ä���
���
����Ƚ�Ǥ���˻����ʪ�̤�١����ˤ��ơ���
���μ�ξ�������ꤷ����
�����⡢���α��·����
��ۤ����ڤǤ��ä���
�ޤ���������������������
�����ޤޤǡ�ʪ�̤�Ǽ�ʾ����Ѳ��˱�������ľ
�����Ǥ��Ƥ��ʤ��ä���
���ä�����٥�ι⤤��
��ʪή��Ҥ�ѡ��ȥʡ��ˤ��ʤ���⡢�����Ƚ�
�Ϥ����Ϥ�褫���ڤ�Ƥ��ʤ��ä��ΤǤ��롣
���������μҤ��������ä��櫓�ǤϤʤʤ���
��
�����ġ��ٰ������Խ�ʬ�ʥɥ饤�С�����ˤϤ�����
�Ѻ�Ψ�ˤĤ��Ƥ⥳�����̤�ʪ�̤ϣμ�¦��ʬ��
�äƤ���Τ����鲿�餫����Ƥ����äƤ��ɤ��ä���
������������ϼ�ξ��������餵����ǽ���ι�
����Ƥ���ʪή��Ҥ˴��Ԥ��뤳�ȤΤۤ��ˤ�
�롣
JULY 2009����18
�� �� �������������Ⱥ︺
����ɤΤȤ������μҤμ���μ�ξ�β���ꤷ��
ʬ���ä����Ȥϡ��礭����ĤǤ��롣
��Ĥϡ���
�Ҥϻ�ʧ�����¤˸��礦������٤���Ǽ�ʤ��б�
�Ǥ��Ƥ���Ȥ������ȡ�
������ͳ��Ʊ�Ҥ����ʤ�
��Ǥ��갷������������������������
�̤λŻ���������äƤ������Ȥ��طʤˤʤäƤ�����
������ܤ��������ۼ֤�Ԥʤ�ʤ������Ⱦ����
����λ����ˤ��Ƥ��ޤ����Ȥ���
�����Ʋ桹��
�μҤβ����Ĵ��������ˡ��ټҰʳ�����μҤ�
�������Ƥ���������ξ�Ȳ��٤�ƻ�Ǥ����äƤ�
����
�����˲����Υ����������Ƥ���Ȳ桹
�Ϲͤ�����
��Ʊ�����ؤΰܹԤDZ��¤����︺
������ޤǣμҤˤ����Ū�������ưפʾ����Ǽ
���褬���Ƥ��Ƥ�����
�������μҤϤ���ʾ��
���Ϥ������Ƥ��롣
�������뾦�����礹��;��
�������
�����ǥ��㡼�����ؤΥ롼�Ȥä�
����Τ����μҤ�������äƤ���¾�ο��ʴ�Ϣ��
�Ҥ��Ѥ߹�碌��٥�ζ�Ʊ������Ԥä��ΤǤ��롣
�ټҤ��μҤΰ������Ƥ�����ĤΥ롼�Ȥ���
�����ʶ�Ʊ��������ե�˰ܹԤ��뤳�Ȥǡ�����
����Υ����ȥ����¸������ΤǤ��ä���
���������ƻ����֤ˤ���ֲ����Ĵ���Ͻ�λ������
��ľ�ʤȤ����ɥ饤�С��пȤλ�ˤȤäƤ⡢��
���֤�Ǵ���ʤ���Ȥˤ������ˤ�����ˤ���
�ˤ˽����ꤹ�뤳�Ȥ��餯�����Ϥξ��פʤɤϡ�
�����ޤ졢����Dz���夲�����ˤʤä���
��������
����Τߤ�ʤ��������κ�Ȥ˽��������������
�פ�Ω�ƤƤ���ΤǤ��롣
���桹��������͢���Ϥ���������ե顢�����ӥ�
�ʼ��ʤɤȷڡ��������ˤ��뤬���������Ƥϸ���
�ˤ�����ɥ饤�С���ͤҤȤ�Υ�����ȴ��ˤ�
���äƤ��롣
���Τ��Ȥ������˴�������줿��
�����
19����JULY 2009
�����������
��
������������ʪή��ңμ�
�����Ƚ�»��Ƚ�
������
�λ���ɾ����������
���
a ��
b��
c��
d ��
e��
f��
��������Ǥ��
g ��
��������Ǥ��
h ��
i ��
j ��
k ��
l ��
m ��
n ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��ʿ��Ǽ�ʷ��15 �� 18 ��Τ������ֻ��꤬50%
��ʪ�̤�¿��Ǽ�����������Ǥ��F ��б���
���ֻ������Ĵ���ġ�
�������롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
��
�ֻ���ϡ�������11��00 �� 13��00�ޤ�Ǽ�ʤǤ����ͥå���
Ǽ�ʤγ������Ķȷ�����ä�
��ʿ�����ԡ�130?/������Ǽ�ʷ������ʿ�ѡ�12 �� 13 ����Ѻ�Ψ��30% ����
�� �����ȡ�����2 �郎�롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
������Ǽ�ʤμ�֡����֤������äƤ��롣
����٤����б���
ɬ�פȤ����Ǽ�����5 ��ô�����Ƥ���
��ʿ�����ԡ�180?/������Ǽ�ʷ������ʿ�ѡ�12 ��ʺ����14 ��ʺǾ���10 ��
���Ѻ�Ψ��60 �� 80%��3t��
�� �������ꥢ��3 ��ˤ��롼�Ȥ���Υ��Ƥ���
�� �����κ����٤��礭�����ᡢi �ᤷ���б��Ǥ��ʤ����֡�
i ��������ɥ饤�С��Ť��꤬��̳��
����
�ϥ������Ǽ�ʤ�Ƥ
��ʿ�����ԡ�150 ? /������Ǽ�ʷ������ʿ�ѡ�15 ��ʺ����18 ��ʺǾ���10 �
���Ѻ�Ψ��50% ����
�� �����ȡ������롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
���ֻ���Ǽ�ʤ�4�濫�뤬�����Ū����Ū����Ͼ��ʤ��롼
�ȤǤ��롣
�Ǥ�㤯��ͥ���ʥɥ饤�С��Τ��ᡢ��ä���٤ι⤤�������Ǥ�Ǥ������
�� ʿ�����ԡ�130 �� 150 ? /������Ǽ�ʷ������ʿ�ѡ�15 ��ʺ����20 ��ʺǾ���10 �
���Ѻ�Ψ50% ����
�� �������롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
���ֻ���Ǥώ�AM �掣��2 ���14��00�ޤǎ���1�
ê����Ǽ�ʤ�
��Ⱦ��
��������̣�����ɤ߾夲���Х饷��êǼ�ʤΥե��б��������Ǽ���褬4 ��
��ʿ�����ԡ�130 �� 140 ? /������Ǽ�ʷ��12 �� 13 ����Ѻ�Ψ40 �� 50��
�� ������������������3 �郎�롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
������15��30 �ʹߤȤ������ֻ��꤬�ͥå���
����
�ȡ������Ф���Ǽ�ʤμ�֡����֤������äƤ��롣
���ֻ���ˤĤ��Ƥϡ����ʳ��Ϥ����ޤ���
����
�������ޤǤζ�����Υ��Ĺ��
����ž�����ʤ����Ƥ���
��������㤯����̳���Ф���ꥹ�����礭����
�ɲ���ʸ�ˤ��ȯ��˰°פ˼���
�Ƥ��ޤ��ʤɶ��顢��Ƴ���Բķ硣
ʿ��Ǽ�ʷ����15 ��������ֻ��꤬5 �ﶯ
���������Ƚ�ˤ������ξ�̼º����ʥ������
��������Ǽ�ʡ���夫��Ķ�
�� �������롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
��ξ��������������Ǽ����餷���ĶȻ��֤γ��ݤ��Բķ�
��ʿ�����ԡ�180 ? /������Ǽ�ʷ��8 �� 10 ����Ѻ�Ψ40 �� 60��
�� �������롼�Ȥ���Υ��Ƥ���
�����ȡ�����Ǽ�ʤμ�֡����֤������äƤ���ʾ�̣�����ɤ߾夲��
Ǽ����������Ž��ˡ�
����12��00 �ʹߡˡ�B��9��10 �ʹߡˡ�C��11��00�ޤǡˡ�D��8��15 �ʹߡˤ�4
��λ��ֻ��꤬�ͥå�
��������Ǽ�ʡ���夫��Ķ�
�� ����ɴ��Ź��3����ˤ�Ǽ�ʤϻ��֤���������Ե�¿����ɴ��Ź��������1h ɬ�ס�
��ô���ܵҰʳ���Ǽ�ʤ⤢�ꡢ�����¾�롼�Ȥ˿����ؤ��뤳�ȤDZĶȸ�Ψ���夬���ԤǤ���
��������Ǽ�ʡ�5 ��ˡ���夫��Ķȡʽ���ˡ�5 ���
������ʪή��ҡ�i ��Υ롼�Ȥ�Ϣư���Ƥ��롣
Ǽ����ΰ����ܴɤ�Ƥ
��Ǽ�ʥ롼�Ȥ�d ��Υ롼�ȤȤۤ�Ʊ��
���������ġ����ʥ����å��ˤ���ʰ㤤�ɻߤ�Ű�줷�Ƥ���
���������Ѱ��Ȥ��Ʒ����ʪ�̤Ȥ��ä����䤷���Ѻ�Ψ�θ��夬ɬ�ס�
�����ؤΥ����Ȥ���
���������ؼ����Ԥ����֤�¿����
���ֻ���ϤۤȤ�ɤʤ�
��������͢����¿����
�����ؤǰ������ʬ���Ѥ߹���ʤɱ����ؤȤ��Ƥ��ղò��ͤ����
��ʿ�����ԡ�150?/������Ǽ�ʷ������ʿ�ѡ�15 ��ʺ����20 ��ʺǾ���11 �� 12 ��
���Ѻ�Ψ��30 �� 40%
�� �����ȡ������롼�Ȥ���Υ��Ƥ��롣
��֡����֤Τ�����Ǽ���褪��ӻ��ֻ�����äˤʤ�
�����������礦����
��1964ǯ���ޤ졣
���Ի�
����طкѳ���´�ȡ�
���
�����ȼԤΥ����륹�ɥ饤
�С���Фơ�89 ǯ������
���縦������ҡ�
ʪή��ȯ
�����ࡦ�ȥ�å����������
�դ�̳��롣
96ǯ����Ω��
���ܥ����ե����ȥ����
Ω����ɽ�˽�Ǥ��
���ߤ˻�롣
HP:http://www.nlf.co.jp/
e-mail:info@nlf.co.jp
|