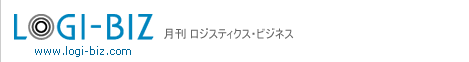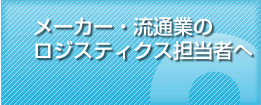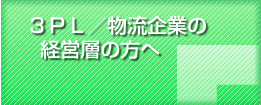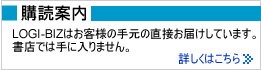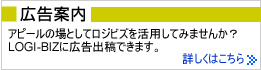|
*������PDF���ƥ����Ȥ���Ф����ǡ����Ǥ���������PDF������������

�����Ҥ�ʪή�Ծ���Ȥ�Ķ�����
MAY 2010����20
������������ػԾ�ϴ������Ϥ�����ݥ���ƥ��졼������
�ӥ��ͥ���ǥ������������
����������ؤε���ʥ���ե�
��ץ�åȥե�����Ȥ��ơ�ʪή���Ȥ�Ķ�����Ƽ�Υ�����
�����Ȥ�Ÿ���������롼�פȤ��Ƥ���Ĺ��ޤ롣
��ʪή����
��Ω�����뤳�Ȥ�ʪή���ȤȤ������̤�ȯ�������롣
��ʹ���ꡦ������
��
to
�áפ�������ϻ��ޤǼ��Ҳ�
�����졻ǯ������ζ��ӤϤޤȤޤ�ޤ�������
���֤ޤ�������Ǥ��������������ͽ�ۤ�Ȭ�塻��
���ߡ��Ķ����פ��������ߤΡ��ܸۤ������̤�
�����Ϥ������Ǥ���
������ޥ�å��αƶ����֤�ȡ�
���ָĿ��١����Ǹ���ȡ���ǯ���〜�������Ĵ�Ǥ�
����������ǯ�ͷ�����ǯ��ޡ������٤Υڡ���
����Ƥ��ޤ���
�����ػԾ����Τμ谷�Ŀ��ϡ�Ȭǯ
�٤˻˾������ǯ��줷�ޤ����������Ҥξ���
����ʤ��ä���
��������ͽ�ꤷ�Ƥ����ۤɤϿ��Ӥ�
�����
���줬����ǯ������˸��פˤʤä�������
��ĤǤ���
��Ȭǯ���������λ���ǯ�ײ�����Ҥ�
��
to
�á٤������ֶ�����ʤ�ޤ�����
�ɥ饤�С�����
���������䤷����
���������������������������
���Ǥ������谷�Ŀ����פä��褦�˿��Ӥʤ��ä���
��ˡ������ۼ��Ǥ��ޤ���Ǥ�����
�����Ծ�Υѥ����̾�����ʤ��ǸĿ������Ӥ���ͳ
�ϡ��ɤ���ᤷ�Ƥ��ޤ�����
�������ҤΣ�
to
�ä������ʼ������夷�����Ȥ���
�β�Ҥ���ʤɤ���ɾ�������������ΤǤϤʤ�����
�ͤ��Ƥ��ޤ���
����ǯ����������ɥ饤�С�������
���Ѥ���ꤷ�ơ�ɬ�פʿͰ�����ݤ���Τ����ǯ
�����äƤ��ޤ��ޤ�����
�������鶵���ͥåȥ��
�κ��Ԥ�Ϥ�ơ���ǯ�����äƤ褦�䤯���Ĥ�����
���Ϥ��
���θ��̤���ǯ�ν����餤��������Ȥ�
��ɽ��Ƥ�����
��������ǯ����������ä�ñ�����礭�������äƤ�
�ޤ���
���ʤ��Ʋ�ʪ����˹Ԥ����ˤ��ä���
�Ǥ�����
����ñ�������Ǥϲ�ʪ�ϼ��ʤ��Ǥ��衣
��ã�ʼ���
�����ä��顢�����˾���Ԥ������β�Ҥ˥��졼�ब
����Τǡ��ȤƤ�ȤäƤ�館�ʤ���
����������
to
�äβ�ʪ�������Ƥ������Ȥϡ���Ϥ�ñ���ˤ�ƶ�
���ޤ���
��
to
�äβ�ʪ�Ͼ������������⥨�ꥢ���
������¿����
�ޤ�������Τʤɤϵ�����ʬ�������ơ�
Ǽ�ʥ�ɥ������û�̤�ޤ�ư���˽ФƤ��ޤ���
��
�����������Υ��û���ʤ��
���֤Ĥޤ��
to
�¤����
to
�äؤΥ��եȤ��ʤ�Ȳ�ʪ
�������������Υ͢���ˤʤ�Τǡ��ɤ����Ƥ�ñ��
�ϲ����롣
���Τ���졻ǯ���������ˤ�ñ������
ǯƱ����ǻ����ߥޥ��ʥ��λ�ȬȬ�ߤޤ�����Ƥ�
�ޤä���
�̴��ǤϤ⤦���������뤫���Τ�ޤ���
��
����������Ϥ����礭�������뤳�ȤϤʤ��ȹͤ���
���ޤ���
���ΰ졻ǯ�٤���ɥ饤�С���ɾ�����٤�
���夲�������ס��̤������Ż뤹�뤫����
���ѹ����ޤ�����
�����ʥ����ɥ饤���Ф��ޤ�����
��ʪ�˸���ä�Ŭ����ñ�����������Ȥ�Ű�줵
���ޤ���
�����֣�
to
�áפ������֤������ϰ�����Ǥ�����
���֤ޤ��ޤ��Ӿ�Ǥ���
����ϤۤȤ�ɥ����˶ᤫ��
����
to
�á٤μ���������Ψ��ǯ��������ͳ�ޤ�
�����夲�ޤ�����
����λ���ǯ��ϻ��ޤǾ夲��
�ײ�Ǥ���
�����֤��������ޤ���
�������塦̾��
���ʤ����ԻԤ��濴�˺��廰ǯ�֤ǥ����ӥ�����
����Ȭ���������ߤ��Ƹ��������ܰʾ�ˤ����
��Ǥ���
����������ؤȥ�ޥȱ�͢�Ǥϥͥåȥ�����߷פ�
��Ȥ���礭���㤤�ޤ���
������ؤ������ϻ��
�����Ū�緿�ε����ǥ��С����Ƥ���Τ��Ф�����
�ޥȱ�͢�Ͼ�����Ź����͡����������ʬ��������
������
����Ϻ�����ؤΥͥåȥ�����ޥȱ�͢��
�褦��ʬ�����˸������ΤǤ�����
SG�ۡ���ǥ�������ƣ�빸���б���άô��������
4 Interview
21����MAY 2010
���֡�
to
�á٤˴ؤ��Ƥϡ���Ϥ��ޥȤ���Ȼ��Ƥ�
�ޤ��͡�
���������Ҥξ��ϡأƣ��� �á٤��ʤ�
�Τǡ���ޥȤ���ۤɤε�������ɬ�פʤ���
�ޤ���
to
�¤ε����֤Ȥ��Ƥϴ��ˤǤ������äƤ��ޤ���
����
�ǣ�
to
�¤ϥ��졼���ۤȤ�ɤ���ޤ���
�����
��𧲽�οʤ�����������ߤ俷�ߤʤɤϹԤ��ޤ�����
�ܳ�Ū��������ɬ�פʤΤϡ������ޤǡ�
to
�á٤Ǥ���
����Ϥ��������������ӥ���ȯ
�������ζȤǤϸ��ߡ�������������Ĥξ����ˤʤ�
�Ƥ��ޤ���
������ؤǤϡ�������¨���ءפȤ�������
�ӥ�̾��ȤäƤ��ޤ������������礹��ˤϽ���
�������ؤȤ��̤˥���ե����ɬ�פ�����ޤ�����
���֥��ꥢ������������Ǥ���С���¸�ε�����㴳
��������Ф��ΤޤȤ��ޤ���
����Ȥ��̤�¨���ؤ�
�Ĥ��ƤϺ�ǯ������Ҷ���ʪ�������Ȥ������
�Х�������ƥ��������麴����ؤ˰ܴɤ��ޤ�����
��
�������ΰ�Ĥ����Ҷ��ؤ�Ȥä�¨���ؤγȽ��Ǥ���
���廰ǯ�֤��ƹҶ���������ʤ��������
¨���ؤ��������Ƥ����ޤ���
���������Ϥ�����������Ԥ��ΤǤ�����
��������ɤ��Ǥ����������Ȥ����櫓�ˤϹԤ��ޤ���
���������ԻԴ֤����������ϼ»ܤ��ޤ���
�Ҷ��ؤ�
�Ȥ�ʤ��̾�������ؤǤ���ͻ��ֲ�Ư�Υ�����
����С������彽����ְ���˥��ꥢ�����Ϥ����
�����ߤǤ⤢��ޤ����顢�Բ�ǽ�ǤϤ���ޤ����
�����
��У̻��ȡ��Ȥ������β�ҤΥ������Ķ�
̳�ˤĤ��Ƥϡ�
���ֱĶȥ��ץ�������ȴ��Ū�˲���ޤ���
������ؤ�
�ǥ�Х��ǽ�Τۤ��ˡ��������ƥ�������ǽ�Ϻ���
�������Х�������ƥ����������������Ϸ�ʪ����ư��
�Ҳ�ҤΣӣǥꥢ��ƥ����б����������ȥ�������
�Υˡ����롼�פǰ�礷�������餦������������
������
����������̳�Ͻ��褫��������ϤΡ֣ӣң�︵��
��ή�̥���︶�פ�������äƤ��ޤ�������
�������ѥ����Σӣңä����襤�������Ȥ�����
����������Ǥʤ������������ټ����Ѥ˲桹����
������ߤ����Ĥ���Ȥ�����������λŻ����ܳ�
Ū�˳��Ϥ��ޤ���
���줬�Ǥ�������κ�̳Ū�ʴ���
���褦�䤯���äƤ�����
Ĺ���֡����ҤϱĶȥ����
����ե������ϰ���Ǥ�����Ǥ��ޤ���Ǥ�����
��ʪ�����ä˹�碌�����������������֤Ƥ���
�����ǡ������ʾ����������뤿�����άŪ�����
�ϤǤ��Ƥ��ʤ��ä���
�����ʤ��Ǥ�����
�������������ػ��狼�����졻ǯ�ϰ����߶ᤤ
ͭ������Ĥν������ɤ��Ƥ��������ֺѤ˥�ɤ�
Ω�ä���κǶ�η軻�Ǥ⡢���ʤ������»�����
���Ƥ��ޤ�����
��ǯ������»�������Ϥδޤ�»�ʤ�
����ͳ�Ǥ���������⡻��ǯ�ˣӣǥꥢ��ƥ�����Ω
���������ǡ����٤��������ޤ�����
�������ΰ仺
�Ϥʤ��ʤä���
���֤��Τ����ǯ�٤��须��ǯ�٤�����бķײ衢
�졻ǯ�֤�Ĺ���ײ����쥹�ƥåפˤʤ뤿��桹
�ϡإե������ȥ��ơ����ץ��٤ȸƤ�Ǥ���ΤǤ�
���������Ǥϣ͡�����ޤ�Ѷ�Ū�����˽Ф褦
�Ȥ������ˤ�Ω�Ƥޤ�����
�Ȥ�����������ޤDz桹
�ϲ�ʪ���������ĶȤ����и����Ƥ��ʤ��ä��Τǡ�
�����α��Ĥ��������餤�ޤ��Ȥ�����������αĶȤ�
���ǤäƤ��ޤä���
���줬�ե������ȥ��ơ����ץ��
��ȿ�����Ǥ���
�졻ǯ�٤���Υ�����ɥ��ơ����ץ�
��ǤϺ��٤��������������β����ޤ���
�������廰ǯ�֤����ײ���߷פǰ�塻�����ߡ�
220
300
550
3.4%
2.5%
0
100
200
300
400
500
600
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
�Ķ�����
�Ķ�����Ψ
��ñ�̡����ߡ�
�ʸ����� �ʷײ��
��ñ�̡����ߡ� ��ñ�̡����
5.0%
�ʼ��ӡ�
8,872 8,900
11,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
09/3��10/3��13/3��
�ʼ��ӡ� �ʸ����� �ʷײ��
09/3��10/3��13/3��
�Ķȼ���
SG�ۡ���ǥ���������бķײ�
�͡���ʬ
�Ķ�����
1,000
10,000
����������ȡ���ư���λ����ߤȣ͡�����
ϻ�������ߤ����ܤ���ޤ���
���֥��롼�פηб���άô����Ǥ�ԤȤ��ơ���ư����
ȯ�Σӣǥꥢ��ƥ����Ф��Ƥϡ����롼����Υ�����
�Ȥ����ǤϤʤ���ʪή���Ȥ���Υ�줿��ȯ�Ʒ�ˤ�
�Ѷ�Ū�˼���Ȥ�褦�˻ؼ���Ф��Ƥ��ޤ���
��ǯ
�������ո���Ԥν�ͧ�ڶ�°���Ȥι������Ϥ��
�����뤳�Ȥ���Τ⡢��������ư���ΰ�ĤǤ���
���Ϥ�����ˡ�ˤĤ��ƺ��ܺ٤�ͤ�Ƥ���Ȥ�����
������ʪή���Ȥ˸��ꤷ�ʤ��ǺǤ��ղò��ͤ����
�Ф��륹��������Ȥ�Ω�Ƥޤ���
����ʪή��ư���ϥ�ޥ�å��αƶ��Ǻ������
���礭�������äƤ��ޤ���
�������Υ����ߥȤ��Ƥϰ�������ޤ���
����
�̻��Ȥˤ��Ƥ⡢�����åȤ���äƤ����ۤ�������
ͭ���Ǥ���
������ʧ���Ȥ�������Ǥϥ���ڤˤ⾡
�Ƥʤ���
�����åȤ���Ĥ��Ȥ��Ƥ���С�ʪή
�Ҳ�ҤΣ͡����Ȥ������ʤ�Ȥ��ʤ���
���ȳ����
����ˤ�����ɬ�פǤ���
���������������Ϥ�����ˡ��ʪή���Ȥ˸��ꤷ�ʤ���
�Ȥ�����̣�ϡ�
����������ϤΣӣңäˤ��Ƥ⡢����ޤǤϣ��У̤�
��Ū�Ȥ��Ƥ���Ȥ�����ꡢ���֤Ȥ��ƤϺ������
�β�ʪ��������뤿��λ��ߤǤ�����
�����������
�ؤ������Ƥ����顢����¾�λ��ȤϤ��ĤޤǤ���
�Ƥ⼫Ω�Ǥ��ʤ���
�ƥ��롼�ײ�Ҥ����˸����äƤ�
������ˡ�����Ϻ�����ؤȤ�Υ�줿������Ω��
���Ǥ�餻�Ƥ����ޤ���
ʪή�Ծ�Ȥ����Ȥ����ͤ�
��ɬ�פϤʤ���
���Ҥ���ϻǯ�˥ۡ���ǥ�������
�ܹԤ��������ϡ������ˤ����Ǥ���
���֥ۡ���ǥ����������ߤ������������Ҥ�ʪή
�Ȥδ��Ĥ������Ȥ�����ޤ���
�ºݡ��ӣǥۡ�
��ǥ��Ȥ�����̾�ˤϡ�ʪή����������
�դ������ޤޤ�Ƥ��ޤ���
�غ���٤Ȥ������դ���
�Ȥ��ޤ���Ǥ�����
��������˥ۡ���ǥ���������
��̣��Ʃ������Τ˻��֤ϳݤ���ޤ�����
�伫�ȡ�
�Ұ����Ф��Ʒ����֤����ΰ�̣����������ɬ�פ���
��ޤ�����
����������������ζ��Ϥ��ޤǤ�ʪή���Ȥ���
��Ƥ��ޤ���
���֤����������ؤȺ�������Х�������ƥ���
���Ͻ���ʪή��ҤǤ���
�������ӣǥۡ���ǥ���
�����Ϥ����ǤϤʤ���Ǥ���
���������ʤळ�Ȥǡ�
��������ܹ���β�ʪ�����äƤ������Ȥ����
�ޤ���
�����ػԾ�����ϲ�����Ω�äƤ�����
����
�Ǥ������롼�פ������ĤäƤ����ʤ���Фʤ�ʤ���
���Τ���˺�����ؤ������DzԤ��Ǥ���Ƥ��뤦��
�ˡ������ذʳ��λ��ȤФ��Ƽ�Ω�����褦�Ȥ�
���Τ������ߤδ�����ά�Ǥ���
���ֶ���Ū�ˤ������ؤ�³������ܤ��줬�������ƥ�
������
�ޤ������͢���Ρأ女�쥯�ȡ٤⺣��ǯ��
���������������߶�η�Ѥ�������Ƥ��ޤ���
��
������ε��Ϥ�����С������ؤˤ֤鲼���������
�ʤ�����ʬ�dz��������Ƽ�Ω��Ĺ�Ǥ���Ϥ��Ǥ���
���η�̡��ؤ���¾���ȡ٤������ȥ�������ץ�
�ե��åȥ������Ѥ�롣
���줬������ؤ��Ф���
�����ȹ��ˤ�ʤ��
������ư����ȯ�ˤ��Ƥ�ɣԤˤ��Ƥ⡢���줾���
�ȳ��ˤ���ȼԤ����ޤ���
ʪή�Ȥ����۶ȼ狼�黲
�����ƾ����ܤϤ���ޤ�����
���֥ץ�åȥե��������äƤ��뤳�Ȥ��桹�ζ���
�Ǥ���
ʪή�Ǹ����Х١�������������äƤ��ơ�����
�ե��;��ǽ�Ϥ�����Ǥ��롣
��ȼԤˤϤ���Ϥ�
���ʤ���
�㤨�и��ߥ��롼����ˤ���ϻ�ͤ�ξ���
MAY 2010����22
�ӣǣȥ��롼�פλ����ΰ����ά����
��������
�������ƥ��������Ȥ���¾����
��ư��������SG�⡼��������
��ư����SG�ꥢ��ƥ���
�ɣԡ�SG�����ƥ��
���Ρʺ���ɥХ�
����
������ �ʳ����ޤ��
��¸�����ΰ迷�������ΰ�
�����ʪή
����Ĵãʪή
�����ʡ�����ʪή
����͢��
���建��ʪή
���״��פζ��� �����ΰ�γȽ�
�ǥ�Х����
�ʺ�����ء� �ʺ�������Х�������ƥ�������
�����ƥब��Ω���Ƥ��ޤ���
��������ǯ�٤��ɤ�
���ޤ���
���η�̡�����ʣɣԥץ�åȥե�����
���Ǥ������롣
����롼����ξ������������
�ʤ����ҳ����Ф��ơ������륯�饦�ɥ����ӥ��Ȥ�
�Ƴ��Ѥ��Ƥ�����
����ô����Ȥʤ�ӣǥ����ƥ�ϡ�
���˳�����Ψ���������ޤǾ夬�äƤ��Ƥ��ޤ���
��������ǯ�٤ˤϻ͡���ˤ���ײ�Ǥ���
����ƥ��졼�������ܻؤ��ʤ�
��������ޤǺ�����ؤϡ֥�����
No.
����ʪή��ȡפ�
�����ӥ�����Ǥ�����ݥ���ƥ��졼�������ܻؤ�
�Ƥ����Ϥ��Ǥ���
�������졻ǯ�٤���λ���ǯ�ײ�
��¤ꡢ���ʪή���Ȥζ����Ϥ����֤�ȹ���
�ܤǤ���
���֡إ�����
No.
���٤Ȥ�������������ϥۡ���ǥ���
�������ߤ��������ߥǼ�겼���ޤ�����
�����ϻ�
���Ȥ��Ǥ��Ѷ�Ū�˥���ƥ��졼����ϩ�������Ǽ�
ĥ������ͤǤ�����������������ä��ͤ�����ä�
���ޤ���
��ݥ���ƥ��졼�����ϥɥ��ĥݥ��Ȥ�����
��ǥ�ˤʤäƤ���Ȼפ��ޤ�������������ܤβ桹
�ˤ������ޤʤ���
�������ܤ������ؤΥ����ӥ���٥�ϴְ㤤�ʤ�����
��Ǥ���
���Ƥ���٤Ƥ���ʤκ������롣
�����
�����ι�Ÿ�����뤳�Ȥˡ��̤����Ƥɤ������
��̣������Τ���
�㤨�о峤�Ǥ����ܤ�Ʊ�������ӥ�
�������˵�����Τ���
��¸���Τ褦�����Ҥϡ�
��ǯ�˾峤�������ػ��ȤϤ������ߤⱿ�Ĥ���
���ޤ���
��������������Ȥ���������β�Ҥ�����
�Ǥ��ꡢ��ʪ���ץ����ƥ�������������ӥ�����
���ƤϤ��Ƥ⡢������¿���βټ礫�������������
�������ؤȤ��̥�ΤǤ���
���ܤǸ����С����ĤƤ�
ɴ��Ź���渵����������˶ᤤ��
���֤��줬�ᤤ���衢���ܤ������ؤΤ褦�ʥɥ���
�ġ����ɥ��Υͥåȥ���˳��礷�Ƥ������ˤĤ���
�ϡ���ˤ������ͼ����ۤʤ��Ǥ��줬���դ��Ƥ�
���ˤϡ���Ϥޤ����֤�������ȻפäƤ��ޤ���
��
�ܤβ桹�����Ϥ˽ФƹԤäƱ��Ĥ���ˤϺ����ܤǤ�
�ʤ���
�����������ʪή����ʤ��Ȥ����櫓
�ǤϤ���ޤ���
���ܤβټ礬�����˿ʽФ��뤳��
��ʪή�̤����������뤳�ȤϺ�����Ѷ�Ū�ˤ��
�Ƥ����ޤ���
�����Ȥʤ�ȣ͡����ϡ��ɤ�ʬ��оݤǤ�����
��������ײ�˷夷��ϻ�������ߤȤ����͡�����ͽ
���ϡ������ؤ�������뤿�����������У̰Ʒ��
���������¾���Ȥ�����ǡ��ۤܶ����˻Ȥ����Ȥ�
���ꤷ�Ƥ��ޤ���
�㤨�Х������ʪή�Ҳ�Ҥ����
�������ˤϡ����Υǥ�Х������ء�����
��Ȥ�������Х�������ƥ����������Ϸ�ʪ�Ϥ�
��¾���ȤΣӣǥꥢ��ƥ��Ȥ��ä�����������������
���Ȥˤʤ�ޤ���
����ʪή���ȤαĶȥ������åȤ��Ѥ�äƤ��ޤ�����
���֥�������鲷�ޤǤ�켡ʪή�������龮����
�Ǥ���ʪή���Ȥ���ȡ����ޤǤ����ҤλŻ��ϰ�
��Ū����ʪή�Ǥ�����
���������ϡ�������䲷
�������ԡ����������ľ�ܾ����Ȥ��ä�����
����ή�̹�¤���Τ��Ѥ�äƤ��Ƥ��ޤ���
�����ʤ�
�Ȳ桹���ή�����äƤ�����������ʤ���
������ή�Σ��У̤Ϥʤ��ʤ����פνФʤ�ʬ��Ǥ���
���֥��������ʬ�Ǥ�äƤ����Ż����Τޤ桹
�����Ĥ�������ʤ�Τ������פ�Ф��Τ�����
��
��������ۤɤ���ư�����Ȥ�����ƥ�Υץ�å�
�ե�����ʤɡ�ʪή���ڥ졼�����ʳ��ˤ⥵���ӥ�
�ΰ����礹�뤳�Ȥǡ��������Ǥ⥰�롼�бĤ���
����̤�Ф���ȹͤ��Ƥ��ޤ���
23����MAY 2010
��ƣ�빸�ʤ���ɤ����Τ֤�����
��1956ǯ���ԻԽпȡ�
������ع�����´��
81ǯ����
����ؤ˥����륹���ɥ饤�С��Ȥ������ҡ�
�Ķ�Ź��ŹĹ
����Ӻ�������ܼұĶ�����������Ĺ����Ǥ�塢98ǯ��
������Իټ�Ĺ��
2000ǯ���ټ�Ĺ��01ǯIT��ά����
Ĺ��̳��
05ǯ��̳������
06ǯ���������SG�ۡ�
��ǥ�����Ω��ȼ��������Ǥ���б���άô����
09
ǯ�����������ɽ��������̳������������Ǥ��
PROFILE
|