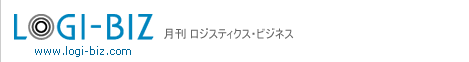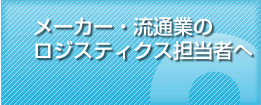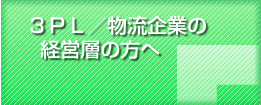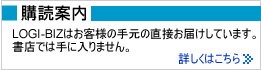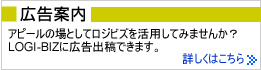|
*������PDF���ƥ����Ȥ���Ф����ǡ����Ǥ���������PDF������������

JUNE 2010����76
�ޥƥϥ��Ƴ����Ƥ˵���
���
żҤ�̾�Ų����ܼҤ��֤����ѥ������
��ǯ������Ȭ���ߡ�
���ƥ���ˤ�����Ծ�
������������Ƕȳ���̤ˤĤ��Ƥ��롣
Ǽ
�����ɴ��Ź������Ź���ǥ�������������
�ʥ����ѡ��ʤɤǡ��������ʤΤۤ�����ǽ���
�äƤ��롣
���谷�����ƥ����ǯ��ʿ�Ѥ���ͻ�������
��
�ѥ�����ʤϥ����ƥऴ�Ȥ˿����������ʤɤ�
Ÿ�������뤿�ᡢ�ºݤΣӣˣդ�����ʿ��ˤ�
�롣
���Ҿ��ʤ���Ⱦ��������ǡ���������
�����˻�����ι�����Ƥ��롣
�����ˤϸ��ʡ����˥��������֤��Ƥ��롣
�ͼ꤬¿���������Ȥ�������Ǵ��뤵��
�ơ��ϸ���̾�Ų����˾��ʤ�͢�����Ƥ��롣
̾
�Ų��������夷����ϡ����Ҥˤ���ʪή����
���˾��ʤ�������ߡ��������ݴɡ���ʬ������
���դ������в٤�������Ƥ��롣
������ʣżҤΣ˻ᤫ���������ܥ����ե�����
��ʣΣ̣ơˤ�Ϣ�������ä���
�ָ��ߡ�����
������У̤ȥ������ĤˤĤ��ƶ��Ĥ�Ԥ�
�Ƥ��뤬�������б���Ǽ���Τ�����٥�ˤ�
���פȤ�����
���������˻��ľ�����̤��뤳�Ȥˤʤä���
��
������Ӻ��ѤǣżҤ����Ҥ��Ƥ�����ǯ�ܤȡ�
�ޤ������������Ȥ⤢�äơ�̾�ɤθ��ϴ�
�輼�ΰ��̼Ұ��Ǥ��ä������ºݤϣżҤκ�̳��
�����ƥࡢʪή�λ�ʬ���Ǥ����Ƥ����
�פΥ����ޥ�Ǥ��ä���
���
żҤϥ����ʡ���Ȥǡ�����Ȥ���©�ҤǤ�
�븽��Ĺ�����Ƥΰջ����ԤäƤ��롣
�˻�
�Ϥ���¦��Ȥ��Ʋ��פο�Ƭ�ش��äƤ�����
�˻�˸����ʤ��Τϡ��˻ᤪ��Ӳ��פ���
��������������뤿��Ǥ��ꡢ�ޤ��桹
���륿��ȤΤ褦�ʼҳ��οʹ֤�������
�ηڤ�ô���Ԥˤɤ��ܤ��Ƥ���Τ����б��ʼ�
������å����������⤢�ä��褦����
�����Σ˻�������ˤ��ȡ��żҤϸ��ߡ�����
�������Ĥΰ����������������У̤ΣмҤȤ�
���Ĥ�ʤ�Ƥ���Τ���������������������
�����Ǥ����ˤ���Ȥ�����
�����Σ��У̡��мҤϣżҤ��Ф����絬�Ϥʥ�
�ƥϥ��ƥ��Ƴ������Ƥ��Ƥ�����
��������
���줬�̤�����ɬ�פʤΤ��˻�ˤϵ�����ä���
�ޤ������Σ��У̤Ϥ���ޤ����Υ����ʪ
ή����Ȥ��Ƥ��ơ�����ʪή��Ź��������
���Ӥ��ʤ����Ȥ��¤��ä���
�����������̤Σ��У̤�ʪή��Ҥ����̤���
�ꡢ�ä��礤����ä����ȤϤʤ��ä���
��Ȥ�
�ȣмҤϡ��˻�οͤ���Ҳ𤵤줿��Ҥ���
����dzؤ�
�������
���ܥ����ե����ȥ
�������졡��ɽ
���ץ��������Ȥϴ��˥������Ȥ��Ƥ�����
�����α��Ĥ����
���룳�У̤��ޤäƤ�����
�����������Σ��У̤���ƤˤϤ�
���ˤ�Ǽ���������ʤ��ä���
���챿�Ĥμ��Ϥˤ⵿���䤬�դ�
����
�����ʡ��бļԤȣ��У̤��Ķ��ߤ�Ǻ��ץ��������ȥ��
��������������Ƥ�����
���ѥ��żҤΣ��У�Ƴ������
��89 ��
�����������礦����
��1964ǯ���ޤ졣
���Ի�
����طкѳ���´�ȡ�
���
�����ȼԤΥ����륹�ɥ饤
�С���Фơ�89 ǯ������
���縦������ҡ�
ʪή��ȯ
�����ࡦ�ȥ�å����������
�դ�̳��롣
96ǯ����Ω��
���ܥ����ե����ȥ����
Ω����ɽ�˽�Ǥ��
���ߤ˻�롣
HP:http://www.nlf.co.jp/
e-mail:info@nlf.co.jp
77����JUNE 2010
����
�˻������ˣмҤ�ô���Ԥ�ȥåפ˾Ҳ�
�����Ȥ����������˰յ���礷�����Ǥϸߤ���
ǧ���äƤ���ȤΤ��ȤǤ��ä���
����Ŭ�ʥѡ��ȥʡ��Ĥ��뤿��ˤϡ�����
�ڤ�»ܤ���Τ��Ĥ���������ɮ�Ԥϥ���
����������
�˻Ἣ�ȡ���������٤����ȶ�
���פäƤ�����
���������ȥåפȣм�ô���Ԥ���
���ä��갮�ꤷ�Ƥ��ޤäƤ��븽���Ǥϡ�����
�ˣ˻�Ȥ����ɤ��ä����ꤵ����ΤϺ����
�褦�Ǥ��ä���
���
мҤ����Ȥ��Ǥ��ʤ��ʾ塢���ϲ�Ҥ�
����ʪή�μ��Ӥ��ʤ��Ȥ����¤Ϥɤ��ˤ��
�äΤ��褦���ʤ���
����Ǥ��絬�Ϥʥޥƥϥ�
�����ƥ��Ƴ���ˤĤ��ƤϤޤ���ľ������
����ǽ�������ä���
���
żҤΥӥ��ͥ��Ϸ��̤���ư���礭����
����
�����Ǥ��뤿�ᡢ������¾�Ҥȶ�ͭ���뤳
�Ȥ�Ǥ��ʤ���
�����˽������Υ����ƥ��Ƴ��
����Х����ȹ�ˤĤ��ΤǤϤʤ����ȣ˻�ϴ�
���Ƥ�����
Ū�Τ�Ƚ�ǤȤ����롣
���
˻�ϣżҤ�ž���������ޤǷ���Ȫ���ä���
������
�������������Ȥϻפ��ʤ��ۤ�ʪή�ˤ�
����¿���Τ��Ȥ�ؤӡ��褯���Ƥ�����
��
�Ѥ����ϲȤǤ⤢��Τ������������äΥ쥹��
����˻����Ƭ���ɤ����ڤ줬������줿��
����ڤʤ��ǥѡ��ȥʡ�����
���ʤ��мҤ��絬�Ϥʥ����ƥ�Ƴ������Ƥ���
���Ƥ���Τ���
�˻�Ȥβ��ä�Ťͤ뤦���ˡ�
������ͳ��ʬ���äƤ�����
�פϣмҤ˸��챿��
�μ������ʤ��ΤǤ��롣
�����ߡ��żҤϼ����ǥ������Ĥ�ԤäƤ�
�롣
�����Ǥϼ�ư��ʬ������ǥ����롦�ԥå�
�������ƥ����Ѥ�����ȥե����������
���äƤ��롣
�мҤϤ��λ��Ȥߤ�����
�⤽�Τޤްܴɤ��褦�Ȥ��Ƥ���Τ���
������ˤ�äưܴɤ�ȼ�����ڥ졼�����κ�
������¤��ޤ����롣
�������θ���ϡ���
�ڥ졼�����˴���Ƥ��Ƥ�������μ������
�������
��¸�����ϴ������ν��Ѥ��
��Ǥ���Τǣż�¦�˺�����;�Ϥ⤢�롣
���
��У̤ΣмҤˤ����������Ƥ�ɬ�פ�
�ʤ��Ʒ�Ǥ��뤿�ᡢ���줬�Ǥ�����ʤ����
�Ǥ���ΤϳΤ���������
����������������ż�
�ϥꥹ��������蘆��뤳�Ȥˤʤ롣
�����Τۤ��ˤ⡢�⤦��ģ˻�ˤϷ�ǰ���Ƥ�
�뤳�Ȥ����ä���
��������Ω���夲���κ�
�𤫤鵰ƻ���ޤǤΥץ������ȡ�������ˡ����
���ʤ����мҤ������������Τ��Ȥ������ȤǤ�
���
��������������Ф��Ʋ桹�Σ̣Ƥϼ��Τ褦
�ʼ»ܹ��ܤ�мҤ˥��ɥХ���������
������ʪή���ȼ�ɾ��ɽ�פ���Ѥ���
�����
мҤȤΥ�٥륮��åפγ�ǧ
���桹�Σ̣Ƥ�����������ʪή���ȼ�ɾ��ɽ��
��Ȥäơ��мҤμ��Ϥ�ɾ������ʼ���ɽ���ˡ�
ʪή�ѡ��ȥʡ��˵����뵡ǽ��ǽ�Ϥ�
���ȡ��ʼ������ġ������ƥ��̤ʤɼ�ϻ���ܤ�
��ɾ�����ƥ����å����롣
�ʤ��������������
��ʤ�¾�Υѡ��ȥʡ�����Ȥμ��Ϥ���Ӥ���
����ġ���Ǥ��ꡢ�żҤξ��ϣмҰʳ��˸�
�䤬���ʤ����ᡢ���θ��̤ϸ���Ū�ˤʤ��
�������Ū��ʪήϢ����Ĥγ���
�������ʰ������������Ū��Ϣ����Ĥ��
�ܤ��롣
Ϣ����Ĥϲ�Ư���������顢�ơ�
���̤ˤ��줾�콵���Υڡ����dz��Ť��롣
��
���Ǹߤ��ο�Ľ�������������Ȳ���������
�ޤǤν�������ʤɤ���롣
��Ω���夲��������������λ϶����ˡ���
�ҡ��мҤθ�����Ǥ�Ԥǥߡ��ƥ���Ԥ���
��
Ư���ʹߤ⤷�Ф餯�������Υߡ��ƥ����
³�������θ�ϸ���ΰ�������ʤ��齵��
�����ʤɤγ������٤˸��餷�Ƥ�����
����ƻ�����Ѥ���������Ϣ����ĤϷ�³
�����ߤ�����˾����Ȥ����б����������ο�Ľ
�����������ͽ��ʿ�����Ǽ�����ȯ������
���ʤ����������ʤɡˤ�ͭ���롣
����ˤϥ�
�ߥ�˥����������Ȥ������̤⤢�롣
����Ω���夲���ˤ������������
�����ʿͰ������ʬô�ˤγ�ǧ
����������Ω���夲�ץ��������Ȥϲ�Ư��
����쥫��Ⱦ�������ܤޤǤ�����ˤʤ롣
��
�����ܤޤǤˤɤ�����α��祹���åդ�������
�뤳�Ȥ��Ǥ���Τ���
���Υ����åդˡ������
�äƤ�餦�Τ������λ��ΣмҤθ�������
�ʴ�������ˤ�ï����
���θ��������ˤϡ���
��ʷи�������Τ��ʤɤ��ǧ���롣
���������ƥ�β�Ư���������ݤ�
�����̤˥�����Ω���夲�˼��Ԥ��븶����
JUNE 2010����78
Ȭ��Ͼ����ƥ�˵������Ƥ��롣
���쥪��
�졼�����γ��Ϥ�����äƾ����ƥ���
Ư�������ƥ��ȥ��δ��֤��ߤ��뤳�Ȥǡ���
��֥��¿���ϲ���Ǥ��롣
������Υ������ǤϽ��褫��żҤ����Ѥ��Ƥ�
���ףͣӤΤޤ������Ǥ����Ѥ��뤳
�Ȥˤʤ뤿���礭�ʥȥ�֥뤬ȯ�����붲���
�㤤�����м�¦�ǤϣףͣӤ����ȥԥå���
�ꥹ�Ȥʤ�Ģɼ����Ф���?����?��ɬ�פˤ�
�뤿�ᡢ��Ϥ�ƥ��ȥ���ɬ�פ���
����ʪή������ɸ��Ƴ��
������κ��������Фơ���ƻ�˾�äƤ����
ʪή������ɸ�˴�Ť���̳�βĻ벽�ʸ�����
���ˤ�»ܤ��롣
Ŭ�ڤʻ�ɸ���ʤ���б��Ĥ�
��꤯���äƤ���Τ��ɤ�����ʬ����ʤ���
����������ʪή������ɸ��¿���μ�������ꤷ
���ȼ¸������ʤ��ʤ롣
����Ū�ˤ�������
�λ�ɸ�ȡ�ʪή�ʼ��λ�ɸ�줾���Ĥ���
�˹ʤꡢ���Υǡ��������İ�������³Ū�˲�
�����������Ƥ����Ȥ�������������Ǥ�
�������ưפǡ����̤�夲�䤹����
���������ɥХ��������Ȥ����˻�ϡ���������
��ɸ��ְ�ʬ����ԥå��Կ��פˡ�������
�ʼ��λ�ɸ��ָ��в�Ψ�פ˹ʤꡢ������
�Уɡʽ�����ɾ����ɸ�ˤȤ���Ƴ�����뤳
�Ȥˤʤä���
�ץ��������Ȥθ���
�������μ»ܹ��ܤ�ץ��������Ȥȸ����ȿ
�Ǥ����뤫�����ǣ˻�ϣмҤȤζ��Ĥ�Ƴ���
����
�����ȼ��
�� �Ҥ���ȥå�
������ǣ� �Ҥ�
�⼨���Ϥ���
����
�����ˤϡ���
�ҡʣżҡˤ���
˾����ˣмҤ�
�б��Ǥ��ʤ���
��ˤϡ�¾�Σ���
�̴�ȤȤξ��̡�
��ĤϤ����
�Ȥ�����ʸ����
���ä���줿��
�����줫����
��ۤɷФä���
����������ƣ˻�
����ɮ�Ԥ�Ϣ��
�������
�⼨��
�����餺���֤�����ˤ��������Ƥ���Τˡ�
�˻ᤫ��Ϣ�����ʤ����Ȥ��礦�ɵ��ˤ���
��������
���
˻������ɮ�Ԥϻפ鷺���ä���
�֣�
�Ҥ��ɥ��åץ����Ȥ��Ƥ��ޤ��ޤ�����
���餿
��ƣ��У�Ƴ���θ�Ƥ��ǽ餫����ľ������
�ˤʤ�ޤ����פȤ�����
����ǰ����ΰ�ĤǤ��ä�?�絬�ϥޥƥϥ�
���ƥ�Ƴ��?�ˤĤ��ơ��żҤϺƸ��ڤ⤷�ʤ�
�ޤ����ˤ����ʤ��ä���
������Ф��ƣżҤ�
�ޤ����ذƤ��Ф��ʤ��ä���
�������������ȸ��äƤ��礭���ä��Τϡ��ż�
�ΥȥåפȰյ���礷���мҤ�ô���Ԥ�������
����Ƥ��ޤä����Ȥ��ä��褦����
��������
��Ǥ�Ԥ������������ޤǤζ��ĤȤΥ���åפ�
���ޤ�ˤ��礭�����мҤؤΰ�������ǰ������
�����ʤ��ä���
������ˤ�äƣżҤ��礭�����֤�������Ƥ�
�ޤä������Ǥʤ�������ˣ��У�Ƴ�����Ф���
�ȥ饦�ޤޤǻĤäƤ��ޤä���
�������
ʣ���Σ��У̤��פ��Ƥ���С��żҤ��Ŭ��
�ѡ��ȥʡ�������Ǥ������⤷��ʤ���
�����μ�Υץ��������ȤϤ�Ϥꥭ�å����ջ���
�ץ������߷פ��������
�ץ��������Ȥοʤ�����
���ޤä����Ȥǡ���꤯�����Ϥ��β��פ��ܺä�
�Ƥ��ޤ����Ȥ����ճ��ʤۤ�¿���ΤǤ��롣
ɽ1����ʪή���ȼ�ɾ��ɽ�פ������ʬ��
ɾ�����о�����A ��B ��C��
ɾ��
?������Ƥζ��������¸���
?ʪή�ʼ���ɸ
?�뻡�ҸˤǤξ��ʼ�갷������
?�����ӥ���٥�
5 2 1 0
5 0 2 0
5 5 2 4
5 4 3 4
20 11 8 8
5 4 0 3
5 2 1 3
5 5 5 5
5 3 2 2
20 14 8 13
5 3 3 3
5 5 2 2
5 3 1 4
5 5 4 4
20 16 10 13
10 10 4 6
10 2 0 2
20 12 4 8
10 10 0 0
10 8 4 4
20 18 4 4
100 71 34 46
?�Ҹ����̳��������Ƥζ��������¸���
?������̳��������Ƥζ��������¸���
?������ʤμ�갷������
?�뻡�Ҹˤα��ľ���
����
����
����
����
����
�硡��
?��Ƥ����Ҹˤ�Ω��
?��Ƥ����ҸˤΥ���ѥ��ƥ�
?�Ҹ����Ⱦ�ꡦ���������߷�
?�Ҹˤ������١��ɿ��к�
?������Ƥζ��������¸���
?�㳲�����б�ǽ��
?���Ѥ���ͥ����
?����ι��ʤ륳���ȥ�����β�ǽ��
����
3. ����
�� �߷�
2. ��̳����
1. ��̳�ʼ�
4. �����ƥ�
5. ������
79����JUNE 2010
?ʪή�ʼ���ɸ�������������ɸ�ͤ��������
ɾ�����оݻ�ɸ����
1. �߸˺���Ψ?�����ƥ��
?���
�ǡ����Կ�
Ǽ������
���ƻ�ɸ��ñ�̷�����ɸ
����ê���ȥ���ԥ塼����ξ�
�ʺ߸˿�����ۤȤκ��ۤγ��
�߸ˤȤ�����·���Ǥ��Ƥ��뾦
�ʤγ��
�߸��ʤΤ����в������˺߸ˤ�
�ʤ��ʤä����ʤγ��
�в������˽в٤Ǥ��ʤ��ä���
�ʤγ��
�вٸ��ʤ��ʰ㤤��������㡢
�в�ϳ�줬ȯ�����줿���ʤγ�
��
Ǽ�ʸ��ʤ�ܵҥ��졼��ˤ��
�ʰ㤤��������㡢�в�ϳ�줬
ȯ�����줿���ʤγ��
�ܵҤ���ʸ��ְ�äƽв٤μ�
�ۤ�Ԥä����ʤγ��
Ǽ�����ְ㤨��������������
������
��«�λ��֤�����ε��ƻ���
�ʾ����夷��Ǽ�ʤ����������
����
2. ?�ҥå�Ψ
?���ڤ�Ψ
���ʺ߸��ʡ�
?���ڤ�Ψ
�������ʡ�
3. ?���и�Ψ
?���в�Ψ
4. ������Ψ
5. ������Ψ
6. ��ǼΨ
���ۥ����ƥ���ʶ�ۡˡ���
�˥����ƥ���ʶ�ۡˡ�100
�߸˾��ʤΥǡ����Կ�������
�ǡ����Կ���100
�߸������ڤ�����ǡ����Կ�
���߸��ʼ����ǡ�������100
�����в٥ǡ����Կ���������
�ټ����ǡ����Կ���100
���и˥ǡ����Կ��������ǡ�
���Կ���100
���в٥ǡ����Կ��������ǡ�
���Կ���100
�������ǡ����Կ��������ǡ�
���Կ���100
������ȯ��Ǽ������������
��Ǽ��������100
��Ǽȯ��Ǽ��������������
Ǽ��������100
?15��ʲ�
?0.5��ʲ�
85��ʾ�
99��ʾ�
84.15��ʾ�
0.1��ʲ�
0.02��ʲ�
0.1��ʲ�
0.02��ʲ�
0.02��ʲ�
�����νв����٤�
ɾ�������ɸ
��·���ξ�����
ɾ�������ɸ
�����νв����٤�
ɾ�������ɸ
�������٤�ɾ������
��ɸ
�������٤�ɾ������
��ɸ
?ʪή��ȸ�Ψ��ɸ�������������ɸ�ͤ��������
ɾ�����оݻ�ɸ����
�ԥå���Ψ�ǡ����Կ�
�ǡ����Կ�
��
���ƻ�ɸ��ñ�̷�����ɸ
�ԥå���ô���Ԥ�����������
�ԥå���Ԥ���ɼ�Կ�
�в٥ǡ����Կ����ԥå���
�����֣��ԡ�ʬ
��
��
�װ��νвٸ�Ψ��Ƚ��
�����ɸ
���ꥢ��
�вٸ�Ψ
���ꥢ���ȤΣ���������νвٿ�
��
�в٥ǡ����Կ������ꥢ��
�겼�Ͱ�
���ꥢ�̤���������
Ƚ�Ǥ����ɸ
����屿����Ψ�롼���̤�����ۤ������ʧ
���¤���Ψ
�롼���̻�ʧ���¡��롼��
������ۡ�100
�롼���̤�������Ψ��
Ƚ�Ǥ����ɸ
?����¾��ɸ������
���߸˵ڤӥ��쥮��顼��̳��ȯ�����������פ���Ƚ�Ǻ����Ȥ��ơ��ʲ��λ�ɸ�����ꤹ���������ɸ�ͤ��������
ɾ�����оݻ�ɸ����
�����̺߸�������
�����ƥ��
Ǽ������
Ǽ������
�ǡ����Կ�
���ƻ�ɸ��ñ�̷�����ɸ
�����̤�ľ��3 ����֤�ʿ�Ѻ߸�
�����ʶ�ۤǤϤʤ��� ʿ�Ѻ߸˿��̡�����������
�вٿ���
30 ��
15��
���ߤ�50��
���ߤ�50��
���ߤ�70��
��
��
�����̤κ߸˾�����
Ƚ�Ǥ����ɸ
��α�߸�Ψ
������ֽвټ��Ӥ��ʤ�������
��������߸˥����ƥ�������
����
����������ָ�˼��������ä�
Ǽ�������
Ǽ�����ô��������
�����յ�
������Ǽ�����ѹ��������б���
�����ؤؤ��ѹ����꤬ȯ������
���
��Ǽ�ʿ����������ʤ�ȯ����
�����ʿ��̤γ�硣
Ǽ�����
�����륹��������ͳ�ȶ����յ�
��α�߸˥����ƥ��������
�˥����ƥ����100
���ʥǡ����Կ���Ǽ�ʥǡ�
���Կ� ��100
���쥮��顼��ȯ������
��Ķ��Ϥζ�����
Ƚ�Ǥ����ɸ
���ֳ��������
?��������
?ô�������륹��
�в�����Ǽ��
��ˡ�ѹ����
?��������
?ô�������륹��
���ֳ��������
?��������
?ô�������륹��
ʪή���������ɸ������
|