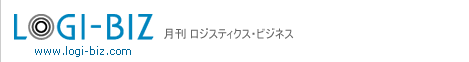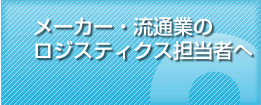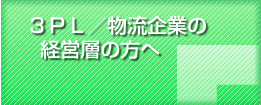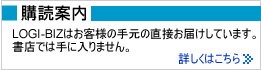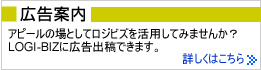|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

AUGUST 2010ΓΓΓΓ78
«·ΨΠΑλΓΜ≤·±ΏΛΈΞœΓΦΞ…Ξκ
ΓΓΘ
≈Φ“ΛœΡΙΒςΈΞΆΔΝςΛρΞαΓΦΞσΛ»ΛΙΛκ«·ΨΠΑλΓΜ≤·
±ΏΛΈ±ΩΝς≤ώΦ“Λ«ΛΔΛκΓΘ
¥Ί≈λΛΥΥήΦ“ΛρΟ÷Λ≠ΓΔΕαΈΌ
ΛΥΤσΞΪΫξΛΈ±ΡΕ»ΫξΛρΙΫΛ®ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΫξΆ≠Φ÷ΈΨ¬φΩτ
Λœ»§ΦΖ¬φΓΘ
ΛΫΛΈΛέΛ»ΛσΛ…Λ§Ξ»ΞλΓΦΞιΓΦΓΔΑλΓΜΞ»
ΞσΦ÷ΓΔΝΐΞ»ΞσΦ÷Λ Λ…ΛΈ¬γΖΩΦ÷Λ«ΛΔΛκΓΘ
«δΛξΨεΛ≤
ΛΈΛέΛ»ΛσΛ…Λœ¬γΦξ ΣΈ°≤ώΦ“ΛΈ≤ΦάΝΛ±ΆΔΝςΓΔΕώ¬Έ
≈ΣΛΥΛœœ©άΰ≤ώΦ“ΘΝΦ“ΓΔΝ“ΗΥ≤ώΦ“Θ¬Φ“ΓΔ ΣΈ°Μ“≤ώ
Φ“ΘΟΦ“ΛΈΜΑΦ“ΛΈΜ≈ΜωΛ«άξΛαΛιΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΘ
≈Φ“ΛΈΛηΛΠΛ ΟφΨ°ΛΈ±ΩΝς≤ώΦ“ΛœΓΔ≤ΌΦγΛ»ΡΨάή
ΦηΑζΛΙΛκΛηΛξΛβΓΔ¬γΦξ ΣΈ°≤ώΦ“ΛΈΞΔΞσΞάΓΦΛΥ≈Α
ΛΖΛΩΛέΛΠΛ§ΓΔΜ≈ΜωΈΧΛ§Α¬ΡξΛΖΓΔΞΎΞ ΞκΞΤΞΘΛ Λ…
ΛΈΞξΞΙΞ·ΛβΡψΛ·Λ ΛκΛ»ΛΛΛΠΖ–±ΡΞ»ΞΟΞΉΛΈ»ΫΟ«ΛΪ
ΛιΓΔΗΫΚΏΛΈΛηΛΠΛ «δΨεΙΫά°ΛρΡΙ«·ΑίΜΐΛΖΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛόΛ«…°Φ‘ΛœΛ≥ΛΈΛηΛΠΛ ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΥΩτ¬ΩΛ·
άήΛΖΛΤΛ≠ΛΩΛ§ΓΔ«·ΨΠΑλΓΜ≤·±ΏΛ»ΛΛΛΠ«δΛξΨεΛ≤Β§
ΧœΛœΓΔ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΥΛ»ΛΟΛΤΛΈΑλΛΡΛΈΞœΓΦΞ…ΞκΛΥΛ
ΛΟΛΤΛΛΛκΛ»¥ΕΛΗΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΑλΓΜ≤·±ΏΛρΤΆ«ΥΛ«Λ≠ΛκΛ»ΓΔ«≥ΈΝ¬εΛδΦ÷ΈΨ»ώ
Λ Λ…ΛΈΙΊΤΰΛΥΞήΞξΞεΓΦΞύΞ«ΞΘΞΙΞΪΞΠΞσΞ»Λ§ΗζΛΛΛΤ
Λ·ΛκΓΘ
Β§ΧœΛΈΞαΞξΞΟΞ»ΛΥΛηΛΟΛΤΞ≥ΞΙΞ»Λ§≤ΦΛ§ΛξΓΔ
Ε»≥ΠΛΥΛΣΛ±ΛκΟΈΧΨ≈ΌΛβΝΐΛΙΛΩΛαΓΔΩΆΚύ≥Έ ίΛ§ΆΤ
ΑΉΛΥΛ ΛκΓΘ
ΛόΛΩ≤ΌΦγΛΪΛιΛΈΩ°Ά―ΛβΙβΛόΛΟΛΤΛ·ΛκΓΘ
ΓΓΘ
≈Φ“ΛœΛ≥ΛΈΞœΓΦΞ…ΞκΛρΛ°ΛξΛ°ΛξΞ·ΞξΞΔΛΖΛΤΛΛ
ΛΩΛ§ΓΔΜωΕ»ΈΈΑηΛρΆΔ«έΝςΛΥΗ¬ΡξΛΖΛΤΛΛΛκ≈άΛΥΤΟ
ΡßΛ§ΛΔΛΟΛΩΓΘ
Θ≈Φ“ΛΈΛηΛΠΛΥΆΔ«έΝςΛΪΛιΜωΕ»ΛρΞΙ
ΞΩΓΦΞ»ΛΖΛΩ≤ώΦ“ΛΈ¬ΩΛ·ΛœΓΔ ί¥…ΛδΈ°ΡΧ≤ΟΙ©ΛΥΕ»
Χ≥ΈΈΑηΛρ≥»¬γΛΖΓΔ…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΙβΛαΛκΛ≥Λ»Λ««δΛξ
ΨεΛ≤ΛρΝœΛΟΛΤΛΛΛ·ΛβΛΈΛάΛ§ΓΔΛΫΛΠΛœΛΖΛΤΛΛΛ ΛΪ
ΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛ≥ΛΥΘ≈Φ“ΛΈ≤ΰΝ±ΞίΞΛΞσΞ»Λ§ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ…°Φ‘Λ§Θ≈Φ“ΛρΟΈΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΩΛ≠ΛΟΛΪΛ±ΛœΓΔΛΔ
ΛκΕβΆΜΒΓ¥ΊΛΈΨ“≤πΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΞξΓΦΞόΞσΞΖΞγΞΟΞ·
Α ΙΏΛΈΡΙΑζΛ·…‘ΕΖΛΥΛηΛΟΛΤΓΔΘ≈Φ“Λ§ΛΛΛηΛΛΛηά÷
ΜζΖ–±ΡΛρΕ·ΛΛΛιΛλΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΩΛ≥Λ»ΛΪΛιΓΔΛΫ
ΛΈΖ–±ΡΨθΕΖΛρΩ«Ο«ΛΖ≤ρΖηΚωΛρΡσΦ®ΛΖΛΤΆΏΛΖΛΛΛ»
ΛΛΛΠΑΆΆξΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΘ
≈Φ“ΛΈΘ‘Φ“ΡΙΛœΓΔ…°Φ‘Λ»ΛΝΛγΛΠΛ…Τ±ΛΛ«·Λ«ΛΔ
ΛΟΛΩΓΘ
Θ≈Φ“ΛΥΫΔΛ·ΛόΛ«Λœ ΣΈ°Λ»ΛœΛόΛΟΛΩΛ·ΧΒ±ο
Λ Μ≈ΜωΛρ≈ΨΓΙΛ»ΛΖΛΤΛΛΛΩΛ§ΓΔΤσΜΆ«·ΝΑΛΥΘ≈Φ“ΛΈ
ΝΑΦ“ΡΙΛΈΧΦΛ«ΛΔΛΟΛΩΗΫΚΏΛΈ±ϋ ΐΛ»ΟΈΛξΙγΛΛΓΔΛΫ
ΛλΛρΛ≠ΛΟΛΪΛ±ΛΥΘ≈Φ“ΛράΎΛξάΙΛξΛΙΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟ
ΛΩΛ»ΛΛΛΠΓΘ
ΓΓΒΝ…ψΛΥΛΔΛΩΛκΝΑΦ“ΡΙΛœΓΔΘ‘ΜαΛΥ¬–ΛΖΛΤ?Θ≈Φ“
ΛΈΛ≥Λ»ΛœΛΣΝΑΛΥ«ΛΛΜΛΩ?Λ»Αλ«ΛΛΖΓΔΛΫΛλΑ ΙΏΛœ
¥ΊœΔ≤ώΦ“ΛΈΖ–±ΡΛΥΟμΈœΛΙΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛξΓΔΦ“ΡΙΛΈ
ΗΣΫώΛ≠Λ≥ΛΫΜΡΛΖΛΤΛΛΛΩΛ§Θ≈Φ“ΛΥΛœΛέΛ»ΛσΛ…Μ―Λρ
ΗΪΛΜΛ Λ·Λ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
Θ‘ΜαΛœΝ¥Λ·±ΩΝςΕ»≥ΠΛΈΛ≥
Λ»Λ Λ… §ΛΪΛιΛ ΛΛΨθ¬÷Λ«ΓΔ≈ωΫιΛœΫςά≠ΜωΧ≥ΑςΛ»
ΤσΩΆΛ««έΦ÷ΛρΙ‘ΛΛΓΔΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΩΛΝΛ»ΛΙΛΟΛΩΛβ
ΛσΛάΛΈΤϋΓΙΛρΖΪΛξΙ≠Λ≤ΛΩΓΘ
ΓΓΩΖΒ§ΚΈΆ―ΛρΛΪΛ±ΛΤΛβΩΆΛ§ΫΗΛόΛιΛ ΛΛΓΘ
ΛδΛΟ
Λ»ΛΈΛ≥Λ»Λ«ΤΰΦ“ΛΖΛΤΛ·ΛλΛΩΦ“ΑςΛβΡΙ¬≥Λ≠ΛΖΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛλΛάΛ±Θ≈Φ“ΛΈΜ≈ΜωΛœΓΔΨηΧ≥ΑςΓΔΜωΧ≥ΑςΛ»ΛβΞœ
ΜωΈψΛ«≥ΊΛ÷
ΗΫΨλ≤ΰΝ±
ΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦ
άΡΧΎάΒΑλΓΓ¬ε…Ϋ
ΓΓ¬γΦξ ΣΈ°≤ώΦ“ΛΈ≤ΦάΝΛ±ΛΈΡΙΒςΈΞ±ΩΝςΛΥ≈ΑΛΖΛΤΛ≠ΛΩΘ≈Φ“ΓΘ
Χή…Η
ΛάΛΟΛΩ«·ΨΠΑλΓΜ≤·±ΏΛρΟΘά°ΛΖΛΩΡΨΗεΛΥΞξΓΦΞόΞσΞΖΞγΞΟΞ·ΛΥΫ±Λο
ΛλΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΗεΛœΗΚΦΐΗΚ±ΉΛ«ά÷Μζ≈ΨΆνΛρΆΨΒΖΛ Λ·ΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
Έ©
ΛΝΡΨΛκ ΐΥΓΛœΛΔΛκΛάΛμΛΠΛΪΓΘ
ΕβΆΜΒΓ¥ΊΛΪΛιΝξΟΧΛρΜΐΛΝΙΰΛόΛλΛΩΓΘ
ΡΙΒςΈΞ±ΩΝςΘ≈Φ“ΛΈΙθΜζ≤ΫΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»
¬η91 ≤σ
ΛΔΛΣΛ≠ΓΠΛΖΛγΛΠΛΛΛΝ
ΓΓ1964«·άΗΛόΛλΓΘ
Βΰ≈‘ΜΚ
Ε»¬γ≥ΊΖ–Κ―≥Ί…τ¬¥Ε»ΓΘ
¬γΦξ
±ΩΝςΕ»Φ‘ΛΈΞΜΓΦΞκΞΙΞ…ΞιΞΛ
Ξ–ΓΦΛρΖ–ΛΤΓΔ89 «·ΛΥΝΞΑφ
ΝμΙγΗΠΒφΫξΤΰΦ“ΓΘ
ΣΈ°≥Ϊ»·
ΞΝΓΦΞύΓΠΞ»ΞιΞΟΞ·ΞΝΓΦΞύΞΝΓΦ
Ξ’ΛρΧ≥ΛαΛκΓΘ
96«·ΓΔΤ»Έ©ΓΘ
ΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦΛράΏ
Έ©ΛΖ¬ε…ΫΛΥΫΔ«ΛΓΘ
ΗΫΚΏΛΥΜξΛκΓΘ
HP:http://www.nlf.co.jp/
e-mail:info@nlf.co.jp
79ΓΓΓΓAUGUST 2010
ΓΦΞ…Λ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
Θ‘ΜαΛΈΩ¥œΪΛœΫ≈Λ ΛξΓΔΛΡΛΛΛΥ¬Έ
Ρ¥Λρ χΛΖΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΛ§ΓΔΛΫΛλΛ«ΛβΒΌΛύΛ≥Λ»ΛœΒω
ΛΒΛλΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΝΑΦ“ΡΙΛœΖ–±ΡΛΈ¬ηΑλάΰΛΪΛιΛœ¬ύΛΛΛΤΛΛΛΩΛβ
ΛΈΛΈΓΔΛΫΛΈΗεΛβ≈ίΜΚάΘΝΑΛΈ±ΩΝς≤ώΦ“Λρ«ψΛΛΦηΛξΓΔ
Θ≈Φ“ΛΥ≈ΐΙγΛΒΛΜΛκΛ»ΛΛΛΠΛΪΛΩΛΝΛ«ΓΔΘΆΓθΘΝΛρΤσ
≈ΌΙ‘ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛΠΛΖΛΩ≈ΐΙγ≤ώΦ“ΛΈ»÷Τ§≥ ΛΈ
Φ“ΑςΛΩΛΝΛ§ΓΔΘ≈Φ“ΛΈ¥¥…τΛ»ΛΖΛΤΡξΟεΛΖΛΤΛ·ΛλΛΩ
Λ≥Λ»Λ«ΓΔΛηΛΠΛδΛ·Θ‘ΜαΛœΗΫΨλΜ≈ΜωΛΪΛι≤ρ ϋΛΒΛλΓΔ
ΩΖΦ“ΡΙΛ»ΛΖΛΤΖ–±ΡΛΥΫΗΟφΛ«Λ≠ΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛ»Λ≥ΛμΛ§ΓΔΛΫΛσΛ ΧπάηΛΥΘ‘Φ“ΡΙΛœΩ»¬ΈΛρ≤θΛΖ
ΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
ΗΫΨλΛΈΚ°ΆπΛ§Φΐ¬ΪΛΖΓΔΛ“Λ»ΛόΛΚΛœ
ΗΣΛΈ≤ΌΛ§ΙΏΛξΛΩΛ»ΛΛΛΠΑ¬Ω¥¥ΕΛΪΛιΛ ΛΈΛΪΓΔΛΫΛλ
ΛόΛ«ΛΥΟΏά―ΛΒΛλΛΩ»ηœΪΛ§ΑλΒΛΛΥ…ΫΛΥΫ–ΛΤΓΔΤΰ±Γ
άΗ≥ηΛρΕ·ΛΛΛιΛλΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛΈ
ΗεΓΔ…¬ΨθΛœΆνΛΝΟεΛ≠ΓΔΗΫΚΏΛœΖ–±ΡΛΥ…ϋΒΔΛΖΛΤΛΛ
ΛκΛ§ΓΔΛΫΛλΛ«ΛβΩ¥œΪΛ§Ϋ≈Λ ΛκΛ»ΜΰΓΙΜΐ…¬Λ§Τ§Λρ
ΛβΛΩΛ≤ΛΤΞάΞΠΞσΛΙΛκΛ≥Λ»Λ§ΛΔΛκΓΘ
Φ÷ΗΥΛΈ §ΜΕΛ«¥…ΆΐΛ§Ν¬ΛΪΛΥ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΘ‘Φ“ΡΙΛΈΛΫΛσΛ Μ―ΛρΗΪΛΤΓΔ»÷Τ§≥ ΛΩ
ΛΝΛ§ ≥Β·ΛΖΛΩΓΘ
ΛβΛ»ΛβΛ»Θ‘Φ“ΡΙΛœΩΤ §»©ΛΈά≠≥
Λ«ΩΆΨπΛΥΗϋΛΛΓΘ
≤ΟΛ®ΛΤ≈ΐΙγ≤ώΦ“Ϋ–Ω»ΛΈ»÷Τ§≥ ΛΩ
ΛΝΛΥΛœΝΑΦ“ΡΙΛΥΫθΛ±ΛΤΛβΛιΛΟΛΩΛ»ΛΛΛΠΑ’Φ±ΛβΛΔ
ΛξΓΔ≥ßΛ§Λ§ΛύΛΖΛψΛιΛΥΤ·ΛΛΛΩΓΘ
ΛΫΛΖΛΤΜΆ«·ΝΑΛΥ
ΛœΓ÷«δΨεΙβΑλΓΜ≤·±ΏΓΉΛ»ΛΛΛΠΧή…ΗΛρ≥ßΛ§ΕΠΆ≠ΛΙ
ΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛξΓΔΤσ«·ΗεΛΥΛΫΛΈΧ¥ΛρΟΘά°ΛΖΛΩΛΈΛ«
ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΞξΓΦΞόΞσΞΖΞγΞΟΞ·ΛΥΗΪ…ώΛοΛλΛΩΛΈΛœΓΔΛΫΛΈΡΨ
ΗεΛάΛΟΛΩΓΘ
«δΛξΨεΛ≤Λ§ΒόΗΚΛΖΓΔΛΖΛΪΛβ±ΩΡ¬ΩεΫύ
Λ§≤ΦΆνΛΖΛΩΛ≥Λ»Λ«ΓΔΛΫΛλΛόΛ«ΛΈά°ΡΙΞΎΓΦΞΙΛΪΛι
Αλ≈άΓΔ¬γ…ΐΛ ΗΚΦΐΗΚ±ΉΛρΆΨΒΖΛ Λ·ΛΒΛλΛΤΓΔΛΡΛΛ
ΛΥΛœά÷ΜζΛΥ¥ΌΛΟΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛσΛ Θ≈Φ“ΛρΚΤΛ”ΙθΜζ≤ΫΛΙΛκΛ≥Λ»Λ§ΓΔ≤φΓΙΤϋ
ΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦΓ ΘΈΘΧΘΤΓΥΛΥΆΩΛ®ΛιΛλΛΩΜ»
ΧΩΛάΛΟΛΩΓΘ
≤φΓΙΛœΛόΛΚΘ≈Φ“ΛΈΗΫΨλΛρΜκΜΓΛΖΓΔ¥¥
…τΛΊΛΈΞ“ΞΔΞξΞσΞΑΛρΙ‘ΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛλΛ» ¬Ι‘ΛΖΛΤ≥Τ
ΦοΛΈΦ¬ά”Ξ«ΓΦΞΩΓΔΜώΈΝΛ Λ…ΛρΞΝΞßΞΟΞ·ΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΘ
≈Φ“ΛœΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈΒκΆΩΛΥ βΙγά©ΛρΤ≥ΤΰΛΖΛΤ
ΛΛΛΩΓΘ
ΡΙΒςΈΞΦγ¬ΈΛΈ±ΩΝς≤ώΦ“Λ«ΛœΡΝΛΖΛΛΛ≥Λ»
Λ«ΛœΛ ΛΛΛ§ΓΔ βΙγΛΈ»φΈ®Λ§¬γΛ≠≤αΛ°ΛΩΓΘ
ΛόΛΩΦ÷
ΗΥΛ§ §ΜΕΛΖΛΤΛΛΛκΛ≥Λ»Λ§±ΤΕΝΛΖΓΔΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦ¥…
ΆΐΓΔ±ΩΙ‘¥…ΆΐΛ§ΛέΛ»ΛσΛ…Λ«Λ≠ΛΤΛΛΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΛΫ
ΛΈΛ≥Λ»Λ§Φ÷ΈΨΜωΗΈΓΔΨΠ… ΜωΗΈΛΈ¬Ω»·ΛρΨΖΛΛΛΤΛΛ
ΛΩΓΘ
ΛΜΛΟΛΪΛ·ΛΈΆχ±ΉΛ§ΜωΗΈ»ώΛ«»τΛσΛ«ΛΛΛΩΓΘ
Ξ≥
ΞσΞΉΞιΞΛΞΔΞσΞΙΓ ΥΓΈαΫεΦιΓΥΛ»ΛΛΛΠ¬ΠΧΧΛΪΛιΛβΓΔ
Θ≈Φ“Λœ?¥μΛ ΛΛΕΕΛρ≈œΛΟΛΤΛΛΛκ?Λ»Λ≥ΛμΛ§≥ά¥÷
ΗΪΛιΛλΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛιΛΈΨπ σΛρΗΒΛΥΓΔ≤φΓΙΘΈΘΧΘΤΛœΘ≈Φ“ΛΈ
?ΓλΓΔΞβΞΈΓΔΞΪΞΆΓΔΨπ σΓΔΛΫΛΈ¬Ψ?ΛΥ¥ΊΛοΛκ
Χδ¬ξ≈άΛ»≤ΰΝ±ΛΈ ΐΗΰά≠ΛρΑ ≤ΦΛΈΛηΛΠΛΥάΑΆΐΛΖΛΩΓΘ
Θ±ΓΞΓλ
?Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈΞΔΞκΞ≥ΓΦΞκΞΝΞßΞΟΞ·Λδ¬–ΧΧ≈άΗΤΛ
Λ…Λ§Λ«Λ≠ΛΤΛΛΛ ΛΛ
ΔΣΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦ¥…ΆΐΛΈ≈ΑΡλ
?Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΥΛηΛΟΛΤάωΦ÷ΛΥ¬γΛ≠Λ·Ξ–ΞιΞΡΞ≠Λ§ΛΔ
Λκ
ΔΣάωΦ÷ΞκΓΦΞκΛΈάΏΡξΛ»≈ΑΡλ
?ΒΌΦ÷Έ®ΞΦΞμ≤ΫΛ»ΖγΕ–ΜΰΛΈ¬–±ΰΈœΝΐΕ·
ΔΣ ΘΩτΛΈΦ÷ΦοΛρΟ¥≈ωΛΙΛκΓ÷ΞόΞκΞΝΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΓΉ
ΛΈ≥»¬γ
?ΚΈΆ―≥ηΤΑΛΈΕ·≤Ϋ
ΔΣ¥…ΆΐΩΠΛΥ?ΆζΈρΫώΛΈΤ…ΛΏ ΐΓΔ?ΧΧάήΛΈΙ‘ΛΛ ΐ
ΛρΫΛΤάΛΒΛΜΛκ
?≤αΒνΑλΓΜΞΪΖνΛΥ¬γΨ°œΜΜΑΖοΛΈΜωΗΈΛ§»·άΗΛΖΛΤ
ΛΛΛκ
ΔΣΦ÷ΈΨΜωΗΈΓΔΨΠ… ΜωΗΈΛΈΚοΗΚ
?Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΒκΆΩΛΈ βΙγ»φΈ®Λ§ΙβΛΛ
?άλ¬ΑΞΙΞίΞΟΞ»Φ÷ΈΨΛΈ¥…ΆΐΛΈΦ¬Μή
ΔΣ«έΦ÷¥…ΆΐΛρΙ‘ΛΛΓΔΫξΚΏΛ»Ε»Χ≥Φ¬¬÷Λρ«ΡΑ°ΛΙΛκ
?Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΓΔΚνΕ»ΑςΛΥ¬–ΛΙΛκΕΒΑιΓΠΗΠΫΛΛΣΛη
Λ”ΜΊΤ≥¬Έά©ΛΈΙΫΟέΓ ΨΠ… ΜωΗΈΓΠΦ÷ΈΨΜωΗΈΓΠΗμ
Ϋ–≤Ό¬–ΚωΛ»ΛΖΛΤΓΥ
?ΜωΗΈ σΙπΫώΡσΫ–ΛΈ≈ΑΡλ
?ΜωΗΈ≈ωΜωΦ‘ΛΥΛηΛκΡΪΈιΜΰΛ«ΛΈΥήΩΆ σΙπΛΈΞκΓΦ
Ξκ≤Ϋ
Θ≤ΓΞΞβΞΈ
?…‘ΆΉΛ ≈ΎΟœΛΈ ÷Β―
?≈ΎΟœΛΈΆ≠Ηζ≥ηΆ―ΛΈΗΓΤΛΔΣΩΖΒ§ΦΐΤΰΛΈ≥ΆΤά
?ΥήΦ“ ί¥…ΞΙΞΎΓΦΞΙ≥»¬γΛΥΛηΛκΝ“ΗΥΦΐΤΰΛΈ≥ΆΤά
?Βρ≈άΫΗΧσΛΥΛηΛκΡ¬¬ΏΈΝΛΈΚοΗΚ
Θ≥ΓΞΞΪΞΆ
?ΖνΦΓΖηΜΜΛΈΚνά°ΛΥΑλΞΪΖνΑ ΨεΛΪΛΪΛΟΛΤΛΛΛκ
Λ§ΓΔΛ≥ΛλΛρΦΖΤϋ¥÷ΞλΞΌΞκΛΥΛόΛ«ΟΜΫΧΛΖΓΔ¬Μ±Ή
Ψπ σΛρΞΙΞ‘ΓΦΞ«ΞΘΛΥΦΐΫΗΛΖ≈ωΖνΛΈΙθΜζ≤Ϋ¬–Κω
Λρ¬«ΛΝΫ–ΛΙΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥ±ΩΡ¬Λ§ΗεΖηΛαΛΥΛ ΛΟ
ΛΤΛΛΛκΦηΑζάηΛ»ΛΈΗρΨΡΛρΙ‘ΛΛΓΔάΝΒαΫώ»·Ι‘Λό
Λ«ΛΈΕ»Χ≥ΞΉΞμΞΜΞΙΛρ≤ΰΝ±ΛΙΛκ
?Φ÷ΈΨ Χ¬Μ±Ή…ΫΛ»Τϋ Χ¬Μ±Ή…ΫΛΈΤ≥ΤΰΛΥΛηΛκΆχ±Ή
¥…ΆΐΛΈ≈ΑΡλ
?«≥»ώ¥…ΆΐΛΈ≈ΑΡλΛΥΛηΛΟΛΤΓΔ«≥ΈΝ»ώΛΈΚοΗΚΓΔΦ÷
ΈΨΛΈΦςΧΩ±δΡΙΓΔΜωΗΈΛΈΚοΗΚΛρ≈ΑΡλΛΙΛκ
?ΖνΛ¥Λ»ΛΥά÷ΜζΓΔΙθΜζΛ§ΤΰΛλΛΪΛοΛξΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛ
AUGUST 2010ΓΓΓΓ80
ΛκΓΘ
ΆΫΜΜΖΉ≤ηΛΈΚνά°ΛΥΛηΛκΒΑΤΜΫΛάΒΛΈΜ≈Ν»ΛΏ
ΛρΚνΛκ
Θ¥ΓΞΨπ σ
?ΨΠ… ΜωΗΈΗΕΑχΛΈΡ…ΒαΛ»≤ρΖηΚωΛΈΟξΫ–
?ΜωΗΈΨπ σΛΈΕΠΆ≠≤ΫΛΥΛηΛκ¥μΗ±ΆΫΟΈΑ’Φ±ΛΈΗΰΨε
?ΗεΖηΛα±ΩΡ¬ΛΈΚοΗΚ
ΘΒΓΞΛΫΛΈ¬ΨΓ ±ΡΕ»ΓΔ¥…Άΐ¬ΨΓΥ
?≤ΌΦγΛ»ΛΈΡΨάήΦηΑζΛρ≥»¬γΛΖΓΔ«δΛξΨεΛ≤ΙΫά°»φ
ΛΈΫΛάΒΛρΩόΛκ
?ΞέΓΦΞύΞΎΓΦΞΗΘ”Θ≈ΘœΓ ΗΓΚςΞ®ΞσΞΗΞσΚ«≈§≤ΫΓΥΛΥ
ΛηΛκΩΖΒ§ΧδΙγΛΜΛΈ≥»¬γ
ΓΓΛ≥ΛλΛιΛΈΤβΆΤΛρ¥πΛΥΛΖΛΤΓΔΘ≈Φ“ΛΈΖ–±Ρ¥¥…τ
ΛΩΛΝΛ»¬ηΑλ≤σΧήΛΈΞΏΓΦΞΤΞΘΞσΞΑΛρΙ‘ΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛλ
ΛΨΛλΛΈΞΤΓΦΞόΛΥΓΔΘ‘Φ“ΡΙΛ§Ο¥≈ωΦ‘Λρ≥δΛξΩΕΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΧσΜΑΞΪΖνΗεΓΔ¬ηΤσ≤σΧήΛΈΞΏΓΦΞΤΞΘΞσΞΑΛΥΫ–
ά ΛΖΛΩ…°Φ‘ΛœΓΔ»ύΛιΛΈΙ‘ΤΑΈœΛΥΕΟΛΪΛΒΛλΛκΛ≥Λ»
ΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΛοΛΚΛΪΛΈ¥ϋ¥÷Λ«ά°ΛΖΩκΛ≤ΛιΛλΛΩΩτ¬Ω
Λ·ΛΈ≤ΰΝ±Λ»ΛΫΛΈά°≤ΧΛ§ΓΔ¬ηΤσ≤σΧήΛΈΞΏΓΦΞΤΞΘΞσ
ΞΑΛ« σΙπΛΒΛλΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΛ ΛΪΛ«ΛβΤΟ…°ΛΙΛΌΛ≠≈άΛρ
Α ≤ΦΛΥΒσΛ≤ΛκΓΘ
?Φ÷ΈΨΜωΗΈΓΔΨΠ… ΜωΗΈΛρΜΆ §ΛΈΑλΛΥΚοΗΚ
?ΜΟΡξ»«ΛΈΖνΦΓ¬Μ±ΉΛ§ΆβΖνΑλΓΜΤϋΛΥΛœΛ«Λ≠ΛΔΛ§
ΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΩ
?≈ΎΟœΛΈ ÷Β―ΓΔΦ÷ΗΥΛΈΫΗΧσΓΔΛΫΛΈ¬ΨΖ–»ώΙύΧήΛΈ
ΗΪΡΨΛΖΛ«Ζν¥÷ΕεΗόΥϋ±ΏΛΈΞ≥ΞΙΞ»ΚοΗΚΛρΦ¬ΗΫΛΖ
ΛΩ
? βΙγ»φΈ®ΛΈΑζΛ≠≤ΦΛ≤ΗρΨΡΛρΧΒΤώΛΥΨηΛξάΎΛξΓΔ
ΝμΩΆΖο»ώΛρΑλΗόΓσΑΒΫΧΛΖΛΩ
?ΚΈΆ―Ο¥≈ωΛΈ¥…ΆΐΩΠΛ§ΆζΈρΫώΛΈΤ…ΛΏ ΐΓΔΧΧάήΛΈ
Ι‘ΛΛ ΐΛρΫ§ΤάΛΖΛΩΛ≥Λ»Λ«ΓΔΨηΧ≥ΑςΛΈ≈ωΛΩΛξΛœ
ΛΚΛλΛ§Λ Λ·Λ ΛΟΛΩ
?ΖΉ≤ηΧΛΟΘΛ§Ω¥«έΛΒΛλΛΩ¥ϋΥωΛΈΜΑΖνΛΈΖνΦΓΛΈ«δ
ΛξΨεΛ≤Λ§¬–ΝΑ«·ΑλΜΑΓΜΓσΛ»Λ ΛξΓΔΚΤΛ”«·ΨΠΑλ
ΓΜ≤·±ΏΛΈ¬γ¬φΛΥΨηΛΜΛΩ
ΓΓΖκ≤ΧΛ»ΛΖΛΤΓΔΘ≈Φ“ΛœΛοΛΚΛΪΜΑΞΪΖν¥÷ΛΈ≥ηΤΑΛ«
ΗΪΜωΛΥΙθΜζ≈Ψ¥ΙΛρά°ΛΖΩκΛ≤ΛΩΓΘ
Θ‘Φ“ΡΙΛ»¥¥…τΛΩ
ΛΝΛΈ¥÷ΛΥΛœΓΔΡΙ«·ΛΈ…’Λ≠ΙγΛΛΛρΡΧΛΗΛΤ?¬®ΜΰΫη
Άΐ?Λ§Α≈ΧέΛΈΞκΓΦΞκΛ»Λ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΛΡΛόΛΛΤ
Λ–ΕΝΛ·Ν»ΩΞΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΛΫΛλΛ§ΙθΜζ≤ΫΛΈΚ«¬γ
ΛΈΆΉΑχΛάΛ»…°Φ‘Λœ…Ψ≤ΝΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
Γ»ΗεΖηΛα±ΩΡ¬Γ…ΛρΛ…ΛΠ≤ρΨΟΛΙΛκΛΪ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔ≤ί¬ξΛβΤσΛΡΜΡΛΒΛλΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΑλΛΡΛœΞ…
ΞιΞΛΞ–ΓΦ¥…ΆΐΛΈΧδ¬ξΛάΓΘ
ΡΙΒςΈΞΆΔΝςΛΈΒρ≈άΛ«Λœ
ΤσΜΆΜΰ¥÷ΓΔΤΰΫ–ΗΥΛ§ΛΔΛκΓΘ
¥…ΆΐΩΠΛ§…‘ΚΏΛΈΩΦΧκ
¬”Λ«ΛΈ¬–ΧΧ≈άΗΤΛδΞΔΞκΞ≥ΓΦΞκΞΝΞßΞΟΞ·ΛρΛ…ΛΠΛδ
ΛΟΛΤΙ‘ΛΠΛΪΓΘ
ΤσΛΡΧήΛœΓΔΗεΖηΛα±ΩΡ¬ΛάΓΘ
ΆΟΦ÷Λ
Λ…Λ«Λœ«έΝςΛΈΫΣΈΜΗεΛΥ±ΩΡ¬ΛΈΖηΛόΛκΞ±ΓΦΞΙΛ§ΛΔ
ΛκΓΘ
Λ≥ΛλΛρΛ…ΛΠ≤ΰΝ±ΛΙΛκΛΪΛ»ΛΛΛΠΧδ¬ξΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΩΦΧκΛΈ≈άΗΤΓΠΞΔΞκΞ≥ΓΦΞκΞΝΞßΞΟΞ·ΛΥΛΡΛΛΛΤΛœΓΔ
ΞΖΞκΞ–ΓΦΩΆΚύΛρΩΖΒ§ΗέΆ―ΛΙΛκΛ»ΛΛΛΠΞΔΞΛΞ«ΞΔΛ§
Ϋ–ΛΩΓΘ
Ξ≥ΞΙΞ»ΞΔΞΟΞΉΛρΧ»ΛλΛ ΛΛΛ§ΓΔΜ≈ ΐΛΈΛ ΛΛ
Λ»Λ≥ΛμΛάΛμΛΠΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΛΫΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΞξΓΦΞάΓΦ
≥ ΛΈ»÷Τ§Λ§Γ÷ΛΠΛΝΛιΜΑΧΨΛ§ΓΔΗρ¬ΊΛ«Ϋ–ΛΤΛ≠ΛόΛΙΓΘ
Γ ΨηΧ≥Ας¥…ΆΐΛρΓΥΛδΛκΑ ΨεΛœ≈ΑΡλΛΖΛΩΛΛΓΉΛ»Φξ
ΛρΒσΛ≤ΛΤΛ·ΛλΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛΥΛœΘ‘Φ“ΡΙΛάΛ±Λ«Λ Λ·≤φΓΙΘΈΘΧΘΤΛβΆξΛβ
ΛΖΛΒΛρ≥–Λ®ΛΩΓΘ
ΛβΛΝΛμΛσ¥¥…τΛΩΛΝΛΈ¥ηΡΞΛξΛΥ¥≈
Λ®ΛΙΛ°ΛκΛΈΛœΛηΛ·Λ ΛΛΓΘ
ΛΛΛΚΛλΛœΞΖΞκΞ–ΓΦΩΆΚύ
≈υΛρΩΖΛΩΛΥ≈ξΤΰΛΙΛκΛ»ΛΖΛΤΛβΓΔΛόΛΚΛœΦΪ §ΟΘΛ«
Φ¬¬÷Λρ«ΡΑ°ΛΖΛΤΛΣΛ·Λ≥Λ»ΛœΫ≈ΆΉΛάΓΘ
ΛΫΛσΛ »ΫΟ«
ΛΪΛιΓΔ¥¥…τΛΩΛΝΛΈΡσΑΤΛρΘ‘Φ“ΡΙΛœ¥νΛσΛ«ΦθΛ±Τΰ
ΛλΛΩΛΈΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΤσ≈άΧήΛΈΗεΖηΛα±ΩΡ¬ΛΡΛΛΛΤΓΘ
ΗεΖηΛα±ΩΡ¬Λ§»·
άΗΛΙΛκΛΈΛœΦγΆΉ≤ΌΦγΜΑΦ“ΛΈΛΠΛΝΛΈΑλΦ“ΓΔΘΊΦ“Λά
Λ±ΛάΛΟΛΩΓΘ
Φ¬Λœ≤φΓΙΘΈΘΧΘΤΛœΓΔ≤αΒνΛΥ¬ΨΛΈΞ·Ξι
ΞΛΞΔΞσΞ»ΛΈΑΤΖοΛ«ΓΔΛ≥ΛΈΘΊΦ“Λ»Τ±ΆΆΛΈΧδ¬ξΛρœΟ
ΛΖΙγΛΟΛΩΛ≥Λ»Λ§ΛΔΛκΓΘ
ΛΫΛΈΖοΛ«ΛœΗεΖηΛα±ΩΡ¬ΛΥ
≤ΟΛ®ΓΔΡΙΜΰ¥÷ΛΥΛοΛΩΛΟΛΤΛΛΛΩά―ΙΰΛΏ¬‘ΛΝΛΈ≤ΰΝ±
Λ§ΞΤΓΦΞόΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΞ·ΞιΞΛΞΔΞσΞ»άηΛΈΦ“ΡΙΛ»ΑλΫοΛΥάη ΐΛΈΞ»
ΞΟΞΉΛΥΡΨΟΧ»ΫΛρΙ‘ΛΟΛΩΓΘ
¬γΦξΨεΨλ¥κΕ»ΛιΛΖΛ·ΓΔΞ»
ΞΟΞΉΛΪΛιΟζΫ≈ΛΥΛΣœΆΛ”ΛρΛΛΛΩΛάΛ≠ΓΔ≤ΰΝ±ΛρΧσ¬Ϊ
ΛΖΛΤΛ·ΛλΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΛ≥ΛΈΞ·ΞιΞΙΛΥΛ ΛκΛ»ΓΔΨε
ΝΊ…τΛΈΗάΛΠΛ≥Λ»Λ»ΗΫΨλΛΈΛδΛκΛ≥Λ»ΛΥΓΔΛΪΛ Λξ≥Ϊ
Λ≠ΛΈΛΔΛκΛ≥Λ»Λ§ΡΝΛΖΛ·Λ ΛΛΓΘ
ΛδΛœΛξΗΫΨλΛΈ¬–±ΰ
Λ§Ϋ≈ΆΉΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΫΛβΛΫΛβΗεΖηΛα±ΩΡ¬ΛœΑΆΆξΦγΛ§Αλ ΐ≈ΣΛΥΑ≠ΛΛ
Λ»ΛΛΛΠΛοΛ±Λ«ΛβΛ Λ·ΓΔΜ≈ΜωΛρΦθΛ±Λκ¬ΠΛΥΛΖΛΤΛβΓΔ
±σΈΗΛΖΛΤΟΆΖηΛαΛρΛΖΛ ΛΛΓΔœΟΛΖΙγΛΛΛρΡϋΛαΛΤΛΛ
ΛκΛ»Λ≥ΛμΛ§ΛΔΛκΓΘ
Φ¬ΚίΓΔΘ≈Φ“Λ«ΛβΘ‘Φ“ΡΙΛ§«έΦ÷
Φ¬Χ≥ΛρΟ¥≈ωΛΖΛΤΛΛΛΩΜΰ¬εΛΥΛœΓΔΆΉάΝΛδœΟΛΖΙγΛΛ
ΛρΖΪΛξ ÷ΛΙΛ≥Λ»Λ«ΓΔΗεΖηΛα±ΩΡ¬Χδ¬ξΛ§ΛέΛ»ΛσΛ…
≤ρΨΟΛΒΛλΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΩ Λα ΐΛρΚΤΛ”ΓΔΗΫΚΏΛΈ«έ
Φ÷Ο¥≈ωΦ‘ΛΥΜΊΤ≥ΛΖΛΤΛΛΛ·Λ≥Λ»ΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΠΛΖΛΩ¥…ΆΐΛδΕΒΑιΛΈά°≤ΧΛ§ΓΔΆχ±ΉΈ®ΛΈΗΰΨε
Λ»Λ ΛΟΛΤΛœΗΫΛλΛΤΛ·ΛκΛόΛ«ΛΥΛœΓΔΛΖΛ–ΛιΛ·Μΰ¥÷
Λ§ΛΪΛΪΛκΓΘ
ΛΫΛλΛ«ΛβΓΔά÷ΜζΛΥ¥ΌΛξΓΔ¥…ΆΐΛβ…‘
ΫΫ §Λ«ΓΔΑλΗΪΛΙΛλΛ–ΞάΞαΛΥΗΪΛ®Λκ±ΩΝς≤ώΦ“Λ«ΛβΓΔ
ΞίΞΛΞσΞ»Λρ≤ΓΛΒΛ®ΛΤΓΔΟεΦ¬ΛΥ≤ΰΝ±Λρ≤ΟΛ®ΛΤΛΛΛ·
Λ≥Λ»Λ«ΓΔΟ·ΛβΛ§«ßΛαΛκΈ…ΛΛ≤ώΦ“ΛΥάΗΛόΛλ ―ΛοΛλ
ΛκΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛρΓΔ…°Φ‘ΛœΘ≈Φ“ΛΈΞ±ΓΦΞΙΛρΡΧΛΗΛΤ
≤ΰΛαΛΤ≥Έ«ßΛ«Λ≠ΛΩΛΈΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
|