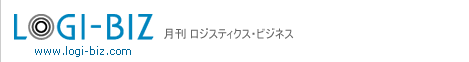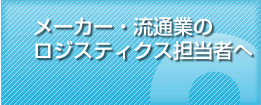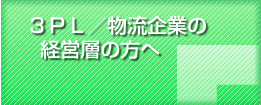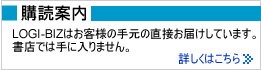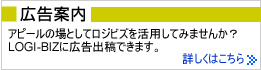|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

NOVEMBER 2010ΓΓΓΓ56
ΓΓΘ
”ΘΟΘΆΛΈΟφ≥Υ≈ΣΛ ΦηΛξΝ»ΛΏΛ»ΛΖΛΤΓΔ≤Λ Τ
Μ‘ΨλΛ«Λœ¬γΦξΞαΓΦΞΪΓΦΛ»¬γΦξΨ°«δΛξΛΥΛηΛκ
Ξ≥ΞιΞήΞλΓΦΞΖΞγΞσΓ Ε®Τ·ΓΥΛ§Ω ΛαΛιΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΤϋΥήΛ«ΛœΞαΓΦΞΪΓΦ®ΔΨ°«δ¥÷ΛΈ
Ε®Τ·Λ§ΛέΛ»ΛσΛ…Ω ΛσΛ«ΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΤϋΥήΛ«Λœ≤Ζ
«δΕ»ΛΈ≤πΚΏΛρΝΑΡσΛ»ΛΖΛΤΓΔΞαΓΦΞΪΓΦ®Δ≤Ζ¥÷
Λ«ΛΈΨπ σœΔΖ»ΛΥΈœ≈άΛ§Ο÷ΛΪΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
≤ΖΖ–Ά≥ΛρΝΣΛσΛάΤϋΥήΛΈΞαΓΦΞΪΓΦ
ΓΓΦΓάΛ¬εΛΈΘ” ΘΟ ΘΆΛœΞαΓΦΞΪΓΦΛ»Ψ°«δΛξΛ»
ΛΈœΔΖ»Λ«ΛΔΛκΛ»ΗάΛοΛλΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦ
Λ§Ψ°«δΛξΛΈΦ¬«δΨπ σΛρΞ«ΞΛΞξΓΦΛ«ΦθΈΈΛΖ
ΛΤΛΫΛλΛράΗΜΚΖΉ≤ηΛΥ≥ηΛΪΛΙΓ÷ΘΟ Θ– ΘΤ Θ“
Γ Collaborative Planning Forecasting and
Replenishment ΓßΕ®Τ·ΛΥΛηΛκΖΉ≤ηΓΔΦϊΆΉΆΫ
¬§ΓΔ δΫΦΓΥΓΉΛ§ΓΔΛΫΛΈ¬ε…Ϋ≈ΣΦξΥΓΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΛ Λ§ΛιΓΔΛ≥ΛλΛόΛ«ΗΪΛΤΛ≠ΛΩΛηΛΠΛΥΓΔ
ΤϋΥήΛ«ΛœΘΟΘ–ΘΤΘ“ΛœΩ ≈ΗΛΖΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΤϋΥή
Λ«ΛΛΛόΦηΛξΝ»ΛόΛλΛΤΛΛΛκΛΈΛœΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΛη
ΛκάνΨε¬ΠΛ»ΛΈœΔΖ»Ε·≤ΫΓΔΛΡΛόΛξΡ¥ΟΘΛ»ΦϊΆΉ
ΖΉ≤ηΛΈΑλΗΒ¥…ΆΐΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΥήΞξΞΒΓΦΞΝΛ«ΛœΓΔ≤ΰΛαΛΤάν≤Φ
Λ»ΛΈΈ°ΡΧœΔΖ»ΛΈΗΫΨθΛΥΛΡΛΛΛΤΓΔΩ©… ΛδΤϋΆ―
Μ®≤Ώ… Λ Λ…ΛΈΘΟΘ–Θ«Γ Consumer Packaged
GoodsΓΥΞαΓΦΞΪΓΦ≥ΤΦ“ΛΥΞΛΞσΞΩΞ”ΞεΓΦΛρΙ‘ΛΟ
ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛΈΖκ≤ΧΓΔΩόΘ±ΛΈΛηΛΠΛ ≥ΤΦοΛΈΧδ
¬ξΛ§…βΛΪΛ”ΨεΛ§ΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΓΓΛΙΛ«ΛΥΈρΜΥΨεΛΈœΟΛ»Λ ΛξΛΡΛΡΛΔΛκΛ§ΓΔΤϋ
ΥήΛΈΘΟΘ–Θ«ΞαΓΦΞΪΓΦΛœΑλΕ廧ΓΜ«·¬εΗε»ΨΛΪΛι
ΕεΓΜ«·¬εΝΑ»ΨΛΥΛΪΛ±ΛΤΓΔΨ°«δ≈ΙΛ»ΛΈ¥÷Λ«ΛΈ
ά―ΕΥ≈ΣΛ Ψπ σœΔΖ»ΛΥΦηΛξΝ»ΛσΛ«ΛΛΛΩΓΘ
ΤΟΛΥ
ΛΫΛλΛΥ«°Ω¥ΛάΛΟΛΩΛΈΛ§ΓΔΞ”ΓΦΞκΞαΓΦΞΪΓΦΛ»Τϋ
Μ®ΞαΓΦΞΪΓΦΛ«ΛΔΛκΓΘ
Ε»Φο ΧΨ°«δΛξΓΔΛΛΛοΛφΛκ
Ξ―Ξ―ΞόΞόΞΙΞ»ΞΔΛρ¬–ΨίΛΥΓΔΨ°«δΛξΗΰΛ±Θ–ΘœΘ”
Γ »Έ«δΜΰ≈άΨπ σΓΥΞΖΞΙΞΤΞύΛρ≥Ϊ»·ΛΖΓΔΘ–ΘœΘ”
Ψπ σΛΈΦΐΫΗΛ»≥ηΆ―ΛρΩόΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛόΛάΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»ΛβΞ―ΞΫΞ≥ΞσΡΧΩ°Λβ…αΒΎ
ΛΖΛΤΛΛΛ ΛΛΜΰ¬εΛάΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΞαΓΦΞΪΓΦΛΈ
±ΡΕ»ΞόΞσΛ§ΓΔ≥ΤΨ°«δ≈ΙΛΈΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛρΞ’
ΞμΞΟΞ‘ΓΦΛ Λ…Λ«≤σΦΐΛΖΓΔΛΫΛΈΞ«ΓΦΞΩ §άœΛΥ¥π
Λ≈Λ·Γ÷«δΛλΛκ≈ΙΚνΛξΓΉΛΈΜΌ±γΛρΙ‘ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΜΌ±γ ΐΥΓΛΈΛ“Λ»ΛΡΛ»ΛΖΛΤΟμΧήΛΒΛλΛΩ
ΛΈΛ§Γ÷ΞΉΞιΞΈΞΑΞιΞύΓ ΟΣ≥δΛξΞΖΞΙΞΤΞύΓΥΓΉΛ«ΛΔΛΟ
ΛΩΓΘ
ΛΒΛιΛΥΛœ«δΛλΙ‘Λ≠ΛΥΙγΛοΛΜΛΤΟΣΞΙΞΎΓΦΞΙ
¬η≤σ
ΞΔΞ”ΓΦΞύΞ≥ΞσΞΒΞκΞΤΞΘΞσΞΑ
Ζ–±ΡάοΈ§ΗΠΒφΞΜΞσΞΩΓΦ
ΦΓάΛ¬εΛρ¬σΛ·
ΤϋΥήΖΩSCM Λ§
≥α≈ΡΛ“ΛΪΛκ
ΤϋΥήΖΩΞ≥ΞιΞήΞλΓΦΞΖΞγΞσΛΈΗΫΨθ
6
Οφ¥÷Έ°ΡΧΛΈ¬ΗΚΏ
Ψ°«δΛξΛ»ΛΈ¥÷ΛΈΞ–ΞΟΞ’ΞΓΓΦΛ»ΛΖΛΤΛΈ¥ϋ¬‘
Ψ°«δPOS Ξ«ΓΦΞΩΛΈΦΝ
≤ώΦ“ΛΥΛηΛΟΛΤΞ’Ξ©ΓΦΞόΞΟΞ»ΛδΞ«ΓΦΞΩΙύΧήΛ§ΑέΛ Λκ
Γ÷ΡξΤΟ §ΈΞΓΉΛ§Λ«Λ≠ΛΤΛΛΛ ΛΛ
…ΗΫύEDI ΛΈάΑ»ςΨθΕΖ
ΞαΓΦΞΪΓΦΓΠ≤Ζ¥÷ΓßΕ»ΦοΛΥΛηΛξΑέΛ Λκ…αΒΎΈ®
Ψ°«δEOSΓßΗΡ Χ¬–±ΰΛΈ…§ΆΉά≠
ΦηΛξΝ»ΛύΛ≥Λ»ΛΥΛηΛκΦηΑζΨρΖοΑ≠≤ΫΛΊΛΈΖϋ«Α
ΦηΛξΝ»ΛΏάηΛΥΆ≠ΆχΛ ΦηΑζΨρΖοΛΊΛΈ ―ΙΙΆΉάΝ
ΕΞΙγΛΪΛιΛΈΤ±ΆΆΛ ΦηΑζΨρΖοΛΊΛΈ ―ΙΙΆΉάΝ
ΩόΘ±ΓΓΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΛΣΛ±ΛκΨ°«δœΔΖ»ΛΊΛΈμ¥μΑ
ΤϋΥήΖΩSCMΛ§ΦΓάΛ¬εΛρ¬σΛ·
57ΓΓΓΓNOVEMBER 2010
Λρ«έ §ΛΖΓΔ»·ΟμΛρΚ«≈§≤ΫΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«ΓΔ¬Ω…―
≈ΌΨ°Ηΐ«έΝςΛράßάΒΛΙΛκΛ»ΛΛΛΟΛΩΦηΛξΝ»ΛΏΛβ≈ω
ΜΰΛΈΖ–Κ―ΜφΨεΛρΤχΛοΛΜΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΛΫΛΈΛηΛΠΛ ΞαΓΦΞΪΓΦ®Γ Ψ°«δ¥÷ΛΈ
œΔΖ»ΛœΛΫΛΈΗεΓΔΫυΓΙΛΥΗε¬ύΛΖΛΤΛΛΛΟΛΩΓΘ
Άΐ
Ά≥ΛΈΑλΛΡΛœΓΔΈΧ»Έ≈ΙΛδΞ≥ΞσΞ”ΞΥΛ Λ…ΛΊΛΈΞΖΞ’
Ξ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
Ν»ΩΞΖΩΨ°«δΕ»Λ«ΛœΓΔΥή…τΛ§≥Τ≈Ι
όΛΈΘ–ΘœΘ”ΞΖΞΙΞΤΞύΛράΑ»ςΛΖΓΔ… ¬ΖΛ®ΛΥΛΡΛΛ
ΛΤΛβΥή…τΛ§ΦηΛξΑΖΛΛΞΔΞΛΞΤΞύΛΈ¬γœ»ΛρΖηΛαΛΤ
ΛΖΛόΛΠΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦ±ΡΕ»Λ§ΗΡΓΙΛΈ≈Ι όΛρΞξΞΤΓΦ
ΞκΞΒΞίΓΦΞ»ΛΙΛκ…§ΆΉά≠Λœ«ωΛλΛκΓΘ
ΓΓΛόΛΩΝ»ΩΞΖΩΨ°«δΕ»ΛΈ¬φΤ§ΛœΓΔΞ―Ξ―ΞόΞόΞΙΞ»
ΞΔΛΈΞΖΞßΞΔΛρΡψ≤ΦΛΒΛΜΛΩΓΘ
Ξ―Ξ―ΞόΞόΞΙΞ»ΞΔΛΈ
¬ΩΛ·Λ§Ξ≥ΞσΞ”ΞΥΛΈΞ’ΞιΞσΞΝΞψΞΛΞΚΛΥΛ ΛκΓΔΛΔ
ΛκΛΛΛœ«―Ε»ΛΙΛκΛ Λ…Λ«ΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛΈΞξΞΤΓΦΞκ
ΞΒΞίΓΦΞ»ΛΈ¬–ΨίΛ»Λ Λκ≈Ι όΩτΦΪ¬ΈΛ§ΗΚΨ·ΛΖΛΤ
ΛΛΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΞαΓΦΞΪΓΦ®Γ Ψ°«δ¥÷ΛΈœΔΖ»Λ§Ηε¬ύΛΖΛΩΛβΛΠ
ΑλΛΡΛΈΆΐΆ≥ΛœΓΔΡψ≤Ν≥ ≤ΫΛΈΩ ≈ΗΛΥΛηΛκΞαΓΦ
ΞΪΓΦΈ°ΡΧά·ΚωΛΈ≈Ψ¥ΙΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΤϋΥήΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛœΡΙΛιΛ·ΓΔΈ°ΡΧΝ¥¬ΈΛρΜΌ«έ
ΛΙΛκΛ»ΛΛΛΠά·ΚωΛρΛ»ΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
≤Ν≥ ά·ΚωΛ«ΛœΓΔ
ΞαΓΦΞΪΓΦΛ§≤ΖΛδΨ°«δΛξΛΈΞόΓΦΞΗΞσΛρΖηΛαΛκΖζ
ΟΆά©ΛρΛ»ΛξΓΔ≤ΖΓΔΨ°«δΛξ≥ΤΟ ≥§ΛΈ»Έ«δ≤Ν≥
ΛρΞ≥ΞσΞ»ΞμΓΦΞκΛΖΛΩΓΘ
ΞΝΞψΞΆΞκά·ΚωΛ«ΛœΓΔΟœ
ΑηΛ¥Λ»ΛΥ≤ΖΛρ¬εΆΐ≈ΙΛόΛΩΛœΤΟΧσ≈ΙΛ»ΛΛΛΠΖΝ
Λ«Ν»ΩΞ≤ΫΛΖΓΔΨ°«δ≈ΙΛΊΛΈ±ΡΕ»ΛΥΛœ≤ΖΛΥ¬εΛοΛΟ
ΛΤΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΡΨάήΫ–ΗΰΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΝ»ΩΞΖΩΨ°«δΕ»ΛΪΛιΛΈΡψ≤Ν≥ ≤ΫΆΉάΝΛΥΛηΛξ
Ξ≥ΞΙΞ»ΡψΗΚΛρ«ςΛιΛλΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΤΛΪΛιΛβΓΔ
ΞαΓΦΞΪΓΦΛΈ¬γ»ΨΛœΓΔ≤ΖΛρΖ–Ά≥ΛΙΛκΤϋΥήΖΩΈ°ΡΧ
ΙΫ¬ΛΛρΦιΛΟΛΩΓΘ
Ξ―Ξ―ΞόΞόΞΙΞ»ΞΔΛΥ¬–ΛΙΛκΞξΞΤΓΦ
ΞκΞΒΞίΓΦΞ»ΛρΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛΥ¬εΛοΛΟΛΤ≤ΖΛ§Ο¥ΛΠ
ΛηΛΠΛΥΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«ΓΔΞ≥ΞΙΞ»ΛρΆόά©ΛΙΛκΛ»ΛΛΛΠ
¬–±ΰΛρΙ‘ΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΗΫΨθΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛœΦΓΛΈΛηΛΠΛ Έ°ΡΧά·ΚωΛρ
ΚΈΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
¬γΦξΝ»ΩΞΖΩΨ°«δΕ»ΛΥΛΡΛΛΛΤΛœ
ΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΡΨάήΓΔΨ°«δΥή…τΛ»ΛΈ¥÷Λ«ΞξΞΤΓΦΞκ
ΞΒΞίΓΦΞ»Λδ±ΡΕ»≥ηΤΑΛρΙ‘ΛΛΓΔΥή…τΛΪΛι»Έ«δ
Ψπ σΛρΤΰΦξΛΙΛκΓΘ
Αλ ΐΓΔ≤ΖΛœΟφΖχΑ ≤ΦΛΈΝ»
ΩΞΖΩΨ°«δΕ»Υή…τΛΊΛΈ±ΡΕ»ΛΣΛηΛ”Ν»ΩΞΖΩΨ°«δ
Ε»ΛΈΗΡ Χ≈Ι όΛδΞ―Ξ―ΞόΞόΞΙΞ»ΞΔΛΊΛΈΞξΞΤΓΦΞκ
ΞΒΞίΓΦΞ»ΓΔ±ΡΕ»ΓΔ ΣΈ°ΓΔΕβΆΜΒΓ«ΫΛρ≤ΧΛΩΛΙΓΘ
ΛΒΛιΛΥ≤ΖΛœΛΫΛλΛιΛΪΛιΤάΛιΛλΛκΜ‘ΨλΛΈΨπ σ
ΛρΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΡσΕΓΛΙΛκΓΘ
ΓΓ¬ΩΛ·ΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΗΫΜΰ≈άΛ«…ΝΛΛΛΤΛΛΛκΛΈΛœΓΔ
Λ≥ΛΈΛηΛΠΛ άΡΦΧΩΩΛ«ΛΔΛκΓΘ
≤ΖΛρΨ°«δΛξΛ»ΛΈ
¥÷ΛΈΫ≈ΆΉΛ Ξ–ΞΟΞ’ΞΓΓΦΛ»¬ΣΛ®ΓΔά―ΕΥ≈ΣΛΥΒΓ«Ϋ
ΛΖΛΤΛβΛιΛΠΛ≥Λ»ΛΥΛηΛξΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΦΪΩ»ΛΈΗζΈ®
≤ΫΛρΩόΛμΛΠΛ»ΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
Θ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩ≥ηΆ―ΛΈΦ¬¬÷
ΓΓΛ ΛΦΤϋΥήΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛœΓΔΨ°«δΛξΛ»ΛΈœΔΖ»Ε·
≤ΫΛρΜ÷ΗΰΛΖΛ ΛΛΛΈΛΪΓΘ
ΛΫΛλΛΥΛœΛΛΛ·ΛΡΛΪΛΈ
ΆΐΆ≥Λ§ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΚΘΛ«Λœ¬γ»ΨΛΈΨ°«δ≈ΙΛ§Θ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛρΦΐΫΗ
ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
Ψ°«δ≈ΙΛ«ΛœΛΫΛλΛρ §άœΛΖΓΔ»·Ομ
ΈΧΛΈΖηΡξΛδΓΔΞ≠ΞψΞσΞΎΓΦΞσ≈υΛΈ»Έ¬ΞΚω ΧΛΈΗζ
≤Χ«ΡΑ°Λ Λ…ΛΥ≥ηΆ―ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛΈΛηΛΠΛ Θ–
ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛœΓΔΆ≠ΫΰΛΔΛκΛΛΛœΧΒΫΰΛ«≤ΖΛδΞαΓΦ
ΞΪΓΦΛΥΛβΡσΕΓΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
Λ ΛΪΛΥΛœΘ–ΘœΘ”
Ξ«ΓΦΞΩΛΈΡσΕΓΛρΨρΖοΛΥ≤Ν≥ ΗρΨΡΛρΙ‘ΛΠΨ°«δΛξ
ΛβΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΛ Λ§ΛιΞαΓΦΞΪΓΦΛœΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛρΫΫ
§ΛΥ≥ηΆ―Λ«Λ≠ΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
≥ΤΦ“ΛΈΘ”ΘΟΘΆ…τΧγ
ΛΊΛΈΞΛΞσΞΩΞ”ΞεΓΦΛ«ΛβΓΔ¬γ»ΨΛœΓ÷±ΡΕ»…τΧγΛδ
ΞόΓΦΞ±ΞΤΞΘΞσΞΑ…τΧγΛ§Θ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛρΤΰΦξΛΖ
ΛΤΛΛΛκΛηΛΠΛάΛ§ΓΔ≤ΩΛΥΜ»Ά―ΛΖΛΤΛΛΛκΛΪΛœ«Ρ
Α°ΛΖΛΤΛΛΛ ΛΛΓΉΛ»ΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΘΟΘ–ΘΤ
Θ“Λ§ΡσΨßΛΒΛλΛΩ≈ωΫιΛΥΝέΡξΛΒΛλΛΤΛΛΛΩΛηΛΠΛ ΓΔ
ΦϊΒκ¥…ΆΐΛΥΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛρ≥ηΆ―ΛΙΛκΛ»ΛΛΛΠ ΐ
ΥΓΛβΛέΛ»ΛσΛ…Λ»ΛιΛλΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΨ°«δΛξΛΪΛιΡσΕΓΛΒΛλΛκΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛœΓΔ≥Τ
Φ“Λ«Ξ’Ξ©ΓΦΞόΞΟΞ»Λ§ΛόΛΝΛόΛΝΛ«ΓΔΛΫΛ≥ΛΥ¥ό
ΛόΛλΛΤΛΛΛκΤβΆΤΛβΑέΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦ
Λ§ΛΫΛλΛιΛρΦϊΆΉΆΫ¬§ΛΥ≥ηΆ―ΛΖΛηΛΠΛ»ΛΙΛλΛ–ΓΔ
Ξ’Ξ©ΓΦΞόΞΟΞ»Λρ¬ΖΛ®ΓΔΤβΆΤΛβ≈ΐΑλΛΙΛκΛηΛΠΛΥ
―¥ΙΛΖΛ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΦξ¥÷ΛρΛΪΛ±ΛΤΞ«ΓΦΞΩΛρ ―¥ΙΛΖΛΩΛ»ΛΖΛΤΛβΓΔ
ΛΒΛιΛΥΤώ¬ξΛ§¬‘ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦΛΈΦϊΆΉΆΫ
¬§ΛΥ…§ΆΉΛ ΛΈΛœΓΔΟ±ΛΥΛ…ΛΈΘ”ΘΥΘ’Λ§≤ΩΗΡ«δ
ΛλΛΩΛΪΛ«ΛœΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛλΛ§Ξ≠ΞψΞσΞΎΓΦΞσΛ««δΛλ
ΛΩΛβΛΈΛ ΛΈΛΪΓΔΟΆΑζΛ≠»Έ«δΛ««δΛλΛΩΛβΛΈΛ
ΛΈΛΪΓΔΛΔΛκΛΛΛœΡξ»÷Λ»ΛΖΛΤ«δΛλΛΩΛβΛΈΛ ΛΈ
ΛΪΛΈΕη §Λ±Λ§ΛΒΛλΛΤΛΛΛ ΛΛΛ»ΓΔΦ¬ΚίΛΥΛœΆχ
Ά―Λ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΨ°«δΛξΛΪΛιΡσΕΓΛΒΛλΛκ
Ξ«ΓΦΞΩΛΈ¬ΩΛ·ΛœΓ÷ΡξΤΟ §ΈΞΓΉΓ Ρξ»÷Λ»ΤΟ«δΛΈ
§ΈΞΓΥΛ§Λ«Λ≠ΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΓΓ≤ΟΛ®ΛΤΦΐΫΗΛ«Λ≠ΛκΞ«ΓΦΞΩΈΧΛΥΛβΗ¬≥ΠΛ§ΛΔΛκΓΘ
NOVEMBER 2010ΓΓΓΓ58
ΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛρΡσΕΓΛΖΛΤΛΛΛκΨ°«δ
ΛξΛœΫυΓΙΛΥΝΐΛ®ΛΤΛœΛΛΛκΛβΛΈΛΈΓΔΛόΛάΞόΓΦΞ±ΞΟ
Ξ»ΛΈ¬γ»ΨΛρΞΪΞ–ΓΦΛ«Λ≠ΛκΛέΛ…Λ«ΛœΛ ΛΛΓΘ
άΗΜΚ
ΖΉ≤ηΛΥ»Ω±«ΛΒΛΜΛκΛΥΛœ…‘ΫΫ §ΛάΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛηΛΠΛ Λ≥Λ»ΛΪΛιΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛΈΘ”ΘΟΘΆ…τ
ΧγΛΥΛΣΛ±ΛκΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛΈΜ»ΛΛΤΜΛœΗ¬ΡξΛΒΛλ
ΛκΓΘ
Θ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛΈΆχΆ―ΥΓΛ»ΛΖΛΤΚΘ≤σΛΈΡ¥ΚΚ
Λ«»φ≥”≈Σ¬ΩΛ·ΒσΛ§ΛΟΛΤΛΛΛΩΛΈΛœΓΔΓ÷Ξ≥ΞσΞ”ΞΥ
ΛΈΟΣΆνΛΝΛΈ«ΡΑ°ΓΉΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΛόΛΩΓ÷ΩΖΨΠ…
ΛΈΫι¥ϋ»Έ«δΈΧΛρΚΘΗεΛΈάΗΜΚΈΧΖηΡξΛΈΜ≤ΙΆΛΥ
ΛΖΛΤΛΛΛκΓΉΛ»ΛΛΛΠ¥κΕ»ΛβΛΔΛΟΛΩΛ§ΓΔΞαΓΦΞΪΓΦ
®Γ Ψ°«δ¥÷ΛΈΨπ σœΔΖ»ΛΥΛηΛκΞαΞξΞΟΞ»ΛœΓΔΚΘ
ΛΈΛ»Λ≥ΛμΛΫΛΈΞλΞΌΞκΛΥΈ±ΛόΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Ε»ΦοΛΥΛηΛΟΛΤΨπ σœΔΖ»ΞλΞΌΞκΛΥ≥ ΚΙ
ΓΓΛΫΛλΛ«ΛœΞαΓΦΞΪΓΦ®Γ ≤Ζ¥÷ΛΈΨπ σœΔΖ»ΛœΗΫ
ΚΏΓΔΛ…ΛΈΛηΛΠΛ ΞλΞΌΞκΛΥΛΔΛκΛΈΛ«ΛΔΛμΛΠΛΪΓΘ
ΓΓΘ
ΟΘ–Θ«Ε»≥ΠΛΥΛΣΛ±ΛκΞαΓΦΞΪΓΦΓΠ≤Ζ¥÷ΛΈΘ≈ΘΡ
Θ…ΛΥΛœΗΫΚΏΓΔ≤ΟΙ©Ω©… ΛΈΓ÷Ξ’ΞΓΞΛΞΆΞΟλà ΘΤ
Θ…ΘΈΘ≈Θ‘ΓΥΓΉΓΔ≤έΜ“ΛΈΓ÷Θε®ΓΛΣ≤έΜ“ΞΆΞΟλùΓΔ
ΤϋΜ®ΛΈΓ÷ΞΉΞιΞΆΞΟλà ȖΘΧΘΝΘΈΘ≈Θ‘ΓΥΓΉΛ»ΛΛ
ΛΠΜΑΦοΈύΛΈΘ÷ΘΝΘΈΛ§¬ΗΚΏΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛλΛΨ
Λλ…αΒΎΨθΕΖΛœΑέΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓ ΩόΘ≤ΓΥΓΘ
ΓΓ≤ΟΙ©Ω©… Ε»≥ΠΛ«Λœ»φ≥”≈ΣΝα¥ϋΛΥΓΔΞΪΞΤ
Ξ¥ΞξΓΦΛ¥Λ»ΛΥΕ»≥ΠΘ÷ ΘΝ ΘΈΛ§ΙΫΟέΛΒΛλΛΩΓΘ
ΑλΕ廧œΜ«·ΛΥΈδ≈ύΩ©… Ε»≥ΠΆ―ΛΈΘ÷ΘΝΘΈΛ§≤‘
Τ·ΓΘ
ΛΫΛΈΆβ«·ΛΥΞ…ΞιΞΛΩ©… Λ§ΛΫΛλΛΥ≤ΟΛοΛξΓΔ
ΛΒΛιΛΥΤσΓΜΓΜΤσ«·ΛΥΛœ ΧΛΥΙΫΟέΛΒΛλΛΤΛΛΛΩ
ΦρΈύΘ÷ΘΝΘΈΛρ≈ΐΙγΓΔΗΫΚΏΛΈΞ’ΞΓΞΛΞΆΞΟΞ»Λ»
Λ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓ¬–ΨίΈΈΑηΛœΙ≠Λ§ΛΟΛΤΛ≠ΛΩΛ§ΓΔΛΫΛΈ…αΒΎΨθ
ΕΖΛœΚΘΛΈΛ»Λ≥ΛμΓΔΛΔΛόΛξΙβΛΛΛ»ΛœΛΛΛ®Λ ΛΛΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦΓΔ≤ΖΛΈΝ– ΐΛ»ΛβΓΔ¬γΦξΛœ≤ΟΤΰΛΖΛΤΛΛ
ΛκΛ§ΓΔΟφΖχΑ ≤ΦΛΈ≤ΟΤΰΈ®Λ§ΡψΛΛΓΘ
ΓΓΤϋ«έ… Λ Λ…ΛΈΨ°Β§ΧœΞαΓΦΞΪΓΦΛœΕαΈΌΛΈΟœΨλ
ΞΙΓΦΞ―ΓΦΛδΨ°«δ≈ΙΛ»ΛΈΦηΑζΛ§ΟφΩ¥Λ«ΛΔΛκΛΩΛαΓΔ
ΛβΛ»ΛβΛ»Ε»≥ΠΘ÷ΘΝΘΈΛρΆχΆ―ΛΙΛκ…§ΆΉά≠ΛΥΥ≥
ΛΖΛΛΓΘ
ΕαΈΌΛΈΑϊΩ©≈ΙΛρ¬–ΨίΛ»ΛΖΛΤΛΛΛκΕ»Χ≥
Ά―≤ΖΛβΛόΛΩΓΔΦηΑζΈΧΛ§Ψ·Λ ΛΛΛΩΛαΛΥΨπ σ≤Ϋ
≈ξΜώΛΥΛœΒΎΛ”ΙχΛάΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥ¬γΦξΞαΓΦΞΪΓΦ
Λ§Ξ’ΞΓΞΛΞΆΞΟΞ»Ζ–Ά≥Λ«ΦθΟμΛ«Λ≠ΛκΦηΑζάηΛΈΩτ
ΛœΗ¬ΛιΛλΛΤΛ·ΛκΓΘ
Ι‘ΩτΛδΫ–≤ΌΈΧΞΌΓΦΞΙΛ«ΛΏΛΤ
ΛβΓΔΟφΡχ≈ΌΛΈ≥δΙγΛΥΛ»Λ…ΛόΛΟΛΤΛΛΛκΛΈΛ§ΗΫ
ΨθΛάΓΘ
ΓΓΑλ ΐΓΔΤϋΆ―Μ®≤ΏΕ»≥ΠΛΈΘ÷ΘΝΘΈΛ«ΛΔΛκΞΉΞι
ΞΆΞΟΞ»ΛœΓΔΚΘΛδΛέΛ»ΛσΛ…ΛΈΤϋΜ®ΞαΓΦΞΪΓΦΓΠΤϋ
Μ®≤ΖΛΥΆχΆ―ΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΞΉΞιΞΆΞΟΞ»ΛœΞιΞΛΞΣΞσΛρΛœΛΗΛαΛ»ΛΙΛκ¬γΦξ
ΞαΓΦΞΪΓΦΕεΦ“Λ§Ϋ–ΜώΛΖΛΤ»§Ηό«·ΛΥΝœΕ»ΓΔΆβ
»§œΜ«·ΛΪΛιΞΒΓΦΞ”ΞΙΛρ≥ΪΜœΛΖΛΩΓΘ
≤ΖΞΝΞψΞΆΞκ
ΛρΖχΜΐΛΙΛκΞαΓΦΞΪΓΦΛΈœΔΙγΝ»ΩΞΛ»ΛΖΛΤ…αΒΎΛΥ
«°Ω¥ΛΥΦηΛξΝ»ΛσΛάΛ≥Λ»ΓΔΛΫΛΖΛΤΕεΓΜ«·¬εΟφ
»ΉΛΪΛιΜœΛόΛΟΛΩΤϋΜ®≤ΖΛΈΚΤ ‘ΛΥΛηΛκ¥κΕ»Β§
Χœ≥»¬γΛ§…αΒΎΛΈΡ…ΛΛ…ςΛ»Λ ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΜ‘ΨλΛΈΞΪΞ–ΓΦΈ®Λ§ΙβΛΛΛ≥Λ»ΛΪΛιΓΔΞΉΞιΞΆΞΟ
Ξ»Λ«Λœ≤ΖΛΈΫ–≤ΌΦ¬ά”ΛρΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΡσΕΓΛΙΛκΛ
Λ…ΓΔΦϊΒκ¥…ΆΐΛΥ≥ηΆ―Λ«Λ≠ΛκΞ«ΓΦΞΩΗρ¥ΙΛρΙ‘ΛΟ
ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛλΛρΦϊΆΉΖΉ≤ηΚωΡξΜΰΛΥΜ≤ΙΆΛΥΛΖ
ΛΤΛΛΛκΞαΓΦΞΪΓΦΛβΛΔΛκΓΘ
ΓΓΘ
ε®ΓΛΣ≤έΜ“ΞΆΞΟΞ»ΛœΓΔΞ’ΞΓΞΛΞΆΞΟΞ»Λ»ΞΉΞι
ΞΆΞΟΞ»ΛΈΟφ¥÷≈ΣΛ …αΒΎΞλΞΌΞκΛΥΛΔΛκΓΘ
≤έΜ“Ε»
≥ΠΛ«Λβ»Έ«δΞΝΞψΞΆΞκΛΈΦγΈœΛœΞ―Ξ―ΞόΞόΞΙΞ»ΞΔ
ΛΪΛιΞ≥ΞσΞ”ΞΥΛδΞΙΓΦΞ―ΓΦΛ Λ…ΛΥΑήΛΟΛΤΛ≠ΛΤΛΣ
Ωό2ΓΓCPG Ε»≥ΠΈ°ΡΧVAN ΛΈΦοΈύΛ»ΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤ΫΈ®
Ω©… ΞαΓΦΞΪΓΦ≤έΜ“ΞαΓΦΞΪΓΦΤϋΜ®ΞαΓΦΞΪΓΦ
Ω©… ≤Ζ≤έΜ“≤ΖΤϋΜ®≤Ζ
ΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤ΫΈ®
e- ΛΣ≤έΜ“ΛΆΛΟΛ» ¬γΦξΈΧ»Έ
Γ ≤έΜ“ VANΓΥ
PLANET
Γ ΤϋΜ® VANΓΥ
FINET
Γ Ω©… VANΓΥ
EOS
Ψ°Οφ¬γ
ΤϋΥήΖΩSCMΛ§ΦΓάΛ¬εΛρ¬σΛ·
59ΓΓΓΓNOVEMBER 2010
ΛξΓΔΛΫΛλΛΥ»ΦΛΛ≤έΜ“≤ΖΛΈΚΤ ‘Λ§Ω ΛσΛ«ΛΛΛκΓΘ
ΛόΛΩΝ»ΩΞΖΩΨ°«δΕ»ΛΊΛΈ»Έ«δΛ«ΛœΓΔΩ©… ≤ΖΛδ
ΦρΈύ≤ΖΛ§Ξ’ΞΓΞΛΞΆΞΟΞ»Ζ–Ά≥Λ«≤έΜ“ΞαΓΦΞΪΓΦΛΥ
Ομ ΗΛΖΛΤΛΛΛκΞ±ΓΦΞΙΛβ¬ΩΛΛΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΛηΛΠΛ Λ≥Λ»ΛΪΛιΓΔΝ¥»Χ≈ΣΛ ΖΙΗΰΛ»ΛΖΛΤΓΔ
≤ΟΙ©Ω©… ΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΛΣΛ±ΛκΦθΟμΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤Ϋ
»φΈ®ΛœΓΔΤϋΜ®ΞαΓΦΞΪΓΦΛηΛξΛβΡψΛΛΓΘ
ΓΓΛΩΛάΛΖΓΔΤ±ΑλΕ»ΦοΛ«ΛΔΛΟΛΤΛβΞαΓΦΞΪΓΦΛΥ
ΛηΛΟΛΤΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤Ϋ»φΈ®ΛœΛΪΛ ΛξΑέΛ ΛκΓΘ
≤Ο
Ι©Ω©… ΞαΓΦΞΪΓΦΛ«ΛβΓΔ¬γΦξ≤ΖΟφΩ¥ΛΈΦηΑζΛ«ΛΔ
ΛλΛ–ΓΔΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤ΫΈ®ΛœΙβΛ·Λ ΛκΓΘ
ΛόΛΩ¬γΦξ
Ψ°«δΛξΛ»ΡΨάήΦηΑζΛρΙ‘ΛΟΛΤΛΛΛκΨλΙγΛβΓΔΨ°
«δΛξΛΈΘ≈ΘœΘ”Λ»ΡΨάήάή¬≥ΛρΙ‘ΛΠΛΩΛαΓΔΛδΛœ
ΛξΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤Ϋ»φΈ®ΛœΙβΛ·Λ ΛκΓΘ
»Έœ©ΛΈΝΣ¬ρ
Λ§ΦθΟμΞΣΞσΞιΞΛΞσ≤Ϋ»φΈ®Λ»Χ©άήΛΥ¥ΊΖΗΛΖΛΤΛΛ
ΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΚΘΗεΓΔΤϋΥήΛΥΛΣΛΛΛΤΘΟΘ–Θ«ΞαΓΦΞΪΓΦΛœΓΔΨ°
«δΛξΛΈΘ–ΘœΘ”Ξ«ΓΦΞΩΛΈ¬εΛοΛξΛΥ≤Ζ«δΕ»ΛΈΫ–≤Ό
Φ¬ά”Ξ«ΓΦΞΩΛρΦϊΆΉΆΫ¬§ΛΥ≥ηΆ―ΛΙΛκΛηΛΠΛΥΛ Λκ
ΛΈΛ«ΛΔΛμΛΠΛΪΓΘ
ΛΫΛΈ≈ζΛ®ΛœΛόΛάΗΪΛ®ΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΛΩΛάΛΖΓΔΛΫΛΈ ΐΗΰΛΥΚ«ΛβΩ ΛΏΛδΛΙΛΛΛΈΛ§ΞΉΞι
ΞΆΞΟΞ»ΛρΜ»Ά―ΛΖΛΤΛΛΛκΤϋΜ®ΞαΓΦΞΪΓΦΛ«ΛΔΛκΛΈ
ΛœΧάΛιΛΪΛάΓΘ
ΛΫΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΞ’ΞΓΞΛΞΆΞΟΞ»ΛΣΛη
Λ”Θε®ΓΛΣ≤έΜ“ΛΆΛΟΛ»ΛρΆχΆ―ΛΖΛΤΛΛΛκ≤ΟΙ©Ω©…
Ε»≥ΠΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΛΫΛΠΛΖΛΩΖΝΛρΛ»ΛκΛηΛΠΛΥΛ
ΛκΛΈΛœΓΔΗΫΨθΛΪΛιΛΙΛκΛ»≈ωΧΧάηΛΈΛ≥Λ»ΛΥΛ
ΛκΛ»ΜΉΛοΛλΛκΓΘ
ΓΓΤϋΥήΛ«ΞαΓΦΞΪΓΦΛ»Ψ°«δ¥÷ΛΈœΔΖ»Λ§Ω ΛόΛ ΛΛ
ΗΕΑχΛœΓΔΘ≈ΘΡΘ…ΛΈάΑ»ςΨθΕΖΛ–ΛΪΛξΛ«ΛœΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΑ ΝΑΛΥΛβΜΊ≈ΠΛΖΛΩΛηΛΠΛΥΓΔΤϋΥήΛΈΨ°«δΜ‘
ΨλΛœ≤Λ ΤΛΈΛηΛΠΛΥ¬γΦξΩτΦ“ΛΥΛηΛΟΛΤ≤…άξ≤Ϋ
ΛΒΛλΛΤΛΛΛκΛοΛ±Λ«ΛœΛ ΛΛΓΘ
¬γΦξΛΈΝ»ΩΞΖΩΨ°
«δΛ«ΛβΜ‘ΨλΞΖΞßΞΔΛœΗ¬ΛιΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛα
ΛΥΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΤΟΡξΛΈΨ°«δΛξΛ»œΔΖ»ΛΖΛΤΛβΓΔΛΫ
Λ≥ΛΪΛιΤάΛιΛλΛκΞαΞξΞΟΞ»ΛœΗ¬Ρξ≈ΣΛάΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛΥ≤ΟΛ®ΓΔΤΟΡξΛΈΨ°«δΛξΛ»ΛΈœΔΖ»Λ§¬Ψ
ΛΈΨ°«δΛξΛ»ΛΈΦηΑζΛΥΑ≠±ΤΕΝΛρΆΩΛ®ΛκΕ≤ΛλΛ§
ΛΔΛκΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦΛ»ΛΈΨπ σœΔΖ»ΛΈΕ·≤ΫΛΥΙγΑ’ΛΖ
ΛΩΨ°«δΛξΛœΓΔ≈ωΝ≥Λ Λ§ΛιΛΫΛΈΗΪ ÷ΛξΛρ¥ϋ¬‘
ΛΙΛκΓΘ
ΞαΓΦΞΪΓΦΛΥ¬–ΛΖΛΤΓΔΫΨΆηΛηΛξΛβΆ≠ΆχΛ
ΦηΑζΨρΖοΛρΒαΛαΛΤΛΛΛ·ΛκΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΆΉΥΨΛΥ±ΰΛΗΛΤΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΦηΑζΨρΖοΛρΆΞ
ΕχΛΖΛΤΛΖΛόΛΠΛ»ΓΔΨπ σœΔΖ»ΛΖΛΤΛΛΛ ΛΛΨ°«δ
ΛξΛΪΛιΛβΤ±≈υΛΈΨρΖοΛΊΛΈ ―ΙΙΛρΆΉάΝΛΒΛλΛκ
≤Ρ«Ϋά≠Λ§ΛΔΛκΓΘ
ΛΫΛλΛρΦθΛ±ΤΰΛλΛ ΛΛΨλΙγΛΥΛœΓΔ
ΦηΑζΟφΜΏΛ Λ…ΛΈΕ·Ι‘ΦξΟ ΛρΛΝΛιΛΡΛΪΛΜΛΤΛ·
ΛκΨ°«δΛξΛβΛΔΛκΛάΛμΛΠΓΘ
ΛΫΛΠΛΖΛΩΞξΞΙΞ·Λ§ΛΔ
ΛκΛΩΛαΛΥΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛΈ¬ΩΛ·ΛœΨ°«δΛξΛΈΨπ σœΔ
Ζ»ΛΥΨΟΕΥ≈ΣΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΜΊΡξΝ“ΗΥΛΈΦ¬¬÷Λ»ΛΫΛΈΕΓΒκ¥…Άΐ
ΓΓΚΘ≤σΛΈΡ¥ΚΚΛ«ΛœΓ÷ΜΊΡξΝ“ΗΥΓΉΛΥΛΡΛΛΛΤΛβΓΔ
ΛΫΛΈΦ¬¬÷ΛρΡ¥ΛΌΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΜΊΡξΝ“ΗΥΛ»ΛœΓΔΝ»ΩΞΖΩΨ°«δΕ»Λδ≥ΑΩ©ΜΚ
Ε»Λ Λ…Λ§Ρ¥ΟΘάηΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΕΓΒκ¥…ΆΐΛρ
Α―¬ςΛΖΛΤΛΛΛκΝ“ΗΥΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛκΓΘ
Γ÷Θ÷ΘΆΘ…
Γ Vendor Managed Inventory Γß ΞΌΞσΞάΓΦ
ΦγΤ≥ΖΩΚΏΗΥ¥…ΆΐΓΥΓΉΓΔΓ÷ΘΟΘ“Θ–Γ Continuous
Replenishment Program ΓßœΔ¬≥ΦΪΤΑ δΫΦ ΐ
ΦΑΓΥΓΉΛ»ΛΛΛΟΛΩ¥κΕ»¥÷Θ”ΘΟΘΆΛΈΙ≠Λ§ΛξΛΥ»ΦΛΛΓΔ
ΜΊΡξΝ“ΗΥΛρΜ»Ά―ΛΙΛκΞ±ΓΦΞΙΛœΝΐΛ®ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΜΊΡξΝ“ΗΥΛΊΛΈ¬–±ΰΜ―άΣΛœΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΛηΛΟΛΤ
¬γΛ≠Λ·ΑέΛ ΛκΓΘ
Γ÷ΛόΛΟΛΩΛ·Ι‘ΛΟΛΤΛΛΛ ΛΛΓΉΛ»
ΛΛΛΠΞαΓΦΞΪΓΦΛ§ΛΔΛκΑλ ΐΛ«ΓΔΝ¥ΙώΑλΓΜΓΜΞΪΫξ
Α ΨεΛ«¬–±ΰΛΖΛΤΛΛΛκΛ»ΛΛΛΠΞαΓΦΞΪΓΦΛβ ΘΩτΛΔΛΟ
ΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔ¬ΩΛ·ΛΈΜΊΡξΝ“ΗΥΛρ±ΩΆ―ΛΖΛΤΛΛ
ΛκΞαΓΦΞΪΓΦΛ«ΛβΓΔΛΫΛλΛρΩ ΛσΛ«ΦθΛ±ΤΰΛλΛΤΛΛ
ΛκΛοΛ±Λ«ΛœΛ ΛΛΓΘ
≥ΤΦ“Λ»ΛβΗήΒ“ΛΪΛιΛΈΆΉάΝ
ΛρΓ÷ΦθΛ±ΤΰΛλΛΕΛκΛρΤάΛ ΛΛΓΉΛ»ΛΛΛΠΨΟΕΥ≈Σ
Λ ΆΐΆ≥ΛΪΛιΜΊΡξΝ“ΗΥΛΥ¬–±ΰΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΜΊΡξΝ“ΗΥΛΥΒαΛαΛιΛλΛκΒΓ«ΫΛœΦηΑζάηΛΥΛηΛΟ
ΛΤΆΆΓΙΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΚΏΗΥΛΈΫξΆ≠ΗΔΛœΞαΓΦΞΪΓΦΛΥΛΔ
ΛκΛΈΛΪΓΔΛΫΛλΛ»Λβ»Έ«δάηΛΪΓΘ
ί¥…ΞΔΞΛΞΤΞύΩτ
Λœ¬ΩΛΛΛΪΨ·Λ ΛΛΛΪΓΘ
Ϋ–≤ΌΛΈ ―ΤΑΛœΛ…ΛΈΞλΞΌΞκ
ΛΪΓΔΛ»ΛΛΛΟΛΩΛηΛΠΛΥΨρΖοΛ§ΚΌΛΪΛ·ΑέΛ ΛκΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛΩΛα±ΩΆ―¬Έά©ΛΥΛβΞ–ΞξΞ®ΓΦΞΖΞγΞσΛ§ΛΔ
ΛκΓΘ
Γ÷Ξ≥ΞσΞ”ΞΥΛΈΞΜΞσΞΩΓΦΛœΘ”ΘΟΘΆ…τΧγΛ§¥…
ΆΐΛΖΓΔ¬ΨΛœΕΓΒκ¥…Άΐ…τΧγΛ§¥…ΆΐΛΖΛΤΛΛΛκΓΉΓΔ
Γ÷¬γΦξΈΧ»ΈΑλΦ“ΛΈΛΏΘ”ΘΟΘΆ…τΧγΛ§¥…ΆΐΓΔ¬ΨΛœ
±ΡΕ»ΓΉΓ÷ΛΙΛΌΛΤΟ¥≈ω±ΡΕ»Λ§ΖηΡξΓΉΛ»ΛΛΛΠΛηΛΠΛΥΓΔ
ΕΓΒκΈΧΛΈΖηΡξΛΥΛΡΛΛΛΤΛβ ΘΩτΛΈ ΐΥΓΛ«¬–±ΰ
ΛΖΛΤΛΛΛκΛ≥Λ»Λ§¬ΩΛΛΓΘ
ΓΓΑλ»Χ≈ΣΛ ΖΙΗΰΛ»ΛΖΛΤΛœΓΔ¬–ΨίΛ»Λ ΛκΜΊΡξ
Ν“ΗΥΛΈΒ§ΧœΓΠΫ–≤Ό ―ΤΑΛ»Λβ¬γΛ≠ΛΛΨλΙγΛœΘ”
ΘΟΘΆ…τΧγΛ§¥…ΆΐΛΖΓΔΦΪΦ“Ξ«ΞίΛ»Τ±ΆΆΛΈ ΐΥΓ
Λ«ΕΓΒκΈΧΛρΖηΡξΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΫΛΈ¬ΨΛΈΜΊΡξΝ“
ΗΥΛΈΕΓΒκΈΧΖηΡξΛœΓΔ±ΡΕ»Λ§Ι‘ΛΠΞ±ΓΦΞΙΛ§¬Ω
ΛΛΓΘ
±ΡΕ»ΛΈ ΐΛ§ΛΫΛΈΗήΒ“ΛΈ»Έ«δΨθΕΖΛΥΨήΛΖΛ·ΓΔ
ΛόΛΩ¥…ΆΐΞΔΞΛΞΤΞύΩτΛ§Ψ·Λ ΛΛΛΩΛαΓΔ≈Σ≥ΈΛΥΕΓ
NOVEMBER 2010ΓΓΓΓ60
ΓΓΤϋΆ―Μ®≤Ώ… ΛœΓΔΨΠ… ΛΈΞξΞΥΞεΓΦΞΔΞκΜΰΛΥΛβ
Θ ΘΝΘΈΞ≥ΓΦΞ…Λœ ―Λ®ΛΚΓΔΒλΨΠ… ΛΈΚΏΗΥΛ§Λ Λ·
Λ ΛξΦΓ¬ηΓΔΩΖΨΠ… Λρ«Φ… ΛΙΛκΛ»ΛΛΛΠΞ―ΞΩΓΦΞσ
Λ§¬γ»ΨΛ«ΛΔΛκΛΩΛαΓΔΈ…… ÷… ΛœΛέΛ»ΛσΛ…»·
άΗΛΖΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΟΣΆνΛΝΓ «δΛλΙ‘Λ≠Λ§Α≠ΛΛΛβ
ΛΈΛρΡΡΈσΟΣΛΪΛιΛœΛΚΛΙΓΥΜΰΛβΓΔΨ°«δΛξΛ§ΗΪ
άΎΛξ»Έ«δΛ««δΛξάΎΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛόΛΩΩ©… Λ«ΛβΦρ
ΈύΛΈΨλΙγΛœΓΔΦρά«Λ§ΛΔΛκΛΩΛαΓΔΞαΓΦΞΪΓΦΛœΈ…
… ÷… ΛρΦθΛ±…’Λ±ΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΛάΛ§≤ΟΙ©Ω©… Λ«ΛœΓΔΨΠ… άΎΛξ¬ΊΛ®ΛδΟΣΆν
ΛΝΜΰΛΥΈ…… Λ§ ÷… ΛΒΛλΛΤΛ·ΛκΓΘ
ΚΘ≤σΡ¥ΚΚΛΖ
ΛΩ≤ΟΙ©Ω©… ΞαΓΦΞΪΓΦΝ¥ΑλΜΆΦ“ΟφΓΔ ÷… ΛρΦθΛ±
…’Λ±Λ ΛΛΛ»≈ζΛ®ΛΩΛΈΛœΑλΦ“ΛΈΛΏΛ«ΓΔΜΡΛξΛœ
ΛΙΛΌΛΤΈ…… ÷… ΛρΦθΛ±…’Λ±ΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΖΛΤΨ°«δΛξΛΪΛιΧαΛΟΛΤΛ≠ΛΩΨΠ… ΛœΓΔΛΫ
ΛΈΜΰ≈άΛ«Ν“ΗΥΛΪΛιΫ–≤ΌΛΖΛΤΛΛΛκΛβΛΈΛΥ»φΛΌ
ΛΤΤϋ…’Λ§Η≈Λ·ΓΔΨ°«δΛξΛΥΛηΛΟΛΤΡξΛαΛιΛλΛΤΛΛ
ΛκΨόΧΘ¥ϋΗ¬ΞκΓΦΞκΛΥΡώΩ®ΛΖΛΤΛΖΛόΛΠΛΩΛαΚΤΫ–
≤ΌΛ§Λ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
«―¥ΰΛΥ≤σΛιΛΕΛκΛρΤάΛ ΛΛΛΈ
Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛΔΛκΩ©… ΞαΓΦΞΪΓΦΛ«ΛœΓΔΓ÷«―¥ΰΛΈΛΠΛΝœΜ≥δ
ΛœΈ°ΡΧΛΪΛιΛΈ ÷… Λ«ΓΔΨΠ… ≤ΰ«―ΛδΟΣΆνΛΝΛΥ
»ΦΛΠΛβΛΈΛ«ΛΔΛκΓΉΛ»ΛΛΛΠœΟΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛΈ
ΛηΛΠΛ ÷… ΛρΒώΛαΛ ΛΛΛΈΛΪΛΩΛΚΛΆΛΩΛ»Λ≥ΛμΓΔ
Γ÷Ξ≥ΞσΞ”ΞΥΛ«ΟΣΆνΛΝΛΖΛΩΛβΛΈΛœ≈Ι όΛΈΞλΞΗΛρ
ΡΧΛιΛ ΛΛΛΈΛ«ΓΔ ÷… ΛρΦθΛ±ΛΕΛκΛρΤάΛ ΛΛΓΉ
Λ»≈ζΛ®ΛΩΞαΓΦΞΪΓΦΛβΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛηΛΠΛ Έ…… ÷… ΓΔΛόΛΩ«Φ… ΜΰΛΈΨόΧΘ
¥ϋΗ¬ΞκΓΦΞκΛΥΛηΛΟΛΤ»·άΗΛΙΛκΓ÷Τϋ…’Β’≈ΨΛΥΛη
ΛξΫ–≤ΌΛ«Λ≠Λ Λ·Λ ΛΟΛΩΛβΛΈΓΉΛ§ΓΔΝ“ΗΥΛΈΟφ
Λ«ΤΑΛΪΛ ΛΛΛόΛόΫη §¥ϋΗ¬ΛρΖόΛ®ΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΛβ
ΛΈΛ»ΕΠΛΥΓΔ«―¥ΰΫη §ΛΥ≤σΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓ≥ΤΦ“ΛΈΆ≠≤ΝΨΎΖτ σΙπΫώΛΪΛιΛΙΛκΛ»ΓΔΟΣ≤Ζ
ΜώΜΚΫη §¬ΜΛΈ«δΨεΗΕ≤ΝΛΥ¬–ΛΙΛκ»φΈ®ΛœΓΔΗΕ
ΚύΈΝΛδΜ≈≥ί… Λβ¥όΛαΛΤΓΔΨ·Λ ΛΛ¥κΕ»Λ«ΓΜΓΠ
ΓΜΑλΓσΓΔ¬ΩΛΛ¥κΕ»Λ«ΛœΑλΓσΡχ≈ΌΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓ«―¥ΰΫη §ΛΈΚοΗΚΛœ¥ΡΕ≠Χδ¬ξΛΈ¥―≈άΛΪΛιΛβ
Ϋ≈ΆΉΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥΛœΓΔΈ°ΡΧΝ¥¬ΈΛ«ΛΈ
ΨΠ¥ΖΙ‘ΗΪΡΨΛΖΛ§…§ΆΉΛ«ΛΔΛκΓΘ
Ψ°«δΛξΛœΈ……
÷… ΛδΤϋ…’Β’≈ΨΕΊΜΏΞκΓΦΞκΛ§ΟœΒε¥ΡΕ≠ΛΥ±Τ
ΕΝΛρΒΎΛήΛΖΛΤΛΛΛκΛΈΛάΛ»ΛΛΛΠ«ßΦ±ΛρΜΐΛΡΛΌ
Λ≠Λ«ΛΔΛμΛΠΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΑλ ΐΓΔ ÷… ΛρΦθΛ±…’Λ±Λ ΛΛΛ»ΛΛΛΠΘΈ
Θ¬Γ Ξ ΞΖΞγΞ ΞκΞ÷ΞιΞσΞ…ΓΥΞαΓΦΞΪΓΦΛβΦ¬ΚίΛΥ
¬ΗΚΏΛΙΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΛΪΛιΓΔ¬ΨΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛβ ÷…
ΚοΗΚΛΊΛΈΤ·Λ≠ΛΪΛ±ΛΥΛβΛΟΛ»ΥήΙχΛρΤΰΛλΛκΛΌΛ≠
Λ«ΛΔΛκΛ»ΛΛΛ®ΛηΛΠΓΘ
ΒκΈΧΛρΖηΡξΛ«Λ≠ΛκΛ»ΛΛΛΠΛΈΛ§ΛΫΛΈΆΐΆ≥Λ«ΛΔΛκΓΘ
Έ…… ÷… Λ»«―¥ΰΧδ¬ξ
ΓΓΨ°«δΛξΛΪΛιΛΈ ÷… ΛβΓΔΤϋΥήΖΩΨΠ¥ΖΙ‘ΛΈ≤ί
¬ξΛΈΑλΛΡΛ«ΛΔΛκΓΘ
Λ»ΛξΛοΛ±ΗΫΚΏΓΔΧδ¬ξΛ»Λ ΛΟ
ΛΤΛΛΛκΛΈΛœΓΔΓ÷ΟΣ¬ΊΛ®Γ Β®άαΥηΛΈΨΠ… ΤΰΛλ¬Ί
Λ®ΓΥΓΉΛΥ»ΦΛΠ ÷… Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΟΣ¬ΊΛ®Μΰ≈άΛ««δΛλ
ΜΡΛΟΛΤΛΛΛΩΚΏΗΥΛ§ΓΔΨΠ… ΛΈ… ΦΝΛδ¥ϋΗ¬ΛΥΧδ
¬ξΛ§Λ ΛΛΛΥΛβΙ¥ΛοΛιΛΚ ÷… ΛΒΛλΛΤΛ·ΛκΓΘ
ΛΛ
ΛοΛφΛκéΔΈ…… ÷… éΘΛ«ΛΔΛκΓ ΩόΘ≥ΓΥΓΘ
ΓΓ≈ωΡ¥ΚΚΛ«≤ΰΛαΛΤΛΫΛΈΦ¬¬÷ΛρΡ¥ΛΌΛΩΛ»Λ≥ΛμΓΔ
ΛΛΛ·ΛΡΛΪΛΈΕΫΧΘΩΦΛΛΜωΦ¬Λ§»ΫΧάΛΖΛΩΓΘ
÷…
Χδ¬ξΛΥ«ΚΛόΛΒΛλΛΤΛΛΛκΛΈΛœΓΔΘΟΘ–Θ«Ε»≥ΠΛΈ
ΟφΛ«ΛβΩ©… ΛάΛ±ΛάΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»Λ§ΛΫΛΈΑλΛΡΛάΓΘ
ΤϋΥήΖΩSCMΛ§ΦΓάΛ¬εΛρ¬σΛ·
Ωό3ΓΓ ÷… ΛΈΞΩΞΛΞΉΛ»ΨΠ¥ΖΙ‘
÷… Έ……
Ημ«Φ
ΟΣ¬ΊΛ®
ΟΣΆνΛΝ
…‘Έ……
«―¥ΰ
«―¥ΰ
«―¥ΰ
ΨΠ¥ΖΙ‘ ―ΙΙΛΥΛηΛξΚοΗΚ≤Ρ«Ϋ
≥α≈ΡΛ“ΛΪΛκΓ ΛΪΛΗΛΩΓΠΛ“ΛΪΛκΓΥ
1981«·ΓΔΤνΞΪΞξΞ’Ξ©ΞκΞΥΞΔ¬γ≥ΊORΆΐ≥ΊΫΛ
ΜΈΦηΤάΓΘ
Τ±«·ΓΔΤϋΥήΞΔΞΛΓΠΞ”ΓΦΓΠΞ®ΞύΤΰ
Φ“ΓΘ
91«·ΓΔΤϋΡΧΝμΙγΗΠΒφΫξΤΰΦ“ΓΘ
2001«·ΓΔ
Ξ«ΞμΞΛλλΓΦΞόΞΡΞ≥ΞσΞΒΞκΞΤΞΘΞσΞΑΤΰΦ“Γ ΗΫ
ΞΔΞ”ΓΦΞύΞ≥ΞσΞΒΞκΞΤΞΘΞσΞΑΓΥΓΘ
ΗΫΚΏΛΥΜξΛκΓΘ
≈≈ΒΛΡΧΩ°¬γ≥Ί¬γ≥Ί±ΓΨπ σΞΖΞΙΞΤΞύ≥Ί≤ ≥Ί
Ϋ―«νΜΈΓΘ
Οφ±ϊΩΠΕ»«ΫΈ®≥Ϊ»·Ε®≤ώΓ÷ΞμΞΗΞΙΞΤ
ΞΘΞ·ΞΙ¥…Άΐ2ΒιΓΠ3ΒιΓΉΛΈΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΕΠΤ±¥ΤΫΛ
ΛΈΛέΛΪSCM¥ΊœΔΛΈΟχΫώ¬ΩΩτΓΘ
ΞΔΞ”ΓΦΞύΞ≥
ΞσΞΒΞκΞΤΞΘΞσΞΑHP http://jp.abeam.com
|