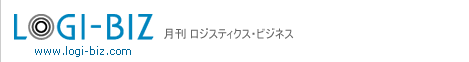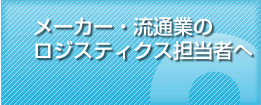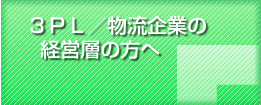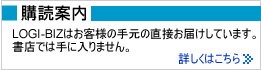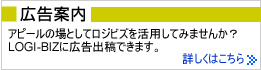|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

MAY 2011ΓΓΓΓ42
≈≈œΟΛΈ…‘ΡΧΛ«ΞΡΞΛΞΟΞΩΓΦΛ§≥ηΧω
ΓΓΚΘ≤σΛΈΩΧΚ“Λ«Λœ≈≈œΟΛ§ΛόΛΟΛΩΛ·Μ»ΛΛΛβΛΈΛΥΛ Λι
Λ Λ·Λ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
≈≈œΟ≤σάΰΛΈά»ΦεΛΒΛ§œΣΡηΛΖ
ΛΩΓΘ
ΛΫΛΈ¬εΛοΛξΓ÷ΞΡΞΛΞΟΞΩΓΦΓ TwitterΓΥΓΉΛδΓ÷ΞΙ
ΞΪΞΛΞΉΓ SkypeΓΥΓΉΛ Λ…ΓΔΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»ΛΈΞ―Ξ±ΞΟΞ»
ΡΧΩ°ΛρΆχΆ―ΛΖΛΩΞΡΓΦΞκΛ§¬γ≥ηΧωΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΤ±ΛΗΛ≥Λ»Λ§¥κΕ»¥÷ΛΈΦθ»·ΟμΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΛβΒ·Λ≠ΛΤ
ΛΛΛΩΓΘ
≈≈œΟ≤σάΰΛρΜ»ΛΟΛΩ»·ΟμΞΖΞΙΞΤΞύΓ÷Θ≈ΘœΘ”
Γ Electronic Ordering SystemΓΥΓΉΛœΜΏΛόΛΟΛΤΛΖΛό
ΛΟΛΩΓΘ
Αλ ΐΛ«ΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»≤σάΰΛΥΛηΛκ≈≈Μ“Ξ«ΓΦΞΩ
Ηρ¥ΙΓ÷Θ≈ΘΡΘ…Γ Electoronic Data InterchangeΓΥΓΉ
ΛœΧδ¬ξΛ Λ·ΒΓ«ΫΛΖΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΗρ¥ΙΒΓΛ«Οφ±ϊΫΗΗΔ≈ΣΛΥΡΧΩ°ΛρΞ≥ΞσΞ»ΞμΓΦΞκΛΙΛκ≈≈
œΟ≤σάΰΛœΓΔΛβΛ»ΛβΛ»Κ“≥≤ΛΥΛœΦεΛΛΓΘ
ΛΫΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤ
ΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»Λœ≥ΥάοΝηΛ§Β·Λ≠ΛΩΜΰΛΈΛ≥Λ»ΛρΝέΡξΛΖ
ΛΤΞ«ΞΕΞΛΞσΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΞΆΞΟΞ»ΞοΓΦΞ·ΛΈΑλ…τΛ§«Υ≤θ
ΛΒΛλΛΤΛβΓΔΦΪΤΑ≈ΣΛΥΛΫΛ≥Λρ±Σ≤σΛΖΛΤΞ«ΓΦΞΩΛ§≈ΝΟΘ
ΛΒΛλΛκΓΘ
ΡΧΩ°¬°≈ΌΛœ≈≈œΟ≤σάΰΛΈΑλΓΜΓΜ«ήΑ ΨεΛ«≈≈
œΟ≤σάΰΛΈΛηΛΠΛΥΆχΆ―Λ§ΫΗΟφΛΖΛΤΞάΞΠΞσΛΖΛΤΛΖΛόΛΠ
Λ≥Λ»ΛβΛ ΛΛΓΘ
Ξ≥ΞΙΞ»ΛβΖεΑψΛΛΛΥΑ¬ΛΛΓΘ
ΓΓΛΫΛΈΛΩΛα¥κΕ»¥÷ΛΈΞΣΞσΞιΞΛΞσΦηΑζΛΥΛœΓΔΤϋΥήΑ
≥ΑΛΈΛ…ΛΈΙώΛ«ΛβΘ≈ΘΡΘ…Λ§ΆχΆ―ΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
Λ»Λ≥Λμ
Λ§ΤϋΥήΛœΛΛΛόΛά≈≈œΟ≤σάΰΛρΜ»ΛΟΛΩ Θ≈ΘœΘ”Λ§¬γΦξΛρ
ΩΕΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΞΣΞσΞιΞΛΞσΦηΑζΛ»ΛΛΛΟΛΤΛβΦ¬ΚίΛΥΛœ»·
ΟμΞ«ΓΦΞΩΛρΝςΩ°ΛΖΛΤΛΛΛκΛάΛ±Λ«ΓΔΘ≈ΘΡΘ…ΛΈΛηΛΠΛ
Ν– ΐΗΰΡΧΩ°Λ«ΛœΛ Λ·ΓΔΚΏΗΥΨπ σΛρ≥Έ«ßΛΙΛκΛ≥Λ»Λβ
Λ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
ΓΓΤϋΥή¥κΕ»Λ§Θ≈ΘΡΘ…ΛρΤ≥ΤΰΛ«Λ≠Λ ΛΛΛΈΛœΓΔ¬γΖΩ»Τ
Ά―Ξ≥ΞσΞ‘ΞεΓΦΞΩΓΦΛρΜ»ΛΟΛΩΗ≈ΛΛΞΩΞΛΞΉΛΈΨπ σΞΖΞΙΞΤ
ΞύΓΔΓ»ΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΓ…ΛρΗεάΗ¬γΜωΛΥ ζΛ®ΛΤΛΛΛκ
ΛΪΛιΛάΓΘ
Θ≈Θ“Θ–ΛρΤ≥ΤΰΛΖΛΩΛ»ΛΛΛΠ¥κΕ»Λ«ΛΔΛΟΛΤΛβΓΔ
ΛηΛ·ΛηΛ· ΙΛΛΛΤΛΏΛκΛ»ΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛ§Αλ»÷±ϋΛΥ
±ΘΛλΛΤΛΛΛκΛ≥Λ»Λ§¬ΩΛΛΓΘ
ΓΓΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»ΛœΓ÷Θ‘ΘΟΘ–ΓΩΘ…Θ–ΓΉΛ»ΗΤΛ–ΛλΛκΡΧ
Ω°ΦξΫγΓ ΞΉΞμΞ»Ξ≥ΞκΓΥΛρΜ»ΛΠΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΗΫΚΏΛΈΑλ
»Χ≈ΣΛ Ξ―ΞΫΞ≥ΞσΛΥΛœ…§ΛΚΘ‘ΘΟΘ–ΓΩΘ…Θ–Λ§Ν»ΛΏΙΰΛόΛλ
ΛΤΛΛΛκΓΘ
Λ»Λ≥ΛμΛ§¬γΖΩ»ΤΆ―ΒΓΛœΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»ΛΈ…α
ΒΎΝΑΛΥάΏΖΉΛΒΛλΛΩΛβΛΈΛ«Θ‘ΘΟΘ–ΓΩΘ…Θ–ΛΥ¬–±ΰΛΖΛΤ
ΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»ΛρΆχΆ―Λ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
Θ≈ΘΡΘ…ΛρΤ≥ΤΰΛ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
ΓΓΤϋΆ―Μ®≤Ώ… Ε»≥ΠΛΈΘ÷ΘΝΘΈΓ …’≤Ο≤ΝΟΆΡΧΩ°Χ÷ΓΥΛρ
±Ω±ΡΛΙΛκ≈ωΦ“ΞΉΞιΞΆΞΟΞ»ΛœΑλΕεΕεΕε«·ΛΥΓΔΛΫΛλΛό
Λ«ΛΈΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛΥΗΪάΎΛξΛρ…’Λ±ΛΤΓΔΘ‘ΘΟΘ–ΓΩ
Θ…Θ–ΛΥ¬–±ΰΛΖΛΩΞΣΓΦΞΉΞσΖœΞΖΞΙΞΤΞύΛΥΑήΙ‘ΛΖΛΩΓΘ
ΛΫ
ΛλΛρΒΓΛΥΞΉΞιΞΆΞΟΞ»ΛΈΞφΓΦΞΕΓΦΛ«ΛΔΛκΤϋΜ®ΞαΓΦΞΪΓΦ
ΛδΤϋΜ®≤ΖΛΥΛβΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛΪΛιΛΈΟΠΒ―ΛρΝ Λ®ΛΤ
Λ≠ΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔ≈ωΫιΛœΛ ΛΪΛ ΛΪΦθΛ±ΤΰΛλΛΤΛβΛιΛ®Λ ΛΪ
ΛΟΛΩΓΘ
ΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΙΙΩΖ¥ϋΛρΖόΛ®ΛΩΞφΓΦΞΕΓΦ¥κΕ»ΛΥΨη
ΛξΙΰΛσΛ«Ζ–±ΡΦ‘ΛράβΤάΛΖΛΤΛβΓΔΛΫΛΈ≤ώΦ“ΛΈΨπ σΞΖ
ΞΙΞΤΞύ…τΛ§»Ω¬–ΛΙΛκΓΘ
ΞΣΓΦΞΉΞσΖœΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΞΉΞμΞΑ
ΞιΞΏΞσΞΑΗάΗλΛδΙΫ¬ΛΛœ¬γΖΩ»ΤΆ―ΒΓΛ»ΛœΝ¥Λ·ΑέΛ ΛΟΛΤ
ΛΛΛκΓΘ
ΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΑιΛΟΛΩΞΖΞΙΞΤΞύΞ®ΞσΞΗΞΥ
ΞΔΛ«Λœ¬–±ΰΛ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
ΓΓΦ¬ΚίΓΔ≤Λ ΤΛ«ΛœΞΣΓΦΞΉΞσΖœΞΖΞΙΞΤΞύΛΊΛΈΑήΙ‘ΛΥΛη
ΛκΞάΞΠΞσΞΒΞΛΞΗΞσΞΑΛρΩ ΛαΛκΛΩΛαΛΥΓΔΘΟΘ…ΘœΓ Κ«Ιβ
Ψπ σά’«ΛΦ‘ΓΥΛ§άηΤ§ΛΥΈ©ΛΟΛΤΨπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΧγΛΈ¬γ
Β§ΧœΛ ΞξΞΙΞ»ΞιΛ§Φ¬ΜήΛΒΛλΛΩΓΘ
Λ»Λ≥ΛμΛ§ΤϋΥή¥κΕ»ΛΥ
Λœ¥ΈΩ¥ΛΈΘΟΘ…ΘœΛ§ΛΛΛ ΛΛΓΘ
Ψπ σΞΖΞΙΞΤΞύ…τΧγΛΈΞ»ΞΟ
ΞΉΛœ…τΧγΛΈ¬ε…ΫΛΥ≤αΛ°ΛΚΓΔΖ–±ΡΛΈΜκ≈άΛΥΛœΈ©ΛΟΛΤ
ΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΦΪΛιΛΈΞΙΞ≠ΞκΛ§»ίΡξΛΒΛλΛΤΛΖΛόΛΠΒΜΫ―≥Ή
ΩΖΛΥΛœΡώΙ≥ΛΙΛκΓΘ
ΓΓΞλΞ§ΞΖΓΦΛΪΛιΛΈΟΠΒ―ΛΥΛœΦ“≥ΑΛΈάλΧγ≤»Λβ»Ω¬–ΛΙ
ΓΓΞΛΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»Λ§Κ“≥≤ΛΥΕ·ΛΛΛ≥Λ»ΛœΚΘ≤σΛΈΩΧΚ“Λ«Λβ
ΨΎΧάΛΒΛλΛΩΓΘ
ΡΧΩ°¬°≈ΌΛδΞ≥ΞΙΞ»ΗζΈ®Λβ≈≈œΟ≤σάΰΛ»Λœ
ΖεΑψΛΛΛΥΆΞΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
Λ»Λ≥ΛμΛ§ΤϋΥή¥κΕ»ΛΈ¬ΩΛ·Λ§ΓΔ
ΛΛΛόΛάΛΥΞΣΞσΞιΞΛΞσΦηΑζΛρ≈≈œΟ≤σάΰΛ«Ι‘ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΞΛ
ΞσΞΩΓΦΞΆΞΟΞ»ΛΥ¬–±ΰΛ«Λ≠Λ ΛΛΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛρΗεάΗ
¬γΜωΛΥ ζΛ®ΙΰΛσΛ«ΛΛΛκΛΪΛιΛάΓΘ
ΓΓΓ ΙΛ≠ΦξΓΠ¬γΧπΨΜΙάΓΥ
ΞΉΞιΞΆΞΟΞ»ΓΓΕΧάΗΙΑΨΜΓΓΦ“ΡΙ
ICT ®Γ®ΓΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛΈ ά≥≤ΧάΛιΛΪΛΥ
¬ηΘ≤…τ Λ≥ΛλΛΪΛι ΣΈ°ΛΥ≤ΩΛ§Β·Λ≠ΛκΛΈΛΪ
ΤΟ ΫΗ 3ΓΠ11Λ…ΛΠΛ Λκ ΣΈ°
43ΓΓΓΓMAY 2011
Ν»ΛσΛ«Λ≠ΛΩΓΘ
ΓΓΞœΓΦΞ…ΧΧΛ«ΛœΦσ≈‘ΖςΞ«ΓΦΞΩΞΜΞσΞΩΓΦΛΥΤ±ΛΗΙΫά°ΛΈ
ΞΖΞΙΞΤΞύΛρΤσΖœ≈ΐ«έΟ÷ΛΖΓΔΥή»÷ΒΓΛ»Λœ ΧΛΥΆΫ»ςΒΓΛρ
ΨοΛΥΒ·ΤΑΛΖΛΩΨθ¬÷Λ«¬‘ΒΓΛΒΛΜΛκΓ÷ΞέΞΟΞ»ΞΙΞΩΞσΞ–ΞΛ
ΐΦΑΓΉΛρΛ»ΛκΛ≥Λ»Λ«Ψψ≥≤»·άΗΜΰΛΥ»ςΛ®ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΒ
ΛιΛΥ¬γΒ§ΧœΚ“≥≤ΛΥΛβ¬–±ΰΛΙΛκΛΩΛαΛΥ¬γΚεΞ«ΓΦΞΩΞΜ
ΞσΞΩΓΦΛΥΛβΛΠΑλΛΡΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛρΓ÷Ξ≥ΓΦΞκΞ…ΞΙΞΩΞσΞ–
ΞΛΓΉΛΈΨθ¬÷Λ«¬‘ΒΓΛΒΛΜΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΖ±ΈΐΛβΥη«·Ι‘ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Κρ«·ΕεΖνΛΥΛœΞιΞΛΞΣΞσΓΔ
ΞφΞΥΓΠΞΝΞψΓΦΞύΓΔΘ–ΓθΘ«Λ Λ…ΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΛδΞ―ΞκΞΩΞΟ
Ξ·ΓΔΛΔΛιΛΩΛ»ΛΛΛΟΛΩ≤Ζ«δΕ»Φ‘Λ Λ…ΖΉœΜΓΜΦ“Α ΨεΛ§
Μ≤≤ΟΛΙΛκ¬γΒ§ΧœΛ Υ…Κ“Ζ±ΈΐΛρΙ‘ΛΟΛΩΓΘ
Φσ≈‘ΖςΞ«ΓΦ
ΞΩΞΜΞσΞΩΓΦΛ§ΞάΞαΓΦΞΗΛρΦθΛ±ΓΔΞΒΓΦΞ”ΞΙΛΈΖ―¬≥Λ§ΚΛ
ΤώΛΥΛ ΛΟΛΩΛ»ΝέΡξΛΖΓΔ¬γΚεΞ«ΓΦΞΩΞΜΞσΞΩΓΦΛ«Ξ≥ΓΦΞκ
Ξ…ΞΙΞΩΞσΞ–ΞΛΛΖΛΤΛΛΛκΞΖΞΙΞΤΞύΛΈΕέΒόΈ©ΛΝΨεΛ≤Λ»Ξφ
ΓΦΞΕΓΦ¬ΠΛΈάΎΛξ¬ΊΛ®ΛρΦ¬ΜήΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΛβΛΟΛ»ΛβΓΔΚΘ«·»§ΖνΛΥΞΉΞιΞΆΞΟΞ»ΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛœ¥Α
Ν¥Λ Ξ·ΞιΞΠΞ…ΛΥΑήΙ‘ΛΙΛκΓΘ
ΗΫΙ‘ΛΈΞΖΞΙΞΤΞύΛ«ΛœΦσ≈‘
ΖςΞ«ΓΦΞΩΞΜΞσΞΩΓΦΛ§ΜΏΛόΛΟΛΩΨλΙγΛΥΓΔΞφΓΦΞΕΓΦ¬ΠΛ«
¬γΚεΞ«ΓΦΞΩΞΜΞσΞΩΓΦΛΥάΎΛξ¬ΊΛ®ΛκΚνΕ»Λ§…§ΆΉΛΥΛ ΛκΓΘ
Ζ±ΈΐΛβΛΫΛΈΛΩΛαΛάΛΟΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΛ≥ΛλΛ§Ξ·ΞιΞΠΞ…ΛΥ
Λ ΛκΛ»ΞφΓΦΞΕΓΦ¬ΠΛΈΚνΕ»Λœ…‘ΆΉΛΥΛ ΛκΓΘ
ΞφΓΦΞΕΓΦ¬Π
Λ«ΛœΑ’Φ±ΛΖΛ ΛΛΛόΛόΛΥΓΔΦΪΤΑ≈ΣΛΥΞΖΞΙΞΤΞύΛ§άΎΛξ¬Ί
ΛοΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΠΛΖΛΩΞ–ΞΟΞ·ΞΔΞΟΞΉ¬Έά©ΛρΙΫΟέΛΖΓΔΑίΜΐΛΖΛΤΛΛ
Λ·ΛΥΛœ≈ωΝ≥ΓΔ»ώΆ―Λ§ΛΪΛΪΛκΓΘ
≤φΓΙΛ§ΛΫΛλΛρ«±Ϋ–Λ«
Λ≠ΛΩΛΈΛœΓΔΒΜΫ―≥ΉΩΖΛΥΛηΛΟΛΤΞΖΞΙΞΤΞύ»ώΛρ≤ΦΛ≤ΛΤΛ≠
ΛΩΛΪΛιΛάΓΘ
Ξ·ΞιΞΠΞ…ΛΊΛΈΑήΙ‘ΛΥΛηΛΟΛΤ±ΩΆ―Ξ≥ΞΙΞ»Λœ
ΛΒΛιΛΥ≤ΦΛ§ΛκΓΘ
ΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛρ ζΛ®ΙΰΛσΛ«ΛΛΛκ
Η¬ΛξΓΔΩΖΛΩΛ ΒΜΫ―ΛΈ≥ηΆ―ΛδΗζΈ®≤ΫΛœΥΨΛαΛΚΓΔ≥δΙβ
Λ »ώΆ―Λ§»·άΗΛΖ¬≥Λ±ΛκΛ≥Λ»ΛρΓΔΖ–±ΡΦ‘ΛœΟΈΛιΛ Λ·
ΛΤΛœΛ ΛιΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΟΧΓΥ
ΛΗΛΟΛΩΛ≥Λ»ΛΈΛΔΛκΩΆ¥÷ΛΥΛ»ΛΟΛΤΛœΚΘΛδΨοΦ±ΛάΓΘ
ΛΖΛΪ
ΛΖΓΔΞ≥ΞσΞ‘ΞεΓΦΞΩΓΦΞαΓΦΞΪΓΦΛδΞΖΞΙΞΤΞύΞΛΞσΞΤΞΑΞλΓΦ
ΞΩΓΦΛœΛΫΛλΛ«Λœ«δΛξΨεΛ≤Λ§Έ©ΛΩΛ Λ·Λ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΠΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥ≤ΰ≥ΉΛΥΛœΡώΙ≥ΛΙΛκΓΘ
ΓΓΘ
…Θ‘ΞξΞΤΞιΞΖΓΦΛΥΥ≥ΛΖΛΛΖ–±ΡΦ‘ΛœΓΔΦ“Τβ≥ΑΛΈάλΧγ
≤»ΛΩΛΝΛΥ»Ω¬–ΛΒΛλΛκΛ»…‘Α¬ΛΥΛ ΛκΓΘ
ΛΣΛΪΛΖΛΛΛ»Λœ
¥ΕΛΗΛ Λ§ΛιΛβΕώ¬Έ≈ΣΛΥΜΊ≈ΠΛ«Λ≠Λ ΛΛΛΈΛ«ΖκΕ…ΓΔΗά
ΛΛΛ ΛξΛΥΛ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΠΓΘ
ΓΓΤϋΥήΛ»Τ±ΆΆΛΥΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛ§ΧΔ±δΛΖΛΤΛΛΛΩ¥Ύ
ΙώΛ«ΛœΕα«·ΓΔΙώΛρΒσΛ≤ΛΩΓ»ΞλΞ§ΞΖΓΦΡ… ϋ±ΩΤΑΓ…Λ§
¥§Λ≠Β·Λ≥ΛξΓΔ¬γΛ≠Λ·ΨθΕΖΛ§ ―≤ΫΛΖΛΩΓΘ
Αλ ΐΓΔΩΖΕΫ
ΙώΛœΞ≥ΞσΞ‘ΞεΓΦΞΩΓΦΛΈΤ≥ΤΰΛ§ΟΌΛΪΛΟΛΩΛΩΛαΛΥΓΔΗε»·
ΛΈΆΞΑΧά≠Λ«ΫιΛαΛΪΛιΞΣΓΦΞΉΞσΖœΞΖΞΙΞΤΞύΛ§Τ≥ΤΰΛΒΛλ
ΛΩΓΘ
ΤϋΥήΛάΛ±Λ§άΛ≥ΠΛΪΛιΦηΛξΜΡΛΒΛλΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛ«ΛβΚΘ≤σΛΈΩΧΚ“Λ«ΓΔΛΒΛΙΛ§ΛΥΤϋΥήΛΈΖ–±ΡΦ‘Λβ
ΞλΞ§ΞΖΓΦΛΈ ά≥≤ΛΥΒΛ…’ΛΛΛΩΛœΛΚΛάΓΘ
ΞΉΞιΞΆΞΟΞ»Λ«Λœ
ΖΪΛξ ÷ΛΖΓ»ΟΠΞλΞ§ΞΖΓΦΓ…ΛρΝ Λ®¬≥Λ±ΛΩΛ≥Λ»Λ«ΓΔΤσΓΜ
ΓΜΕε«·ΫΫΑλΖνΛΥΛηΛΠΛδΛ·ΧσΑλΓΜΓΜΓΜΦ“ΛΥΨεΛκΛΙΛΌ
ΛΤΛΈΞφΓΦΞΕΓΦΛ§Θ‘ΘΟΘ–ΓΩΘ…Θ– ΐΦΑΛΥάΎΛξ¬ΊΛοΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΞΉΞιΞΆΞΟΞ»Λ»œΔΖ»ΛΖΛΤΛΛΛκΦρΈύΓΠΩ©… Ε»≥ΠΛΈΞ’ΞΓ
ΞΛΞΆΞΟΞ»ΛΥΛœΓΔΛόΛάΘ≈ΘœΘ”ΛρΜ»ΛΟΛΤΛΛΛκΞφΓΦΞΕΓΦΛ§
ΜΡΛΟΛΤΛΛΛκΛ§ΓΔΚΘΗεΛœΞλΞ§ΞΖΓΦΥ–Χ«±ΩΤΑΛΥ«οΦ÷Λ§
ΛΪΛΪΛΟΛΤΛΛΛ·ΛάΛμΛΠΓΘ
≈≈œΟ≤σάΰΛΈ≤ΜάΦΛρΞ«ΞΗΞΩΞκΩ°
ΙφΛΥ ―¥ΙΛΙΛκΞΔΞ ΞμΞΑΞβΞ«ΞύΛ Λ…ΓΔΚΘΛ«ΛœΛ…Λ≥ΛβάΗ
ΜΚΛΖΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘ
ΞλΞ§ΞΖΓΦΛΈΗ¬≥ΠΛœΧάΛιΛΪΛάΓΘ
ΚΘ«·»§ΖνΛΥΛœΞ·ΞιΞΠΞ…ΛΥ¥ΑΝ¥ΑήΙ‘
ΓΓΨπ σΡΧΩ°ΞΖΞΙΞΤΞύΛœΚΘΛδΞΒΞΉΞιΞΛΞΝΞßΓΦΞσΛΈΞΛΞσ
Ξ’ΞιΛάΓΘ
Λ»ΛξΛοΛ±≤φΓΙΛΈΑΖΛΠάΗ≥η…§Φϊ… ΛΈΞΒΞΉΞιΞΛ
ΞΝΞßΓΦΞσΛœΚ“≥≤ΜΰΛ«ΛΔΛΟΛΤΛβΜΏΛόΛΟΛΤΛΖΛόΛΠΛ≥Λ»Λ§
ΒωΛΒΛλΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥΞΉΞιΞΆΞΟΞ»Λ«ΛœΓ÷Θ¬ΘΟΘ–
Γ ΜωΕ»Ζ―¬≥ΖΉ≤ηΓΥΓΉΛΥΤσΓΜΓΜœΜ«·ΛΪΛιά―ΕΥ≈ΣΛΥΦηΛξ
ΛκΓΘ
≈ωΦ“Λ§»·¬≠≈ωΜΰΛΥΤ≥ΤΰΛΖΛΩΓ÷Θ…Θ¬ΘΆΘ≥ΘΑΘΙΘΑΓΉ
Λ»ΛΛΛΠ¬γΖΩ»ΤΆ―ΒΓΛœ≤Ν≥ Λ§ΧσΤσΓΜ≤·±ΏΛάΛΟΛΩΓΘ
ΛΫ
ΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΗΫΚΏΓΔ≈ωΦ“Λ§Μ»Ά―ΛΖΛΤΛΛΛκΞ≥ΞσΞ‘ΞεΓΦΞΩ
ΓΦΛœΗόΓΜΓΜΥϋ±ΏΡχ≈ΌΓΘ
ΞΣΓΦΞΉΞσΖœΞΖΞΙΞΤΞύΛœΞ―ΞΟΞ±
ΓΦΞΗΞΫΞ’Ξ»ΛρΜ»Λ®ΛκΛΈΛ«≥Ϊ»·»ώΛβ≥ Ο ΛΥΑ¬ΛΛΓΘ
ΓΓΞλΞ§ΞΖΓΦΞΖΞΙΞΤΞύΛρΦΈΛΤΛΤΛΖΛόΛ®Λ–ΓΔΨπ σΞΖΞΙΞΤ
ΞύΛΈΞ≥ΞΙΞ»ΛœΖύ≈ΣΛΥ≤ΦΛ§ΛκΓΘ
¬ΩΨ·Λ«ΛβΞΖΞΙΞΤΞύΛρΛΪ
0
ΔΘΜωΕ»Ζ―¬≥ΖΉ≤ηΛΈ¬–ΨίΛ»Λ ΛκΞξΞΙΞ·
ΞΉΞιΞΆΞΟΞ»¬η2 ≤σΚ“≥≤¬–ΚωΞΔΞσΞ±ΓΦλà 2010 «·7 ΖνΦ¬ΜήΓΔ187 Φ“Λ§≤σ≈ζΓΥ
ΔΘ¬γΒ§ΧœΩΧΚ“Λ§»·άΗΛΙΛκ≤Ρ«Ϋά≠ΛΥΛΡΛΛΛΤ
ΔΘΜωΕ»Ζ―¬≥ΖΉ≤ηΛΈ¬–ΨίΛ»Λ ΛκΞΖΞΙΞΤΞύ
¬γΒ§ΧœΚ“≥≤
ΞΖΞΙΞΤΞύΨψ≥≤
≤–Κ“
¬φ…ςΓΠΙκ±ΪΛ Λ…ΛΈΦΪΝ≥Κ“≥≤
ΛΫΛΈ¬Ψ
20 40 60 80
Γ ΓσΓΥ
Γ ΓσΓΥ
1 «·Α Τβ
3.2Γσ
1ΓΝ2 «·Α Τβ
3.2Γσ
2ΓΝ3 «·Α Τβ
2.7Γσ
3ΓΝ4 «·Α Τβ
4.3Γσ
15.1Γσ
Β·Λ≥ΛξΛΫΛΠΛΥΛ ΛΛ
7.6Γσ
20 «·ΛηΛξΗε
10ΓΝ20 «·Α Τβ
26.5Γσ
5ΓΝ10 «·Α Τβ
27.0Γσ
4ΓΝ5 «·Α Τβ
0 10.3Γσ
Φθ»·Ομ
ΣΈ°
άΝΒαΓΠΜΌ ß
ΚΏΗΥ¥…Άΐ
Ψπ σΖœΓ ≈≈Μ“ΞαΓΦΞκΛ Λ…ΓΥ
άΗΜΚ¥…Άΐ
ΛΫΛΈ¬Ψ
20 40 60 80 100
ΩΖΖΩΞΛΞσΞ’ΞκΞ®ΞσΞΕΛ Λ…ΛΈ
¥ΕάςΨ…
|