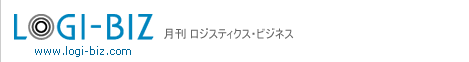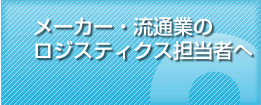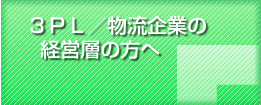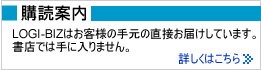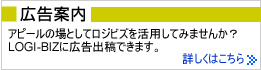|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

71ΓΓΓΓJULY 2011
«Φ… Έ®ΛράΒΛΖΛ·¥…ΆΐΛΙΛκ
ΓΓΥήΦ“ΛρΟφΙώΟœΕηΛΥΟ÷Λ·Θ–Φ“Λœ«·ΨΠΧσΤσΓΜΓΜ≤·
±ΏΛΈΟφΖχΤϋΆ―Μ®≤Ώ… ≤ΖΛ«ΛΔΛκΓΘ
Τ±Φ“ΛœΨ°«δΛξΕ»
¬÷ ΧΛΥΜΑΛΡΛΈΜωΕ»…τΛράΏΛ±ΛΤΛΣΛξΓΔάλΧγ≈ΙΞΝΞß
ΓΦΞσΛδΝμΙγΈΧ»Έ≈ΙΓ Θ«ΘΆΘ”ΓΥΛρΝξΦξΛ»ΛΙΛκΈΧ»Έ
ΜωΕ»…τΛ§ΛΫΛΈΛΠΛΝΛΈ≤‘Λ°Τ§Λ»Λ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΤ±ΜωΕ»…τΛΈΦηΑΖΞΔΞΛΞΤΞύΩτΛœΧσΜΑΥϋΓΘ
«Φ… άη
ΛœΥΧ≥ΛΤΜΛρΫϋΛ·Ν¥ΙώΛΥΛόΛΩΛ§ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΑλΓΜ«·
ΛέΛ…ΝΑΛόΛ«ΛœΓΔΤάΑ’άηΛΈΩτΛœΗ¬ΛιΛλΛΤΛΛΛΤΓΔΦη
ΑζΛΈΛ ΛΛΆ≠ΈœΞΝΞßΓΦΞσΛβ¬ΩΛ·ΜΡΛΒΛλΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΛΫ
ΛΈΖξΛρΥδΛαΛκΛΌΛ·ΓΔΘΆΓθΘΝΛρ¥όΛαΛΩ≥»¬γΚωΛΥ¬«
ΛΟΛΤΫ–ΛΤΓΔ«δΛξΨεΛ≤Λρ¬γΛ≠Λ·Ω≠Λ–ΛΖΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΒ§ΧœΛ≥ΛΫ≥»¬γΛΖΛΩΛβΛΈΛΈΓΔ…τ §Κ«
≈§ΛΈΖ―Λ°¬≠ΛΖΛρΖΪΛξ ÷ΛΖΛΩΛΪΛΩΛΝΛΈΝ»ΩΞΛœΓΔΛΠ
ΛόΛ·ΛœΒΓ«ΫΛΖΛΤΛΛΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΗΫΨλΛρΫœΟΈΛΖΛΩΟΓ
Λ≠ΨεΛ≤ΛΈΘ–Φ“Ξ»ΞΟΞΉΛœΓΔΝ¥¬ΈΚ«≈§ΛρΩόΛκΛΩΛαΛΥΓΔ
ΣΈ°ΛΪΛιΞαΞΙΛρΤΰΛλΛκΛΌΛ≠ΛάΛ»»ΫΟ«ΛΖΛΩΓΘ
≤ΰ≥Ή
ΛΥΗΰΛ±ΛΩΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝΓΦΞύΛ§Ν»ΩΞΛΒΛλΓΔΛΫΛΈ
ΩδΩ ΧρΛ»ΛΖΛΤ≤φΓΙΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦΓ ΘΈΘΧ
ΘΤΓΥΛΥΛΣάΦΛ§ΛΪΛΪΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ≤φΓΙΛœΧσΑλ«·»ΨΛΥΛοΛΩΛξΚνΕ»ΛΈΗζΈ®≤ΫΛδΜΌ ß
ΛΛ±ΩΡ¬ΛΈΚ«≈§≤ΫΛ Λ…ΞΌΓΦΞΖΞΟΞ·Λ ≤ΰΝ±ΛΥΦηΛξΝ»
ΛσΛάΓΘ
ΛΫΛΖΛΤΓΔΛΛΛηΛΛΛηΩΖΛΩΛ Ο ≥§ΛΥΛΩΛ…ΛξΟε
ΛΛΛΩΓΘ
«Φ… Έ®ΛΈ≤ΰΝ±Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΈ°ΡΧΕ»ΛΥΖ»ΛοΛΟΛΤΛΛΛκΤ…Φ‘ΛΈ ΐΛ ΛιΛΣ §ΛΪΛξ
Λ«ΛΔΛμΛΠΛ§ΓΔ«Φ… Έ®Λœ≤ΖΛΥΛ»ΛΟΛΤΚ«Λβ¬γΜωΛ ΜΊ
…ΗΛΈΑλΛΡΛ«ΛΔΛκΓΘ
Φ¬ΚίΓΔάλΧγ≈ΙΞΝΞßΓΦΞσΛδΘ«ΘΆ
Θ”ΛΈ¬ΩΛ·Λ§ΓΔ≤ΖΛΈ«Φ… Έ®ΛρΗΪΛΤΓΔΛΫΛΈ≤ΖΛ»ΛΈ…’
Λ≠ΙγΛΛ ΐΛρΖηΛαΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓ«Φ… Έ®ΛœΟ±ΫψΛΥ?ΑλΞόΞΛΞ ΞΙΖγ… Έ®?Λ«ΖηΛό
ΛκΛοΛ±Λ«ΛœΛ ΛΛΓΘ
Ζγ… Λ§»·άΗΛΖΛΤΛβ¬ΨΛΈΒρ≈άΛδ
ΤσΦΓ≤ΖΛΪΛιΡ¥ΟΘΛ«Λ≠ΛλΛ–«Φ… Έ®ΛœΑίΜΐΛ«Λ≠ΛκΓΘ
ΫΨΛΟΛΤΓΔΛΫΛΈ≤ΖΛΈΨΠ… ΕΓΒκΈœΓΔΛΫΛΖΛΤ ΣΈ°ΈœΛ§
«Φ… Έ®ΛΥ…ΫΛλΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓ≤ΰΝ±ΛΥΦηΛξΛΪΛΪΛκΝΑΛΈΘ–Φ“ΛΈΝ¥Ιώ ΩΕ―«Φ…
Έ®ΛœΓΔΕ廧ΓΠΜΑΓσΛ»ΓΔΖηΛΖΛΤΑ≠ΛΛΟΆΛ«ΛœΛ ΛΪΛΟ
ΛΩΓΘ
Λ»ΛΛΛΠΛηΛξΞιΞΛΞ–ΞκΛΈ≤ΖΛ»»φΛΌΛΤΆΞΫ®Λ«ΛΔ
ΛξΓΔΞΪΞΤΞ¥ΞξΓΦΛΥΛηΛΟΛΤΛœΑλΑΧΓΔΤσΑΧΛρΝηΛΠΛέ
Λ…Λ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛλΛ«ΛβΓΔΞ≥ΞσΞ”ΞΥΛρΜœΛαΛ»ΛΖΛΩ
ΞΣΞΎΞλΓΦΞΖΞγΞσάΚ≈ΌΛΈΙβΛΛΕ»≥ΠΛΈΞλΞΌΞκΛΥΛœΛό
ΛάΟΘΛΖΛΤΛΛΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΛΔΛκΛΛΛœΝ¥ΙώΒ§ΧœΛΈΞαΞ§
≤ΖΛ»»φ≥”ΛΖΛΩΨλΙγΛΥΛœΓΔΞ―Ξ’Ξ©ΓΦΞόΞσΞΙΛΥ≥ΪΛ≠
Λ§ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΘ
–Φ“ΛΈΞ»ΞΟΞΉΛœΓΔΗΫΨθΛΈ«Φ… Έ®Ε廧ΓΠΜΑΓσΛρ
≤Ρ«ΫΛ Η¬ΛξΑλΓΜΓΜΓσΛΥΕαΛ≈Λ±ΛΤΛΛΛ·Λ≥Λ»Λ ΛΖΛΥΓΔ
ΖψΛΖΛΛΕΞΝηΛράΗΛ≠»¥Λ·Λ≥Λ»ΛœΛ«Λ≠Λ ΛΛΛ»ΙΆΛ®ΛΤ
ΛΛΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΨΎΒρΛΥ«Φ… Έ®Λ§ΗΕΑχΛ«ΤΰΜΞΛρΦΚΟμΛΙ
ΜωΈψΛ«≥ΊΛ÷
ΗΫΨλ≤ΰΝ±
ΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦ
άΡΧΎάΒΑλΓΓ¬ε…Ϋ
ΓΓ«Φ… Έ®Λœ≤Ζ«δΕ»ΛΈάΗΧΩάΰΛ»ΛΛΛ®ΛκΓΘ
ΞΣΞΎΞλΓΦΞΖΞγΞσΛΈάΚ≈ΌΓΔ
ΨΠ… Ρ¥ΟΘΈœΓΔΨπ σΕΠΆ≠ΛΈΞλΞΌΞκ≈υΓΙΓΔΛΙΛΌΛΤΛΈΒΓ«ΫΛ§«Φ… Έ®
ΛΥΫΗΧσΛΒΛλΛΤ…ΫΛλΛκΓΘ
«Φ… Έ®ΛΈ≤ΰΝ±ΛΥΛœ ΣΈ°ΛΈœ»ΤβΛΥΜΏΛόΛΟ
ΛΩΦηΛξΝ»ΛΏΛάΛ±Λ«Λœ…‘ΫΫ §ΛάΓΘ
ΤώΑΉ≈ΌΛΈΙβΛΛΞΤΓΦΞόΛΥΟφΖχ≤Ζ
Λ§άΒΧΧΛΪΛιΡ©ΛσΛάΓΘ
«Φ… Έ®ΗΰΨεΛΥΡ©ΛσΛάΟφΖχΤϋΜ®≤Ζ
¬η102 ≤σ
ΛΔΛΣΛ≠ΓΠΛΖΛγΛΠΛΛΛΝ
ΓΓ1964«·άΗΛόΛλΓΘ
Βΰ≈‘ΜΚ
Ε»¬γ≥ΊΖ–Κ―≥Ί…τ¬¥Ε»ΓΘ
¬γΦξ
±ΩΝςΕ»Φ‘ΛΈΞΜΓΦΞκΞΙΞ…ΞιΞΛ
Ξ–ΓΦΛρΖ–ΛΤΓΔ89 «·ΛΥΝΞΑφ
ΝμΙγΗΠΒφΫξΤΰΦ“ΓΘ
ΣΈ°≥Ϊ»·
ΞΝΓΦΞύΓΠΞ»ΞιΞΟΞ·ΞΝΓΦΞύΞΝΓΦ
Ξ’ΛρΧ≥ΛαΛκΓΘ
96«·ΓΔΤ»Έ©ΓΘ
ΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦΛράΏ
Έ©ΛΖ¬ε…ΫΛΥΫΔ«ΛΓΘ
ΗΫΚΏΛΥΜξΛκΓΘ
HP:http://www.nlf.co.jp/
e-mail:info@nlf.co.jp
JULY 2011ΓΓΓΓ72
ΛκΛ≥Λ»ΛβΛΖΛ–ΛΖΛ–ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ≤ΖΛ§¥…ΆΐΜΊ…ΗΛ»ΛΖΛΤΑλ»Χ≈ΣΛΥΚΈΆ―ΛΖΛΤΛΛΛκ«Φ
… Έ®ΛΥΛœΓΔ¬γΛ≠Λ·ΤσΛΡΛΈΦοΈύΛ§ΛΔΛκΓΘ
Γ÷Ϋ–≤Ό«Φ
… Έ®ΓΉΛ»Γ÷ΤάΑ’άη«Φ… Έ®ΓΉΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΛΠΛΝΫ–≤Ό«Φ… Έ®Λ»ΛœΞΜΞσΞΩΓΦΛΪΛιΛΈΫ–≤Ό
Ο ≥§Λ«ΛΈΟμ ΗΫΦ¬≠Έ®Λ«ΛΔΛκΓΘ
Αλ ΐΛΈΤάΑ’άη«Φ…
Έ®Λœ≈Ι όΛ«ΛΈΗΓ… ΗεΛΥΧάΛιΛΪΛΥΛ Λκ«Φ… Έ®ΛρΜΊ
ΛΙΓΘ
ΗΓ… ΛΥΛηΛΟΛΤ»·≥–ΛΖΛΩΞΏΞΙΛδ«Υ¬ΜΛΈ §ΛάΛ±
Ϋ–≤Ό«Φ… Έ®ΛηΛξΛβΡψΛΛΩτΜζΛΥΛ ΛκΓΘ
ΓΓΤϋΜ®Ε»≥ΠΛ«Λœ≈Ι όΟ ≥§Λ«ΛΈΦθΛ±ΤΰΛλΗΓ… ΛρΨ
Έ§ΛΙΛκΓ÷ΞΈΓΦΗΓ… ΓΉΛ§ΓΔΚΘΛ«ΛœΙ≠Λ·…αΒΎΛΖΛΤΛΛ
ΛκΓΘ
ΗΓ… ΗεΛΈΞ«ΓΦΞΩΛρ ÷ΛΖΛΤΛ·Λκ≈Ι όΛœΗ¬ΛιΛλ
ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΫ–≤Ό«Φ… Έ®ΛάΛ±Λ«ΞΣΞΎΞλΓΦΞΖ
ΞγΞσΛΈάΚ≈ΌΛρ¬§ΛκΛΈΛœ¥μΗ±ΛάΓΘ
ΤάΑ’άη«Φ… Έ®Λ»
ΛΈ–ΣΈΞΛρΧΒΜκΛΖΛΩ¥…ΆΐΛœΦΪΗ Υΰ¬≠ΛΥ¥ΌΛκΓΘ
ΛΫΛΈ
Ζκ≤ΧΓΔΗήΒ“ΛΪΛιΛΈ…Ψ≤ΝΛρΟχΛΖΛ·ΆνΛ»ΛΖΛΤΛΖΛόΛΠ
Ε≤ΛλΛ§ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛόΛΩΓΔΦθΟμΖΝ¬÷ΛΥΛηΛΟΛΤΛβ«Φ… Έ®ΛΥΛœΤσΛΡΛΈ
≤ρΦαΛ§ΛΔΛκΓΘ
Γ÷άΒΨοΦθΟμΓΉΛ»ΓΔΛΛΛοΛφΛκ?ΞάΞΏ
ΓΦΙΰΛΏΦθΟμ?ΛΈΛ…ΛΝΛιΛρ § λΛΥΛ»ΛκΛΪΛ»ΛΛΛΠΑψ
ΛΛΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓάΒΨοΦθΟμΛœ ΗΜζΡΧΛξΗήΒ“ΛΪΛιΛΈΦ¬Ομ ΗΛ«ΛΔ
ΛκΓΘ
Αλ ΐΛΈΞάΞΏΓΦΙΰΛΏΦθΟμΛΈ?ΞάΞΏΓΦ?Λ»ΛœΓΔ±Ρ
Ε»Λ§Ζγ… ΛρΕ≤ΛλΛκΛΔΛόΛξΓΔΛΔΛκΛΛΛœΟ¥≈ωΗήΒ“ΛΈ
»Έ¬ΞΓ ΤΟ«δΓΥΛρΗΪ±έΛΖΛΤΓΔΟμ ΗΩτΛρΨεΨηΛΜΛΖΛΤ
ΛΛΛκΞ±ΓΦΞΙΛρΜΊΛΙΓΘ
ΓΓ ΣΈ°…τΧγΛœΓΔάΒΨοΦθΟμΛΈ«Φ… Έ®ΛΈΗΰΨεΛΥ≈ΊΛα
ΛκΛΈΛœΛβΛΝΛμΛσΛΈΛ≥Λ»ΓΔΞάΞΏΓΦΙΰΛΏΦθΟμΛΈ«Φ…
Έ®ΛΈ≤ΰΝ±ΛΥΛβΦηΛξΝ»Λύ…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΓΘ
±ΡΕ»Λ»ΛΈœΔ
Ζ»ΞΤΓΦΞόΛ»ΛΖΛΤ ΣΈ°…τΧγΛ§ΦγΤ≥ΛΖΛ ΛΛΗ¬ΛξΓΔΛ
ΛΪΛ ΛΪ≤ΰΝ±ΛΒΛλΛ ΛΛΧδ¬ξΛάΛΪΛιΛ«ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΕώ¬Έ≈ΣΛΥΛœΛόΛΚΓΔΞάΞΏΓΦΙΰΛΏΦθΟμΛΥΛηΛΟΛΤΓΔ
Λ…ΛλΛάΛ±ΛΈΕβ≥έ≈Σ¬ΜΦΚΛ§άΗΛΗΛΤΛΛΛκΛΪΛρΜΜΫ–ΛΙ
ΛκΓΘ
ΛΫΛΖΛΤΫ–≤ΌΞΜΞσΞΩΓΦΛ¥Λ»ΛΥ±ΡΕ»ΗΰΛ±ΛΈάβΧά
≤ώΛρ≥ΪΚ≈ΛΖΓΔΜΜΫ–Ζκ≤ΧΛρ σΙπΛΙΛκΛΈΛ«ΛΔΛκΓΘ
άβ
Χά≤ώΛΈΗεΛβΨπ σ»·Ω°ΛœΖ―¬≥ΛΖΛΤΙ‘ΛΛΓΔΛΫΛλΛΥ¬–
ΛΙΛκ≤ρΖηΚωΛρ±ΡΕ»Ο¥≈ωά’«ΛΦ‘Λ» ΣΈ°…τΧγΛΈΕ®ΒΡ
ΛΈΛΠΛ®Λ«ΖηΡξΛΖΦ¬ΜήΛΙΛκΓΔΛ»ΛΛΛΠΛδΛξ ΐΛ§Ά≠Ηζ
Λ«ΛΔΛκΓΘ
ΣΈ°ΛΈœ»≥ΑΛΥ¬≠ΛρΤßΛΏΫ–ΛΙ
ΓΓΘ
–Φ“ΛΈΈΧ»ΈΜωΕ»…τΛœ¥Ί≈λΓΔΟφΒΰΓΔΟφΙώΛΈΜΑ
ΞΪΫξΛΥΘΡΘΟΓ ΚΏΗΥΖΩΓΥΞΜΞσΞΩΓΦΛρ«έΟ÷ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
Λ≥ΛΈΛΠΛΝΓ÷άΒΨοΦθΟμΓΉΛΥΛΣΛΛΛΤ«Φ… Έ®ΕεΦΖΓΠΜΑ
ΓσΛ»ΓΔΚ«ΛβΩτΟΆΛ§Α≠ΛΪΛΟΛΩΟφΒΰ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΪ
Λι≤ΰΝ±ΛΥΟεΦξΛΙΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΑλ»ΧΛΥ«Φ… Έ®ΛρΑ≠≤ΫΛΒΛΜΛΤΛΛΛκΗΕΑχΓΠ≤ί¬ξΛœΓΔ
Τ±ΛΗ≤ώΦ“Λ«ΛΔΛΟΛΤΛβΒρ≈άΛΥΛηΛΟΛΤΑέΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΟφΒΰ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΈΨλΙγΛœΓΔΞΙΞΎΓΦΞΙ≈ΣΛ Ξ≠Ξψ
Ξ―ΞΣΓΦΞ–ΓΦΛΈΛέΛΪΛΥΓΔ¬γΈΧ»·ΟμΛΊΛΈ¬–±ΰΛ»ΓΔΞα
ΓΦΞΪΓΦΖγ… ΛΈ≤ρΨΟΛ§Ϋ≈ΆΉΛ ≤ί¬ξΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΫΨΆηΛΪΛιΘ–Φ“Λ«ΛœΓΔΗήΒ“Λ§»Έ¬ΞΞ≠ΞψΞσΞΎΓΦΞσ
≈υΛρΦ¬ΜήΛΙΛκΨλΙγΛΥΛœΓΔΟ¥≈ω±ΡΕ»ΞόΞσΛ§ΜωΝΑΛΥ
Γ÷¬γΈΧ»Έ«δΩΫάΝΫώΓΉΛρΡσΫ–ΛΙΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛ
ΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΛΫΛΈ±ΩΆ―άΚ≈ΌΛ§Α≠ΛΪΛΟΛΩΓΘ
Λ…ΛλΛά
Λ±ΛΈΈΧΛρΡΕΛ®ΛΩΨλΙγΛΥΓ÷¬γΈΧΓΉΛ»ΛΙΛκΛΈΛΪΛ»ΛΛ
ΛΠ≈άΛβέΘΥφΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΒΛιΛΥΛœ¬γΈΧ»·ΟμΑ ≥ΑΛΈΡΧΨοΛΈ»·ΟμάΚ≈ΌΛΥΛβ
ΒΩΧδΛ§ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΛβΛΠΑλ ΐΛΈΞαΓΦΞΪΓΦΖγ… ΛΈΧδ¬ξ
Λβ¥όΛαΓΔ≤ρΖηΛΥΛœ±ΡΕ»…τΧγΛδΡ¥ΟΘ…τΧγΛ»ΛΈœΔΖ»
Λ§…‘≤ΡΖγΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛόΛ«ΛΈΘ–Φ“ΛΈ≤ΰΝ±Λœ ΣΈ°…τΧγΛΈ¥…Άΐ¬–Ψί
»œΑœΤβΛ«≤ρΖηΛ«Λ≠ΛκΞΤΓΦΞόΛΥΜΏΛόΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΛΖ
ΛΪΛΖΓΔΟφΒΰ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΈ≤ί¬ξΛ»≤ρΖη ΐΥΓΛρ §
άœΛΖΛΤΛΛΛ·Λ≥Λ»Λ«ΓΔ ΣΈ°…τΧγΛρΟφΩ¥Λ»ΛΙΛκΞΉΞμ
ΞΗΞßΞ·Ξ»ΞαΞσΞ–ΓΦΛΩΛΝΛœΓΔΖ–±ΡΛΈΜκ≈άΛΥΈ©ΛΟΛΩ
≤ΰ≥ΉΓΔΝ¥¬ΈΚ«≈§≤ΫΛ§…§ΆΉΛ«ΛΔΛκΛ≥Λ»Λρ«ßΦ±ΛΙΛκ
ΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓ≤φΓΙΛœ¬Ψ…τΫπΛ»ΛΈœΔΖ»ΛΥΛηΛκΝ¥Φ“≤ΘΟ«≈ΣΛ ≤ΰ
Ν±Λρ≥ΪΜœΛΖΛΩΓΘ
ΫΨΆηΛœ ΣΈ°Λ»ΛΛΛΠœ»ΤβΛ«≥ηΤΑΛΖ
ΛΤΛΛΛΩΦψΦξΛΈΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞαΞσΞ–ΓΦΛΩΛΝΛ§ΓΔΧΨ
ΝΑΛœΟΈΛΟΛΤΛΛΛκΛ§œΟΛρΛΖΛΩΛ≥Λ»ΛβΛ ΛΛ¬Ψ…τΧγΛΈ
…τΡΙΞ·ΞιΞΙΛΥάΦΛρ≥ίΛ±ΓΔ¬ΩΨ·ΛΣΛ…ΛΣΛ…ΛΖΛ Λ§Λι
Λβ?œ»?ΛΈ≥ΑΛΥΨ·ΛΖΛΚΛΡΤßΛΏΫ–ΛΖΛΤΛΛΛΟΛΩΛΈΛ«
ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΘ
–Φ“Λ ΛιΛΚΛ»ΛβΝ¥¬ΈΚ«≈§≤ΫΛρΧήΜΊΛΖΛΩΦηΛξΝ»
ΛΏΛρΞήΞ»ΞύΞΔΞΟΞΉΛ«Ω ΛαΛκΛ»Λ ΛκΛ»ΓΔ¬Ψ…τΧγΛ»
ΛΈΡ¥άΑΕ»Χ≥ΛΥ¬ΩΛ·ΛΈœΪΛρ»ώΛδΛΙΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛκΓΘ
ΛΖ
ΛΪΛΖΓΔΛΫΛΈΖκ≤ΧΛ»ΛΖΛΤΤάΛιΛλΛκΗζ≤ΧΛœΩ”¬γΛ«ΛΔ
ΛκΓΘ
Ο±Λ ΛκΗζΈ®≤ΫΛάΛ±Λ«Λ Λ·ΓΔΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝ
ΓΦΞύΞαΞσΞ–ΓΦΛΈά°ΡΙΛρ¬ΞΛΖΓΔΦ“ΤβΛΈ…ςΡΧΛΖΛρΈ…
Λ·ΛΙΛκΗζ≤ΧΛ§ΛΔΛκΓΘ
ΓΓ≥ΈΛΪΛΥΞ»ΞΟΞΉΞάΞΠΞσΛ«ΦηΛξΝ»ΛΏΛρΩ ΛαΛΤΛΖΛό
Λ®Λ–Ο¥≈ωΦ‘ΛΈΕλœΪΛœΖΎΗΚΛΒΛλΓΔΞ¥ΓΦΞκΛΥΛœΝαΛ·
ΛΩΛ…ΛξΟεΛ·ΛάΛμΛΠΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΞήΞ»ΞύΞΔΞΟΞΉΖΩΛΈΦη
ΛξΝ»ΛΏΛΥΛβΦΈΛΤΛ§ΛΩΛΛΧΞΈœΛ§ΛΔΛκΛ»…°Φ‘ΛœΙΆΛ®
ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΛΒΛΤΓΔ≤φΓΙΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝΓΦΞύΛœΟφΒΰ ΣΈ°ΞΜΞσ
ΞΩΓΦΛΈ«Φ… Έ®ΗΰΨεΛρΧήΜΊΛΖΓΔΕώ¬ΈΚωΛ»ΛΖΛΤΑ ≤Φ
ΛΈΜΑΙύΧήΛΈΦ¬ΜήΛρΧρΑς≤ώΛΥΡσΑΤΛΖΛΩΓΘ
ΛΙΛ ΛοΛΝ
Γ÷?±ΡΕ»Λ»ΛΈΡξ¥ϋ≈ΣœΔΆμ≤ώΒΡΛΈ≥ΪΚ≈ΓΉΓΔΓ÷?¬γΈΧ
»·ΟμΛΈ¥πΫύΛΈ≈ΐΑλΓΉΓΔΓ÷? ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΈΞΙΞΎΓΦ
ΞΙ≥Έ ίΓΉΛ«ΛΔΛκΓΘ
73ΓΓΓΓJULY 2011
ΓΓΛ≥ΛΈΛΠΛΝΓ÷?±ΡΕ»Λ»ΛΈΡξ¥ϋ≈ΣœΔΆμ≤ώΒΡΛΈ≥ΪΚ≈ΓΉ
ΛΥΛΡΛΛΛΤΛœΓΔ¥πΥή≈ΣΛΥΖνΑλ≤σΓ »ΥΥΜ¥ϋΖνΤσ≤σΓΥ
ΛΈ≥ΪΚ≈Λ»ΛΖΓΔΥη≤σΑ ≤ΦΛΈœΜΙύΧήΛΥΛΡΛΛΛΤΓΔΛΫΛλ
ΛΨΛλ ΣΈ°Λ»±ΡΕ»Λ§ σΙπΛΖΓΔΗΓΨΎΛρΙ‘ΛΠΛ»ΛΛΛΠΖΉ
≤ηΛρΡσΑΤΛΖΛΩΓΘ
Γ 1ΓΥ
Ζγ… σΙπΓ ΣΈ°ΔΣ±ΡΕ»ΓΥ
Γ 2ΓΥ
¬ΎΈ±ΚΏΗΥ σΙπΓ ΣΈ°ΔΣ±ΡΕ»ΓΥ
Γ 3ΓΥ
ΫΣ«δΨπ σ≥Έ«ß
Γ 4ΓΥ
ΩΖΒ§«Φ… άηΓ ΦηΑζάηΓΥΨπ σΕΠΆ≠
Γ 5ΓΥ
¬γΈΧ»·ΟμΗΪΙΰΛΏΨπ σΓ ±ΡΕ»ΔΣ ΣΈ°ΓΥ
Γ 6ΓΥ
»Έ¬ΞΨπ σΓ ±ΡΕ»ΔΣ ΣΈ°ΓΥ
ΓΓΓ÷?¬γΈΧ»·ΟμΛΈ¥πΫύΛΈ≈ΐΑλΓΉΛ«ΛœΗό«·ΛέΛ…ΝΑ
ΛΥΦηΛξΖηΛαΛΩ¥πΫύΛ§ΡΡ…ε≤ΫΛΖΓΔΛΪΛΡΖΝ≥Φ≤ΫΛΖΛΤ
ΛΛΛΩΛΩΛαΓΔ¬–ΨίΨΠ… ΛρΗΪΡΨΛΖΓΔΞξΞΥΞεΓΦΞΔΞκΛΙ
Λκ…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΛ≥Λ»ΛρΜΊ≈ΠΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΛόΛΩΓ÷? ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΈΞΙΞΎΓΦΞΙ≥Έ ίΓΉΛΥ¥Ί
ΛΖΛΤΛœΓΔΑ ≤ΦΛΈΛηΛΠΛ ΘΩτΛΈΝΣ¬ρΜηΛρΒσΛ≤ΛΤΖ–
±ΡΞλΞΌΞκΛΈ»ΫΟ«ΛρΕΡΛΛΛάΓΘ
ΓϋΞΜΞσΞΩΓΦΤβΛΈΜωΧ≥ΫξΛρ«―ΜΏΛΖΛΤΞΙΞΎΓΦΞΙΛρ≥Έ
ίΛΙΛκ
Γϋ¬ΎΈ±ΚΏΗΥΛρ¥όΛύΚΏΗΥΚοΗΚ
ΓϋΞΜΞσΞΩΓΦΑή≈Ψ
ΓϋΞΌΞσΞάΓΦΡΨΝςΛΈΩδΩ
ΓϋΤάΑ’άηΛΥΞ≥ΞΙΞ»ΞαΞξΞΟΞ»ΛρΡσΦ®ΛΖΛΩΛΠΛ®Λ«Ϋ–
≤ΌΤϋΛΈΡ¥άΑΛρΩόΛκ
Γϋ≈Ι ΧΛΈΜ≈ §Λ±ΫηΆΐΛρΓΔœ©άΰ≤ώΦ“ΛΈΞΩΓΦΞΏΞ Ξκ
ΛΥΑή¥…ΛΙΛκ
ΓΓΧρΑς≤ώΛΈΖκ≤ΧΓΔΓ÷?±ΡΕ»Λ»ΛΈΡξ¥ϋ≈ΣœΔΆμ≤ώΒΡ
ΛΈ≥ΪΚ≈ΓΉΛ»Γ÷?¬γΈΧ»·ΟμΛΈ¥πΫύΛΈ≈ΐΑλΓΉΛΥΛΡΛΛ
ΛΤΛœΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝΓΦΞύΛΈΡσΑΤΛ§ΛΫΛΈΛόΛόΨΒ«ß
ΛΒΛλΛΩΓΘ
ΓΓΓ÷? ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛΈΞΙΞΎΓΦΞΙ≥Έ ίΓΉΛΥΛΡΛΛΛΤΛœΓΔ
ΟφΒΰ ΣΈ°ΞΜΞσΞΩΓΦΛ§ΦΪΦ“ ΣΖοΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛβΛΔΛΟ
ΛΤΓΔ≥Τ¬–ΚωΛρΦ¬ΜήΛΖΛΩΜΰΛΈ±ΤΕΝΛρΖ―¬≥ΛΖΛΤΗΓΨΎ
ΛΙΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΛ≥ΛλΛβ≤ώΒΡΛΪΛιΜΑ
ΞΪΖνΗεΛΥΛœΞ»ΞΟΞΉΛΈ»ΫΟ«Λ«ΓΔΓ÷ΞΜΞσΞΩΓΦΑή≈ΨΓΉΛΥ
Ξ¥ΓΦΞΒΞΛΞσΛ§Ϋ–ΛΩΛΈΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΠΛΖΛΤΘ–Φ“ΛΈΦηΛξΝ»ΛΏΛœΟεΦ¬ΛΥΝΑΩ ΛΖΛΤΛΛ
ΛκΓΘ
ΞΉΞμΞΗΞßΞ·Ξ»ΞΝΓΦΞύΛΈΞαΞσΞ–ΓΦΛΩΛΝΛœ¬γΛ≠Λ·
ά°ΡΙΛΖΓΔΝ¥¬ΈΚ«≈§ΛΈΜκ≈άΛ§≤ΟΛοΛΟΛΩΛ≥Λ»Λ«ΩΖΛΩ
Λ ≤ΰ≥ΉΞΤΓΦΞόΛβΗΪΛΛΫ–ΛΜΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΓΓ≤Ζ«δΕ»ΛΥΛ»ΛΟΛΤΛœ± ±σΛΈΞΤΓΦΞόΛ»ΛβΗάΛ®Λκ«Φ
… Έ®ΛΈΗΰΨεΛΥΛβΕΎΤΜΛ§Ϋ–ΆηΛΡΛΡΛΔΛκΓΘ
άηΖνΛΪ
ΛιΓΜΓΠΑλ〜ΓΜΓΠΤσΞίΞΛΞσΞ»Λ«ΛœΛΔΛκΛ§ΓΔΜΊ…ΗΛ§
ΨεΛ§ΛΟΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΣΈ°Λ§ΗΫΨλΞ«ΓΦΞΩΛρΆ―ΛΛΛΤ±ΡΕ»ΓΔ
ΙΊ«ψΛΫΛΖΛΤΞΖΞΙΞΤΞύΛΥ?ΛβΛΈΩΫΛΙ?ΛηΛΠΛΥΛ ΛΟ
ΛΩΛ≥Λ»ΛΈά°≤ΧΛάΛ»…°Φ‘Λœ…Ψ≤ΝΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
|