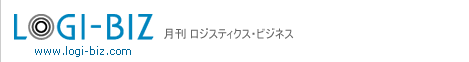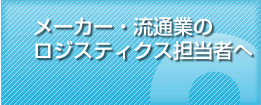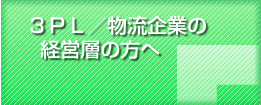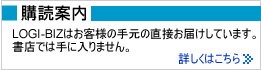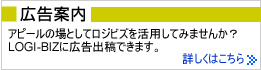|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

DECEMBER 2011ΓΓΓΓ66
ΛΣΛσΛήΛμΦ÷ΈΨΛΥ≤ΘΨηΛξΡ¥ΚΚ
ΓΓΘ
»Φ“ΛœΕαΒΠΟœ ΐΛΈΤσ…ήΜΆΗ©ΛΥΑλΓΜΞΪΫξΛΈ±ΡΕ»
ΫξΛρ≈Η≥ΪΛΙΛκΕ»Χ≥Ά―«≥ΈΝΞαΓΦΞΪΓΦΛ«ΛΔΛκΓΘ
«δΨε
ΙβΛœΧσΗόΓΜ≤·±ΏΓΘ
ΗΕΈΝΛ»Λ ΛκΫ≈ΧΐΛρΗΒ«δΛξ≤ώΦ“
ΛρΡΧΛΖΛΤΜΚΧΐΙώΛΪΛιΆΔΤΰΛΖΓΔ¬γΚε…ήΙΌ≥ΑΛΈΦΪΦ“
άΚάΫΙ©ΨλΛ«ΧσΤσΗόΓΜΞΔΞΛΞΤΞύΛΥ≤ΟΙ©ΛΖΛΤ»Έ«δΛΖ
ΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓάΫ… ΛΈΧσΕε≥δΛœάΚάΫΙ©ΨλΛΪΛιΞ®ΞσΞ…ΞφΓΦΞΕΓΦ
ΛΥΡΨάή«Φ… ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΜΡΛξΛœ±ΡΕ»ΫξΛρΖ–Ά≥ΛΖΛΤΓΔ
±ΡΕ»Ο¥≈ωΦ‘Λ§ΤάΑ’άηΛΥ«Φ… ΛΙΛκΓΘ
≤ΌΜ―ΛœΞ…ΞιΞύ
¥ΧΓΔΞήΞ»ΞκΓΔΚ≠ ώΞ±ΓΦΞΙΛ Λ…ΆΆΓΙΛ«ΓΔΤάΑ’άηΛΈ
¥ιΩ®ΛλΛβ¬γΦξΞαΓΦΞΪΓΦΛΪΛιΨΠ≈ΙΞλΞΌΞκΛόΛ«¬Ω¥τ
ΛΥΛοΛΩΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΘ
»Φ“Λ« ΣΈ°Ο¥≈ωά’«ΛΦ‘ΛρΧ≥ΛαΛκΘΝ…τΡΙΛœΛ Λ§
ΛιΛ·ΓΔΡΨΝς §ΛΈ«έΝςΛρΑ―¬ςΛΖΛΤΛΛΛκΕ®Έœ±ΩΝς≤ώ
Φ“ΛΥΛηΛκ«Φ… ΞΏΞΙΓΔΨΠ… éΞΦ÷ΈΨΜωΗΈΛΥΤ§Λρ«ΚΛό
ΛΜΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΘΝ…τΡΙΛ»«έ≤ΦΛΈΘ”≤ίΡΙΛΈΤσΩΆΛ§ΟφΩ¥
Λ»Λ ΛΟΛΤ≤ΰΝ±Λρ¬ΞΛΖΛΤΛ≠ΛΩΛ§ΓΔΞ»ΞιΞ÷ΞκΖοΩτΛœ
ΑλΗΰΛΥΗΚΛκΒΛ«έΛ§Λ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΛΫΛ≥Λ«≥Α…τΛΈάλΧγ
≤»ΛΪΛιΜΊΤ≥ΛρΦθΛ±ΛηΛΠΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛξΓΔ≈ωΦ“
ΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦΓ ΘΈΘΧΘΤΓΥΛΥΕ»Χ≥≤ΰΝ±ΛΈ
ΑΆΆξΛ§ΤΰΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΜωΝΑ¬«ΛΝΙγΛοΛΜΛΈΛΩΛαΘΝ…τΡΙΓΔΘ”≤ίΡΙΛ»ΧΧΟΧ
ΛΖΓΔΛόΛΚΛœΘ»Φ“ΛΈΆΉΥΨΛρ≥Έ«ßΛΖΛΩΓΘ
ΤσΩΆΛΈάβΧά
ΛΥΛηΛκΛ»ΓΔΞΏΞΙΛΈ¬ΩΛ·ΛœΓΔ≈Ν…ΦΛΈ≤σΦΐΥΚΛλΛ»«Φ
… ΩτΈΧΛΈ¥÷ΑψΛΛΛ«ΛΔΛξΓΔΛόΛΩΨΠ… ΜωΗΈΛδΦ÷ΈΨΜω
ΗΈΛβΨ·Λ Λ·Λ ΛΛΛΩΛαΓΔΤάΑ’άηΛΥ¬γΛ≠Λ Χ¬œ«ΛρΛΪ
Λ±ΓΔΞ·ΞλΓΦΞύΛρ»·άΗΛΒΛΜΛΤΛΛΛκΛ»ΛΈΛ≥Λ»Λ«ΛΔΛΟ
ΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΫηΆΐ»ώΆ―ΛδΧΛΦΐΕβΛΈ»·άΗΛ Λ…Λ§ΓΔΘ»Φ“
ΛΥΛ»ΛΟΛΤ¬γΛ≠Λ …ιΟ¥ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΚ«ΫιΛΈΧΧΟΧΛΪΛιΧσΑλΞΪΖνΗεΓΔ≤φΓΙΘΈΘΧΘΤΛΈΞΙ
ΞΩΞΟΞ’Λ§ΗΫΟœΡ¥ΚΚΛΥΤΰΛΟΛΩΓΘ
Θ»Φ“ΛœΕ®Έœ≤ώΦ“ΜΑ
Φ“ΓΠΖΉΤσΗό¬φΛΈΦ÷ΈΨΛρ«έΝςΛΥΜ»ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ
Μ»Ά―
Φ÷ΈΨΛΈΤβΧθΛœΞΩΞσΞ·ΞμΓΦΞξΓΦΦ÷Τσ¬φΓΔΜΆΞ»ΞσΦ÷ΦΖ
¬φΓΔΜΑΞ»ΞσΦ÷œΜ¬φΓΔΤσΞ»ΞσΦ÷ΑλΓΜ¬φΛ«ΛΔΛκΓΘ
Λ≥
ΛΈΛΠΛΝΗό¬φΛρΝΣΛ”ΓΔΛΛΛοΛφΛκ?≤ΘΨηΛξΡ¥ΚΚ?Λρ
Φ¬ΜήΛΖΛΩΓΘ
«έΝςΦ÷ΈΨΛΈΫθΦξά ΛΥΨηΛξΙΰΛσΛ«ΓΔά―
ΛΏΙΰΛΏΛΪΛιΆΔ«έΝςΓΔ≤ΌΙΏΛμΛΖΓΔ«Φ… ΓΔ≤σΦΐΛόΛ«
ΛΈΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈΑλœΔΛΈΕ»Χ≥ΛρΞΝΞßΞΟΞ·ΛΖΛΩΛΈΛ«
ΛΔΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈ≤ΘΨηΛξΡ¥ΚΚΛ§ΜΑΤϋΧήΛρΖόΛ®ΛΩΚΔΛΥΛœΓΔΞ»
ΞιΞ÷ΞκΛΈΦγΛΩΛκΗΕΑχΛ§ΛΡΛΪΛαΛΤΛ≠ΛΩΓΘ
ΗΕΑχΛΈΑλ
ΛΡΛœΙβΈπ≤ΫΛάΓΘ
Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈ¬γ»ΨΛœΗόΓΜ¬εΑ Ψε
Λ«ΓΔ ΗΜζΛΈΚΌΛΪΛ ≈Ν…ΦΛδΑ≈ΛΛΟφΛ«ΛΈ≈Ν…ΦΞΝΞßΞΟ
Ξ·Λ§…ιΟ¥ΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
≤ΟΛ®ΛΤΓΔ¬γΦξ¥κΕ»ΛΥ«Φ
… ΛΙΛκΨλΙγΛ Λ…ΛΥΛœΓΔΘ»Φ“ΛΈ«Φ… ≈Ν…ΦΛΈΛέΛΪΛΥ
¬γΦξΤάΑ’άηΗΰΛ±ΛΈΓ÷ΜΊΡξ≈Ν…ΦΓΉΛβΫηΆΐΛΖΛ Λ±Λλ
ΜωΈψΛ«≥ΊΛ÷
ΗΫΨλ≤ΰΝ±
ΤϋΥήΞμΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦ
άΡΧΎάΒΑλΓΓ¬ε…Ϋ
ΓΓΕ®Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΥΛηΛκ«Φ… ΓΔΞœΞσΞ…ΞξΞσΞΑΛΈΞΏΞΙΓΔΦ÷ΈΨΜωΗΈ
≈υΛΈΞ»ΞιΞ÷ΞκΛ§¬ΩΛ·ΓΔΑλΗΰΛΥΙΞ≈ΨΛΙΛκΒΛ«έΛ§Λ ΛΛΓΘ
Ε»ΛρΦ―Λδ
ΛΖΛΩ≤ΌΦγΛ§Φ“≥ΑΛΈΞ≥ΞσΞΒΞκΞΩΞσΞ»ΛΈΦξΛρΦΎΛξΓΔ≤ΰΝ±ΛΥΥήΙχΛρ
ΤΰΛλΛκΛ≥Λ»ΛΥΓΘ
Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈΕ»Χ≥Φ¬¬÷ΛρΡ¥ΛΌΛΩΛ»Λ≥ΛμΓΔΆΫΝέ
Α ΨεΛΥΜω¬÷ΛœΩΦΙοΛάΛΟΛΩΓΘ
«≥ΈΝΞαΓΦΞΪΓΦΘ»Φ“ΛΈΆΔΝς… ΦΝ≤ΰΝ±
¬η107 ≤σ
67ΓΓΓΓDECEMBER 2011
Λ–Λ ΛιΛΚΓΔΚνΕ»Λ§»ΥΜ®Λ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ≤Ό ΣΛΈά―ΛΏΙΰΛΏΜΰΛΈΩτΈΧΗΓ… Λβ≈ΈάώΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
Ϋ–Ε–Μΰ¥÷Λ§ΟΌΛ·ΓΔΫ–»·Ξ°ΞξΞ°ΞξΛόΛ«ά―ΛΏΙΰΛΏΛρ
Ι‘ΛΟΛΤΛΛΛκΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛβΛΛΛΤΓΔΗΓ… Λρ≈ΑΡλΛΙΛκ
Λ…Λ≥ΛμΛΪΞΈΓΦΞΝΞßΞΟΞ·Λ§≤ΘΙ‘ΛΖΛΤΛΛΛΩΓΘ
«Φ… άη
Λ«ΛβΓΔΗΓΚΚΨλΛδΜώΚύΗΥΛΥΨοΟσΛΈΞΙΞΩΞΟΞ’Λ§ΛΛΛκ
ΨλΙγΛΥΛœΈ©≤ώΛΛΗΓ… Λ§Ι‘ΛοΛλΛκΛ§ΓΔΛΫΛλΑ ≥ΑΛΈ
Λ»Λ≥ΛμΛ«ΛœΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛ§ΦΪ §Λ«≥ «ΦΗΥΛΥ»¬ΤΰΛΖΓΔ
ΜωΧ≥ΫξΛ«ΦθΈΈΞΒΞΛΞσΛρΛβΛιΛΠΛ»ΛΛΛΟΛΩΛδΛξ ΐΛά
ΛΟΛΩΓΘ
«Φ… ΞΏΞΙΛ§»·άΗΛΙΛκΛΈΛβ≈ωΝ≥ΛάΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛβΓΔΞΩΞσΞ·ΞμΓΦΞξΓΦΦ÷Α ≥ΑΛΈ«Φ… ΛœΓΔΞ’
Ξ©ΓΦΞ·ΞξΞ’Ξ»Λ«ΛΈΞ―ΞλΞΟΞ»ΙΏΛμΛΖΛΪΦξΙΏΛμΛΖΛ«ΓΔ
ΙβΈπΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΥΛœΚνΕ»…ιΟ¥Λ§¬γΛ≠Λ·ΓΔΛόΛΩΫ≈
ΈΧ ΣΛΈΛΩΛαΛΥΞœΞσΞ…ΞξΞσΞΑΞΏΞΙΛΥΛηΛκάΫ… ΛΈΆν
≤ΦΓΔ«Υ¬ΜΛρΛΖΛ–ΛΖΛ–»·άΗΛΒΛΜΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΧΐΈύΛΈ
«Υ¬ΜΛœΓΔΛΫΛΈάΕΝίΛ»ΫηΆΐΛΥ¬γ ―Λ Φξ¥÷Λ§ΛΪΛΪΛκΓΘ
ΞΏΞΙΛρΛΖΛΩΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΦΪΩ»Λ§ΗΫΨλΛ«ΫηΆΐΛρΛΖΛΤΓΔ
«Φ… άηΛΥΦ’ΚαΛΖΓΔΛΫΛΈΨλΛ«¥ίΛ·ΦΐΛαΛΤΛΛΛκΞ±ΓΦ
ΞΙΛβΛΔΛΟΛΩΛ§ΓΔ¬γΛ≠Λ ΜωΗΈΛΥΛ ΛκΛ»ΓΔΘ»Φ“ΛΥΡΨ
άήΞ·ΞλΓΦΞύΛ§ΆηΛΩΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΞ·ΞλΓΦΞύΝκΗΐΛ»Λ ΛκΘ”≤ίΡΙΛœΓΔΘΝ…τ
ΡΙΛΥΝ¥ΛΤΛρ σΙπΛΖΛΤΛΛΛκΛοΛ±Λ«ΛœΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
Ε®
Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΈΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΥ¬–ΛΙΛκ≤ΙΨπΛβΛΔΛΟΛΩ
ΛΈΛΪΛβΟΈΛλΛ ΛΛΛ§ΓΔΛΫΛΈΛ≥Λ»Λ§ΆΔΝς… ΦΝΛΈ≤ΰΝ±
ΛΥΛœΞ÷ΞλΓΦΞ≠Λ»Λ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΓΓΦ÷ΈΨΛΈΫΐΛΏΛβΙσΛΪΛΟΛΩΓΘ
«≥ΈΝΛρΦηΛξΑΖΛΟΛΤΛΛ
ΛκΛΩΛαΦ÷ΈΨΛœΨοΛΥΞΣΞΛΞκΛ«±χΛλΛΤΛΛΛκΨθ¬÷Λ«ΛΔ
ΛΟΛΩΓΘ
άωΦ÷ΛœΙ‘ΛΟΛΤΛΛΛκΛβΛΈΛΈΓΔ…αΡΧΛΈΛδΛξ ΐ
Λ«ΛœΛ ΛΪΛ ΛΪ±χΛλΛ§ΆνΛΝΛ ΛΛΓΔΛύΛΖΛμάςΛΏ…’ΛΛ
ΛΤΛΛΛ·ΜœΥωΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΩΖΖΩΦ÷Λρ≈ξΤΰΛΖΛΤΛβΛΙΛΑ
ΛΥ±χΛλΛΤΛΖΛόΛΠΛ≥Λ»ΛΪΛιΓΔΕ®Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΛœΗ≈
Λ·Λ ΛΟΛΩΦ÷ΈΨΛρΘ»Φ“ΛΈΕ»Χ≥ΛΥ≤σΛΙΖΙΗΰΛ§ΛΔΛΟΛΩΓΘ
œΖΒύ≤ΫΛΖΛΩΦ÷ΈΨΛ§¬ΩΛ·ΓΔΞιΞΛΞ»άΎΛλΛδΞ―ΞσΞ·Λ§
Ζν ΩΕ―ΜΑΓΝΗόΖοΒ·Λ≠ΛΤΛΛΛΩΓΘ
Ξ÷ΞλΓΦΞ≠ΛΈΆχΛ≠Λβ
Α≠Λ·ΓΔ≤ΘΨηΛξΡ¥ΚΚΛ«ΫθΦξά ΛΥΨηΛΟΛΤΛΛΛΩ…°Φ‘Λœ
≤Ω≈ΌΛβΈδΛδ¥άΛρΛΪΛΪΛΒΛλΛκΛ≥Λ»ΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΕ®Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΛœΛΛΛΚΛλΛβΘ»Φ“Λ»ΛœΡΙΛΛ…’Λ≠Ιγ
ΛΛΛ«ΓΔΕ»Χ≥±ΩΆ―ΨεΛΈΞκΓΦΞκΛδ σΙπΛ Λ…ΛœέΘΥφΛΥ
Λ ΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
Ε®Έœ≤ώΦ“ΜΑΦ“ΛΈΛΠΛΝ±ΩΙ‘Τϋ σΛρΘ»
Φ“ΛΥΡσΫ–ΛΖΛΤΛΛΛΩΛΈΛœΑλΦ“ΛάΛ±ΓΘ
¬ΨΛΈΤσΦ“ΛœΤϋ
σΛρΦΪΦ“ΛΥΜΐΛΝΒΔΛΟΛΤΛΛΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΤβΆΤΛρΡ¥ΛΌΛΤ
ΛΏΛΩΛ»Λ≥ΛμΓΔΒ≠Ϋ“ΛœΛΛΛΛ≤ΟΗΚΛ«ΕθΆσΛβ¬ΩΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΙβΈπΦ‘ΛΥ«έΈΗΛΖΛΤ≈Ν…ΦΞλΞΛΞΔΞΠΞ»ΛρΫΛάΒ
ΓΓΛ≥ΛλΛιΛΈΡ¥ΚΚΖκ≤ΧΛρΘΝ…τΡΙΛ»Θ”≤ίΡΙΛΥ σΙπΛΖ
ΛΩΓΘ
ΛΫΛΈΤβΆΤΛΥΤσΩΆΛœΕΟΛ≠Λρ±ΘΛΜΛ ΛΪΛΟΛΩΓΘ
ΛΫ
Λ≥ΛόΛ«Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈΕ»Χ≥Λ§…‘Α¬ΡξΛΪΛΡΞκΓΦΞΚΛ«
ΛΔΛκΛ»ΛœΩ°ΛΗΛ§ΛΩΛΛΛ»ΛΛΛΟΛΩ…ΫΨπΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΡΧ
ΨοΛΈΆΔ«έΝς¥…ΆΐΛ«ΛœΫ–»·ΜΰΛΈΨθΕΖΛΖΛΪΗΪΛκΛ≥Λ»
Λ§Λ«Λ≠Λ ΛΛΛΩΛαΓΔΦ¬¬÷ΛρΡœΛαΛΤΛΛΛ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛ«
ΛΔΛκΓΘ
DECEMBER 2011ΓΓΓΓ68
ΓΓΗεΤϋΓΔ≤φΓΙΛœΦΓΛΈΙύΧήΛρ≤ΰΝ±ΚωΛ»ΛΖΛΤΘ»Φ“ΛΥ
ΡσΦ®ΛΖΛΩΓΘ
ΛΛΛΚΛλΛβ¥πΥή≈ΣΛ ΦηΛξΝ»ΛΏΛ«ΛΔΛκΛ§ΓΔ
ΛΫΛΈ≈ΑΡλΛ§…§ΆΉΛ»»ΫΟ«ΛΖΛΩΓΘ
?Θ»Φ“«Φ… ≈Ν…ΦΛΈ≤ΰΝ±
?±ΩΙ‘Τϋ σΡσΫ–ΛΈΒΝΧ≥≤Ϋ
?Γ÷ΆΔΝς… ΦΝΗΰΨεΞΏΓΦΞΤΞΘΞσΞΑΓΉΛΈΡξ¥ϋ≥ΪΚ≈
?Φ“ ΧΓΠΟ¥≈ωΦ‘ ΧΞΏΞΙΓΠΜωΗΈΞΑΞιΞ’ΛΈΡΞΛξΫ–ΛΖ
?ΜΊΚΙΛΖΗΓ… Γ ΩτΈΧΓΥΛΈ≈ΑΡλ
ΓΓΛ≥ΛΈΛΠΛΝΓ÷?Θ»Φ“«Φ… ≈Ν…ΦΛΈ≤ΰΝ±ΓΉΛœΓΔ≈Ν…Φ
ΛΈΞλΞΛΞΔΞΠΞ»ΛρΙβΈπΦ‘ΛΥΛβΗΪΛδΛΙΛ·ΛΙΛκΛ≥Λ»Λ«ΓΔ
Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΈΤ…ΛΏ¥÷ΑψΛΛΛρΗΚΛιΛΙΛ≥Λ»Λ§Χή≈ΣΛ«
ΛΔΛκΓΘ
ΤάΑ’άηΛΈΜΊΡξ≈Ν…ΦΛρΘ»Φ“Λ«ΨΓΦξΛΥ ―ΙΙΛΙ
ΛκΛ≥Λ»ΛœΛ«Λ≠Λ ΛΛΛ§ΓΔΘ»Φ“Λ§»·Ι‘ΛΖΛΤΛΛΛκ«Φ…
≈Ν…ΦΛ«ΛΔΛλΛ–ΓΔΛΙΛΑΛΥΛβΫΛάΒΛ«Λ≠ΛκΓΘ
ΓΓΕώ¬Έ≈ΣΛΥΛœΓΔΜφΛΈΞΒΞΛΞΚΛœ ―ΙΙΛΜΛΚΛΥΓΔ ΗΜζ
ΛρΑλ≤σΛξ¬γΛ≠Λ·ΛΖΓΔΙ‘ΩτΛβΫΫΤσΙ‘ΛΪΛιΦΖΙ‘ΛΥΗΚ
ΛιΛΖΛΩΓΘ
ΛΫΛΖΛΤΙ©ΨλΤβΛΈΞ‘ΞΟΞ≠ΞσΞΑΞξΞΙΞ»Λ»Τ±
ΆΆΛΥΓΔΩτΈΧΗΓ… ΛΈΙ‘ΥηΛΈΞΝΞßΞΟΞ·ΆσΛ»≈ωΜωΦ‘ΛΈ
ΫπΧΨΆσΛράΏΛ±ΛΩΓΘ
ΓΓΓ÷?±ΩΙ‘Τϋ σΡσΫ–ΛΈΒΝΧ≥≤ΫΓΉΛΥ¥ΊΛΖΛΤΛœΓΔΕ®
Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΥ≤ΰΛαΛΤΞκΓΦΞκΛρ≈ΝΛ®ΛκΛ»Τ±ΜΰΛΥΓΔ
Θ»Φ“¬ΠΛ«ΛβΕ®Έœ≤ώΦ“ΛΪΛιΡσΫ–ΛΒΛλΛΩΤϋ σΛΈ¥…Άΐ
ΛρΓΔ ΣΈ°¥…Άΐ…τΧγΛΈΤϋΨοΕ»Χ≥ΛΈΛ ΛΪΛΥΧά≥ΈΛΥΑΧ
Ο÷…’Λ±ΛΩΓΘ
ΓΓΦ÷ΈΨ¥…ΆΐΛΥ¬–ΛΙΛκΫ≈ΆΉά≠Λρ¬ΞΛΙΝάΛΛΛΪΛιΤϋ σ
ΛΥΛœΓΔ≥ΤΦ÷ΈΨΛΈΫ–»·ΝΑ≈άΗΓΛΈΓ÷ΧΛΓΉΓΔΓ÷Κ―ΓΉΛρ…§
ΛΚΤΰΛλΛΤΛβΛιΛΠΛ≥Λ»ΛΥΛΖΛΩΓΘ
ΛΫΛΖΛΤ«Φ… ΗεΛΈΦ÷
ΈΨΛœΘ»Φ“ΛΥΧαΛιΛΚΓΔΕ®Έœ≤ώΦ“≥ΤΦ“ΛΈΦ÷ΗΥΛΊΡΨάή
ΧαΛκΛ≥Λ»Λ»Λ ΛΟΛΤΛΛΛκΛΩΛαΓΔ≥ΤΦ“ΛΈΜωΧ≥ΫξΛΪΛι
Θ»Φ“ΛΊΞ’ΞΓΞΟΞ·ΞΙΛΙΛκΛ»ΛΛΛΠΈ°ΛλΛρΚΈΛΟΛΩΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛρΘ»Φ“¬ΠΛ«ΛœΘ”≤ίΡΙΛ§ΞΝΞßΞΟΞ·ΛΖΛΤΓΔ≥Τ
Φ÷ΈΨΛΈ±ΩΙ‘ΒςΈΞΓΔ«Φ… ΖοΩτΓΔΜΡΕ»Μΰ¥÷Λρ«ΡΑ°ΛΙ
ΛκΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΛΥΘ”≤ίΡΙΛΈΕ»Χ≥ΛΈΑλ…τΛρΞ―ΓΦΞ»Φ“
ΑςΛΥΩΕΛξ¬ΊΛ®ΛΤΓΔΩΆΑςΛρΝΐΛδΛΙΛ≥Λ»Λ Λ·ΓΔ ΣΈ°
¥…ΆΐΙύΧήΛΥ±ΩΙ‘¥…ΆΐΛρΡ…≤ΟΛΖΛΩΓΘ
ΓΓΓ÷?ΆΔΝς… ΦΝΗΰΨεΞΏΓΦΞΤΞΘΞσΞΑΓΉΛœΓΔΛΫΛλΛό
Λ«ΛΈ?¥ί≈ξΛ≤?Λρ≤ΰΛαΓΔΖνΑλ≤σΓΔΥηΖν¬ηΜΑ≈ΎΆΥ
ΤϋΛΈΗαΗεΛΥΓΔ≤ΌΦγΛ»Ε®Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΜΑΦ“ΛΈά’«ΛΦ‘
Λ§Τ±ΛΗΞΤΓΦΞ÷ΞκΛρΑœΛσΛ«ΓΔ≤ΰΝ±ΛρΩ ΛαΛΤΛΛΛ≥ΛΠ
Λ»ΛΙΛκΛβΛΈΛάΓΘ
Θ”≤ίΡΙΛ§Μ ≤ώΧρΛρΧ≥ΛαΓΔ≈ωΧΧΛœ
ΘΝ…τΡΙΛβΤ±ά ΛΖΓΔΦγΛΥΑ ≤ΦΛΈΒΡ¬ξΛΥΛΡΛΛΛΤΤΛΒΡ
ΛΙΛκΓΘ
ΓϋΝΑΖνΛΈΞΏΞΙΓΔΜωΗΈΖοΩτΓΔΨθΕΖΛΈ σΙπ
ΓϋΛΫΛλΛΥ¬–ΛΙΛκ≤ΰΝ±≈άΓΔΟμΑ’≈άΛΈΜΊΦ®
Γϋ«Φ… άηΛΪΛιΛΈΑ’ΗΪΓΠΆΉΥΨΓΠ…Ψ≤ΝΛΈ≈ΝΟΘ
ΓΓΓ Ξ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΔΣΘ»Φ“ΓΔΘ»Φ“ΔΣΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΓΥ
ΓϋΚΘΖνΛΈΆΫΡξΓΔΟμΑ’ΜωΙύ
≤ΌΦγΛΈ≥–ΗγΛ§Ε®Έœ≤ώΦ“ΛρΤΑΛΪΛΙ
ΓΓΓ÷?Φ“ ΧΓΠΟ¥≈ωΦ‘ ΧΞΏΞΙΓΠΜωΗΈΞΑΞιΞ’ΓΉΛœάΚ
άΫΙ©ΨλΛΈΫ–≤ΌΞΙΞΎΓΦΞΙΛΥΈΌάήΛΖΛΤΗΫΨλΜωΧ≥ΫξΝΑ
ΛΥ¬γΛ≠Λ·ΡΞΛξΫ–ΛΙΛ≥Λ»ΛΥΛΖΛΩΓΘ
≈ωΫιΛœΞ…ΞιΞΛΞ–
ΓΦΛΈΗΡΩΆΧΨΛόΛ«ΡΞΛξΫ–ΛΙΛΈΛœΛδΛξ≤αΛ°Λ«ΛœΛ ΛΛ
ΛΪΛ»ΛΛΛΠΑ’ΗΪΛβΫ–ΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔΞ»ΞιΞ÷ΞκΛ§…―»·
ΛΖΛΤΛΛΛκΗΫΨθΛ«ΛœΛδΛύΛρΤάΛ ΛΛΦξΟ Λ«ΛΔΛξΓΔ≥Ϊ
Φ®ΛΥ¬―Λ®ΛιΛλΛ ΛΛ≤ώΦ“ΛβΛΖΛ·ΛœΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΥΛœ
¬ύΨλΛΖΛΤΛβΛιΛΠΛΖΛΪΛ ΛΛΛ»≥–ΗγΛρΖηΛαΛΩΓΘ
ΓΓΓ÷?ΜΊΚΙΛΖΗΓ… Γ ΩτΈΧΓΥΛΈ≈ΑΡλΓΉΛœΓΔΩτΈΧΗΓ
… ΛΈΛδΛξ ΐΛ»ΛΖΛΤ?ΜΊΚΙΛΖ?Λ»ΛΛΛΠΕώ¬Έ≈ΣΛ ΤΑ
ΚνΛρΜΊΡξΛΙΛκΛ»Λ≥ΛμΛ§ΞίΞΛΞσΞ»ΛάΓΘ
≈ωΫιΛœΓ÷ΞΣ
ΞόΞ®ΛΈΩτΛρΤ…ΛύάΦΛ§¬γΛ≠ΛΙΛ°ΛΤΞΣΞλΛ§ΩτΛ®ΛιΛλ
Λ ΛΛΓΣΓΉΛ»¬ΨΛΈΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛΪΛι≈ήΛιΛλΛΤΛΛΛκΦ‘Λβ
ΛΛΛΩΓΘ
¬γ»ΨΛ§ΙβΈπΦ‘Λ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛβΛΔΛΟΛΤΓΔΩΖΛΖ
ΛΛΛδΛξ ΐΛΥ¥ΖΛλΛκΛΥΛœΨ·ΓΙΜΰ¥÷ΛρΆΉΛΖΛΩΛ§ΓΔΛΫ
ΛλΛ«ΛβΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛœΝμΛΗΛΤΕ®Έœ≈ΣΛ«ΓΔΫυΓΙΛΥΡξ
ΟεΛΖΛΤΛΛΛΟΛΩΓΘ
ΓΓ≥ΪΜœΛΪΛιΜΑΞΪΖν¥÷ΛΈΦηΛξΝ»ΛΏΛ«ΓΔΜΉΛΠΛηΛΠΛΥ
ΩτΟΆΛ§ΙΞ≈ΨΛΖΛ ΛΛΨλΙγΛœΓΔΕ®Έœ±ΩΝς≤ώΦ“ΜΑΦ“ΛΈ
ΛΠΛΝΓΔΚ«Λβά°ά”ΛΈΑ≠ΛΪΛΟΛΩΑλΦ“Λ»ΛΈΖάΧσΛρΗΪΡΨ
ΛΙ ΐΩΥΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
Λ≥ΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΛœΕ®Έœ≤ώΦ“Α Ψε
ΛΥΓΔΘ»Φ“ΛΈΞΣΓΦΞ ΓΦΛ§Ω¥«έΛΖΛΤΛΛΛΩΓΘ
?Λ≥ΛσΛ
Λ¥ΜΰάΛΓ …‘ΕΖΓΥΛΥΞΠΞΝΛΈΜ≈ΜωΛ§ΧΒΛ·Λ ΛλΛ–ΓΔΛΫ
ΛΈ≤ώΦ“ΛœΡΌΛλΛΤΛΖΛόΛΠ?Λ»ΦΰΑœΛΥœ≥ΛιΛΖΛΤΛΛΛΩ
Λ»ΛΛΛΠΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔΞΣΓΦΞ ΓΦΛΈΩ¥«έΛœέΙΆΪΛΥΫΣΛοΛΟΛΩΓΘ
Φη
ΛξΝ»ΛΏΝΑΛΥΛœΥηΖνΑλΓΜΖοΑ ΨεΛΔΛΟΛΩΞ»ΞιΞ÷ΞκΛ§
ΜΑΞΪΖνΗεΛΥΛœΖνΑλΖοΡχ≈ΌΛΥ¬γΛ≠Λ·≤ΰΝ±ΛΒΛλΛΩΓΘ
ΛΫ
ΛΈ σΙπΛρΦθΛ±ΛΩΞΣΓΦΞ ΓΦΛœΓΔ?ΦΓΛœΝ¥Φ“ΛΈ ΣΈ°Ξ≥
ΞΙΞ»ΚοΗΚΛ§ΞΤΓΦΞόΛά?Λ»ΓΔ ΣΈ°¥…ΆΐΟ¥≈ωΛΈΤσΩΆ
ΛΫΛΖΛΤ≤φΓΙΘΈΘΧΘΤΛΥΡΧΙπΛΖΛΩΛΈΛ«ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΛΔΛΣΛ≠ΓΠΛΖΛγΛΠΛΛΛΝ
ΓΓ1964«·άΗΛόΛλΓΘ
Βΰ≈‘ΜΚΕ»¬γ≥Ί
Ζ–Κ―≥Ί…τ¬¥Ε»ΓΘ
¬γΦξ±ΩΝςΕ»Φ‘ΛΈ
ΞΜΓΦΞκΞΙΞ…ΞιΞΛΞ–ΓΦΛρΖ–ΛΤΓΔ89«·
ΛΥΝΞΑφΝμΙγΗΠΒφΫξΤΰΦ“ΓΘ
ΣΈ°≥Ϊ
»·ΞΝΓΦΞύΓΠΞ»ΞιΞΟΞ·ΞΝΓΦΞύΞΝΓΦΞ’
ΛρΧ≥ΛαΛκΓΘ
96«·ΓΔΤ»Έ©ΓΘ
ΤϋΥήΞμ
ΞΗΞ’ΞΓΞ·Ξ»ΞξΓΦΛράΏΈ©ΛΖ¬ε…ΫΛΥΫΔ
«ΛΓΘ
ΗΫΚΏΛΥΜξΛκΓΘ
ΦγΛ ΟχΫώΛΥΓΊΖ–
±ΡΛΈΞΤΞ≥ΤΰΛλΛœ ΣΈ°≤ΰΝ±ΛΪΛιΓΌΧά
ΤϋΙαΫ–»«Φ“ΓΔΓΊ ΣΈ°ΛΈΛΖΛ·ΛΏΓΌΓ Τ±
Η¥έΫ–»«ΓΥΛ Λ…Λ§ΛΔΛκΓΘ
HP:http://www.nlf.co.jp/
e-mail:info@nlf.co.jp
PROFILE
|