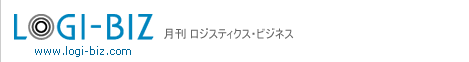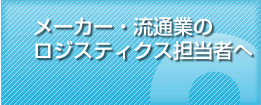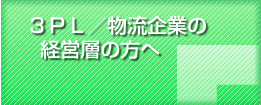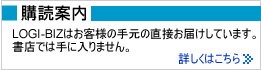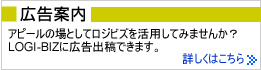|
*������PDF���ƥ����Ȥ���Ф����ǡ����Ǥ���������PDF������������

APRIL1 2012����52
ŷ�������֤ν�ͭ�����������
��������ؤ�����ǯ�٤ޤǤˡ��ãϣ���
���ӽ��̤���ǯ�����ϻ��︺������ɸ��
�Ǥ��Ƥ��롣
������ɸ�ͤϡ��������絬�Ϥ�
�����Ķ��ݸ����Ρ֣ףףơ����������ݸ��
��ˡפȼ�����Τ���
�ףףƤ�������
ʪ���ݸ����Ū�˰��ϻ��ǯ����Ω���졢��
�ߤϤ����о��ΰ���ϵ�Ķ������ˤޤǹ���
������졻������dz�ư���Ƥ��롣
���
ףףƤ������ǯ�˥������Ȥ����֥���
����ȡ������С����ץ������פϡ����
�ȤΥѡ��ȥʡ����åפˤ�ä��ϵ岹�Ȳ���
�ߤ˼���Ȥ�Ȥ�����ˡ����ʳ�ư����
�ץ�
�����˻��ä����Ȥ��ףףƤȤ��ä��礤
�ǽ������⤤��ɸ�����ꤷ�Ʋ������̥�
���κ︺��ʤᡢ���μ»ܾ����ˤĤ����軰
�Ե��ؤ����ڤ�Ԥ���
���Ķ���ư�ˤ����Ƴƶȳ��Υȥåץ��ʡ�
���ܻؤ���Ȥ�������ˤ��뤳�Ȥ��ӽ�
�︺��ư���Ƥߤ�Ĥ���ȤȤ�ˡ��軰�Ԥ�
���ڤˤ�äƴ�Ȥμ���Ū�ʳ�ư��Ʃ������
��������Ϳ���褦�Ȥ������������롣
�����
�Ǥ������ƹ���δ�Ȥ��ץ������˻�
�ä��Ƥ��롣
��������ؤϡ���ǯ�����ܴ�Ƚ顢��͢��
�ҤȤ��Ƥ������ǽ�˥��饤��ȡ�������
�����ץ������ؤ�Ĵ����Ԥä���
���κݤ�
���ꤷ���Τ���Ƭ�Ρְ졻ǯ�֤��ӽ��̤�
ϻ��︺����פȤ���Ĺ����ɸ����
���ӽк︺��ɸ�ˤĤ��ƹ���ξʥ���ˡ�ʤ�
�ϡ����ͥ륮�������̤�����ʤɤdz�ä�
�ָ�ñ�̡פˤ�ä����ꤷ���︺���Ϥ�����Ū
��ɾ��������ˡ��ȤäƤ��롣
���Τ��ᡢ��
��夲�ο��ӤȤȤ�˥��ͥ륮���λ����̤�
�����Ƥ⡢��������ʬ�����夲�ο��Ӥ�
���и�ñ�̤�������ɸ��ã���Ǥ��롣
��������Ф����饤��ȡ������С����ץ�
�����Ǥϡ����ӽ��̡פȤ��������̤���ɸ
�ͤ����ꤹ�롣
���äƶ��Ӥο��Ӥ��礭����
����ɸã���ؤΥϡ��ɥ�Ϲ⤯�ʤ롣
���������ץ������Υ������ȸ�˺�����ؤ�
�͡����ˤ�äƴ���͢�������Ҷ���ʪ��
�ȤΥ��롼�״�Ȥ�ۼ����Ƥ��롣
���η�̡�
����ޤǻ�����оݳ����ä��ãϣ��ӽ��̤�
����ʬ�˲ä�뤳�Ȥˤʤä���������ˤĤ�
���Ķ��ʤΥȥ饤������Ȥ˻��褷��ʪή�ȳ���
�Ρ֥����ܥ˥塼�ȥ��פ�ǧ�ڼ������ܻ�
����
��֤ǽ��ۤ�Ԥ��Ի����Ρ֥����ӥ�����
���פ��оݤˡ�����CO2�ӽ��̤Ф������롼
�פ���ͭ���뿹�Ӥ�������������ư�Ǽ���������
�쥸�åȤǴ������껦���롣
�Ķ��к�
�������
�ȳ���Ρ֥����ܥ˥塼�ȥ����ܻؤ�
����������ư�Ǽ����������쥸�åȤ�����
�֤���¾�פϡ�������ؤ���ͭ���Ƥ���ǥ�������֤����ʿ��27
ǯ��dz����ã���֤�ʿ��17 ǯ���ӥ�������Ŭ��֤ι�����
�������Ƴ���ο��
�����
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
��02 ��03 ��04 ��05 ��06 ��07 ��08 ��09 ��10
1,110 1,647 2,197 2,693
49
3,290
52
304
3,695
86
4,254
100
4,355
100
4,349
99
26
39
61
1,716
4,417
4,835
5,598
����¾
�ϥ��֥�åɼ�
ŷ�������ȥ�å�
53����APRIL 2012
�ƤϣףףƤȤμ����ǡ���ɸã����ɾ��
�ϴ��ǯ�ʡ���ǯ�١������λ����ϰϤǤ���
�ӽ��̤��Ȥ˹ԤäƤ褤�Ȥ��줿��
��������ؤμ谷��ʪ�̤�ǯ������³���Ƥ�
�롣
�����ؤ�ǯ�ּ谷�Ŀ��ϥ������Ȼ�����
�٤��Ķ��������
�ãϣ��ӽФ�������
��ϻ��︺����Ȥ�����ɸ�ϡ��ˤ�ƹ⤤��
�ͤȸ����롣
������ꥢ���뤿��ν����ܺ��Ȥ���Ʊ
�ҤϤ���ޤǡ��ǥ�������֤���٣ãϣ��ӽ�
�̤���侯�ʤ�ŷ�������֤�Ƴ����ʤ�Ƥ�
����
�ץ�������Ĵ�����ˡ�����ǯ�٤ޤǤ�
�߷פǼ����������Ƴ��������ɸ��Ǥ�����
�������ã���ؤΥХ�������ˤ��Ƥ��롣
�������Ѥ�ŷ��������Ŷ������ɤ�ĶȽ��
���֤���ʤɴĶ�������Ʊ���˹Ԥ����졻ǯ
�ټ��ӤǤ���ͭ������ͻ��Ͷ���ޤ���������
����ˤ�äƺ�ǯ��Ʊ�ҤϹ��ŷ��������ư
�ֶ��������ǺǤ�ŷ�������ȥ�å�����
ͭ�����ȤȤ���ǧ�ꤵ��Ƥ��롣
�����Τۤ���������֤�Ʊ�����ѤΥ����
�ʲ�ʪ��֥֡����ѡ��졼�륫�����פ����餻
��ʤɥ⡼���륷�եȤˤ��Ѷ�Ū�˼���Ȥ��
������
�ޤ����ɥ饤�С����Ф���ž��ε�ȯ
�ʡ���®���ޥ֥졼���������䥢���ɥ��
�����ȥåפμ»ܤ�¥���֥��������ɥ饤�֡�
��ư�⡢dz�����Ѥ������ˤĤʤ�����ƻ�ʼ�
���Ȥߤΰ�Ĥ���
������˶�ǯ�ϡ��ȥ�å����������֤�
���ؼ�ž�֤�Ȥäƽ��ۤ�Ԥ��֥����ӥ���
���פ����ԻԷ����Ի����˽���Ÿ������
���ꡢ�����ãϣ����ӽк︺�˰�����ä�
���롣
������ϻԶ�Į¼ñ�̤ǹٳ��δ���ƻϩ�褤
�ʤɤˡֱĶ�Ź�פ����֤����ȥ�å��ǥ���
����ν��ۤ�Ԥ��Τ����ܤ��ä���
�������
�������ӥ������ϡ����ܡ�ñ�̤dz����
���֤���Ⱦ�°쥭������ξ����ʽ��ۥ��ꥢ
�С����롣
�����ε��Ϥϥ���ӥ˥���
�����ȥ��¤ߤǡ��Ķ�Ź���ɳ����륨�ꥢ��
������ô���������Ȥ�Ķ�Ź���饻��
�ز�ʪ����������֤ʤɤ��������롣
����Ȥ�ȡ����ڤˤ�뽸�۸�Ψ�ΰ�������
���Ķ��ؤ���٤��㸺���뤿��ˡ��Կ��Υ�
�ե��������˲ڳ����濴�����֤��Ƥ�����Ρ�
��ϻǯ��ƻϩ����ˡ������ϩ��βٻ������
���Ф��������꤬�������ʤꡢ�����к���
��ĤȤ����ߤ���¦�̤⤢�롣
�Ի����ν��ۤǤϡ�æ�ȥ�å���
��������ǯ�����ξ��ʤ�Ϥ���Ȥ����
to
��
���ۡפλ��ȴ��פ�������Ū�ǥ����ӥ�
�������������®�������Ƥ��롣
�Ŀ���
�ؤ�������̳���������ʤɤ��ղå����ӥ�
��ȼ���������ӻ����Ϥ���ܵҤΤ��ޤ���
����˾�˱�����ɬ�פ����롣
�Ķ�Ź����ȥ�
�å��ǹ���ν��ۤ�Ԥ����⡢ƻϩ�����
��������ʤ������ӥ������Τۤ�����
�ϰ��̩�夷������Ǥ���٤����б����Ǥ�
�뤫�����
���졻ǯ�٤����Ʊ�Ҥ�����бķײ�Ǥ⡢
��
to
�����ۤ˶���͢��������ե�ι��ۡפ��
������ΰ�Ĥ˵����ζ��κ��Ȥ��ơ֥�
���ӥ������פʤɤξ�����Ź�ޤ�������
���䤹���ˤ��Ǥ��Ф�����
����ޤǤ����Ի�
���������μ����ԻԤ��濴�˻͡���Ź�ްʾ�
�Υ����ӥ�������Ÿ����
�Կ��ʤɤξ���
�϶�Ǥϸޡ�����ȥ뤪���˿��������֤�
�Ƥ�����⤢�롣
��Ʊ�ҤϤ��Υ����ӥ��������ǥ�ˡ�
��ǯ�λ����֥����ܥ˥塼�ȥ��פ�
��������ü�δĶ���ư�˼���Ȥ�Ǥ��롣
�������ܥ˥塼�ȥ��Ȥϡ���Ȥʤɤ�
�������̥������ӽк︺���Ϥ�Ԥä������ǡ�
�︺�Ǥ��ʤ��ä��ӽ��̤����̤�ۤ����ӽ�
�︺���ۼ���ư�ˤ�äƺ︺�����ӽ��̤ǥ�
�ե��åȡ��껦�ˤ��뤳�Ȥ���
�ӽ��̤�
�������껦����֥����ܥ��ե��åȡפ�
�����Ƨ�߹��������Ȥߤ���
�����ƤǤϰ��強ǯ�˥����ܥ��ե���
�Ȥλ��Ȥߤ���ȯ����ưʹߡ���ʴ�Ȥ��
���ΣǣϤ��濴�ˤ�����ڤ���¤˿ʤߡ���
���ܥ˥塼�ȥ��ˤĤ��Ƥ⡢��ȥ��
��ǿ�ʤ˼���Ȥ�ư�����ФƤ��Ƥ��롣
�����ܤǤϡ�Ȭǯ�˴Ķ��ʤ������ܥ���
���åȤ���ڳ�ư�Ϥ���ƱǯȬ��˥���
���åȤ��Ѥ����ӽк︺���ۼ��̤�ǧ�ڤ���
����Ρ֥��ե��åȡ����쥸�åȡʣʨ��
֣ţҡ�
���١פ����ߤ�����
��ǯ��������ߤǰ컰��
��Υ��쥸�åȤ�ǧ�ڤ���Ƥ��롣
APRIL 2012����54
�������Ʊ�ʤϺ�ǯ�ͷ����μ���Ȥߤ�
�����¤ߤ˳����������뤳�Ȥ�������������
�˥塼�ȥ��θ�Ƥ�����Ȥ�����
��
��ˡ֥����ܥ˥塼�ȥ��ǧ�����١פ�
���ߡ����μ��Ӻ��Τ���ˡ�ǧ�ڼ�������
�ؤ����ȼԤλٱ����Ū�Ȥ����Ի��Ȥ���
����Ԥä���
��������ؤϤ��λ��Ȥˡ��֥����ӥ�����
�α��Ѥ�ȼ���ãϣ��ӽ��̤����̤��Ӥ���
���������ˤ�äƵۼ������ӽ��̤ǥ��ե���
�Ȥ���פȤ�������ȤߤDZ��礷���ۤ��λ�
��ȤȤ�˺��줿��
ʪή�ȳ�����λ���
��Ʊ�Ҥ�������
���ޤ���Ʊ�Ҥϡ����롼�פǽ�ͭ���뿹�Ӥ�
������ư�ˤ�äƼ��������֥��ե��åȡ���
�쥸�åȡפλȤ�ƻ��Ƥ���Ƥ���Ȥ�����
���
��������˥����ܥ˥塼�ȥ��ǧ
�ڻ�Ի��Ȥθ�����Τꡢ���쥸�åȤ�
�ܥ˥塼�ȥ��Ȥ�������ʤ���Ķ���
ư�˳��Ѥ��뤳�Ȥ��դ�����
��������إ��롼�פκ����ӶȤϻ�ι���
�������縩�˹�碌��ϻȬ�ޥإ�������ο�
�Ӥ���ͭ�����ϸ��ο����ȹ�Ȥζ�Ư�ǰ�
����������ư��ԤäƤ��롣
��ǯ�μ������
���ˤ��ο��Ӥ��ʨ��
֣ţҤˤ�겹�����̥�
���εۼ����Ȥ���ǧ�ꤵ�졢�졻���������
ǯ�֤εۼ��̤ˤ��������ϻ�����ȥ�ʬ�Υ�
�ե��åȡ����쥸�åȤ����������
��������ؤϻ��ȳ�ư�ʤɤˤ��ǯ�֤˻�
�졦Ȭ���ȥ�ʰ졻ǯ�ټ��ӡˤΣãϣ�����
�Ȥˤ��ꡢ�����ܥ˥塼�ȥ��μ����
�ߤ�Ҳ�˥��ԡ��뤷�䤹���ȹͤ�����
�������ӥ�������쥫���ߤ���ȡ��Ķ�
Ź�ν��ۥ��ꥢ�ΰ�����������ͥȥ�å���
��ʬ����������������֤ˤ���������Ѥ�ꡢ
����ʬ�Σãϣ��ӽ��̤�︺�Ǥ��롣
������
�Ķ�Ź���饻���ؤϥȥ�å��Dz�����͢
���뤿�ᡢ����ˤ�äƣãϣ����ӽФ���
�롣
�����Ǥ��ŵ��λ��Ѥ�ȼ���ãϣ���ȯ
�������ʤ���
�����ܥ˥塼�ȥ��
�ϡ������٤ƥ��쥸�åȤ��껦������
�����ӽ��̤��ˤ������Ȥߤ���
��ȯ�ƼԤ�ݯ������Ķ���ʲݷ�Ĺ�ϡ�����
�ǤϤޤ������ܥ��ե��åȤǤ���ǧ����
���㤤��
�ʰ���ʤ���˥����ܥ˥塼�ȥ�
��ʹٳ��ε����ǤϤʤ��˰��̤Τ�����
�˶ᤤ�����ӥ������Ǽ»ܤ��ơ�����Ȥ�
�����Ƥ��ΤäƤ�餦�յ����礭���פȶ�Ĵ
���롣
����Ի��Ȥ����Ȭ�Ž������Ի;�ʡ��
��¿�λ��϶�Υ����ӥ������ǻ������
���˥������Ȥ�����
������оݤϻ��϶�Ǥ�
�ĶȽ�������֤�͢���ȥ������ŵ�
�Ф��Ƥ��롣
�ʨ��
֣ţҤ�ǧ�ꤵ�줿���Ӥˤ�
��ۼ��̤ΰ�ǯʬ��Ȭ�����ȥ�ϡ����Ρ���
ϻ������������롣
�ʥ���ˡ�ǵ�̳�դ����
�Ƥ����ǯ�֤˰��︺�������ɸ�μ����
���������ã���Ǥ��������
��Ʊ�Ҥϼ����������ե��åȡ����쥸�åȤ�
ͭ�����Ѥ��뤿��ˡ������������ӥ����ʤ�
��ȯ��Ƥ���Ƥ�����
�������Ω��Ʊ�Ҥϴ�
����ư�ΰ�Ĥǡ���Ϣ��ǧ�ꤹ��֥���ɡ�
���ߥ�����������ȯ�ťץ��������ȡפ��Ͻ�
���줿�ãϣ��ӽи������������Ȭǯ������
�ζȼԤȶ�Ʊ�ǡ֣ãϣ��ӽи��դ���������
�ءפ��ʲ����Ƥ��롣
�����ξ��ʤι����Ԥ��������ۥ����ӥ�����
�Ѥ���ȡ���Ĥ������͢�����ӽФ����ʬ
���ӽи���������ؤ����������ܤ�̵������
���졢���Ե������ӽк︺ʬ�Ȥ��ƥ�����
�Ȥ����Ȥ������Ƥ���
Ʊ�ҤΥ����ӥ�����
���ƾ���Ԥ˴Ķ��ؤι����ʤ�����������
���
�����ӥ�������ǧ�ڤ��оݤ�
�������ܥ˥塼�ȥ�����٤�ǧ�ڤ����
��ˤϡ��оݴ��֤��о��ϰϤ����ꤷ���ӽ�
�̤λ����Ԥ������ǯ���Ф���︺���Ϥ�
���̲����������ǡ��ӽ��̤����̤ե���
�Ȥ���Ȥ�������Ƨ�ࡣ
�����μ���Ȥߤ˺Ǥ�դ��路�������Ȥ���
Ʊ�Ҥϥ����ӥ��������������
������
������ͳ�ΰ�Ĥϣãϣ����ӽ��̤餹��
������ؤ�ݯ������
�Ķ���ʲݷ�Ĺ
55����APRIL 2012
�åȤο��̤����ꤷ�ʤ���Фʤ�ʤ���
�����ǯ���ӽ��̤ϡ����������֤�����
���о��϶���������Ƥ����ȥ�å�����ǯ��
�˻��Ѥ���dz�����Ȥ˻��Ф�����
�Ķ�Ź
�Ǥϰ�����ʲݤȤ������𤬱��Դ�����Ԥ���
�ɥ饤�С��α�ž������Ȥ˼�ξ���椺��
�����Ե�Υ��롼�ȡ������̤ʤɤ��İ�����
���롣
���Υǡ���������ǯ���ӽ��̤λ���
����ǽ�ˤʤä���
�����֤�Ϣ�Ȥ����
���оݴ��֤��ӽ��̤λ�ˤ�dz��ˡ���Ѥ�
����
������͢�������ξ���������ꤷ����
��Ź���饻���ޤǤε�Υ�ȱ������ؿ���
��͢����Υ��Ф���dz��dz�ä�dz��������
���������
�����ǯ���ӽ��̤����϶�ι�פǼ����ȥ�
���ä��Τ��Ф����оݴ��֤β�����͢������
�����Ѥ��碌���ӽ��̤ϻ͡��ȥ�˸����
����Ƥ��롣
���λ͡��ȥ�쥸�åȤ�
���ե��åȤ��롣
�����϶�Τ���ʡ����¿�϶�Ǥϡ��쥻��
���ǤϤʤ��ʣ���¿�ؼ��դˤ���ޥ���Υ�
�����о��ϰϤˤ�����
�����ӥ�����
�ϥ��ڡ��������������������������ʪ���
��Ź������٤��������뤳�ȤϤǤ��ʤ���
��
�ֻ���ʤɤΥ����ߥ�Ϥ��ä����˲���
�������ز��������롣
�������β���Ͼ�
�ʤ��ۤɴĶ��ˤȤä�˾�ޤ��������ҤΥˡ�
���ˤ���٤����б�����ȱĶ�Ź�Ȥα�����
����������Ȥ��������ޤ����롣
�����β����Ȥ��ƶ��ܤ��륻���֤Ƕ�
̳���䴰���礦��ˡ���ͤ����롣
����绰
�Ķ�ô����Ĺ�ϡ֤�������Ÿ���ؤΤ��ä���
�ˤʤ�Фȴ��Ԥ������϶����Τ������
���ϰϤˤ����ʥ����֤�Ϣ�Ȥ����ӽк︺
�ˤɤ�ʸ��̤�����Τ��ڤǤ���褦��
�����פ��������롣
������μ���ȤߤǤ��ӽ��̤Ф��뤿��
�ˡ��Ķ�Ź�����������ξ�Τ������ɤμ�ξ
�������ؤβ�������ô�������������ꤹ
���Ȥ�ɬ�פˤʤ롣
�����Ѥʤ�Х�������
�Ȥ˼�ξ�����ꤷ�Ƥ��뤬��������͢������
�ˤ�ä��������ư�����ꡢ���Ĥ�Ʊ����ξ
��ô������Ȥϸ¤�ʤ���
�����dz������
�̤����̤��黻�Ф��뤳��ޤǤΤ�����Ȥ�
���꤬�ۤʤ롣
���ָ���δ��������Ѥ�������ʬ������������
�ӽ��̤�����İ����뤳�Ȥ������ܥ�
�˥塼�ȥ��˼���Ȥ�����Ȥʤ롣
�����
�����ǧ�����뤦����ͭ�յ��ʺ�Ȥ��Ȼפ���
��ݯ�ķ�Ĺ���ä��Ƥ��롣
�ʥե���㡼�ʥꥹ�ȡ����Ļ������
���Ѥˤ���ӽ��̡�
���ǯ�ϻ��϶�˥�����
���������ߤ������Ρ�Ȭǯ�٤����ꤷ��
�оݴ��֤ϰ�ǯ�֤Ȥ�����
��Ʊ�ҤǤϽ��衢�ʥ���ˡ�ʤɤ��б�����͢
�����ӽ��̻��Ф�dz��ˡ���Ѥ��Ƥ��롣
����
�����dz���ι����̤䡢���ҥ�����ɤǵ���
������ϥ�����η�¬�ͤˤ�ä�dz����
���̤��İ�����������Ȥ˻��Ф�������
����
����λ�Ի��ȤǤⲣ����͢���Σãϣ�
�ӽ��̤λ��ФϤ�����ˡ�ǹԤ���
��Ʊ�Ҥ����������Τ�ǧ�����٤Ρַײ���Ͽ��
�Ȥ�����ʬ�ǡ������ܥ˥塼�ȥ���ã
�����뤿��ηײ褬�μ¤˼»ܤ�����Τ�
�ɤ�������������롣
�����ˤ����äƤϴ��
ǯ���ӽ��̤���ꤷ���оݴ��֤��ӽ��̤��
�����ƥ����ܥ˥塼�ȥ���ɬ�פʥ��쥸
������ؤ�����绰
�Ķ�ô����Ĺ
ʡ����¿�Υ����ӥ�������
��֤ˤ�������ǤϽ��������åդ������
|