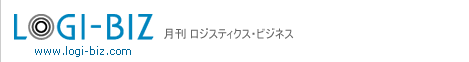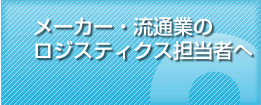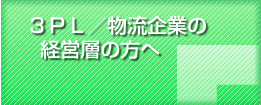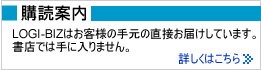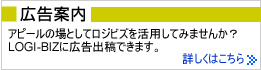|
*������PDF���ƥ����Ȥ���Ф����ǡ����Ǥ���������PDF������������

JULY 2013����50
���롼�װ��Τǻ���Ÿ��
�����ͥ��ϲ����ʤ䵡ǽ�����顢���ʡ��饤
�ե������ʤɡ����ޤ��ޤ�ʬ��˻��Ȥ�
Ÿ�����벽�إ��������
���Τ����Ǥ����
�夲���礭���ΤϿ��ʻ��Ȥǡ��컰ǯ��
�����Ϣ������ͼ�ϻ�Ͳ��ߤ��Ф�����
�ʻ��Ȥ�����ϰ컰���ߤ����Τ���
����Ȭ������Ƥ��롣
���ޡ������䥷�硼�ȥ˥��ѥ�����
�ɡ��ѥ��ۻҸ����βù����������ǡ�
����ʬ��ǤϹ���ȥåץ��饹�Υ���������ġ�
��¤�ϥ��ͥ��ι⺽����ʹ⺽���Ƚ�ˤΤ�
�����Ҳ�Ҥο������ʤ䥫�ͥ����ѥ���
�ʤ�ϻ�Ҥι��줬ô���������ͥ�������Ҳ�
�Ҥ��̤������ѥ���������١������
�����ĿͷбĤΥ���������åפ˻���
�ǡ��������桼�����ؤ����ʤ뤷�Ƥ��롣
����ǯ��Ʊ���ʻ��ȥ��롼�פ���Ĥ��礭��
���פ�»ܤ��Ƥ��롣
ʪή�κƹ��ۤ��μҤ�
�������
�����ͥ��Ͻ��衢�����ͤĤ��ϰ��ʬ����
���ͥ��������䡢������ͥ��������䡢��
�����ͥ��������䡢�彣���ͥ������������
���һͼҤ˳��ϰ�������ô�������Ƥ�
����
���μҤϤ��줾��Υ��ꥢ�μ����ԻԤ�
��Ź���ĶȽ��Ÿ�����ơ�����٤���ʪή��
���ۤ����ϰ�̩�巿��������ά���ȼ��˿�
��Ƥ�����
���ܵҤ���˾�˱����ƥѥ��ۻҤ���¤��ɬ
�פʺ������ȥåפ����뤳�Ȥ˼�
����֤������ͥ����ʤ����Ǥʤ�¾�����ʤ�
������ˤ��Ϥ���������
����ˤ����μҤϡ�
������·����ʪή�֤ˤĤ��ƸܵҤ���⤤ɾ
��������������줾����ϰ��ͭ�ϲ��Ȥ���
�����פ��ۤ�����
����ǯ7��1���դǿ��ʻ���������ϰ��������
��4�Ҥ����礹�롣
���ѥ����۸��������Ǥ϶�
����Ȥʤ������ϤΥե�饤�Ȥ��ƺƽ�ȯ
�����롣
�������Ω�äƥ��롼�פ�ʪή��ƹ��ۡ�
�������緿���������֤��ƴ�������ᵦ����
����������
���롼�פκ߸˴����ȼ������
�δ����ʰ층����������Ū����
SCM
���ͥ�
�����˿������緿�������ߤ�ʪή�ƹ���
�μ����絡�˥��롼�߸ˤ����층��
���ꥳ�������������� 3�������Ҹˤ��� ������ܥå����ѥ�åȤǾ������ݴ�
�ɥå������륿���Ϲ�碌��46�� ���Թ⡦�ر�ƻ������ƻ�ع���������
���ͥ�����������ʪή����
�ȡ�����ԥå����Ź�̻�ʬ��
51����JULY 2013
�������������ʲù��Ѻ����λ��ȴĶ��ϸ���
���������Ƥ��롣
���ΰ¿��������ؤδؿ���
��ޤ�ȤȤ�˲��ٴ����ζ�����ȥ졼����
��ƥ����γ��ݤ�����������褦�ˤʤ�
�Ƥ��롣
���ΰ����ǡ�����Ԥ�����ʻָ���
�����뤿����ʶ����Ϥ�����Ȥ�Ծ�Ǿ�
��ȴ�������ɬ�������
������ˤϡ����ͥ����롼�פ����פʥ�����
�åȤȤ���ѥ�Ծ�ˤ����ơ����夲����
�Ť������ѥ�ǥ����ȴ��Фβۻҥѥ��
Ĵ���ѥ�ذܤäƤ������Ȥ⡢�Ķ��Ѳ�����
�֤�ݤ��Ƥ��롣
���ѥ�ȼԤ����״����Τ�
�ᥪ�ꥸ�ʥ�ƥ����ι⤤�ѥ�Ť������
�˸Ʊ���������������ˤ�Х饨�ƥ�����
�٤�����ʳ�ȯ��������褦�ˤʤä���
�����פ����Ū���ꤷ�Ƥ��뿩�ѥ���Ф���
�ۻҥѥ�����夲�ϵ����ή�Ԥ��礭����
������롣
�����ʤ������ȻԾ����������ơ�
���ʥ饤�ե������뤬û���ʤꡢ���륳���
�����뤬���ʤä���
¿�ʼᆵ�̲��ο�Ÿ
�ˤ�ä�ʪή�θ�Ψ�Ⱝ��������
�����������Ķ��Ѳ����б����뤿��˥��ͥ�
�ϡ�����ޤǤΤ褦�˥��ͥ��ȳ��ϰ��μҤ�
���̤˲���˼���Ȥ�ΤǤϤʤ������롼��
���Ϥ�뽸����ư�����ȤǶ����Ϥ�����
�������ˤ�ž��������
�����Τ���ˡ��ޤ��ϥ��ͥ����μҤ�ʪή��
������Ԥ������碌��ʪή��ǽ�ι��ٲ����
�롣
���ξ���ϰ��μҤ��Ҥ����礷�ơ���
�ۻҸ��������Ǥ϶ȳ���Ȥʤ�������
���䲰��ȯ�����롢�Ȥ������ʥꥪ������
����
�ޥ����Ҹˤ��佼��ȥ�����
�����μ¸��˸���������ǯ��Ⱦ�Ф˿���
�������ˡ֥����ȥ�����ץ��������ȡפ�ȯ
�����μҤ�ޤ�߸˵����ν���ˤĤ��Ƹ�
Ƥ�Ϥ�����
������졻ǯ�ˤϿ��ʻ�
����Ĺľ���Ρ�ʪή���ץ�����ʸ���ά����
���롼��̳��ʪή���ץ�����ˡפ��ߡ���
�롼�פ�ʪή�ƹ��ۤ���ꤷ����
��ʪή�ƹ��ۤϵ������������ʺ︺�Ⱥ߸˴�
���ΰ층������˿ʤ��
�����衢���ʥ��롼�פ�ʪή�����ϥ����
���μҤ��碌����˸ޡ����ꤢ�ä���
�μ�
�ε����ϡ��μ��Ҹˡפȡ��μһ�Ź�Ҹˡפ�
�����ꡢ���롼�פι�������ʤͥ�����
�ˤ�����μ��Ҹˡפؽв٤����������μҤ�
���롼�׳���������줿���ʤȤȤ�ˡ��μ�
��Ź�Ҹˡפ��ͳ���ƥ桼���������������
����ʪή�������äƤ�����
����������������Ԥˤ�äƵ�������Ⱦ��
���٤ޤǸ��餷¿�ʳ�ʪή�β�ä�ޤ롣
��
�Τ�����������緿ʪή�������ߤ���
�ײ��Ω�Ƥ���
�����Υ����ˡ����줾��
������ȶᵦ���ˤ��륫�ͥ����μҤκ߸ˤ�
���롣
������Τ褦�˥�������μҤ��̡��˺߸�
���������ȡ����Τ��Τ�Ƚ�Ǥǰ����߸ˤ�
���Ĥ褦�ˤʤ�ȡ�����߸ˤ����ä���
������
�߸ˤν���ȴ����ΰ층���ˤ�äƤ�
�������������ä��褦�Ȥ��������Ǥ��롣
��������ʪή�����ϥ��롼�פΡ֥ޥ�����
�ˡʣͣģáˡפȤ��ư����դ��롣
�ͣģä�
�ϸ�§�Ȥ��ƥ��ͥ����ʤ��������ƥ�ȡ���
�Ҥ�¾�Ҥ��������뾦�ʤ���μ��ץ�����
��κ߸ˤ���ġ�
�����ƴ��졦�ᵦ���Υ桼
�����ؤ����������Ǥʤ��������ˤ����μҤ�
���ϰ�����ʣģáˡפ��Ф��ƺ߸ˤ��佼���
��1��ʪή��ά�������
���롼��ʪή���Ĥؤ��ѳס����롼��Ʊʪή����
���롼�ץ����Ҹ˲���ʪή����̳�������
�Ҹ�����
�Ҳ����
���ͥ��ɳ��μҴɳ�
��¤���쥫�ͥ��Ҹ��μ��Ҹ��μһ�Ź�Ҹ˺ǽ��ܵ�
��¤���� �μһ�Ź�Ҹ� �ǽ��ܵ�
̵�߸˲�
���롼�ץ����Ҹ�
ʪή����층��������ʣʪή��̳�����硦����
JULY 2013����52
����ǽ��������롣
�����ۤ��濴�Ȥʤ�ͣģäη��ߤ������äơ�
���ʻ�����������μҤΥ��С�����ʤ���
�������͵��ϤΥץ��������ȥ������Ω����
������
�����Υ����̤˥������ʬ���Ƥ�
�줾���ʪ�λ��ͤ�쥤�����ȡ����⥪�ڥ�
�������λ��Ȥߡ�͢������̳�Ȥ�Ϣ�Ȥλ�
�������ѥ롼��ʤɾܺ٤ˤĤ��Ƹ�Ƥ��Ť�
�Ƥ��ä���
���졻ǯϻ��ˤޤ���������ŻԤ˱��
����������ʿ����ȥ��������ʪή��
���ʣףͣģáˤ���ư������
³���ư���
ǯ���ˤϺ�̸���ۻԤ˱�پ�����ʿ����
���ȥ��������ʪή�����ʣţͣģáˤ�
��ư������
��ξ�ͣģä����ࡦ��¢���ﲹ�λ�������
���Ҹˤ����������������Ĵ������ǽ����
���ˤ��ߤ���ʤɲ��ٴ�����������
�����ͥ����ʤ����иˡ��ԥå������ʺ�
�Ȥˤ����С������ɤΡ֣ѣҥ����ɡפ�
���ѡ�
¾�����ʤˤ����˥�٥�ΥС�������
����Ѥ��ƺ�Ȥθ�Ψ�������٥��åפ�ޤ�
����
������Ƴ�������Ҹ˴��������ƥ�ʣף�
�ӡˤα��Ѥ��̤��ƥȥ졼���ӥ�ƥ���������
�¸�������
���ԥå���Ȥ��߷פǤ�¿�ʼᆵ�̲���
���б���Ż뤷����
�μҤ��������ʤ�¾�һ�
�����ʤ�ޤ���饢���ƥ�˾�롣
�ѥ�
�Һ�������Ǥ�ͤ�ʪ�ζ��˻��Ѥ���륯
���ʤɤΡ֥ե���פȸƤФ�����
�Τ褦�ʷ��Ǻ߸ˤΰ층����¸����뤫�Ȥ�
�����Ȥ��ä���
��Ƥ�������μҤ������ʬ��
���Ȥ��ơ�����ޤǤ���쥹�ƥåס������
�����ƥåפȰ����դ������ʳ��ǰ층��
��ʤ�뤳�Ȥˤ�����
���
ͣģäβ�ư�����μ�����ޤǤ���쥹��
�åפǤϡ�����ޤǴ�����ȶᵦ���ˤ��ä�
�μҤκ߸ˤ�ͣģäؤν����ȼ�����ä���
������ʻ������˺߸ˤ��֤���������
����
�����ʤ����������Σͣģäǰ�����äƥ���
���λ������߸ˤȤ����ݴɤ����ͣģä˽в�
�ؼ����Ф��������μҤ˽�ͭ����ܤ���
�������ȼ���ͣģä����ϰ�ģäؤ��佼��
ˡ��ľ������
����ϳ��μҤ�����������Ƚ
�Ǥ���ɬ�פʿ��̤ͥ����Ҹˤ��鼫ʬ��
�Ҹˤذ������Ȥ��������������ˤʤä�
������
����������Ǥϻ������β����ͣ�
��¦���佼��ȥ����뤹�뤫�������Ѥ�
����
�ģ��̤˥����ƥऴ�Ȥδ��߸ˤ�����
�����߸ˤο�ܤʤ������ͤˣͣ�
�ä���ģä�������ࡣ
�����������μҤ��������ʤϥ��ͥ����ʤ���
�ǤϤʤ���
���ϤΥ桼�����Υˡ����˹�碌��
���줾����μҤ����롼�׳����������Ƥ�
�뾦�ʤ���갷���Τ��ʤ�Υ������Ȥ����롣
���κ߸ˤν�ͭ���ϳ��Ϥ��μҤˤ��ꡢ�߸�
��������륳��ȥ�������μҤ�ô�äƤ��롣
�����Τ�����쥹�ƥåפǤϣͣģ���κ߸�
�Τ������ͥ����ʤϻ���������¾�һ�������
���μҤ����줾���������Ȥ�����§Ū�ʷ�
�ϤȤ�櫓���ब˭�٤ǡ�Ź�ޤ������ʸ��
�ۤȤ�ɤ��ԡ���ñ�̤���
�������ǥ����ƥ��̤˥ȡ�����ԥå�����
�����ޤ�������Ź���̤˻�ʬ���륷���ƥ�
��Ƴ�������ԡ�������ǽ�Ϥ�������
���衢
�μҤε����Ǥϥȡ�����ԥå�������Ԥ���
Ź���̤λ�ʬ����Ȥ϶�̳������������ȼ�
�����Ҥ��Ҹˤؾ��ʤ٤��Ƥ���ԤäƤ�
����
�ͣģä�Ź���̻�ʬ����ǽ���ߤ��뤳��
�Ƕ�̳�θ�Ψ���ȥ��ԡ��ɥ��åפ�ޤä���
���̾�Ǽ�ʤȤ��̤ˡ��ĿͷбĤξ�����ñ��
Ź�����Ф��Ƽ»ܤ��Ƥ���롼�ȥ����륹��̳
�β�����Ԥä���
����ϥ롼�ȥ����륹��ô
���Ԥ������μҤ��Ҹˤ�ô�����ꥢ��Ź����
��ʬ����ԤäƤ�����
���λ�ʬ����Ȥ�ͣ�
�äΥԥå������ƥ���оݤ˲ä�����
����
�ˤ�äƥ롼�ȥ����륹ô���Ԥ�Ź���̻�ʬ
���κѤ�����ʤ������ꡢ��������������
̳�ϤǤ���褦�ˤʤä���
���Ƥκ߸ˤ��μҤ��층����
������β��פ�ʪή���ץ����ब�Ǥ��礭��
����Ȥ����Τϡ��ɤ�ʥ��ƥåפ�Ƨ�ߡ���
���ͥ��ο��ʻ�������ά��
�祰�롼��̳��ʪή���ץ�
�����Ǥ��Ȭ�ڹ��л�
53����JULY 2013
���塢���Ѥ����ˤˤʤꡢ���Υǡ�������
�Ǥ�ͽ¬���٤��夬��ʤ��ʤäƤ�����
�������Ǻ�����μҤαĶȥޥ�ȯ�������
������ͽ¬�˳褫����
�����˲�ư�������
�����ƥ�˱ĶȥޥĶȳ�ư�ˤ�äƼ���
�������̡�������������ϡ�
ľ����������
���Ȥ˼���ͽ¬���륵�֥����ƥ�ǻ��Ф�
���ǡ����ν�����Ԥ���
����ˤ����������
ľ�����Ȥ�ͽ¬�����٤���롣
���ͥ�¦��
�������줿������˹���������ײ���ѹ�
���ƺ�Ŭ����ޤ롣
���Ķȥޥ�ξ���������ײ��ȿ�Ǥ������
���������ǥ��ϡ����ˤ⸡Ƥ���줿���ȤϤ�
���
�������������ޤǼ¸����Ƥ��ʤ��ä���
������ͳ��Ȭ�ڻ�ϡ�?�Ĥ���Τϥ������
���Τ��μ�?�Ȥ����ڤ�ʬ���������ΰռ�
����ˤ��ä�������פ�ʬ�Ϥ��롣
����������ϼ���ͽ¬��ǽ�ȤȤ���μҤ���
����Ǥ����Ĥ褦�ˤʤ롣
���η�̡��ֱĶ�
�ޥ�ϼ�ʬ����������å������Ծ�ξ����
������ȡʥ����ƥ�ˡ�����ʤ��ȡʣӣã�
�Ρ˻��Ȥߤ���餺�������Τ����ʤ�
�ʤ뤳�ȤФ���Ϥ���
����ޤǤȤ��礭
���Ѥ��������פȸ��Ƥ��롣
��ʪή�����κ��ԤϤޤ�ƻȾ�С�
�μҤ�����
������ƺ��塢���롼�פ�ʪή�ͥåȥ��
�������®�����롣
�ϰ�ģä����ԤΥ�����
�åȤˤʤ롣
������ϥ�ɥ���������꤬�����ʤ��³�
�ޤǣģäο��餷�������Σͣģä��餽
�줾�������ܡ������ܤι����ϰϤС���
�빽�ۤ��ä���
������������̺Ҥ�����
����������
�£ãСʻ��ȷ�³�ײ���б���
�Ż뤷�ƣͣģðʳ��ˤ�߸˵������ߤ��뤳
�Ȥˤ�����
��������β����ʳ�Ū���ϰ����
�κ����֤�Ԥ��ײ����
�ʥե���㡼�ʥꥹ�ȡ����Ļ������
�ˤʤ롣
�ޤ����ͥ����ʤκ߸ˤ⡢�ͣģä�
���ϰ�ģä˽в٤��ưʹߤ��μҤ˽�ͭ����
���롣
��������Ф����μ����������ƥåפ�
�ϡ�¾�Ҥ���λ������ʤϤ�Ȥ�ꥫ�ͥ���
�ʤˤĤ��Ƥ⡢�߸ˤν�ͭ���������������
��¦�˰ܤ���
�ͣģä���ӣģäˤ������Ƥ�
�߸ˤ��μҤ��층�������뤳�Ȥˤʤ롣
�
�����ǤϤʤ������ץ饤����������¦����
�����μҤ��߸���Ǥ���餤���ͣģä���ģ�
�ؤ��佼�Υ���ȥ�����⼫��Ԥ����ˤ��롣
�����ʻ�������ά���祰�롼��̳��ʪή
���ץ������Ǥ��Ȭ�ڹ��л�ϡ֥������
�μҤΤɤ���¦����������٤�������������
���ϽФ��������롼�����Τ��Ψ�����ƾ���
�ζ�����Ŭ������ˤϡ��Ծ�ˤ��ᤤ��
�����Ǻ߸˴�������������Ԥ��ۤ�������
�Ȥ���Ƚ�Ǥˤʤä��פ��������롣
�Ķȥޥ�ξ���������ײ��ȿ��
����ǯ��������������һͼҤϥ��ͥ���
�������¸³��Ҥ������Ԥ�������̾�֥�
�ͥ����ʡפȤ��ƺƽ�ȯ���롣
��ǯ������
��ɤˣͣģäκ߸ˤ�������߸ˤ����μҺ�
�ˤ��ڤ��ؤ���ͽ�����
������˹�碌������ʪή�����ƥ�Υ�˥�
�������Ԥ����ӣãͤλ��Ȥߤ�ƹ��ۤ��롣
����ϥ����¦�Dz��μ��Ӥʤɤ��˼�
��ͽ¬��Ԥ��������ײ��Ω�ƤƤ�����
������
¿�ʼﲽ�ȶ��˼�����ư���礭�����ʤ�����
��2��QR�����ɤ���Ѥ����Ҹ˥��ڥ졼�����
������ʪή�����ˤϡ��Ҹ˴��������ƥ��WMS�ˤ�Ƴ�������С������ɡ������QR�����ɡʥ��ͥ��ʤΤߡˤ�
���Ѥ����Ҹ˱��Ĥ�ԤäƤ��롣
������
DC
�����˶�̳��
QR��٥륹�����QR��٥륹�����
�ڽвٶ�̳��
TC
���ٸ���
�߸˰���
�ԥå���
�и�
����
�в�
���˸���
��������
���ͥ�HOST WMS
�߸˴���ê���вٻؼ�
�ϥ�ǥ������ߥʥ����Ѥ��ߥ��ɻ�
QR��٥����
WMS�ˤ�����������KPI�ǡ�������
���ͥ����롼����¾�һ�������
���
���ٸ���
|