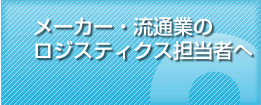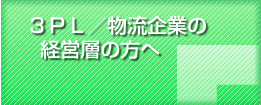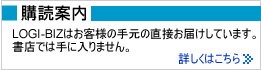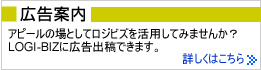|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

奥村宏 経済評論家
JULY 2013 72
つまらない書評
「本が売れない」「良い本がない」という声を聞くが、それ
はまさに「出版文化の衰退」と言うしかない。
なぜ、こんなことになったのか?
これについて、私は二〇〇四年に出した『判断力』(岩波
新書)で次のように書いている。
「映画や演劇にとって批評がいかに大事か、ということは
いうまでもない。
よい創作はよい批評があって生まれる。
最近は『良い本がない』という声をよく聞くし、私もそ
れを痛感している。
出版文化の衰退ということがいわれるが、
その原因のひとつは書評のあり方にあるのではないか。
あり
ていにいって、書評を本の宣伝と間違えている人が多い」(同
書、一六八頁)。
そして、書評がいかに大事かということについて書いてい
るのだが、同時に、書評をする時にその人の本音が現れると
いうことを指摘している。
つまらない本を良い本だと書くような人は、その人自身が
いかにつまらない人間かということを現している。
そう思っ
て読むと、実につまらない書評が多い。
それは本を宣伝しているだけで、批評になっていない。
そのような書評を読んで、その本を読みたいと思う人はい
ないだろう。
こうして書評をする人が出版社や本屋の宣伝マンになって
いることが、日本の出版文化を破壊しているのである。
「そう思って毎週、日曜日の新聞に載る書評を見ていると、
ほとんどが本の紹介ないし宣伝で、批評にはなっていない。
これでは日本の出版文化は堕落するばかりでなく、日本の知
性の崩壊というしかない」(同書、一八八頁)。
私がこう書いてから一〇年近くなるが、事態はますます悪
化するばかりである。
そこでは新聞の書評について書いてい
るのだが、雑誌に載る書評についても同じである。
私が経験した事件
このことを私が痛感するような事
・
・ 件
が
起
こ
っ
た
(
事・
・ 件
と
言
うのはいささか大げさだが)。
私は頼まれてある週刊誌の書評委員をしているが、最近、
パナソニックについて書かれた本について書評を書いて編集
者に送った。
その中で私は会社評論のあり方について問題提
起をした。
というのは、その本では松下幸之助をはじめとするパナソ
ニックの歴代の社長の発言について、あれこれと詳しく書い
ているのだが、これではパナソニックという会社はどういう会
社であり、どこに問題があるのか、ということが分からない。
そこで問われているのは会社評論のあり方で、それを根本
的に考え直すことが必要である、と指摘した。
ところが、この書評を読んだ編集者は、これでは批判ばか
りでこの本の良い点を指摘していない、「これでは、この本
を読むな」と言うに等しい、こんな書評は載せられない、と
して私の原稿をボツにしたのである。
私はその週刊誌には四〇年以上も前から頼まれて書評を書
いているが、原稿をボツにされたのは初めてである。
ずっと以前、この週刊誌にある経営学者の書いた本の書評
をし、そこでかなり厳しくその本を批判したことがある。
そ
のためにその学者は激しく怒って反論してきたことがあるが、
しかし当時の編集者は私の原稿をそのまま載せていた。
私は、私の原稿がボツになったことに対して激しい怒りを
覚えたが、しばらく冷却期間を置いて、別の本の書評をした
いとその編集者にメールで伝えた。
ところが、それに対して、私を書評委員から解任するとい
う通知が来た。
この編集者は私の原稿をボツにしたことについて「上の者」
に相談したというのであるが、おそらく書評委員を解任する
ことについても「上の者」と相談した上でのことであろう。
書評が本の批評ではなく、単なる本の宣伝に堕してしまってい
る。
編集者が自分では本を読まず、書評委員に委ねたところから
この堕落は始まった。
第134回 出版文化の衰退
73 JULY 2013
書評に地が現れる
私の先の本で「批評する時にその人の地が出てくる」と書
いているが、それは人物評の時に現れるし、書評の時にも現
れる。
いくら高い見識を誇っている人でも、他人についてそ
の人が語る時に、その人の地が現れる。
同じことが書評につ
いても言える。
そう思って新聞や雑誌に載っている書評を読んでいる
と、平素は立派なことを言っている人でも、実はその人は
お・
・・・・・
べっか使いか、ご
・ ・・・
ますりだということが分かる。
そこで、読者はそういう書評を書いている人の書いたもの
は読まなくなるし、そのような書評欄も読まなくなる。
さら
にそのような書評を載せている新聞や雑誌を読まなくなる。
私の書評原稿をボツにした編集者は、こうして自分たちが
作っている雑誌の書評欄を読者が読まないようにしているの
である。
それは雑誌の質を低下させることを編集者が進んで
しているということであるが、おそらく、そういう自覚は全
くないだろう。
それは雑誌の質の低下から、ジャーナリズムの質の低下、さ
らには文化の破壊へとつながるのだが、そのことが全く分か
っていない。
書評は本の宣伝であるという考え方はこの編集者だけでな
く、ほかの編集者、さらには「上の者」にも染み通っている
ようである。
それも本の広告なら、広告料をもらっているの
だろうが、書評欄の宣伝では、出版社も広告料は出していな
い。
それはまさに「タダの広告」である。
それだけなら、放っておいてもよいのだが、しかしこうい
う書評のあり方が本の質の低下、そして出版文化の荒廃へと
つながっていっているのである。
「本が売れない」「良い本がない」──ということの背景に
はこのような書評のあり方がある。
それはまさに「文明の破
壊」である。
書評は宣伝ではない
私の書評がおかしいというのであれば、そこで取り上げて
いる本を読んで、どこがおかしいかということを指摘しなけ
ればならない。
ところが、この編集者はその本を全く読んでいないのであ
る。
ただ、私がこの本を批判しているだけで、良い点を挙げ
ていないというだけである。
「上の者」に相談する前に、まず当の本を読んで、私の書
評のどこがおかしいかということを指摘すべきだが、そうは
しない。
これでジャーナリストと言えるのだろうか?
この編集者は、私に対して、書評ではいかにこの本が良い
本かということを書き、それに対する批判はせいぜい二割程
度にとどめるべきだ、というのである。
これには私は驚いた。
この編集者は、本の書評は本の宣伝
だと思っているのである。
「ありていにいって、書評を本の宣伝と間違えている人が
多い」と先の本で私は指摘しているが、この編集者もまさに
そうなのである。
そしておそらく「上の者」もそうなのであ
ろう。
そうでなければ、私の原稿をボツにすることはできな
いと思われるからである。
私がその週刊誌の書評委員を頼まれたのは二〇〇六年だが、
それ以前にはその週刊誌には書評委員という制度はなかった。
そこで編集者は自分で本を読んで、誰に書評を頼むか、とい
うことを考える。
ところが書評委員という制度を作って、自分では本を読ま
ないで、書評委員に全て任せる。
これは新聞社がそういうシ
ステムを作ったのだが、この週刊誌もそれに倣った。
ここから書評の堕落が始まる。
そして書評は本の宣伝、広
告となっていったのである。
これは書評の堕落であるが、そ
れが出版文化の破壊につながっていった。
おくむら・ひろし 1930 年生まれ。
新聞記者、経済研究所員を経て、龍谷
大学教授、中央大学教授を歴任。
日本
は世界にもまれな「法人資本主義」で
あるという視点から独自の企業論、証
券市場論を展開。
日本の大企業の株式
の持ち合いと企業系列の矛盾を鋭く批
判してきた。
近著に『東電解体 巨大
株式会社の終焉』(東洋経済新報社)。
|