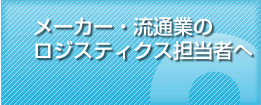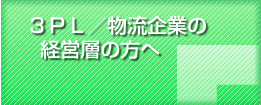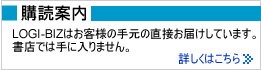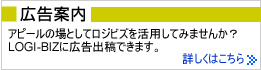|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

奥村宏 経済評論家
第24回 名門カネボウの落日
MAY 2004 50
破綻したカネボウを国家が救うことは小泉首相の構造改革路線に逆行する。
しかも産業再生機構にカネボウを再建するだけの経営能力があるとも思えない。
必然性なき国家管理は、日本資本主義の悲劇なのだろうか。
事実上の国家管理
カネボウが産業再生機構の支援を受けることになったが、
これは事実上の倒産といえる。
創業一一七年の名門、かつ
ては東洋紡績、大日本紡績(現ユニチカ)と並んで三大紡
績メーカーとして君臨していた会社である。
私はこの会社にはいろいろな思い出がある。
かつて繊維担
当記者として何回も大阪・都島にあったカネボウの本社で
取材したが、当時の社長であった武藤絲治氏にも何回も会
ったことがある。
大正時代、三井銀行から鐘淵紡績に送り
込まれ、やがてこれを名門紡績会社にしたのが武藤山治。
そ
の息子が武藤絲治氏で、イギリスのパブリック・スクールで
教育を受けた名門の「坊ちゃん」経営者であった。
この武藤絲治社長の秘書をしていたのが伊藤淳二氏で、の
ちにカネボウの社長、会長になり、さらに日本航空の会長に
までなったことで有名になった人である。
この伊藤氏の下で
秘書をしていたのが永田正夫氏で、この人とは何回も飲み
に行ったものである。
その永田氏ものちにカネボウの社長になったが、カネボウ
では「慶應出にあらずば人にあらず」で、これらの人はみな
慶應大学出身者だった。
私が繊維担当記者だったのは昭和三〇年代で、当時すで
に「紡績産業は午後三時の産業」といわれ、斜陽産業のレ
ッテルを張られていた。
しかし、なお日本の財界では大きな
力を持っていた。
とりわけ大阪ではその存在は大きかった。
その名門カネボウが花王に化粧品部門を売ることになっ
たというので驚いていたら、労働組合の反対によってそれが
破談になり、ついに産業再生機構に持ち込まれて、その支
援を受けることになった。
産業再生機構はいうまでもなく政
府の機関であり、公的資金によって企業を救済するという
ものである。
これでカネボウという会社は事実上倒産したも
同じで、国家管理の会社になったということになる。
総合化の失敗
武藤絲治社長のころからカネボウは繊維以外の部門に進
出しようとしていた。
斜陽産業から脱却するためには多角化
する以外にはないというので、まず化粧品に進出した。
もと
もとカネボウの子会社であった鐘淵化学が手がけていた事業
を取り上げたのである。
さらにカネボウ本社の近くにあった
薬品会社を買収して薬品部門にも進出した。
そして食品部
門からさらに住宅にまで手をのばした。
こうしてカネボウの「ペンタゴン経営」が打ち出されたの
だが、繊維、化粧品、薬品、食品、住宅の五角形というの
で「ペンタゴン経営」という名をつけたのである。
伊藤社長時代にこの「ペンタゴン経営」が有名になった
が、これら五つの事業分野にはなんの有機的関連もない。
ただ、あるとすれば「カネボウ」というブランドだけで、その
ブランドでそれぞれの商品の売り上げを伸ばそうとしていた
のである。
このような事業の多角化、総合化が失敗したのはいうま
でもない。
なんらの関係もない事業を統合しても効率が良く
なるはずはない。
それどころか「選択と集中」ということが
時代の流れになっているのに、カネボウはそれに逆行するこ
とをやっていたのである。
このような多角化、総合化の失敗にもかかわらずカネボウ
の経営が続けられてきたのはなぜか。
ひとつは化粧品部門が
好調だったということもあるが、より根本的には「売り食
い」である。
明治時代以来、各地に工場を作ってきたので、
その工場をひとつ売れば何十億円というカネが入ってくる。
カネボウはこうして「売り食い」によって経営を続けてき
たのだが、ついにそのネタがつきたところから経営が成り立
たなくなった。
そこでメーンバンクである三井住友銀行が化
粧品部門を花王に売れとせまったのだが、それが不調に終わ
ったというわけだ。
51 MAY 2004
の破綻を招いたのである。
日本資本主義の悲劇
小泉首相の構造改革路線は「民間にできることは民間に
任せる」ということを旗印にしている。
道路公団や郵政事
業を民営化するというのもこの方針による。
ところがカネボウという民間の会社は産業再生機構によっ
て事実上の国家管理会社になる。
なんのことはない「民間に
できなくなったら国が助ける」ということで、これはかつて
イタリアのムッソリーニ首相がやったのと同じことである。
カネボウをなぜ国家管理会社にしなければならないのか。
もともと民間の会社である花王がカネボウを助けるといって
いたものをなぜ国が取り上げるのか。
産業再生機構がカネボウを支援するというニュースが伝えられると、財界でもこれに疑問を呈する人が多かった。
この
会社を国家が救済しなければならない必然性がないからであ
る。
経営破綻した会社を再建するためにはどうしたらよいか。
そのために会社更生法という法律があり、さらに民事再生
法という法律もできている。
これによって経営破綻企業の債
務は棚上げになり、新しい経営者によって会社を再建して
いく。
これが常道である。
カネボウもこういう形で会社再建をはかるべきであった。
ところがそこに産業再生機構という、性格のあいまいな国家
機関が乗り出すことでおかしくなってしまった。
この産業再
生機構にカネボウを再建するだけの経営能力があるとはとて
も思えない。
かつて三井財閥のドル箱であった三井鉱山と、そして外様
とはいえ三井財閥と深いつながりがあったカネボウ。
この二
社がともに産業再生機構の管理下に入って、国家管理される。
歴史の皮肉というべきか、それとも日本資本主義の悲劇
というべきか……。
おくむら・ひろし 1930年生まれ。
新聞記者、経済研究所員を経て、龍谷
大学教授、中央大学教授を歴任。
日本
は世界にも希な「法人資本主義」であ
るという視点から独自の企業論、証券
市場論を展開。
日本の大企業の株式の
持ち合いと企業系列の矛盾を鋭く批判
してきた。
近著に『会社をどう変える
か』(ちくま新書)。
総会屋と労働組合
カネボウは慶應閥の会社だといったが、もうひとついえば
「坊ちゃん経営」の会社であった。
これは武藤絲治社長が
「坊ちゃん」であったところからそういわれたのだが、この
「坊ちゃん経営」には「お家騒動」がつきものであった。
戦前、カネボウは中国に進出して、工場をあちこちに作っ
ていたが、その従業員が引き揚げてきて作ったのが鐘淵化学
である。
そこでカネボウとは親子関係にあるはずだが、とこ
ろがこの両社が激しく対立していた。
そのカネボウにさらに「お家騒動」が起った。
「山田副社
長事件」といわれるもので、武藤社長が山田副社長を追い
出そうとして内紛が起こり、大事件になった。
その時、武藤
社長側が使ったのが総会屋で、以後、カネボウには総会屋
が食い入って離れない。
私は新聞記者時代、社長秘書室でこのような総会屋をよ
く見かけたものだが、この総会屋に渡している金額は相当な
額に達しているといわれた。
伊藤淳二氏はこの武藤社長の秘書をしていたが、当時か
ら不思議な人物であった。
私が繊維担当記者をしていたこ
ろ、彼はカネボウを辞めて武藤社長の個人秘書をしていた。
にもかかわらずベンツを乗りまわしているといわれていた。
この伊藤淳二氏がやがてカネボウの社長になるのだが、彼
がまだ四五歳の時である。
武藤社長のころからカネボウは
「お家騒動」のために総会屋を使うとともに労働組合を使っ
ていたといわれた。
その労働組合対策をやっていたのが伊藤
淳二氏だった。
このやり方は伊藤氏が日本航空の会長にな
ってからも行われた。
これは山崎豊子の小説『沈まぬ太陽』
にも書かれているところでもある。
このように会社が労働組合を使ったことが皮肉なことにカ
ネボウの破綻を招いたのである。
労働組合の反対によって花
王への化粧品部門の売却話が破談になったことがカネボウ
|