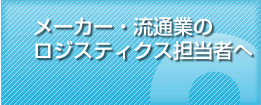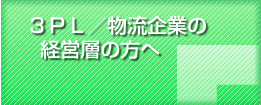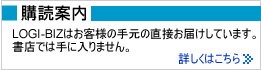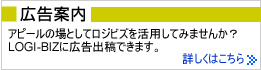|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

AUGUST 2004 24
経営戦略の三つの方向性
前回の寄稿(本誌二〇〇四年六月号)では、「ロジ
スティクス企業のブランディング」というテーマで、
ロジスティクス企業にとってもブランディングが有効
な差別化手段になり得るということを確認した。
今回
はテーマを物流子会社にフォーカスし、前回には触れ
なかった顧客以外の他のステークホルダー、すなわち
社員と株主(この場合、主として親会社およびグルー
プ会社であるが、物流子会社にとっては同時に最大顧
客でもある)に対するブランディングについても考え
てみたい。
図1に今後、物流子会社が採るべき戦略方向性を
図式的に示した。
図の縦方向の矢印、これは親会社
への貢献を第一の優先事項と捉え、サービスの高度
化・低コスト化を徹底的に追及する道だ。
当然、海
外の親会社拠点に対する物流サービスも視野に入って
くる。
調達物流や海外物流は、荷主としての親会社
への食い込みがとりわけモノを言う分野だ。
この方向
性の到達点の一類型は、グローバルな土俵で、親会社
あるいはグループ会社に3PL的なサービスを提供す
るということになろう。
次に横方向。
これは、自社の得意とする分野の横
展開政策、すなわち親会社・グループ会社以外の企
業に対してもサービスを提供するという選択だ。
そう
したグループ以外の企業へのサービスの提供=「外
販」の対象としては、異業種の企業と同業種の企業
の双方が考えられる。
外販の対象が親会社の同業他社に対してのもので
ある場合は、当該業種の物流プラットフォームが形成
され、業界最適が目指されるということにも繋がって
いく。
勝手知ったる業界特有の物流機能を担うという
ことであるから、理屈の上では筋の通ったオプション
とは言える。
しかし現実には、親会社の同業他社にもそれぞれ物
流子会社が存在していることが多く、競合相手の物
流子会社へのアウトソーシングは内部的な抵抗が大き
い。
子会社同士の経営統合や吸収・合併などもスム
ーズに進むとは考えにくい。
横展開においては、親会
社の同業種よりも異業種での顧客企業を獲得するこ
とのほうが相対的に容易に違いない。
また横展開にも、親会社に対して完璧な物流サービ
スを提供するために(つまり基本は縦方向なのだが)、
たとえば低コスト化を達成するために、どうしても外
販をやらなければならないというケースもあり、また
現行の機能のみの外販ではなく、親会社に対するサー
ビス機能を拡張してからの横展開も考えられる。
した
がって縦の垂直展開と横展開という二つの方向性を
共存させる、すなわち図で右斜め下に向かう矢印の方
向性も多少なりとも存在すると言っていい。
親会社の冠が意味するもの
このように物流子会社の戦略方向性を整理した上
で、以下にブランドの視点からの議論を始めたい。
ま
ず認識すべきは、どういう方向性であっても、あるい
は物流子会社がどう発展しようとも、物流子会社は
親会社やグループ会社に対するサービスを絶対に無視
することはできないという大前提だ。
もちろん、その物流子会社が他の物流会社に身売
りする、吸収される、統合されるといった事態になれ
ば様相は多少異なってくる。
そうでない限り顧客の一
つに大株主である親会社が存在し続け、親ブランドと
して機能しているということは、物流子会社のブラン
ディング上も決定的な意味を持つ。
物流子会社のブランディング
物流子会社にとって親会社の冠はどのような意味を持つのか。
ブランディングの視点からそれを理解し、自らの将来ビジョンを
明確化することで、物流子会社の進むべき道が見えてくる。
菊池隆ヴィブランド・コンサルティング副社長
25 AUGUST 2004
しかし既に述べたように物流子会社は、ほとんどの
場合、親会社あるいはグループ会社以外へサービスを
提供する外販にも、多かれ少なかれ取り組まなければ
ならない状況になっている。
その時に物流子会社が親
会社の名前を冠しているということ、そして親会社が
最大の顧客であるということが、外部の顧客企業には
どのように受け取られるのであろうか。
マイナスの影響も考えられなくはない。
親会社に対
するほどには外販顧客に資源を投入しないのではない
かという懸念、情報の秘匿性が危うい――つまり競合
会社に自社の情報が漏れてしまうことへの危惧など、
親会社の冠を戴くことで外部顧客に何らかのネガティ
ブなイメージを持たれてしまうこともあり得る。
そうしたデメリットを重視して、極端な場合には社
名から親会社の名前を外すという選択も机上では想
定できる。
しかし、実際に親会社の冠を社名から外し
てしまうケースは極めて希だ。
外販顧客といえども、
親会社の冠が想起させるネガティブなイメージのみに
頼って購買を判断するとは考えにくいからである。
顧
客はサービスをより実態的・プラグマティックに捉え
ている。
逆にその物流子会社の親会社に対するサービスが非
常に効率的、効果的なものであると広く認知されてい
る、つまりブランドの実体がきちんと評価されている
場合には、これはすなわち「子会社ブランド」が既に
成立しているということだ。
たとえば日立物流の場合、日立というブランドを支
える「物流機能」と言うだけではなく、「日立物流」
という企業ブランドあるいはサービスブランドが既に
顧客の間で高く評価されている。
ここまでくれば、前
回の寄稿で提示した、顧客が不完全にしか知り得ない
物流子会社の実体をブランド力によって補うという
「ブランドの情報補填機能」も効いてくる。
実際には多くの物流子会社ブランドは、親会社の
確立されたブランドによって信頼性や品質などの側面
でエンドース(保証)されており、ビジネス上その恩
恵を多いに受けていると考えるべきだろう。
したがって物流子会社がどういう規模で外販を進め
ようとも、親会社に対するサービスの質を下げること
は禁じ手といえる。
これまでと同様かそれ以上のサー
ビスを提供することが外販の獲得においても大前提と
なる。
実際、日産自動車から独立したバンテックなど、
親会社との資本関係が既にない企業であっても、旧親
会社に対して従来と変わらない、あるいは従来以上の
サービスを提供しているはずだ。
親ブランドの活かし方
さて、このような同じ冠を戴くグループ会社内にお
けるブランディングとは、どのような「体系」になっ
ているのであろうか。
この議論を進める前に前回提示した重要な概念で
ある「ブランドプロミス」について思い起こしていた
だきたい。
ブランドプロミスとは、ある企業が絶対・
確実に顧客に対して提供すると約束するものであり、
総合的な意味で企業の差別化要因、他とは違うとこ
ろ、つまり個性である。
ブランドプロミスは事業領域、差別化要素そしてパ
ーソナリティーの三要素から成立している。
このブラ
ンドプロミスに沿って、企業の全ての機能が機動し、
またそのコンセプトが外部に伝達されるという、ブラ
ンド政策の真に中核部分である(
図2参照)。
これに対してブランドの「体系」とは、簡単に言っ
てしまうと、ブランドを階層的に整理し、それぞれの
プロミスを定義し、下位ブランドとコーポレートブラ
AUGUST 2004 26
ンド(この文脈では親ブランド)との関係を規定した
ものだ。
それを踏まえた上で、図3を見ていただきた
い。
この図の上に行けば行くほどブランドプロミスは抽
象化する。
つまり多くのブランドを抱えれば抱えるほ
ど、それをまとめる親ブランドは抽象的な意味合いに
なっていく。
逆に下に向かえばブランドプロミスはよ
り具体的になる。
下位のブランドは親ブランドのプロ
ミスを内包しているという点で共通性を持つ。
図で示せば、下位ブランドが三角内に位置すれば、
下位ブランド群のブランドプロミスは、親ブランドの
ブランドプロミスを共通にもつことになる。
ブランド
プロミスの一要素は事業領域であり、通常、提供する
製品の投入分野を規定することになる。
日立であれば、
家電・エレクトロニクスから重電までということであ
ろうし、ホンダであれば自動車・二輪車・汎用機器だ
ろう。
このようなブランド体系のコアブランドの三角形の
中には物流子会社は入らない。
物流は基本的には製
品やそれを作るために必要な部品を需要者まで届ける
ための付帯サービスであり、それ自体が事業領域を構
成しない。
つまり物流子会社ブランドが親会社の「ブ
ランディング上の」コアブランドには通常の場合はな
りえないということだ。
この議論で注意する必要があるのは、コアブランド
とコア事業との違いである。
たとえば、日立グループ
にとって、日立物流は利益貢献度の高いコア事業の
一つである可能性がかなり高いものの、「日立物流」
というブランドが日立製作所にとってのコアブランド
であるわけではない。
もちろん、メーカーとしてのブランドを拡大して、コ
ングロマリット的なブランドを育成しようというとき
には、物流子会社がコアブランドになることも理論的
にはあり得る。
しかし現実には、ほとんどの物流子会
社のブランドは、その属する企業グループの「準コア
ブランド」として位置づけられると判断していいだろ
う。
準コアブランドは、親ブランドとの関係を積極的に
顧客に対して訴求するものではないが、その関係は顧
客の意識に残るという位置にあるブランドを指すこと
が多い。
独立ブランドとしてのブランド力はあるが、親
ブランドのブランドプロミスのエンドース(保証)を
受けたほうが全体としてのブランド力が高まるという
ときには、準コアブランドとしての位置付けが有効に
機能する。
物流子会社の場合、事業領域上は親ブランドと適
合するものではないが、親ブランドのプロミスの一部
を拝借することで恩恵を受けられることが多い。
具体
的には松下、日立、ソニー、NEC、キユーピー、サ
ッポロビールなどの親ブランドから想起される、信頼性、安心、誠実、真面目などといった差別化のポイン
トの一部とパーソナリティーを拝借するわけである。
(図3の鍵型矢印を見ていただきたい)
ちなみに実際に物流子会社が親会社ブランドとの関
係性を定義するに当たっては、社員のアイデンティテ
ィーとの合一性を熟慮しなければならない。
たとえば
松下ロジスティクスの社員のアイデンティティーは、
どの程度松下グループの一員であることで構成されて
いるのであろうか、また松下のブランドプロミスのど
の程度の影響下にあるのであろうか。
あるいは今後、
どう自分たちを規定していけばいいと考えるだろうか。
ブランディングを考える場合、内(アイデンティティ
ー)と外(ブランド)の齟齬があってはならないので
ある。
27 AUGUST 2004
ブランディングの四つの方向性
以下にブランディングと物流子会社の戦略方向性
との関係を整理してみよう。
先に述べたように、どの
ような戦略方向性を選択しようとも、物流子会社にと
って顧客としての親会社は存在し続ける。
それでは、
物流子会社は親会社をどのような存在である(べき)
と規定すればいいだろうか。
ここで焦点になるのは、親会社の物流子会社に対す
る政策と、物流子会社自身が描く企業ビジョンや事
業ビジョンである。
親会社が、物流子会社を人員の受
け皿や天下り先、利益調整の対象として捉えるという
のは、もはや現実的な意味を持たないアナクロニズム
だろう。
また戦略策定部門というブレーン部分を持た
ない純粋にオペレーショナルな物流子会社というのも、
発展の可能性が限定される可能性が高い。
親は子に何を期待するのか。
長期的な政策を決める
必要がある。
同時に子会社は、最大顧客・株主とし
ての親会社の位置づけを長期的なビジョンの中で自ら
規定しなければならない。
ブランドが長期的に機能す
るものである以上、物流子会社は、現在から将来、少
なくとも七年から一〇年後に向けて、どういう企業ブ
ランドでいたいのか、いるべきなのか、徹底して詰め
て考える必要がある。
そのフレームワークとして
図4を用意した。
縦軸に
物流子会社の第一優先の目標、横軸にはグループ企
業としてのアイデンティティーを残したいか(残すべ
きか)、そうでないかを示してある。
この図から少な
くとも四つの典型的なパターンが浮かび上がる。
?グループ企業としてのアイデンティティーを残し、
親会社やグループ会社の「事業利益」に貢献するこ
とを最大の目標とする。
事業利益に貢献するということは、最高品質・最
低コストの物流サービスを親会社・グループ会社に提
供するということだ。
したがって、この場合のいわゆ
る外販は、親会社への貢献という文脈でのみ追及され
る。
外販からの利益自体は大きな問題ではない。
このオプションでは、親会社の浮沈に大きく左右さ
れるというリスクを抱える反面、冒頭の戦略方向性の
ところで言及したように親会社ビジネスへの深耕度合
は最大化され、グループ企業の全体最適を考える立場
となり、それゆえのビジネスチャンスが大きく広がる
可能性がある。
この場合、物流子会社独自のブランドは、ほとんど
意味を持たない。
あくまで本体の物流部門というのに
近く、社員の意識(アイデンティティー)も親会社の
社員のそれとさほどは変わらなくなる。
親会社は、子
会社のオペレーションのコントローラーとして機能し、人事権も場合によっては有し、単なる投資家として振
舞う訳ではない。
親会社からの出向者も転籍者も存
在するだろう。
また株式公開もこの場合は考えにくい。
親会社の立場で言えば、「良い子は身内でしっかり育
てる」という類型だ。
?グループ企業としてのアイデンティティーは維持す
るが、最大目標は物流子会社自身の事業利益の最
大化に置く。
親会社は、基本的に顧客の一つ(One of Them)
という捉え方になるが、当面は最大顧客であり物流子
会社のルーツとして存在し続ける。
つまりブランドと
いう側面から見れば、親会社のブランドプロミスの一
AUGUST 2004 28
部のエンドース(保証)を受けている物流子会社ブラ
ンドということになる。
また逆に子会社が親会社のブランドを強めるという
こともあり得る。
これが先に示した準コアブランドの
現実的なあり様である。
この場合、親会社の確立され
たブランドが既に存在するので、子会社ブランド育成
のコストはさほど大きくはない。
社員のアイデンティティーにはグループ会社員とし
ての誇りのようなものが含まれることにはなるが、そ
の大半は独立法人としてのそれである。
ブランドプロ
ミスも独自のものを全面的に押し出すこととなる。
親
会社の名前は、商売上その方が便利であり、社員の
納得感の高い限りにおいては使わせてもらうという重
要性に留まる。
この時、親会社は投資リターンを主に考慮する最大
株主というポジションになる。
親会社の人間は、転籍
となる場合が多く、やがて一人も存在しなくなるだろ
う。
人事制度なども子会社独自のビジネスに適応した
形のものが制定される。
親会社の立場で言えば、「良
い子には旅をさせ、自立させる」という類型だ。
?グループ企業としてのアイデンティティーは残さず
に、親会社の事業利益への貢献を至上の使命とし
て捉える。
このケースは実際にはほとんどあり得ないだろう。
?グループ企業としてのアイデンティティーを払拭し、
自社の事業利益最大化を事業目標とする。
これはほとんどグループ離脱と同じである。
社名か
ら親会社名は消える。
親会社は、依然として大口顧
客ではあるが、位置づけは完全にOne of Themであ
る。
ブランディングの面では、ブランドビルディングに
相対的に大きなコストと時間がかかる。
親会社からの
エンドースはもはや望めず、一から自社ブランドを立
ち上げていくしかない。
親会社のブランド体系とは無
関係になる。
確立したブランドがないために、優秀な
人材の採用には困難が予想されるが、実態として子会
社ではなくなるため独立企業というポジティブなイメ
ージを学生などには与えるかもしれない。
このオプションでは、事業上の自由度は最も高くな
るが、親会社という、時によっては緩衝として機能し
ていた存在がなくなるリスクを負うことになる。
親会
社の株式が残っていたとしても、投資リターンが最大
関心事の投資家という意味合いしかない。
人の派遣も
もはやなくなる。
この四つの類型のうち多くの物流子会社は、上記の
?と?の間を行ったりきたりしているというのが実状ではないだろうか。
そしてできれば、?と?を両立さ
せるのが、最善解として見えているのではないだろう
か。
だが、その両立はかなり困難であることが予想さ
れる。
事業的に、また資源の限定性から言っても、親会
社ビジネスへの深耕と他社への広範なサービス提供を
両立させるのは無理がある。
またアイデンティティー
の面でも、一人の人間の中で両者を昇華させるのは不
可能に近い。
無理に同居させようとすると、必ず親会
社ビジネスに従事している社員と外販の社員の間で分
裂が起きる。
二つのセクターの間でシナジーは生じにくくなり、
一つの組織である意味合いがほとんどなくなる。
結果、
社員の求心力は減退する。
したがって、長期的にはど
29 AUGUST 2004
の方向を目指すのか早期に決断しておかないと、ブラ
ンディングを本格的に行うにしても手遅れになる可能
性が高い。
また時間軸をより長くとれば、大規模なロジスティ
クス専業企業に対抗していくためには、?というオプ
ションを「選択し続ける」事も、経済合理性のみから
考えるとあり得ない。
親会社への貢献を中心にオペレ
ートし続けてきた物流子会社が、コスト面・品質面に
おいて、トップクラスのロジスティクス専業企業を凌
駕できるとは考えにくい。
それでも親会社は子を選択し続けるだろうか。
どこ
かの段階では、独立企業体に向かうことが求められる
はずだ。
したがって、タイムスパンを拡げた場合のオ
プションは、?か?以外には考えられない。
ブランド経営の7ステップ
以上を踏まえて、物流子会社がブランディングに取
り組む場合のありうべきステップについてまとめてみ
よう。
Step1
何が自社の現在の(あるいは将来的に獲
得できる)組織能力、組織資源なのか、物流のどうい
う領域でどういう機能の組み合わせで付加価値を最大
化できるのかについて徹底的に議論を重ね、可能な限
り(潜在)競合優位性を明確にする。
Step2
将来の親会社・子会社の相対的な位置づ
け、物流子会社の事業ビジョンについて親会社となる
べく早い段階で合意する。
もはや問題の先送りは許さ
れない。
親会社が上記?を望まず、猶予を与えること
なくその時々で最適な業者を選んでいくという方針の
場合は、中期的に見ても?を追求することは難しくな
り、?か?を選択する確率が高くなるだろう。
Step3
社員の望むアイデンティティーの方向性
を調査し、その意向をできる限り受容する。
(場合に
よってはトップダウンでアイデンティティーの方向性
をはっきり示す。
)
Step4
?あるいは?という方向性が決まったら、
企業ブランドの長期における意味合いを明確にするた
めにブランドプロミスを確定する。
上記の組織能力・
組織資源にしたがって、事業領域(自社が勝てる生存
ゾーン)、差別化のポイント、パーソナリティーを定義
する。
事業領域においては、単に3PLとか総合物流
とか規定しても、抽象的・総花的すぎるかもしれない。
それでは、自社の個性の規定が十分でなく、ブランド
の「とんがり=鋭角性」に欠け、顧客に対してのイン
パクトが縮小する。
Step5
M&Aなどが想定される場合には、それにも適応できるブランド体系を前もって考慮しておく。
Step6 ブランドプロミスを基にして、(潜在)顧
客への一貫したコミュニケーションを開始する。
Step7
内部向けには、制度・システム(人事制
度、意思決定システムなど)を整備し、社員の求心力
を増強し、ブランドを体現できるような環境を整える。
?と?のケースで、上場を目標とするのであれば、
ブランド政策策定の重要性は益々高めるということを
付言しておきたい。
また、ファンドや競合からの買収
に対しては、ブランド価値を高めておくことが最大の
防御となり得ることを最後に強調しておく。
きくち・たかし「ブランド経営」コンサルティングのヴィブラ
ンド・コンサルティング代表取締役副社長。
東京大学文学部西洋
史学科卒。
米国スタンフォード大学MBA。
学部終了後、現・商
船三井入社。
日本と米国において海上コンテナの動態管理に従事。
その後、A.T.カーニーや英国系大手ブランド・コンサルティング
会社を経て、2003年7月より現職。
コンサルタントとして大手
エレクトロニクス企業のブランド価値評価、中央官庁への無形財
産価値測定手法の提言等、事業戦略策定のみならず、ブランド戦
略策定を含む無形財産関連の多くのプロジェクトをリード。
また、
ロジスティクス分野の活動・研究にも注力。
セミナー講師も務め、
また雑誌寄稿(日経ロジスティクス、流通設計等)多数。
連絡
先:kikuchi@viebrand.com
PROFILE
|