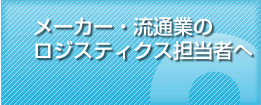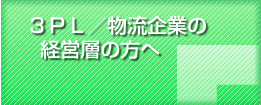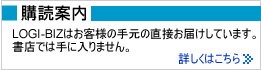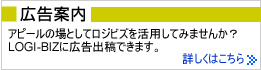|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

奥村宏 経済評論家
第29回『 実学』のすすめ
OCTOBER 2004 54
日本の経済学者たちはお互いを「経済学を知らない」とののしりあっている。
しかしその経済学とは現地直輸入の虚学にすぎない。
日本の現実に立脚した実
学としての経済学がないこと、これこそが経済学の危機である。
経済を知らない経済学者
ついこの間のことだが、不況を打開するためにインフレ目
標政策を導入すべきかどうかをめぐって、経済学者たちが激
しい論戦を戦わせていたことがある。
よくもまあこんなナンセンスなことを議論するものだと思
っていたが、そのころ「経済学を知らない」と経済学者がお
互いに非難し合うということが流行した。
野口旭専修大学教授の『経済論戦』(日本評論社)や若田
部昌澄早稲田大学助教授の『経済学者たちの戦い』(東洋経
済新報社)などがその見本だが、このような本を読んで私は
索漠とした感じを抱いたものである。
「経済学を知らない」と、この人たちは日本の経済学者や
エコノミストたちを批判するのだが、「では経済学を知った
ら経済がわかるのか」と聞きたいものだと思った。
この人たちの「経済学」というのはアメリカ、あるいはイ
ギリスの経済学を輸入したものだが、アメリカやイギリスの
経済学者はアメリカやイギリスの現実の分析から経済学を
打ちたてたのであって、「経済学」を勉強したことによって
理論を作り出したのではない。
D・リカードは株屋だったし、J・S・ミルは東インド
会社のサラリーマンだった。
アダム・スミスにしても「経済学」の本を読んで『国富
論』を書いたわけではないし、J・M・ケインズにしても現
実のイギリス経済を分析することで『一般理論』を書いたの
である。
それにくらべ日本の経済学者たちは外国の経済学を輸入
することに一所懸命だが、日本の現実から理論を作りだす
ことはしない。
せいぜいのところ輸入理論を日本に適用する
だけである。
これでは学生が経済学にソッポを向くのは当然である。
大
学の経済学部の人気が落ちているのは当然だというしかない。
石橋湛山の経済学
石橋湛山といえば一九五六年に総理大臣になったが、二
カ月で病気のために辞めた人として有名である。
その石橋湛山は戦前、東洋経済新報社の社長になったが、
その前、昭和初年の「金解禁論争」で高橋亀吉などととも
に論陣を張ったことで有名である。
もともと日蓮宗のお寺に生まれ、自分自身も宗教家にな
るつもりで早稲田大学の文学部哲学科を卒業したあと、同
大学の宗教研究科の特待研究生になった。
ところが東京毎
日新聞に就職したあとすぐに東洋経済新報社に転職し、以
後ジャーナリストとして活躍した人物である。
その石橋湛山
は『湛山回想』(岩波文庫)の中で次のように書いている。
「元来私は早稲田大学で哲学を修めた者で、経済のケの字も当時は知っていなかったので、もし東洋経済新報社が『東
洋時論』を発行していなかったら、私は絶対に当社に就職
することはなかったに違いない。
したがってまた、私はおそ
らく一生経済学に親しむ機会を持たなかったかも知れない。
されば私自身が、今の私と違っていたことはもちろん、東洋
経済新報社もまた、今のそれとは面目を異にしていたであろ
う。
よかったか、悪かったかはわからぬが、思えばまことに
偶然の回り合わせであった」(同書一六八〜一六九頁)。
東洋経済新報社で湛山ははじめは主として政治問題につ
いて論陣を張って軍備拡張に反対するなどしたのだが、やが
て経済問題についても金解禁などをめぐって持論を展開し
た。
湛山は次のようにも書いている。
「立派な経済学者であり、日本銀行の総裁であり、晩年は枢
密顧問官の要職についた深井英五氏も、経済学は中年から
自修した人で、その最初の自修書の一つは『東洋経済新報』
であったと、氏自身語っている。
氏はそのころ『東洋経済新
報』を、その広告の端にいたるまで一字残さず毎号読んだと
いうことだ」(同一七三〜一七四頁)。
55 OCTOBER 2004
実学と虚学
日本の経済学が駄目になったのはそれが輸入理論による
「虚学」であったからである。
そこで経済学が生き返るため
には、なにより「実学」にならなければならない。
私が大学で教えていたころ、学生たちからよく「先生はマ
ル経ですか、近経ですか」と聞かれたものである。
当時はま
だマルクス経済学者の力が強くて、どこの大学でもマル経と
近経(近代経済学)の先生が人事問題などで激しく対立し
ていた。
そこで学生も私が、そのどちらに属するのか、聞き
たがったのである。
それに対して私は「そのどちらでもない。
私は実学派だ」
と答えたものである。
ここで「実学」というのは実業の役に
立つ学問という意味ではない。
現実の中から理論を作り出していく学問だという意味である。
私の法人資本主義論はこのような「実学」の産物である。
したがって輸入理論の「経済学者」たちからは評価されない
し、私もそういう人を相手にしない。
唯一、私の法人資本主義を評価して下さったのは今は亡き
ロンドン大学名誉教授の森嶋通夫先生であった。
先生が編集
している『経済学の歴史と発展についての古典』というマク
ミラン社のシリーズに私の本が『コーポーレト・キャピタリ
ズム・イン・ジャパン』という題で訳され出版されている。
先に言ったようにスミスもミルも、そしてケインズもみな
現実のイギリス経済の現実の中から自分の理論を作り出し
た。
同じように石橋湛山も経済の現実を分析することから
自分の主張をした。
それにくらべて戦後の日本ではアメリカ産の輸入経済学
が唯一の「経済学」で、それを知らない経済学者やエコノミ
ストを「経済学を知らない」とののしりあっている。
こうして日本には「経済を知らない経済学者」ばかりにな
っている。
これが経済学の危機でなくしてなんであろう。
おくむら・ひろし 1930年生まれ。
新聞記者、経済研究所員を経て、龍谷
大学教授、中央大学教授を歴任。
日本
は世界にも希な「法人資本主義」であ
るという視点から独自の企業論、証券
市場論を展開。
日本の大企業の株式の
持ち合いと企業系列の矛盾を鋭く批判
してきた。
近著に『判断力』(岩波新
書)。
大事な会社の研究
先にあげた『経済論戦』でもそうだが、そこで「経済学」
といわれているのはいわゆるマクロ経済学で、インフレ政策
を導入すべきか、それとも需要創出(デマンド・プル)をや
るべきか、ということをめぐる論戦である。
それはいうなれば政府や官庁で議論されている問題ではあ
るが、経済の現実とはかけ離れた議論で、このような「論
戦」を読んでも日本経済の現実の解明にはなんの役にもた
たない。
日銀総裁であった深井英五が一字も残さず読んだという
当時の『東洋経済新報』は会社記事が中心で、いわゆる私
経済に力を入れ、公経済(マクロ経済)には重きをおかなか
った。
これも『湛山回想』の二四七頁以下に出てくるとこ
ろだが、会社が経済を動かしている以上、経済雑誌が会社
記事に力を入れるのは当然のことである。
もっとも『東洋経済新報』が会社記事に力を入れたのは
株式投資家のためだったということは『湛山回想』に出てい
るが……。
戦後、とりわけ一九五五年ごろからの日本は法人資本主
義であるというのが私の主張だが、ここでいう法人とは会社
のことであり、英語でいえばコーポレート・キャピタリズム
である。
それだけに戦後の日本経済を知るためにはなにより会社の
ことを研究しなければならない。
しかもそれはアメリカ産の
ミクロ経済学のような抽象的な内容のものでなく、会社のな
まの現実を総体としてとらえるものでなければならない。
ところが日本の経済学者がもっとも不得意とするのがこの
ような分野の研究である。
もし会社を研究している学者がい
るとすればそれは経営学者たちだが、これまた輸入理論か、
それとも会社の「御用学者」になってしまっており、批判的
に会社を解明しようとする学者はいないといってもよい。
|