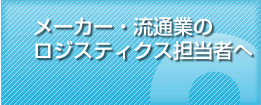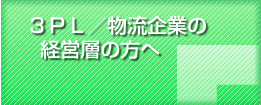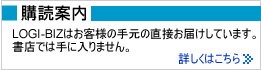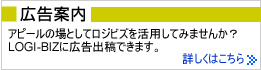|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

DECEMBER 2003 38
最年少社長の打ち出す新サービス
今年九月、宅配便最大手であるヤマト運輸
の関連会社に、グループで最年少の社長が誕
生した。
土田正浩氏、三二歳。
九二年四月入
社の若手社員だ。
今回社長に抜擢されるまで、
同氏は一般ユーザーから寄せられる宅急便の
再配達依頼などを処理するコールセンターの
運営を任されていた。
現在、ヤマト運輸には情報システム系のヤ
マトシステム開発、書籍販売のブックサービ
スなどグループ会社が国内に四四社ある。
社
長の平均年齢は五六・六歳だ。
それだけに三
二歳で社長就任となった今回の人事は極めて
異例と言える。
「最年少社長としてのプレッシャーがまったく
ないと言えば嘘になる。
しかし社長になった
以上、ヤマト運輸の看板に傷をつけないよう
にきちんと会社を経営していきたい」と土田
社長は意気込んでいる。
土田社長が率いるのは「ヤマトコンタクト
サービス」(以下、YCS)。
荷主企業に代わ
って、顧客に直接コンタクト(連絡・交渉)
する。
具体的には顧客からの電
話注文を処理するコールセンタ
ー業務などを請け負う。
今風に
言えば、「テレマーケティングサ
ービス」を提供する会社だ。
資
本金は二〇〇〇万円で、今年九
月に設立された。
社内ベンチャー制で32歳の社長誕生
宅急便+テレマーケティングを商品化
昨年9月、社内ベンチャー制度を新設した。
物流現場の最前線で活躍する社員たちの斬新
なアイデアを事業化するのが狙い。
第1回目
の募集には15件の応募があり、このうち「テ
レマーケティングサービスの提供」が第1号
案件に選ばれた。
1年間の準備期間を経て、
今年9月に新会社「ヤマトコンタクトサービ
ス」を発足した。
ヤマト運輸
―― 新規事業
ヤマトコンタクトサー
ビスの土田正浩社長
39 DECEMBER 2003
同社が用意しているサービスはユニークな
ものばかりだ。
例えば「ヤマトプレコールサ
ービス」。
このサービスは発送人の代わりに同
社が荷受け人に事前に電話連絡して在宅日時
を確認。
その後、指定された時間に商品を届
けるというものだ。
とりわけ高額ギフト商品
や生花、生鮮食品に適しているという。
百貨店で歳暮品として魚介類を購入。
それ
を遠方の友人に送るとしよう。
歳暮品が届く
ことを知らないその友人は会社から帰宅後、
郵便ポストに宅配便会社の不在票が投げ込ま
れていることに気づく。
しかし、すでに深夜
で再配達を依頼できない。
明日も朝が早い。
しかも国内出張で明日から三日間ほど自宅を
空ける。
荷受けできるのは早くても四日後に
なる。
魚介類はすぐに鮮度が落ちてしまう。
冷蔵庫で保管されたとしても四日も経過すれば、口
にできなくなる可能性がある。
食べられない
ものをもらっても嬉しくない。
当然、友人は
百貨店に商品を返品して、新しいものに取り
替えてもらおうと考える。
そして百貨店は要
求に応じる。
結局、百貨店は腐ってしまった
商品と新しい商品のコスト負担を強いられる。
これに対して、「ヤマトプレコールサービ
ス」を利用すれば、こうした問題は基本的に
解消される。
友人は好きな時間に商品を受け
取れる。
一方、百貨店サイドでは不在による
商品の持ち戻りが発生しない。
賞味期限が過
ぎてしまったため、商品を再送するといった
無駄なコストも掛からない。
発送人と荷受け
人の双方がメリットを享受できるわけだ。
「荷物を受け取る側は自分にいずれ荷物が
届くということを事前に知るから、『どんな商
品が届くのだろうか』とワクワクした気持ち
になるはず。
単に贈り物が届くよりも、この
ワクワク感がある分、贈り物の価値は高まる」
と土田社長は説明する。
宅急便をカスタマイズ
「ヤマトアフターコールサービス」も珍しいサ
ービスだ。
このサービスは「宅急便」や「メ
ール便」で商品や資料を届けた後、タイミン
グを見ながら荷主企業に代わって電話などを
通じて荷受け人に対してセールスを行ったり、
お礼の挨拶を述べるというもの。
荷主企業の
認知度を高めたり、売り上げの拡大に貢献す
ることを目的としている。
例えば、ある化粧品メーカーがユーザーの
女性に新作の化粧品の試供品を送ったとしよ
う。
まず化粧品メーカーは試供品が到着する
日に「試供品の送付を申し込んでくれたこと
に対するお礼」をユーザーに電話で述べるよ
うYCSに依頼する。
さらにその二週間後。
今度は試供品使用の感想のヒアリングと商品
のセールスもYCSに代行してもらうことが
できる。
単に試供品を送りつけるだけでは消
費者は注文に走らない。
送付後のフォローを
大切にすることで、ヒット率を高めようとい
う狙いだ。
三つ目が「ヤマトピックアップコールサー
ビス」。
今年九月にサービスを開始して以来、
特に引き合いが多い。
修理品やリコール品、
リース満了品などをユーザーから回収して指
定された場所に集めるサービスだ(図参照)。
荷主企業に代わってユーザーに直接電話連
絡を入れて、回収品の集荷日時を決めたり、
リコールの発生を詫びたり、これまでの利用
に対するお礼を述べたりといったオプション
サービスが用意されている。
YCSに委託す
れば、荷主企業は「ユーザーとの折衝や、商
品回収を担当するヤマト運輸との情報のやり
取りなど手間の掛かる業務から解放される」
(土田社長)。
すでにいくつか案件も動き出している。
例
えば、ある工具メーカーは、もともとユーザ
ヤマトピックアップコールサービス
荷主企業 YCS
ヤマト運輸
宅急便センター
顧客
?ピックアップデータ
?ピックアップ完了データ
?集荷指示
?集荷
?荷主企業に代わり、ご
挨拶・お詫びとともにに、
集荷日時を確認
当日夕方までの集荷依頼に
関しては、当日処理が可能
ピックアップ対象商品
通販………キャンセル品
メーカー…修理品・リコール品
リース……リース満了品など
DECEMBER 2003 40
ー→工具店→メーカーという順序で修理品を
回収していたが、これを同サービスの利用で
ユーザーから直接、回収する体制に改めた。
また、あるカーオーディオメーカーはカー用
品店に持ち込まれる修理品の回収に同サービ
スを活用している。
YCSではこのほかにも受注窓口やキャン
ペーンの問い合わせ窓口などを代行する「ヤ
マトインバウンドサービス」、宅急便やロジス
ティクス、決済などヤマト運輸グループのサ
ービス機能を自由に組み合わせることで、受
注から商品発送、クレーム処理などのアフタ
ーサービスまでを丸投げできる「ヤマトフル
フィルメントサービス」といったメニューを
用意している。
いずれもこれまでのヤマト運輸にはなかっ
た痒い部分に手の届くサービスだ。
顧客の反
応も上々で、土田社長は「イケるという手応
えを感じている。
三年後に売り上げ五億円を
達成する」ことを目標に掲げている。
コールセンター時代に発案
もともとヤマト運輸には宅急便など物流に
付随するサービス、例えば今回のようなテレ
マーケティングサービスなどを引き受けても
らえないかといった依頼が数多く寄せられて
いた。
ところが、これまでヤマトではこうし
たニーズに対して各営業所が個別にできる範
囲内で対応するだけで、会社として専門的な
組織を用意してこなかった。
一商品ではなく、
ある特定企業のための例外的なサービスという位置付けにすぎなかった。
しかし、土田社長にはテレマーケティング
サービスを商品化すれば絶対にビジネスとし
て成立するという確信があった。
前述したよ
うな一風変わったサービスはすべて土田社長
がコールセンターを担当していた時代に発案
したものだ。
土田社長は常に自分のアイデア
を具現化できるチャンスを探ってきたという。
「きっと私だけじゃない。
荷主企業と接してい
るヤマトの営業マンであれば誰もが物流市場
にこうしたニーズがあることを認識していた
と思う」と土田社長は指摘する。
土田社長にとって追い風となったのは、昨
年九月に社内ベンチャー制度「Y―Venture
Dream
(ワイベンチャードリーム)」が新設
されたことだった。
この制度は物流現場の最
前線で活躍する社員たちの斬新なアイデアを
事業化することを目的としている。
新サービ
スのアイデアやビジネスモデルを記した書類
を募集期間内にベンチャー事務局に提出。
そ
の後プレゼンテーションや役員審査などを経
て、見事採用されれば新たに会社を設立でき
るという仕組みだ。
もちろん土田社長は自分が温めてきたアイ
デアを応募することにした。
ただし、土田社長
には社長になりたいという野心はなかった。
社
長のイスを獲得することよりも「テレマーケテ
ィングの事業モデルをどうしても成功させた
いという気持ちのほうが強かった」という。
ヤマト版「マネーの虎」
「ワイベンチャードリーム」
の第一回募集期間は昨年九月
一日から三〇日までの一カ月
間だった。
応募は一五件あっ
た。
事務局では当初、応募し
てくる社員の年齢層を二〇〜三〇代と想定し
ていたが、実際には二〇〜五〇代までの幅広
い年齢層から申し込みが寄せられた。
職層も
管理職から最前線のセールスドライバーまで
と多岐に渡った。
ちなみに一五件の具体的な
中身は今後事業化に漕ぎ着ける可能性もある
ため、ヤマトでは非公開としている。
土田社長を含めた応募者の一五人はまず第
一次審査としてプレゼンテーションに臨んだ。
そこで?アイデアおよび事業モデル、?アイ
デアを市場でどう販売していくかというアク
ションプラン、?出資および資金計画――と
いったビジネスモデルの内容を審査メンバー
に詳しく説明した。
プレゼン後、審査メンバ
ーからビジネスモデルに欠けている部分や修
正すべき箇所など?ダメ出し〞をもらって、
一次審査は終了した。
一次審査を通過した応募者たちはその後約
一カ月間費やして、今度は「企画書」よりも
精度の高い「事業計画書」を作成した。
そし
てこの事業計画書をベースに二次審査である
役員相手のプレゼンに挑んだ。
プレゼンの持
ち時間は一人三〇分。
もう三〇分は質疑応答ヤ
マ
ト
運
輸
の
斉
藤
政
義
グループ経営推進課長
41 DECEMBER 2003
の時間で、役員からビジネスモデルに関して
容赦なく質問を浴びせられた。
二次審査を通過できれば、ベンチャー企業
の立ち上げをほぼ手中に収めたこととなる。
ただし、会社を設立する前にもう一度、市場
にどれだけのニーズがあるかをきちんと調査
する期間が与えられる。
シミュレーションを
繰り返して、事業化に問題ないことを確認す
るためだ。
この作業を経てから会社設立の具
体的な準備に取り掛かる。
会社の定款や就業規則の作成。
さらに社会
保険等の手続きなど起業時に必要となる煩わ
しい事務作業はすべて新会社が自らで処理す
るルールを設けている。
ヤマト本体は出資な
どを通じて新会社を側面支援するだけ。
余計
な口出しはしない。
こうした放任主義の姿勢には会社と事業を
ゼロから興すことができる真のベンチャー経
営者を育成するという狙いが込められている。
「自分の企画を事業化することにどれだけ熱
意があるかでベンチャーの成否は決まってく
る。
しかし、熱意やアイデアだけでは会社は
機能しない。
立ち上げ準備などの苦労も味わ
ってもらったほうが経営者になる本人にとっ
てプラスになるはずだ」とベンチャー制度を
運営する企画部グループ経営推進課の斉藤政
義課長は力説する。
昨年九月の初の公募では一五件の応募のう
ち、最終的に二件が採用されることになった。
一つはYCSの案件。
そしてもう一つは今年
一〇月に会社設立を済ませ、現在、本格的なサービス開始を準備している案件だ。
後者の
ほうは近日中にその詳細を正式発表する予定
だという。
さらに今年三月には第二回目の募集も実施
した。
応募は八件と前回に比べ減少したが、
その中身は大いに期待が持てるものばかりだ
った。
もちろん今回寄せられた案件も将来事
業化される可能性が高いため、その詳細は明
らかにしていない。
それでも斉藤課長は「YCSのように宅急
便事業に付随するサービスと、宅急便とはま
ったく関係のない新サービス。
事務局に寄せ
られる案件はこの二つのいずれか」と新サー
ビス候補の中身についてのヒントを披露する。
もう一つの隠し球
「スキー宅急便」、「ゴルフ宅急便」、「配達時
間帯指定サービス」など、ヤマト運輸はこれ
まで数多くのヒット商品を世に送り出してき
た。
そしてこれらのほとんどは現場で日々活
躍する社員たちの声を反映させて開発したも
のだった。
一〇億個に上る宅急便の取扱個数、
業界屈指の高い収益力の維持はこうしたヒッ
ト商品の存在なしでは到底成し得なかった。
しかしここ数年、ヤマトにはこれといった
ヒット商品が誕生していない。
そのため市場
では宅急便に付随したサービスは出尽くして
しまったのではないかという見方が拡がって
いる。
ところがこれに対して、ヤマトの認識
はまったく異なる。
「お客さんと接している現
場の社員には『こういうサービスがあれば必
ずヒットするのになあ』という閃きがまだま
だ沢山あるようだ」(斉藤課長)と見ている。
昔からヤマトには現場社員が役員を相手に
新サービスのアイデアを披露する場が用意さ
れていた。
それに今回ベンチャー制度という
仕組みを新たに加えたのは、「社長のイス」と
いう特典を与えることで、社員たちの新サー
ビス開発に対する意識を再び鼓舞したいとい
う狙いがあったからだ。
ベンチャー制度には出資金の限度額など枠
は何も設けられていないという。
ヤマトでは
事業化できるアイデアであれば、投資は惜し
まない方針だ。
事務局も「応募期間は三月と
九月の年に二回ある。
これは、と思うアイデ
アがあればどんどん出してほしい」(斉藤課
長)と期待を寄せている。
今後、この制度が社内に浸透していくかど
うかは第一号案件であるYCSの成否に掛か
っている。
しかし、心配はいらないようだ。
Y
CSの業績はこれまでのところ、当初計画し
た通りに推移しているという。
仮に失敗したとしても、実はもう一つ、今
回とはまったく異なる新サービスという隠し
球を、土田社長は持っている。
「そのアイデア
の中身はもちろん秘密だ」(土田社長)。
いず
れにしてもヤマトから久しぶりにヒット商品
が誕生するのはほぼ確実なようだ。
(刈屋大輔)
|