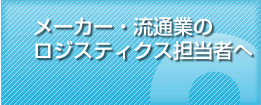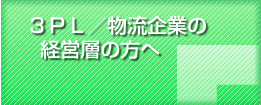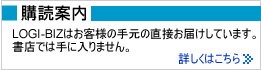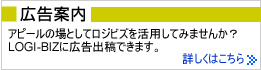|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

JUNE 2002 16
米国型3PLは成り立たない
――かつての第一貨物は長距離幹線輸送(路線)を事
業の中心に据えた典型的な特別積み合わせ事業者(特
積み)というイメージが強かった。
それが九〇年代の
後半から急速に3PLにシフトしつつあるように見え
ます。
「私自身は当社をサードパーティーとは考えていま
せん。
我々はアセット(資産)を持ったキャリア(実
運送会社)ですから、サードパーティーという言葉は
馴染まない。
むしろ、ロジスティクス・サービス・プ
ロバイダー(LSP)という言葉の方が適切だと思っ
ています」
――しかし第一貨物はヤマダ電機や住友スリーエムな
ど、日本では先進的と言える3PLプロジェクトをい
くつも手がけている。
「そもそも契約形態自体に、日本と米国では『オー
プン・ブック』と『クローズド・ブック』の違いがあ
ります。
オープン・ブックとはサービスの提供側のコ
ストとマネジメント・フィーが荷主側に公開されてい
る契約形態。
要するに実運賃にいくら乗せたかが分か
る契約です。
3PLが日本に紹介されたときに調べた
のですが、米国ではそれが基本になっている。
しかも
契約の中には、アウトソーシングによって出た成果を
事業者と荷主側とで分ける、つまりゲインシェアリン
グまで明記されていると聞いています」
「ところが日本は、ほとんどがクローズド・ブックで
す。
つまり運賃をどう使おうが荷主は関知しない。
そ
の代わりマネジメント・フィーを支払うという感覚も
ない。
従って当社としては、現状の契約金額の中でい
かに自社のアセットを使って投資のリターンを求める
か。
また当社自身で全てのアセットを賄うのは不可能
ですから、いかに協力業者を管理してスキルを上げて
いくかというアプローチをとることになる」
――しかし日本の運賃タリフも基本的にはコスト・プ
ラス・マージンで作成されています。
「タリフというのは、あくまでも基準となる料金で
あって、実際の原価を反映したものではありません。
標準原価ではあるけれども、その計算自体に机上の空
論的な部分がある。
実際には、ある部分では儲かり、
ある部分では損をして、最終的に一定の利益が出れば
いいという形の使われ方がされています」
――日本の荷主は物流業者のコストを把握していな
い?
「皮肉っぽく言えば、物流事業者自身がこれまで一
件ごとの明確なコストを把握していなかった。
これに
対して米国の3PLは実運送会社ではないから誰の
目から見てもコストは明らかです。
実際の支払い運賃
がコストですからね。
後はそこにいくら上乗せするか
という交渉になる」
――3PLはアセット型がいいのか、ノンアセット型
かという議論は以前からありましたが、ノンアセット
型こそが3PLという認識なのですね。
「私はサードパーティーを、キャリアでもなく、ウエ
アハウスでもない第三者のことだと理解しています。
その意味でいえばアセット型3PLという言葉は矛盾
しています」
――しかし日本市場にはノンアセット型の3PLなど
ありません。
「日本の場合、汗水流して、車を動かして、モノを
移動して、倉庫管理をしてナンボという考えが根強く
て、マネジメントやアイデアなど、目に見えないもの
に対してお金を払うという習慣があまりない。
とくに
運送事業には馴染まないと思います」
「路線のアセットをSCMに活かす」
過去10年で日本の物流市場の環境は一変した。
もはや特別積
み合わせ事業者の既存のビジネスモデルは通用しない。
業態転換
は待ったなしだ。
ただし米国のようなノンアセット型の3PLは
日本市場には馴染まない。
特積みのアセットを活かした独自の物
流アウトソーシング事業を目指す。
第一貨物 武藤幸規社長(日本路線トラック連盟会長)
Interview
17 JUNE 2002
――3PLの定義はともあれ、日本の物流市場にアウ
トソーシングのニーズが生まれていることは確かです。
「それはその通りです。
コアコンピタンスやアウトソ
ーシングといった欧米流のビジネスモデルが日本でも
ポピュラーになりつつある今、物流を単に物の流れや
輸送という観点だけでなく、全体で捉えなければマー
ケットの中で仕事をしていくのは難しくなっている。
こうした認識は以前からありましたが、この五年間は
特に強くなってきています」
従来型の路線事業は衰退へ
――その影響をモロに受けているのが、既存の特積み
業者だと思います。
特積み事業と3PLは全く噛み合
いません。
3PLというのは個別の荷主仕様のサービ
スですが、特積みは一種のパッケージ商品です。
この
二つは水と油のような印象を受ける。
「それは違いますね。
特積み事業には従来からオー
ダーメード的な部分がかなりあった。
顧客仕様に合わ
せた伝票の作成を始め、あらゆることが行われてきま
した。
もちろん、そうした個別の顧客仕様のサービス
とネットワーク全体の効率をどう両立するかという問
題については九〇年以前からずっと意識されてきまし
た。
一時は荷主の業種でくくるのも一つの方法だと考
えましたが、やはりそれでもうまくいかない」
「しかし、そこで立ち止まってしまうと前には進ま
ない。
市場なくして事業はあり得ません。
路線が使わ
れた時代は既に過ぎ去っています。
市場から見れば、
もはや路線がどうだ、区域がどうだ、宅配がどうだと
いう区分は関係ありません。
荷主企業は単に自分の仕
事に集中したいから全てをアウトソーシングしたいと
だけ考えている。
それなのにいまだに従来型の路線事
業を企業戦略の柱として考えているとしたら、その会
社は間違いなく衰退を辿ります。
そうしたことを我々
は肌で感じている」
――かつては路線業のサービス自体が荷主から強く求
められた時代もありました。
「もちろんありました。
路線の機能そのものが市場
で売り買いされていた。
しかし市場は劇的に変わって
います。
そこで従来のやり方を変えて、一種の路線業
である非常にニッチな共同配送を手掛けることで生き
ていこうとする路線会社もまだ多くありますが、それ
にも限界がある」
「ただし私は必ずしも単純な特積み衰退論者ではあ
りません。
路線業が担ってきた『積み合わせ』という
概念はこれからの時代に絶対に活きてくる。
とくに一
番のポイントとなるのは路線業のヤードです。
仕分け
場を持っている我々は、今日のSCMで指向されてい
る在庫を持たない経営、そこで必要とされるスルー型
の流通では大いに力を発揮できる」
――それは不特定多数の荷物を混載する従来の路線業者が、個別の顧客仕様に合わせた専属業者に転換し
ていくことを意味するはずです。
「そうですね。
最終的には顧客仕様ということにな
ります。
路線業を装置産業と考えれば矛盾かも知れま
せんが、それを受け入れなければならない。
ただし当
社には契約先が約四万社あります。
その全てに対して
顧客仕様にすることは不可能です。
したがって、双方
に対応することのできる、かなり柔軟な業務形態が取
れるような仕組みにしているつもりです」
――お手本は米国にありますか。
「ないでしょうね。
米国や日本の大手キャリアは3
PLをどんどん別会社にしています。
それらの3PL
子会社は親会社のアセットに縛られないことを売りに
しています。
それに対して当社は現在のアセットの有
JUNE 2002 18
効活用を前提にしている。
こうした展開の仕方は米国
でもレアケースだと思います」
中堅業者の舵取り
――ノンアセット3PLを子会社として立ち上げよう
とは考えなかった?
「もちろん、以前から欧米型の3PL会社を作って
展開すれば、という誘惑はかなりあるし、現実にそう
していないために仕事を失ったこともあります。
しか
し、当社のような中堅規模の業者が、大手と同じこと
をやっていたら量と力によって負けてしまう。
当社は
当社のやり方でいきます」
「当然のことですが『強み』がないと競争には勝てま
せん。
我々の強みが何かというと、非常に逆説的かも
しれないが、キャリアだから、アセット型だからとい
うことなんです。
当社のネットワーク、アセットをい
かにフルに活用して、コスト競争力を上げていくか。
事実そこに利益の大半を求めています」
「そもそも第三者を使うのではなく自社のアセット
を使って成果を上げることができるのなら、それに越
したことはない。
サービスの信頼性という問題に加え
て、物流オペレーションのコストダウンのカギはピー
クとオフの間をどう埋めていくか。
つまりアセットの
アイドル(遊び)をなくすことにあるわけですから」
――第一貨物のような中堅規模の路線業者は現在、一
番難しい舵取りを強いられているように思います。
資
産という意味では大手には敵わない。
しかしノンアセ
ットの身軽さもない。
「それは間違った指摘ではないと思いますし、『どっち
つかず』という批判に対しては、絶えず自問自答して
います。
しかし、中途半端な規模である我々が、なぜ
市場から評価されるのか。
漠然とした言い方になりま
すが、やはり信用力なんだと思います。
『まじめにこ
つこつ』という当社のスタンスを信頼していただいて
いるのだと思う。
それと情報力については大手と比べ
ても遜色ないつもりです」
――今風に言うとブランド・マネジメントですね
「それほど格好いいものではありませんよ。
ただし、
トップレベルの品質の維持、徹底的なコストダウン、
また情報処理の仕組み作りは絶えず進めてきたつもり
です。
それが、どっちつかずの規模にある当社に、市
場における存在感をもたらしてくれているのだと考え
ています」
――これまで物流業者は、ブランド力やブランド・マ
ネジメントというテーマを、それほど意識していなか
ったはずです。
「そうですね。
当社もブランド・マネジメントという
言葉を意識したわけではありません。
当社の生まれて
育ってきた前提、そして市場の将来を認識して、今の
時代にどう合わせていくかを考え抜いた結果が、会社
の個性、ブランド力を前面に出すことにつながってい
ます。
みんなで一緒に汗水垂らして仕事をするのが当
社の社風だと強く認識しているから、ノンアセットで
はなくてアセットでいく。
当社の強みはそこにあると
考えています」
「確かに規模では大手にはとても敵わない。
しかし、
お客様ごとにロジスティクスを作り込んでいく部分で
は絶対に負けない。
仕組みを作り込んで、実際に運営
していく力では絶対に負けない」
――第一貨物にとって従来型の路線業から3PLへの
転機になったのは、やはりヤマダ電機の受注ですか。
「それ以前から3PL的な仕事は手がけていました
が、取引規模という意味でいってもヤマダ電機さんと
住友スリーエムさん。
この二社からのアウトソーシン
19 JUNE 2002
グを受けたことがやはり大きな転機になりました」
――ヤマダ電機も住友スリーエムも全国規模の会社で
す。
アセットだけを評価すれば第一貨物ではなく、他
の大手業者に軍配が上がるはずです。
何が受注の決め
手だったのでしょう。
「やはり営業力ですよね。
これは米国の事例研究で
学んだのですが、アウトソーシングのコンペで最後に
どこの業者に決めるかという段階で、一つのポイント
になるのがトップセールスなんです。
アウトソーシン
グは一回限りの取引ではなく、会社と会社のパートナ
ー契約ですから、お互いに相手のトップの顔が見えな
いのはダメです。
逆の立場になってみれば当然、相手
のトップが何を考えているのか知りたいですからね。
そういう意味での行動力は他社に負けているつもりは
ありません。
実際、ほとんどの案件は私が営業に出向
いています」
特積みは再び脚光を浴びる
――そうやってアウトソーシング・ビジネスを拡大す
る一方で、逆に切り捨てる必要があるのは、どの部分
になりますか。
業態転換を進めていく上で不要になる
事業やアセットもあるはずです。
例えば宅配事業はど
う展開されますか。
「現在、当社はほとんど宅配はやっていません。
完
全に止めたわけではありませんが、積極的に当社から
営業することはない。
コアはあくまでもB
to
Bです」
――第一貨物は、トナミ運輸や西武運輸、岡山県貨物
運送などの中堅路線業者と貨物追跡システムの共用
を行っていますね。
こうした共同化の範囲は今後も広
がっていくのでしょうか。
「まあ、そうですね。
これはお互いの認識の一致が
必要ですけれど、機が熟したときはそうなる可能性は
十分あります。
ただ現在の中継業務(特積み業者同
士の輸送ネットワークの相互利用)はお互いもっとち
ゃんとやりたいし、他の事業者との幹線輸送のリード
タイム競争には今後も勝っていかなければならない」
――今後、特積み市場は寡占化が急速に進むはずです。
淘汰を生き残るために中堅同士が合併して日通やヤマ
ト、佐川に対抗できる第三勢力を作るというシナリオ
は?
「ないですね。
少なくとも現在は能動的に動こうと
は思いません。
単に規模だけの競争になってしまえば
当社の強みも消えてしまう。
合併したことによって負
けるという皮肉な結果になりかねない」
「確かに米国市場を見ると、八〇年の規制緩和の後、
極めてドラスティックに寡占化が進んだ。
しかし、い
ったん数社まで寡占化されて以降、現在は逆に業者
数が増えてきているんです。
翌日配達のネットワーク
を実際に管理できるのが路線業者しかいないからです。
日本でも集配を面的に展開できるヤードを持った路線
事業が再び脚光を浴びる時代になると思います」――ただし、かつての特積み事業は長距離幹線輸送が
コアでしたが、そこでは集配がコアになる。
ビジネス
モデルが全く違ってくる。
腰の重い特積み業者が変わ
れますか。
「既に幹線がコアだと認識している路線業者などい
ません。
むしろ幹線輸送は顧客に顔が見えないわけだ
からアウトソーシングしたって一向に構わない。
コア
が集配だと今や誰もが認識しています」
「物流業者に限らず、企業経営では市場に対する感
受性が問われます。
市場がどう動いているかというこ
とを感知して、それに自らをすり合わせる。
自分の体
力や筋力、持って産まれたものを含めてどう適応させ
ていくか、環境に馴染ませていくか。
それがマネジメ
ントだと考えています」
|