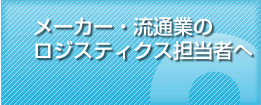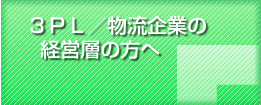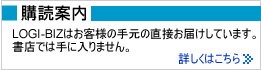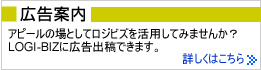|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

JULY 2007 28
物流システムで初の認証
「エコリーフ」は二〇〇二年四月に日本で
運用が始まった新しいISO規格の環境ラベ
ルだ。
一般に環境ラベルといえば、「エコマーク」がよく知られている。
第三者機関の審
査によって一定の環境基準を満たしていると
認定された商品にはこのラベルをつけること
ができる。
また、自社製品が環境負荷の少な
い商品であることをアピールするために、企
業が独自の基準で判断して環境ラベルをつけ
ることもISO規格で認められている。
「エコリーフ」は、これらの環境ラベルのよ
うに商品が環境面で優れていることを訴える
ものではない。
優れているかどうかを取引先
や消費者に判断してもらうため、その根拠と
なる情報を企業が自ら開示することを目的と
している。
開示するのは、原料や部品など製
品を構成する材料の内訳から、製造・物流・
ユーザーによる使用・廃棄・リサイクルまで、
すべてのライフステージにおける定量的な環
境情報だ。
どんな情報を収集し、どのように開示する
かについては、製品ごとに「製品分類別基準
(PSC)」というルールが設けられている。
認証を受ける企業は、このルールに則ってデ
ータ収集を行い、環境情報を作成する。
環境情報の作成には三段階のステップを踏
む。
まずステージごとにエネルギー使用量な
どの基礎データを収集して、これを製品一台
あたりなどに定量化した「製品データシート」
を作成する。
次にこの基礎データをLCA
(ライフサイクルアセスメント)手法によって
分析し、環境負荷に関連付けた「製品環境情
報開示シート」で表わす。
さらにこれらの情
報を、グラフなどで視覚的にわかりやすくし、
しかも統一性をもたせて表現した「製品環境
情報」を作成する。
認証機関の産業環境管理協会(JEMA
I)によって情報の客観性が検証された製品
は、「エコリーフ環境ラベル」を取得する。
そ
の登録番号を元にJEMAIのホームページ
からアクセスすることで、ユーザーにこれら
の情報が公開されるという仕組みだ。
この制度に参加する企業は、製品のライフ
サイクル全体を通じて環境データを収集する
ことになる。
それ自体が有意義な環境活動と
なる。
またグリーン調達志向の強い企業が増えていくことで、「エコリーフ」がコミュニケ
ーションツールとして活用される機会も多く
なると期待されている。
「エコリーフ環境ラベル」の対象には、製
品だけでなくサービスも含まれている。
もっ
ともこれまでに四〇〇件以上が認証を受けて
いるが、その大半は精密機器や通信機器、住
宅用部材など中間製品も含めた製品に限られ
ていた。
それに対してモスフードサービスは
今年二月、「食材配送システム」というサー
ビスで初の「エコリーフ環境ラベル」認証を
取得した。
環境対策
モスフードサービス
食材配送の環境負荷情報を公開
産地〜店舗までの輸送データ収集
ハンバーガーチェーンのモスフードサービス
は、食材配送システムで初の「エコリーフ環境ラ
ベル」認証を取得した。
産地で収穫された野菜が
店に届くまで、全物流工程でのエネルギー使用
量を一年がかりで算出し、環境負荷情報を公開
している。
産地までさかのぼって輸配送データ
を収集するなど、小売業としては極めて意欲的
な取り組みだ。
29 JULY 2007
同社は二〇〇〇年に設置した環境推進グル
ープ(二〇〇七年三月に社会貢献グループに
改組)を中心に、本社や配送センター、店舗
でのエネルギー使用量の削減、廃食油や残渣
の回収・リサイクルなど環境への負荷を軽減
する活動を進めてきた。
さらに活動の対象を広げるべく、同グルー
プでは倉庫から店舗へ食材を配送する際の環
境負荷についても定量的に数値化する方法を
探っていた。
そんな折、「エコリーフ環境ラベ
ル」認証の対象にサービスが含まれ、同社のよ
うな小売業にも参加資格があることを知った。
作成する情報はサービスも製品と同じ。
た
だしデータ収集の範囲が異なる。
製品の場合
は製造から廃棄までの全ライフサイクルを対
象とするのに対して、「食材配送システム」は
食材を産地や加工工場から調達して店舗へ配
送するまでのすべての物流工程がデータ収集
の対象となる。
産地から配送拠点まで、さらに店舗までの
輸配送データ、配送拠点でのエネルギーや包
装材の使用量を収集して公開する。
これはま
さしく、同社が環境活動の次のターゲットと
していた内容そのものだった。
しかも同社は情報公開の仕方にも着目した。
社会貢献グループリーダーの中山卓三氏は「第三者機関から検証を受けるという信頼性の高いやり方で情報を公開できる。
数年前か
らCSR活動の一環で情報公開に取り組んで
おり、この制度を利用することで活動に弾み
をつける狙いもあった」と話す。
通常であれば小売業が産地から店舗までの
輸配送データを収集するのは極めて困難だ。
日本では商品原価に調達のための物流コスト
を含める考え方が一般的で、店舗へ納入する
までの物流費をベンダー側が負担しているケ
ースが多い。
このため小売り側では輸配送の
実態を把握しにくい。
ところがモスの場合は、輸配送を始めとす
る物流関連の詳細なデータを収集するための
条件が揃っていた。
まず同社は食材をメーカ
ーや産地から直接仕入れている。
一般食材に
ついては全国一〇カ所に、また野菜について
は全国七カ所に配送センターを設け、これら
の拠点でメーカーや生産者から納品を受ける。
しかも食材をセンターに入荷した時点で同
社の在庫とし、外部委託するセンターの運営
費や店舗までの配送費を、すべて負担してい
る。
仕入れ価格の構造を明確にする目的で、
従来から自社で物流費を負担する形をとって
きた。
従って配送センターから店舗までの配
送については自社の管理下にあり、同社は荷
主の立場でデータを収集することができる。
野菜四品目を対象に
問題はそれより上流の、メーカーや産地の
拠点から同社の配送センターに納品されるま
での輸送データだ。
この部分の輸送については
同社が直接の荷主ではないため、データ収集に
も制約がある。
ただし野菜だけはほかの食材と事情が異な
る。
同社は食の安全性を確保するため?生産
者の顔が見える野菜〞を提唱、栄養価や肥
料・農薬の使用量などをもとに自ら選定した
契約農家から、すべての野菜を仕入れている。
商品流通部のアグリ事業グループの担当者が
契約農家を定期的に訪問して緊密な関係を築
いており、これまでも、農家から農薬の散布
回数や施肥量などの情報を提供してもらい消
費者への情報公開に取り組んできた。
こうした関係から、ほかの食材に比べて輸送データ
の収集をしやすい環境にある。
そこで同社はこの?生産者の顔が見える野
菜〞を対象に、産地までさかのぼってデータ
を収集することにした。
〇五年四月から〇六
年三月までの一年間をデータの収集期間とし、
野菜のなかで重量比の八割以上を占めるレタ
ス・トマト・タマネギ・カットタマネギの四
品目を選出、一トンを店舗に配送するまでの
環境負荷を算出した。
「食材配送システム」の製品分類別基準(P
SC)に対応した主なデータ収集のステージ
社会貢献グループリーダー
の中山卓三氏
JULY 2007 30
報から算出した。
輸送距離の計測では、産地
の県庁所在地を起点に配送センターまでの道
路上の距離を用いた。
カット野菜は加工場を
経由して配送センターに搬入されるため、そ
の経路も含めて算出した。
配送センターから全国に一一八二カ所ある
店舗への配送は四トン車がメーンだ。
他社と
の共同配送を実施しておりルートは日によっ
て変わる。
このため輸送距離は実際に巡回し
た距離ではなく、センターから各店舗までの
片道距離を合算して割り出した。
配送センタ
ーではフォークリフトなどの電力使用量のほ
か、段ボールや野菜の残渣などの排出量のデ
ータを収集した。
リターナブル容器を導入
この活動を同社は〇六年度も継続し、「エ
コリーフ」環境情報の更新を行った。
商品流
通部の大垣充部長は、「一年目の活動でデー
タの収集や数値化の方法を習得できたので、
二年目からはどんな工夫をすれば数値が改善
されるかを検討して、具体的な施策に反映さ
せてきた」と振り返る。
〇六年度には段ボールの使用量削減と残渣
のリサイクルを進め、数値の改善を図った。
そ
の一環として昨年の十二月には、四品目のう
ちのレタスの包装容器を全国規模でリターナ
ブル化した。
容器をリースして産地から店舗
まで一貫利用するものだ。
配送の帰り便で店舗
から配送センターに容器を回収し、それをさ
らにリース会社に委託して産地に戻している。
それまでレタスは段ボールで包装していた。
産地の畑で収穫したレタスをその場で出荷用
の段ボールに詰め込み、その荷姿のまま店舗
まで流通させていた。
雨天のときは収穫の際に段ボールが濡れる
ため、出荷前に上屋で新しい段ボールに入れ
替えなければならなかった。
また輸送中など
にレタスが蒸れてしまい、センターで廃棄処
分しなければならないこともあった。
そこでリターナブル化にあたり、収穫したまま野菜
の水切りができるカゴ状のプラスチック製通
い箱を採用した。
環境面だけでなく品質保持
による歩留まり向上の効果を狙った。
段ボールから通い箱への切り替えに合わせ
て、店の発注単位も変更した。
それまでは段
ボールの荷姿で店まで流通させるため、レタ
スの発注は一ケースが最小の単位だった。
だ
が店によっては一ケース分を一日で使いきれ
ないところもある。
そこで新たにハーフサイ
ズの発注単位を設定した。
配送センターでは、ハーフサイズのオーダ
は、?産地〜配送センター間の輸送、?配送
センター、?配送センター〜店舗間の配送の
三つ。
収集作業はそれぞれ、?産地〜配送セ
ンター間を商品流通部のアグリ事業グループ
が、?配送センターを社会貢献グループが、
?配送センター〜店舗間を商品流通部の物流
グループが担当し、輸送データやエネルギー
投入・排出量、包装材の使用量などの把握に
あたった。
おりしも省エネ法(エネルギー使用の合理
化に関する法律)が改正され、所有権を持つ
貨物の年間輸送量が三〇〇〇万トンキロ以上
の荷主は、昨年四月から輸送データの収集を
行わなければならなくなった。
モスの場合、
輸送量の規模から省エネ法の対象にはなって
いないが、規制に先行する形で独自にデータ
収集活動を開始したわけだ。
省エネ法と同様に「食材配送システム」の
PSCでは、輸配送時の燃料使用量の算出方
法として、燃料法、燃費法、トンキロ法の三
通りの方法が認められている。
モスはこのな
かで、使用燃料や燃費の実測値を必要としな
いトンキロ法を採用した。
トラック輸送の場
合、輸送重量と距離、車種、燃料の種類(軽
油かガソリンか)が把握できれば、エネルギ
ー消費量を算出できる。
野菜四品目の産地は計五二カ所。
ここから
七カ所の配送センターまでは主に一〇トント
ラックで輸送している。
産地によっては船や
航空機も利用している。
輸送重量は仕入れ情
商品流通部の大垣充部長
31 JULY 2007
ーが入ると、店舗別に仕分ける際に通い箱の
中身を半分にし、空いたスペースに小口の野
菜を詰めて店に配送する。
バラ出荷だったも
のも一つの荷姿にまとまり輸送効率が向上し
た。
店では必要な分だけ発注できるため鮮度
アップにつながった。
このほか、七カ所ある配送センターのうち
東京地区の拠点では、昨年から野菜の残渣の
リサイクルを実施している。
回収した残渣を埼
玉県内の加工場で堆肥にし、近隣の農家に利
用してもらうというリサイクルだ。
二三区内
の直営店からもいっしょに回収している。
これに先立ち同社は、食材を店舗に配送す
る車両で野菜くずを回収するというユニーク
な仕組みにもトライしている。
車両にリサイ
クル装置を搭載して、回収した野菜くずを走
行中に攪拌・裁断しながら減量化し、さらに
配送センターで車に積んだまま乾燥させて堆
肥の原料となるチップに加工する。
配送車で野菜くずを回収
野菜くずをゴミではなく有価物として扱う
ことによって、廃棄物処理法の適用を受けず
に一台の車両で配送と回収を同時に行えるよ
うにしたところがミソだ。
モスはこの仕組み
を、静脈物流への参入を狙う物流業者といっ
しょに構築、〇三年に仙台で農林水産省の実
証実験としてスタートした。
〇五年には、リサイクル装
置を搭載せずに折りたたみ式の
専用容器で回収するだけの簡
易的な方法を新たに採用し、名
古屋地区で実験を開始した。
現
在も二つの地区では実験を継
続しており、年間に三五トン
(〇五年実績)を回収している。
モスではこの仕組みを同業
他社などと共同利用すること
によって、社会システムとして
確立することをめざしてきた。
だがその後、回収の共同化は
期待通りには進んでいない。
一つには、売れ残りや食べ
残しまでは「有価物」として認
められないため、回収できる対象が野菜くず
などに限定されてしまうことがあげられる。
また荷主自身に残渣を食材といっしょに運ぶ
ことへの抵抗がある点も障害となっている。
実際に名古屋地区では、共同配送しているほ
かの荷主への配慮から、モスの店が最後の配
送先となるコースだけしか残渣の回収を行っ
ていないという。
「配送と回収を一度で行う方が環境にもい
いという認識がもっと広がらないと、この仕
組みを拡大するのは難しい」と中山リーダー
は見る。
昨年スタートした東京二三区のケー
スでは、コンビニチェーンなどと共同で一般
の廃棄物として回収する方法をとっている。
当面はこの方法でリサイクルを進める考えだ。
同社は〇六年度、チェーン全体で食品廃棄
物のリサイクル率が二〇%を超え、食品リサ
イクル法の示す目標を達成した。
一般食材の配送センターでのリサイクル率が九五%とい
う高い水準になったことなどが寄与している。
今年度は輸送の環境数値の改善に取り組む方
針だ。
これまでにも同社は店舗配送の共同化や三
温度帯一括配送に早くから着手し、拠点間輸
送のモーダルシフトも進めてきた。
次の施策
として今年は「エコリーフ」のデータをもと
に産地の見直しを行う。
「大消費地に近い産
地を選べば輸送距離が短くなり、環境数値は
もっとよくなる」と大垣部長は意欲的だ。
(
フリージャーナリスト・内田三知代)
|