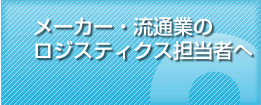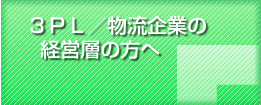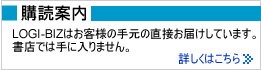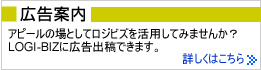|
*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

AUGUST 2007 32
「自動車もカマボコも一緒」
水産練り製品メーカー大手の紀文食品の社
内に昨年、「生産調査室」という部署が発足
した。
トヨタ自動車の社内でトヨタ生産方式を推進しているセクションを彷彿とさせる部
署名である。
紀文の石塚和仁生産調査室長は、
「いま我々は製造部門を非常に強くしていか
なければならない。
そのために改めてトヨタ
さんのやり方を勉強しろという意味合いで、
トップはこういう名称をつけたのだと思う」
と述懐する。
紀文は一九四七年の設立以来、流通の変
化に対応して物流管理を進化させ続けてきた。
腐りやすい製品を扱っていることから、保管
や輸送といった物流機能以上に、生産から納
品までのリードタイムの短縮や温度帯管理な
どを一貫して重視してきた。
もっとも一九六〇年代までの販路は、百貨
店と市場(問屋)が中心で、工場から出荷す
る製品をまとめて納品すればよく、物流管理
は複雑ではなかった。
その後、スーパーマー
ケットをはじめとするチェーン小売業の台頭
によって、納品先が徐々に量販店へとシフト
していった。
難易度を増した物流ニーズに対応するため、
七二年には「東京流通センター」(TRC)
内に低温物流拠点を稼動。
チルド物流ネット
ワークの構築に着手した。
さらに八〇年代に
は、紀文の物流管理にとって特筆すべき二つ
のターニングポイントが訪れた。
一つはNP
S研究会への参加。
もう一つは物流子会社の設立である。
紀文はNPS(ニュー・プロダクション・
システム)研究会の初期メンバーの一社だ。
当時から経営トップの座にあった保芦將人社
長が、NPS流の活動をいち早く実践してい
たウシオ電機の工場を七九年に見学して感銘
を受け、翌年には紀文の社内にNKP(紀文
式NPS)の推進本部を設置。
八一年にNP
S研究会が正式に発足したときには中核的な
会員企業として参画し、現在に至るまで熱心
に活動を続けている。
NPS研究会というのは、トヨタ生産方式
定温物流
紀文食品
有力物流子会社から企画管理機能を吸収
役割分担を改めロジスティクスを再構築
チルド物流で定評のある物流子会社、紀文フ
レッシュシステムをグループ内に擁する。
一方、
紀文食品の社内では「営業+生産+物流」の全
体最適化のための試行錯誤をずっと続けてきた。
10年前には、子会社の持つ物流現場の管理機能
をいったん親会社に取り込み4年間ほど内製化。
グループ内の役割分担を再構築している。
33 AUGUST 2007
の創始者である大野耐一氏の右腕だった鈴村
喜久男氏を中心に設立された団体だ。
「一個
流し」(実需に応じて製品を一個ずつ生産す
る)の考え方に基づく無在庫経営の実践を提
唱してきた。
同研究会について書かれた『N
PSの奇跡』(東洋経済新報社)の中には、紀
文の保芦社長に対して大野耐一氏が、ことあ
るごとに「自動車もカマボコも作り方は一緒」
と言っていたと紹介されている。
トヨタ生産方式の発想をベースとしながら
も、徹底的に「A(営業)+B(生産)+C
(物流)」の連携にこだわるのがNPS流だ。
ただ当初、紀文の社内で実践されたNKPは
現場の改善活動が中心だった。
「営業+生産+
物流」を横断的に見直す動きを本格化するの
は、八〇年代の半ば以降になってからだ。
子会社まかせだった物流管理
もう一つ、紀文の物流管理にとって特筆す
べきは、八四年の物流子会社の設立だ。
社内
の「物流事業部」を分社・独立して紀文フレ
ッシュサプライ(現・紀文フレッシュシステ
ム)を設立した。
最初に手掛けたのは、大手
コンビニエンスストアの配送センターの運営
だった。
大手コンビニは店舗納品の効率化の
ためにチルド商品の物流インフラを必要とし
ていた。
しかし当時、それを担う専門業者は
存在しなかった。
そこでベンダーである紀文が顧客の要望に応えるかたちで事業化に乗り
出した。
紀文フレッシュサプライが紀文本体から全
面的に工場以降の物流管理を任され、チルド
物流ネットワークの整備を本格化するのは設
立から約半年後の話だ。
つまり食品メーカー
の物流子会社の多くが親会社の単なる元請と
して設立されたのに対し、この物流子会社は
市場のニーズから生まれた。
その後、同社は
順調に外販を拡大し、現在の外販比率は六割
を超える。
今日、同社が優良物流子会社の一
つに数えられるまでに至っているのは、その
生い立ちが深く関係している。
ただし、紀文本体の物流管理に軸足をおい
て見ていくと、物流子会社の成功は必ずしも
プラスの面ばかりではなかったことが分かる。
八四年に工場から先の物流管理を紀文フレッ
シュサプライに全面的に委ねたことで、紀文
の本体からは、物流を統括する部署がなくな
った。
全国各地の支店の指示に基づいて物流
子会社が製品を移動し、その結果としての物
流費の請求が支店にあがってくる。
これを全
体として管理するセクションはどこにも存在
せず、工場以降の管理は事実上、物流子会社
に丸投げという状態になった。
一方で、紀文本体にとっての物流管理の焦点は、前述したNKPによる「営業+生産+
物流」の最適化を工場段階でいかに実現する
かに絞られた。
取り組みの内容は極めて先進
的だった。
八六年に実施した「ラベル分荷」
はその最たる例だ。
これは、顧客の発注に応
じて、どこの小売店に、どのような製品を出
荷するのかを、出荷順に事前にラベルで打ち
出し、その順番通りに生産活動を実施しよう
という活動だ。
まさにトヨタと同様の「後工
程」から引っ張る生産を、水産練り製品の製
造現場にも適用しようというものだった。
当時の常識では、かなり極端な行為といえ
紀文食品・生産調査室の
石塚和仁室長
AUGUST 2007 34
鮮度への強いこだわりから、「製品を九州
から飛行機で運んだりして、NPS研究会の
指導者から?空飛ぶ何とか〞などと言われて
よく怒られていた」(石塚室長)という。
在
庫を極小化して、しかも実需に応じて製品を
供給しようとするトヨタ流の活動を、現場レ
ベルで無理に実践しようとするときに陥りが
ちな非効率の典型だった。
そこで紀文は九五年に発想を転換。
新たに
「供給圏」という考え方に基づく管理をスタ
ートした。
工場から二時間で行ける範囲を
「供給圏」として、そのエリアを越えて製品
を運ぶことを禁止したのである。
供給圏が狭
いほどリードタイムは短くなり、タイミング
よく、しかも最低限のコストで出荷できる。
この考え方が、工場からの生産日の「当日出
荷」と、客先への「翌日納品」を実現するう
えで大きな契機になった。
実際の「供給圏」の設定では、まず紀文の
製造拠点を主幹工場とこれを支える補完工場
に分類して、全国を六エリアに分割した。
当
時は地図情報システムなどは普及していなか
ったため、日本地図に工場をプロットし、そ
こを中心とする同心円を描いてエリアを設定
した。
さらにエリア内に輸送のためのデポや
プラットフォーム(積み替え拠点)を配置し
て輸送業務を最適化していった。
これによっ
て、平和島の物流センターにいったん製品を
集めていた従来のモノの流れは、根底から改
められることになった。
紀文本体による「供給圏」の設定は、それ
まで紀文FSまかせだった工場以降の物流管
理に親会社が参画することをも意味していた。
この傾向はどんどん加速し、翌九六年には紀
文の本社内に物流部門が新設され、それまで
支店任せだった管理を一元化した。
さらに九
七年になると、新たに稼動した東京工場(千
葉県印旛郡)を舞台に、物流管理を全面的に
紀文本体に?内製化〞するという思い切った
手段に打って出た。
一〇年間余りのNKPを通じて「営業+生産+物流」を追求していたものの、物流の実
務を管理するノウハウは紀文の社内にはなか
った。
「物流とはどういうものなのか、物流
機能とはどういう役割を持っているのかを見
つめ直す狙いがあった。
そのためには、やは
り自分たちでやってみなければ分からないじ
ゃないか」(永島副室長)という率直な反省
から出てきた荒業だった。
一番最初に物流の内製化に踏み切った東京
工場は、レイアウト設計の段階から物流を強
く意識して作られていた。
それ以前の物流拠
点が基本的に工場とは別に置かれていたのに
た。
「今でこそラベルを貼って納品するよう
にお客様から指示されることは珍しくないが、
当時そんなことを言っていたところはほとん
どなかった。
出荷時にラベルを貼るだけでも
画期的だったのに、このラベルを生産ライン
の一番前の攪拌工程に持っていき、この通り
に作ってくれということまでやっていた」と
生産調査室の永島裕明物流企画担当副室長
は振り返る。
紀文の本体でこうした試行錯誤が続けられ
る一方で、物流子会社によるネットワークの
整備も進行していた。
八八年には全国的な配
送網が完成。
さらに九三年になると「物流と
いうのはモノを運ぶだけでは足りない。
情報
を活用しなければダメ」との発想から、紀文
フレッシュサプライを紀文グループの情報子
会社と合併した。
このとき物流と情報を一手
に担う現在の紀文フレッシュシステム(以下、
紀文FS)が誕生した。
物流を再構築した九〇年代後半
紀文にとって九〇年代の半ばは、NKPで
掲げた「営業+生産+物流」による全体最適
化を?考え方〞から?実践〞のレベルへと落
とし込む時期だった。
この当時は、生産から
納品までのリードタイムの短縮こそが追求す
べき課題で、品質・納期・原価改善という三
つの観点から「営業+生産+物流」の見直し
を進めた。
リードタイムに執着しすぎて、と
きには非常識なことも行われていた。
紀文食品・生産調査室の
永島裕明物流企画担当副室長
35 AUGUST 2007
対し、ここでは完全に併設。
生産工程と出荷
機能を物理的に統合した。
このとき物流実務の管理まで自ら手掛けた
ことで、「お客様への出荷を意識しながら作
るということが非常に強く出てきた」(石塚
室長)。
大きな手応えを感じた同社は横浜工
場などでも同様の内製化を推進し、これを全
社に広げていった。
早く届けるだけでは足りない
このタイミングで紀文本体が物流管理に本
腰を入れた背景には、経済的な側面もあった。
当時は小売業界で一括物流センターの新設が
相次いでおり、多くのメーカーが物流管理の
複雑化とコスト負担の増大に頭を痛めていた。
いかに優秀な物流子会社でも、自らの身を削
るコスト削減は簡単ではない。
ここにも紀文
本体が物流管理に乗り出す理由があった。
結局、物流の内製化は、二〇〇一年に再び
物流管理を紀文FSに戻すまで約四年間つづ
いた。
その後は、紀文本体の物流部門は企
画・管理を担い、物流子会社は現場運営を手
掛けるという役割分担を明確化した。
紀文F
Sにとっては、四年間の厳しい時期を乗り切
ったことで体質がさらに強化され、より外販
志向を強めることになった。
ただし、この頃になると、紀文にとってま
ったく新しい状況が生まれていた。
かつては
製品に製造年月日だけを表示していたのが、
賞味期限の明記が義務づけられるようになっ
ていた。
さらに二〇〇〇年に雪印乳業が引き
起こした大規模な食中毒事件を一つのきっか
けとして、日本の消費者の「食の安全・安
心」に対する意識はどんどん先鋭化していた。
もはや作ったものを迅速に届けるだけでは
対応できない時代になっていた。
紀文として
も、「賞味期限こそが鮮度なんだ。
その賞味
期限を我々が保証していくんだという考え方
を持ちはじめていた」(石塚室長)
リードタイムを短縮しようとする従来の活
動の背景には、腐りやすい製品だからこそ早
く届けたいという事情があった。
それが賞味
期限を意識しはじめたことで、腐りにくい製
品を作るという新たな方向性が生まれた。
も
ちろん添加物などには頼らない。
生産工程に
おける衛生技術の高度化や、製品パッケージ
の工夫によって、製品のロングライフ化を図
るという動きが出てきたのである。
物流管理という意味でも、〇五年に本社内
に「物流構造改革委員会」という組織を立ち
上げた。
「物流部門というのは、ややもする
と物流企画だけのアプローチに陥りがちだ。
これに歯止めをかける姿勢を、生産部門や営
業部門とのプロジェクトとして示した」と永
島副室長はこの活動を振り返る。
同委員会は一年間で役割を終えたが、後を
引き継ぐように「生産調査室」が設置された。
そして、それまで本社内の独立部門として存
在していた物流企画部はここに飲み込まれた。
これもある意味では、物流が孤立することを
避けて、「営業+生産+物流」をさらに深耕していく工夫といえる。
しかし、石塚室長は、「現在の体制は、あ
る意味で過渡的なものだと私は考えている。
いずれ物流はもっと強い力で、会社をリード
していく立場になっていくと思う」と明かす。
新たに岡山県に大規模工場を稼動したことな
どによって供給圏は変化しつづけている。
最
近、NKPで注力している構内物流の作業改
善は、やればやるほど新たな課題が出てくる。
傍目には完成度が高く見える紀文の物流だが、
これからも立ち止まることはなさそうだ。
(
フリージャーナリスト・岡山宏之)
|