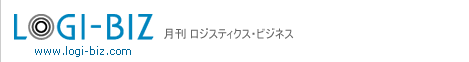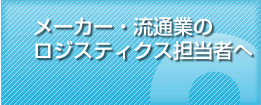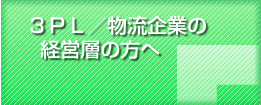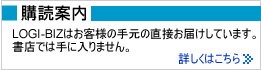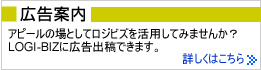|
*≤ΦΒ≠ΛœPDFΛηΛξΞΤΞ≠ΞΙΞ»ΛρΟξΫ–ΛΖΛΩΞ«ΓΦΞΩΛ«ΛΙΓΘ±ήΆςΛœPDFΛρΛ¥Άς≤ΦΛΒΛΛΓΘ

±ΩΝςΕ»Ζ–±ΡΦ‘ΛΈ≤α»ΨΩτΛ§ΦΖΓΜΚ–Α Ψε
ΓΓΙώ≈ΎΗρΡΧΨ ΛΈΜώΈΝΛΥΛηΛκΛ»ΓΔ±ΩΝςΕ»ΛΈ«―Ε»ΛœΓΜ
»§«·≈ΌΛΥΫιΛαΛΤΤσΓΜΓΜΓΜΖοΛρΡΕΛ®ΛΩΓΘ
ΓΜΕε«·≈ΌΛœ
ΧσΑλœΜΓΜΓΜΖοΛόΛ««―Ε»ΛΈΩτΛœΗΚΨ·ΛΖΛΩΛ§ΓΔΑΆΝ≥Λ»
ΛΖΛΤΙβΩεΫύΛΈΛόΛόΛάΓΘ
Τ±Μΰ¥ϋΛΈ±ΩΝςΕ»ΛΈ≈ίΜΚΖοΩτ
Λœ«·¥÷ΗόΓΜΓΜΖοΡχ≈ΌΛ«ΛΔΛΟΛΩΛ≥Λ»ΛΪΛιΓΔ«―Ε»ΛΖΛΩ
≤ώΦ“ΛΈ¬ΩΛ·ΛœΚΡΗΔΦ‘ΛΈΙγΑ’ΛΈΛβΛ»Λ«Ι‘ΛοΛλΛκ«ΛΑ’
άΕΜΜΛΥΛηΛΟΛΤ≤ώΦ“Λρ≤ρΜΕΛΖΛΩΛβΛΈΛ»ΙΆΛ®ΛιΛλΛκΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔ¬ΨΛΥΛβ ΐΥΓΛœΛΔΛΟΛΩΛΈΛΪΛβΟΈΛλΛ ΛΛΓΘ
≤ώ
Φ“ΛράΕΜΜΛΙΛκΛΥΛœ…‘ΤΑΜΚΛδΦ÷ΈΨΛ Λ…ΛΈΜώΜΚΛρΝ¥ΛΤ«δ
Β―ΛΖΗΫΕβ≤ΫΛΙΛκ…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΓΘ
άΕΜΜΛ«Λ≠ΛΩΛ»ΛΛΛΠΛ≥
Λ»ΛœΓΔΛΫΛΈΜώΕβΛ«…ιΚΡΛρ ÷ΛΜΛΩΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛάΓΘ
Γ÷¥π
Υή≈ΣΛΥΛœΓΔάΕΜΜΛΈΛ«Λ≠Λκ≤ώΦ“ΛœΘΆΓθΘΝΛ§≤Ρ«ΫΛ ≤ώ
Φ“ΛάΓΉΛ»ΓΔΟφΨ°¥κΕ»Λρ¬–ΨίΛ»ΛΖΛΩΘΆΓθΘΝΞΔΞ…Ξ–ΞΛ
ΞΕΞξΓΦΛρΧ≥ΛαΛκΞΙΞ»ΞιΞΛΞ·ΛΈά–ΡΆΟΛ»§ΦηΡυΧρΛœΛΛΛΠΓΘ
ΓΓ ΣΈ°Ά―ΟœΛœΈ°ΤΑά≠Λ§ΡψΛΛΛΩΛαΓΔΛΙΛΑΛΥΗΫΕβ≤ΫΛΖ
ΛηΛΠΛ»ΛΙΛλΛ–¬≠≤ΦΛρΗΪΛιΛλΛΤΛΖΛόΛΠΓΘ
ΛΖΛΪΛΖ≤ώΦ“
Λρ«δΒ―ΛΖΛΤΓΔΛΫΛΈΛόΛό ΣΈ°ΜωΕ»ΛΥΜ»Ά―ΛΙΛκΛΈΛ«ΛΔ
ΛλΛ–ΓΔΜώΜΚΛρΛΛΛΩΛΚΛιΛΥΧήΗΚΛξΛΒΛΜΛκΛ≥Λ»ΛœΛ ΛΛΓΘ
άΕΜΜΜΰΛΥΛœ¬ύΩΠΕβΛρΞαΓΦΞσΛ»ΛΙΛκœΪΤ·ΚΡΧ≥ΛΈΜΌ ß
ΛΛΛβ»·άΗΛΙΛκΛ§ΓΔ«δΒ―ΗεΛβ¥ϊ¬ΗΫΨΕ»ΑςΛΈΗέΆ―ΛρΑί
ΜΐΛ«Λ≠ΛκΛΈΛ«ΛΔΛλΛ–ΓΔΚΘΛΙΛΑΞ≠ΞψΞΟΞΖΞεΛρΆ―Α’ΛΙΛκ
…§ΆΉΛœΛ ΛΛΓΘ
ΓΓΘ
ΆΓθΘΝΛœά«ά©ΧΧΛ«ΛβΆ≠ΆχΛΥΤ·Λ·ΓΘ
άΕΜΜΗεΛΥΜΡΛΟ
ΛΩΜώΜΚΛρΞΣΓΦΞ ΓΦΛ§ΦΪ §ΛΈΛβΛΈΛΥΛΙΛκΛΥΛœΓΔ≤ώΦ“
Λ»ΛΖΛΤΦ¬Ηζά«Έ®ΧσΜΆΓΜΓσΛΈΥΓΩΆά«ΛρΜΌ ßΛΟΛΩΛΠΛ®
Λ«ΓΔΛΒΛιΛΥΗΡΩΆΛ»ΛΖΛΤΚ«¬γΗόΓΜΓσΛΈΫξΤάά«ΛρΜΌ ß
ΛΠΤσΫ≈≤ίά«Λ§»ρΛ±ΛιΛλΛ ΛΛΓΘ
Λ≥ΛλΛ§≥τΦΑΛΈΨυ≈œΛ«
ΛΔΛλΛ–ΓΔΑλΈßΤσΓΜΓσΛΈΩΫΙπ §ΈΞ≤ίά«Λ«Κ―ΛύΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛάΛ±ΛΈΞαΞξΞΟΞ»Λ§ΛΔΛξΛ Λ§ΛιάΕΜΜΛΥΤßΛΏάΎΛκ
ΟφΨ°±ΩΝς≤ώΦ“Λ§¬ΩΛΛΛΈΛœΓΔΘΆΓθΘΝΛΥ¬–ΛΙΛκΞόΞΛΞ ΞΙ
ΞΛΞαΓΦΞΗΛδ«ß
Φ±…‘¬≠Λ§¬γΛ≠
ΛΛΓΘ
ά–ΡΆΦηΡυ
ΧρΛœΓ÷ΞΣΓΦΞ ΓΦ
ΛΥΛœ«δΛξΛΩΛΛ
Λ»ΛΛΛΠΒΛΜΐΛΝ
ΛœΛΔΛΟΛΤΛβάΛ
¥÷¬ΈΛ§ΛΔΛΟΛΤ
άΦΛΥΫ–ΛΜΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛσΛ Λ≥Λ»Λ§≥ΑΛΥœ≥ΛλΛΩΛιΦηΑζάηΛδΕδΙ‘ΛΪΛιΞΫΞΟ
ΞίΗΰΛΪΛλΛΤΛΖΛόΛΠΛ»ΛΛΛΠΕ≤…ίΩ¥Λ§ΛΔΛΟΛΩΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔ
ΚΘΗεΛœΟφΨ°±ΩΝς≤ώΦ“ΛΈΘΆΓθΘΝΛ§≥ΈΦ¬ΛΥΝΐΛ®ΛΤΛΛΛ·ΓΉ
Λ»Ο«ΗάΛΙΛκΓΘ
ΓΓΤ±Φ“Λ§Ρ¥ΚΚΒΓ¥ΊΛΈΞ«ΓΦΞΩΛρ §άœΛΖΛΩΖκ≤ΧΓΔΖ–±Ρ
Φ‘ΛΈ«·ΈπΛ§ΦΖΓΜΚ–Α ΨεΛΈΞ»ΞιΞΟΞ·±ΩΝς≤ώΦ“ΛœΚΘΛδΕ»
≥ΠΝ¥¬ΈΛΈΗόΦΖΓΠΜΑΓσΛράξΛαΛΤΛΛΛκΛ≥Λ»Λ§»ΫΧάΛΖΛΩ
Γ ΩόΘ±ΓΥΓΘ
¬ΨΛΈΕ»ΦοΛ»»φ≥”ΛΖΛΤΛβΖ–±ΡΦ‘ΛΈΙβΈπ≤ΫΛ§
ΑΒ≈ί≈ΣΛΥΩ ΛσΛ«ΛΛΛκΓΘ
Ιβ≈ΌΖ–Κ―ά°ΡΙΜΰ¬εΛΥΜωΕ»Λρ
Έ©ΛΝΨεΛ≤ΛΩΞΣΓΦΞ ΓΦΖ–±ΡΦ‘ΛΈ¬ΩΛ·Λ§ΗΫΚΏΓΔΑζ¬ύΛΈΜΰ
¥ϋΛρΖόΛ®ΓΔΜωΕ»ΨΒΖ―Χδ¬ξΛΥΡΨΧΧΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΧσœΜΥϋΦ“ΛΥΨεΛκΤϋΥήΛΈΞ»ΞιΞΟΞ·±ΩΝς≤ώΦ“ΛΈΕε
ΕεΓσΑ ΨεΛœ«·ΨΠΤσΓΜ≤·±ΏΑ ≤ΦΛΈΟφΨ°¥κΕ»ΛάΓΘ
ΛΫΛΈ
ΜωΕ»ΨΒΖ―ΛœΤσ¬εΧήΓΔΜΑ¬εΧήΛΊΛΈΝξ¬≥Λ§ΟφΩ¥Λ»Λ ΛκΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΓΔ¬©Μ“Λ§ΛΛΛ ΛΛΨλΙγΛδΓΔ¬©Μ“ΛœΛΛΛΤΛβΥήΩΆ
ΛΥάΉΛρΖ―ΛΑΑ’ΜΉΛ§Λ ΛΛΨλΙγΛΥΛ…ΛΠΛΙΛκΛΪΓΘ
¬©Μ“ΛΥ
Τ±ΛΗΕλœΪΛρΛΒΛΜΛΩΛ·ΛœΛ ΛΛΛ»ΙΆΛ®ΛκΖ–±ΡΦ‘ΛβΨ·Λ
Λ·Λ ΛΛΓΘ
ΘΆΓθΘΝΛ§Ά≠ΗζΛ ΝΣ¬ρΜηΛΈΑλΛΡΛΥΛ ΛκΓΘ
ΓΓΛΫΛλΛ«ΛœΓΔΛ…ΛσΛ ≤ώΦ“Λ§ΘΆΓθΘΝΛΈ¬–ΨίΛ»ΛΖΛΤ…Ψ
≤ΝΛΒΛλΛκΛΈΛΪΓΘ
±ΩΝς≤ώΦ“Λρ«ψΛΠ¬ΠΛΈΝάΛΛΛ»ΛΖΛΤΛœ¬γ
Λ≠Λ·Α ≤ΦΛΈΗόΛΡΛ§ΒσΛ≤ΛιΛλΛκΓΘ
?≤ΌΦγΛΈ≥ΆΤάΓΔ?
ΜωΕ»Ξ®ΞξΞΔΛΈΞΏΞΙΞόΞΟΞΝ≤ρΨΟΓΔ?Ε»Χ≥ΗζΈ®≤ΫΓΔ?Φΰ
’ΜωΕ»ΛΊΛΈΜ≤ΤΰΓΔ?Μΰ¥÷Λρ«ψΛΠΓΘ
Λ≥ΛλΛιΛΈΞΥΓΦΞΚ
NOVEMBER 2011ΓΓΓΓ28
ΟφΨ°±ΩΝςΕ»ΓßΜωΕ»ΨΒΖ―ΛΈΗΫΨθ
ΓΓΞ»ΞιΞΟΞ·±ΩΝςΕ»≥ΠΛœΖ–±ΡΦ‘ΛΈΙβΈπ≤ΫΛ§¬ΨΜΚΕ»Α Ψε
ΛΥΩ ΛσΛ«ΛΛΛκΓΘ
ΜωΕ»ΨΒΖ―Χδ¬ξΛ§Λ≥ΛλΛΪΛι¬γΛ≠Λ ΞΤΓΦ
ΞόΛΥΛ ΛΟΛΤΛ·ΛκΓΘ
ΟφΨ°ΈμΚΌΞΣΓΦΞ ΓΦΛβM&AΛ»ΛΛΛΠΝΣ
¬ρΜηΛρΟΈΛΟΛΤΛΣΛ·…§ΆΉΛ§ΛΔΛκΓΘ
ΞΣΓΦΞ ΓΦΛΈΑζ¬ύΗεΛβ
ΜωΕ»Λρ¬Η¬≥ΛΒΛΜΓΔΫΨΕ»ΑςΛΈΗέΆ―ΛρΦιΛκΛΩΛαΛΈΆ≠ΗζΛ
ΦξΟ Λ»Λ ΛξΤάΛκΓΘ
Γ ΥήΜο ‘ΫΗ…τΓΔ ‘ΫΗΕ®Έœ=ΞΙΞ»ΞιΞΛΞ·ΓΥ
ΩόΘ±ΓΓ±ΩΝςΕ»Ζ–±ΡΦ‘ΛΈ«·Έπ
40 ¬εΑ ≤Φ 3.3Γσ
50 ¬ε
15.3Γσ
60 ¬ε
24.1Γσ
41.3Γσ
70 ¬ε
16.0Γσ
80 ¬εΑ Ψε
ΞΙΞ»ΞιΞΛΞ·ΛΈ
ά–ΡΆΟΛ»§ΦηΡυΧρ
¬η 6 …τ
29ΓΓΓΓNOVEMBER 2011
ίΨΎΛœΛ ΛΛΓΘ
Βρ≈άΛΈ≈ΎΨμ±χάςΛδ¬ηΜΑΦ‘ΛΊΛΈΚΡΧ≥ ί
ΨΎΛ Λ…ΓΔΛ…ΛσΛ ΛΥάΚεΧΛ Ρ¥ΚΚΛρΛΖΛΤΛβΆΫ¬§Λ«Λ≠Λ
ΛΛΧδ¬ξΛ§ΗεΛΪΛι»·άΗΛΙΛκ≤Ρ«Ϋά≠Λρ»ίΡξΛ«Λ≠Λ ΛΛΓΘ
ΓΓΞξΞΙΞ·≤σ»ρΛΈ ΐΥΓΛ»ΛΖΛΤΞΙΞ»ΞιΞΛΞ·Λ«ΛœΘΆΓθΘΝΛΈ
«ψΛΛΦξ¬ΠΛΈ¥κΕ»ΛΥ¬–ΛΖΛΤΓΔΦΓΛΈΜΆΛΡΛΈ ΐΥΓΛρΞΔΞ…Ξ–
ΞΛΞΙΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
?Ξ«ΞεΓΦΞ«ΞξΞΗΞßΞσΞΙΓ «ψΦΐ¥ΤΚΚΓΥ
ΛΈ¬–ΨίΛ»Λ ΛΟΛΩ≥ΤΙύΧήΛΥΛΡΛΛΛΤ«δΛξΦξ¬ΠΛ»≥Έ«ßΛΙ
ΛκΓΘ
?ΑλΡξ¥ϋ¥÷ΛρΡξΛαΓΔΛΫΛΈ¥ϋ¥÷ΤβΛΥ»·άΗΛΖΛΩ μ
≥ΑΚΡΧ≥Λœ«δΛξΦξ¬Πά’«ΛΛ»Λ ΛκΛ≥Λ»ΛρΖάΧσΫώΛΥΧάΒ≠
ΛΙΛκΓΘ
?«ψΦΐ¬εΕβΛρ §≥δΛΖΛΤΜΌ ßΛΠΓΘ
?ΘΆΓθΘΝΗε
ΛΈΑζΖ―¥ϋ¥÷ΛρΛ«Λ≠ΛκΛάΛ±ΡΙΛ·Λ»ΛξΓΔΑζΖ―¥ϋ¥÷ΟφΛœ
ΝΑΞΣΓΦΞ ΓΦΛΥΚ«ΡψΖνΛΥΑλ≤σΛœ¥ιΛρΫ–ΛΖΛΤΛβΛιΛΠΓΘ
ΓΓΛΖΛΪΛΖΓΔ ΛΫΛΈΝ¥ΛΤΛρ≈ΑΡλΛΖΛΤΛβΑλΓΜΓΜΓσΞξΞΙΞ·Λρ
ΞΊΞΟΞΗΛΙΛκΛ≥Λ»Λœ…‘≤Ρ«ΫΛάΓΘ
ΛΫΛλΛ«Λβ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΈ
«ψΦΐΛΥΑ’ΆΏ≈ΣΛ ≤ώΦ“ΛœΨοΛΥΑλΡξΩτ¬ΗΚΏΛΙΛκΓΘ
Λ»Λξ
ΛοΛ±ΚΘΛœ«ψΛΛΦξ¬ΠΛΈΑ’ΆΏΛ§Ε·ΛΛΓΘ
ΗΫΨθΛΈΛόΛόΛ«Λœ
Ωξ¬ύΛΖΛΤΛΛΛ·ΛάΛ±ΛάΛ»»ΫΟ«ΛΖΛΩΖ–±ΡΦ‘Λ§Ε·ΛΛΑ’ΜΉ
ΛΈΛβΛ»ΛΥΘΆΓθΘΝΛΥΤΑΛΛΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΓ÷ΘΆΓθΘΝΛ«Κ«ΛβΫ≈ΆΉΛ ΛΈΛœΓΔ«δΒ―ΛΈΞΩΞΛΞΏΞσΞΑΛάΓΉ
Λ»ά–ΡΆΦηΡυΧρΛœΛΛΛΠΓΘ
Άΐœά≈ΣΛΥΛœΕ»ά”Λ§Ξ‘ΓΦΞ·Λρ
ΖόΛ®ΛΩΜΰΛ§Κ«Λβ«δΒ―ΛΥ≈§ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
Ε»ά”Λ§≤ΦΙΏάΰ
ΛΥΗΰΛΪΛ®Λ–¥κΕ»≤ΝΟΆΛœ¬γΛ≠Λ·≤ΦΛ§ΛκΓΘ
ΞΣΓΦΞ ΓΦΑ ≥Α
ΛΈΞ≠ΓΦΞ―ΓΦΞΫΞσΓΔ±ΡΕ»ά’«ΛΦ‘Λδ±ΩΙ‘¥…Άΐά’«ΛΦ‘Λ Λ…
ΛΈ«·ΈπΛβΫ≈ΆΉΛάΓΘ
Ξ≠ΓΦΞ―ΓΦΞΫΞσΛ§Ρξ«·¥÷ΕαΛΈ≤ώΦ“ΛœΓΔ
ΨόΧΘ¥ϋΗ¬Λ§ΟΜΛΛΛ»«ψΛΛΦξ¬ΠΛΥ»ΫΟ«ΛΒΛλΛΤΛΖΛόΛΠΓΘ
ΓΓά–ΡΆΦηΡυΧρΛœΓ÷ΜωΕ»ΨΒΖ―Χδ¬ξΛρ ζΛ®ΛΤΛΛΛκ≤ώΦ“
ΛœΓΔΕ»ά”ΛΈΈ…ΛΛΛΠΛΝΛΥΨ≠ΆηΛρΖηΟ«ΛΙΛΌΛ≠ΛάΓΘ
ά÷Μζ
ΛρΑζΛ≠ΛΚΛΟΛΤΦΎΕβΛ§ΥΡΛαΛ–ΓΔΥήΆηΛ ΛιάΗΛ≠ΜΡΛλΛκ
ΛœΛΚΛΈ≤ώΦ“Λ«ΛβΦξΟΌΛλΛΥΛ ΛΟΛΤΛΖΛόΛΠΓΘ
±ΩΝςΕ»ΛΈ
ΘΆΓθΘΝΛœΚΘΛΈΛ»Λ≥ΛμΛœ«δΛξΦξΜ‘ΨλΛάΓΘ
ΛΖΛΪΛΖΚΘΗε
Λœ«δΛξΦξ¬ΠΛ§ΝΐΛ®ΛΤΛ·ΛκΓΘ
«ψΛΛΦξ¬ΠΛ§ΝΣΛ÷Έ©ΨλΛΥ
Λ ΛκΓΉΛ»ΖΌΙπΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
«ψΛΛΦξ¬ΠΛΈΜωΨπΛΥΛηΛΟΛΤ ―ΛοΛΟΛΤΛ·ΛκΓΘ
¬ΨΛΈΨρΖο
ΛΥ¬ΩΨ·Χδ¬ξΛœΛΔΛΟΛΤΛβΓΔΛΫΛΈΞ®ΞξΞΔΛΈ≤Ό ΣΓΔΛΫΛΈ
ΨλΫξΛΥΒρ≈άΛρ…§ΆΉΛ»ΛΖΛΤΛΛΛκ«ψΛΛΦξΛ§ΗΪΛΡΛΪΛλΛ–
ΞόΞΟΞΝΞσΞΑΛœά°Έ©ΛΙΛκΓΘ
ΛΫΛ≥Λ§±ΩΝςΕ»ΛΈΘΆΓθΘΝΛΈΤώ
ΛΖΛΛΛ»Λ≥ΛμΛ«ΛΔΛξΓΔΛόΛΩΧΞΈœΛ«ΛβΛΔΛκΓΉΛ»ά–ΡΆΦη
ΡυΧρΛœΛΛΛΠΓΘ
Ε»ά”Ξ‘ΓΦΞ·ΜΰΛ≥ΛΫ«δΒ―ΛΈΞΩΞΛΞΏΞσΞΑ
ΓΓ«δΒ―≤Ν≥ ΛΈΜΜΡξ ΐΥΓΛ»ΛΖΛΤΛœΓΔΟφΨ°±ΩΝς≤ώΦ“ΛΈ
ΨλΙγΓΔΦ¬¬÷Λ»ΛΖΛΤΛœΓ÷ΫψΜώΜΚΥΓΓΉΛ§¬γ…τ §ΛράξΛα
ΛκΓΘ
ΩόΘ≤ΛœΓΜœΜ«·ΛΪΛιΓΜ»§«·ΛΥά°Έ©ΛΖΛΩΘΆΓθΘΝΑΤ
ΖοΛΈ¥κΕ»≤ΝΟΆΜΜΡξ ΐΥΓΛρΞΙΞ»ΞιΞΛΞ·Λ§ΫΗΖΉΛΖΛΩΛβ
ΛΈΛάΓΘ
Ν¥¬ΈΛ»ΛΖΛΤΛœΓ÷ΘΡΘΟΘΤΓ Ξ«ΞΘΞΙΞΪΞΠΞσΞ»ΓΠ
Ξ≠ΞψΞΟΞΖΞεΓΠΞ’ΞμΓΦΓΥΥΓΓΉΛ»Γ÷Μ‘Ψλ≥τ≤ΝΥΓΓΉΛΣΛη
Λ”Γ÷ΈύΜς≤ώΦ“»φ≥”ΥΓΓΉΛ§ΑΒ≈ί≈Σ¬ΩΩτΛράξΛαΛΤΛΛΛκΓΘ
ΓΓΛ≥ΛΈΛΠΛΝΘΡΘΟΘΤΥΓΛœΓΔΜωΕ»ΖΉ≤ηΛρΞΌΓΦΞΙΛΥΓΔΛΫ
ΛΈ≤ώΦ“Λ§Ψ≠ΆηΛΥΛοΛΩΛΟΛΤάΗΛΏΫ–ΛΙΞ≠ΞψΞΟΞΖΞεΛρΗΫΜΰ
≈άΛΥ≥δΛξΑζΛΛΛΤ¥κΕ»≤ΝΟΆΛρΜΜΡξΛΙΛκ ΐΥΓΛ«ΓΔΚ«Λβ
Αλ»Χ≈ΣΛ …Ψ≤Ν ΐΥΓΛ»ΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
Αλ ΐΓΔΜ‘Ψλ≤ΝΟΆ
ΥΓΛœΨεΨλ¥κΕ»ΛΈΨλΙγΛΈ≥τΦΑΜΰ≤Ν…Ψ≤ΝΓΔΈύΜς≤ώΦ“»φ
≥”ΥΓΛœΓΔΛΫΛΈ≤ώΦ“Λ»ΜςΛΩΨεΨλ¥κΕ»ΛΈΜΰ≤Ν…Ψ≤ΝΛρ¥π
ΫύΛΥΛΙΛκ…Ψ≤ΝΥΓΛρΜΊΛΙΓΘ
ΓΓΛ≥ΛλΛΥ¬–ΛΖΛΤΓΔΟφΨ°±ΩΝς≤ώΦ“ΛΈΨλΙγΛœΓΔΜωΕ»ΖΉ
≤ηΛΈΩ°Άξά≠Λ§ΡψΛΛΛΈΛ«ΘΡΘΟΘΤΥΓΛ§ΚΈΛξΛΥΛ·ΛΛΓΘ
ΜωΕ»
Β§ΧœΛΈ≈άΛΪΛιΈύΜς≤ώΦ“»φ≥”ΥΓΛβΤκάςΛόΛ ΛΛΓΘ
ΛΫΛΈ
ΛΩΛαΫξΆ≠ΜώΜΚΛρΜΰ≤Ν…Ψ≤ΝΛΖΓΔΘ¬ΓΩΘ”ΛΈ §άœΛρ≈ΑΡλΛΖ
ΛΩΛΠΛ®Λ«ΓΔΞ≠ΞψΞΟΞΖΞεΞ’ΞμΓΦΛ§ΙθΜζΛΈ≤ώΦ“ΛΥΛœΞΉΞλ
ΞΏΞΔΞύΛρ…’Λ±ΛκΓΘ
ά÷ΜζΛΈΨλΙγΛœΓΔΛΫΛΈ §ΛρΫψΜώΜΚΛΪ
Λι≥δΛξΑζΛ·ΛΪΛΩΛΝΛ««ψΦΐ≤Ν≥ ΛρΖηΛαΛκΛ≥Λ»Λ§¬ΩΛΛΓΘ
ΓΓΟφΨ°±ΩΝςΕ»ΛΈ«ψΛΛΦξ¬ΠΛΈΞξΞΙΞ·ΛœΖηΛΖΛΤΨ°ΛΒΛ·
Λ ΛΛΓΘ
«ψΦΐΗεΛβ¥ϊ¬ΗΛΈΜ≈ΜωΛρΖ―¬≥Λ«Λ≠ΛκΛΈΛΪΓΘ
Μω
ΝΑΛΥ≤ΌΦγΛΪΛιΘΆΓθΘΝΛΥ¬–ΛΙΛκΨΒ¬ζΛρΤάΛΩΛ»ΛΖΛΤΛβ
Λ»ΙγΟΉΛΖΛΤΛΛΛκΨλΙγΛΥΛœΓΔΈψΛ®ά÷Μζ≤ώΦ“Λ«ΛΔΛΟΛΤ
ΛβΗΓΤΛ¬–ΨίΛΥΛ ΛξΤάΛκΓΘ
ΓΓΛόΛΚΛœΓΔΛΫΛΈ≤ώΦ“ΛΈΞ–ΞιΞσΞΙΞΖΓΦλà ȬΓΩΘ”ΓΥΛρ
ΗΪΛΤΓΔΡΔ μΨεΛΈ…Ψ≤ΝΛ«ΛœΛ Λ·Μΰ≤Ν…Ψ≤ΝΛρΜΜΫ–ΛΙΛκΓΘ
≈ΎΟœΛΈ¥όΛΏ¬Μ±ΉΛδ¬ύΩΠΕβΛΣΛηΛ”Φ“≤ώ ίΗ±¥ΊΖΗΛΈΖ–
»ώΫηΆΐΛρ≥Έ«ßΛΖΓΔΚβΧ≥ΛΈΦ¬¬÷Λρ»ΫΟ«ΛΙΛκΓΘ
ΡΔ μΨε
ΛœΚΡΧ≥ΡΕ≤αΛ«Λβ≈ΎΟœΛΈ¥όΛΏ±ΉΛρΜΰ≤Ν…Ψ≤ΝΛΙΛλΛ–Μώ
ΜΚΡΕ≤αΛΥΛ ΛκΞ±ΓΦΞΙΛ§ΓΔœΖ όΛΈ±ΩΝς≤ώΦ“ΛΥΛœΨ·Λ Λ·
Λ ΛΛΓΘ
…Ψ≤ΝΛΈΖκ≤ΧΓΔΚΡΧ≥ΡΕ≤αΛ§»ΫΧάΛΖΛΩΨλΙγΛ«ΛβΓΔ
Ξ≠ΞψΞΟΞΖΞεΞ’ΞμΓΦΛ§ΙθΜζΛ«ΛΔΛλΛ–ΗΓΤΛΛΈΆΨΟœΛœΜΡΛκΓΘ
ΓΓΛΩΛάΛΖΓΔ¬Μ±ΉΖΉΜΜΫώΓ Θ–ΓΩΘΧΓΥΛΥΛΖΛΤΛβΓΔΘΆΓθ
ΘΝΛΈάλΧγ¥κΕ»Λœ≥έΧΧΡΧΛξΛΥΛœΦθΛ±ΦηΛιΛ ΛΛΓΘ
ΟφΨ°
¥κΕ»ΛΈΨλΙγΓΔΥΓΩΆά«ΛρΆόΛ®ΛκΛΩΛαΛΥΑ’Ωό≈ΣΛΥά÷Μζ
ΛΥΛΖΛΤΛΛΛκΞ±ΓΦΞΙΛ§ΡΝΛΖΛ·Λ ΛΛΓΘ
Β’ΛΥΙθΜζΛΈΞ±ΓΦΞΙ
Λ«Λœ ¥ΨΰΛΈΕ≤ΛλΛ§ΛΔΛκΓΘ
ΛΫΛΈΛΩΛαΧρΑς σΫΖΛΈ≥έΓΔΗρ
Κί»ώΓΔΗΚ≤ΝΫΰΒ―ΓΔ≥ΑΟμ»ώΛ Λ…ΛρΞΝΞßΞΟΞ·ΛΖΛΤΓΔΛΫ
ΛΈ≤ώΦ“ΛΈΦ¬ΈœΛρΗΪΕΥΛαΛκΓΘ
ΓΓΚβΧ≥ΛάΛ±Λ«Λœ»ΫΟ«Λ«Λ≠Λ ΛΛΧΧΛβΛΔΛκΓΘ
Γ÷ΛΫΛΈ≤ώΦ“
Λ§ΜΐΛΟΛΤΛΛΛκΜ≈ΜωΛδ ΣΈ°…‘ΤΑΜΚΛ Λ…ΛΈΜωΕ»≤ΝΟΆΛœΓΔ
100.0Γσ
80.0Γσ
60.0Γσ
40.0Γσ
20.0Γσ
0.0Γσ
ΛΫΛΈ¬Ψ
8.6Γσ
ΫψΜώΜΚΥΓ
10.8Γσ
ΩόΘ≤ΓΓ¥κΕ»≤ΝΟΆΛΈΜΜΡξ ΐΥΓ
Γ ΘΩτΛΈ…Ψ≤ΝΥΓΛρΆ―ΛΛΛκΞ±ΓΦΞΙ¥όΛύΓΥ
2006ΓΝ2008 «·ΛΈΘΆΓθΘΝΜωΈψΛρΞΙΞ»ΞιΞΛΞ·Λ§Τ»ΦΪΛΥΫΗΖΉ
ΘΡΘΟΘΤΥΓ
90.7Γσ
Μ‘Ψλ≥τ≤ΝΥΓ
91.4Γσ
ΈύΜς≤ώΦ“»φ≥”ΥΓ
54.5Γσ
ΤΟ ΫΗ
|